
写真の説明はのちほど…。
本日は、また長くなるかもぉ…先にごめんなさいです。
まずは、昨日行こうとして時間切れだったところ、
「風俗博物館」といいます。駅からがんばって歩ける距離です。
最初にここを知ったのは、まず「本」をみつけたことでした。
上の写真がその本です。「源氏物語と京都 六條院へ出かけよう」です。
正直なところを言いますと、表紙のセンスはイマイチかなぁと思ったのですが、
表紙カバーを裏返すと、こんな写真が…。貴族のお屋敷を上から見たところ、
実はこれが博物館の展示物です。

ちょっと部分拡大してみました。黒い紐のようなものが
十二単のお人形の「髪」ですね。
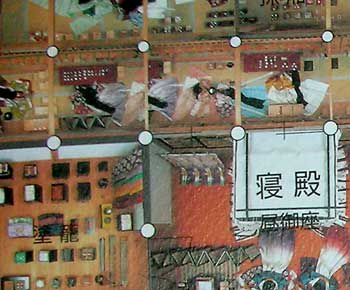
以前から「平安・雅の世界」についてもっと知りたいなぁと思っていましたので、
まず本を購入してみました。そしてこの雅な世界が四分の一スケールで、
具現化されて常設展示されていることを知ったわけで、
んじゃ行ってみるか…だったのです。
HPを調べたところ、博物館と言っても普通のビルのワンフロア、
ちょっと通り過ぎてしまいそうなビルだし、そんなに広くはないんだなと思い、
実を言うとそーんなに期待はしていませんでした。
でも、行ってよかったです。源氏物語や十二単などの衣装、それとお人形に
興味のある方にはお勧めです。
ちょっと説明致しますと、ここの博物館の館長さんは「井筒與兵衛」氏、
創業が1705年7月という、とんでもなく古いお店、
要するに「宗教関係・祭事関係」のさまざまな衣装や道具を作る会社、
僧侶・神主の衣装から、仏壇神前の飾り物、お祭関係(夜店じゃありませんよ、
京都のお祭ですから、それなりの氏子さんたちの衣装などです)
それに雅楽に使われる楽器などを扱っておられます。
京都ならではの御商売ですね。
で、ここの社長さんが「源氏物語の場面を具現化して平安貴族の暮らしぶりを
実際に見て、感じていただく」ということを考えられたわけです。
行ってみましたら、ビルの一階はその「店舗」でして、横のガラス戸から入り、
正面右のエレベーターで5階へ、扉が開くともう会場です。
さてその「四分の一スケール」ですが、まずはフロアいっぱいに
「光源氏の大邸宅 六條院」がありまして、左から順路でぐるりとまわります。
ありがたいことにここは「写真撮り放題」しかも「撮った写真を
個人ブログに載せてもよろしいでしょうか」とお尋ねしたら「かましまへん」と!
ではまず一枚目、こんな風にできていまして、
通路のところどころに、こうして上から見られるよう階段がついています。

大きな「邸」をぐるりとまわると、各場所がそれぞれに
源氏物語のさまざまな場面になぞらえて作られています。
家具や小道具衣装なども、全部四分の一で正確に作り上げられたものです。
こちらは衣装「襲の色目」をあらわしたものが並べられています。
四分の一ですから、高さ3~40センチくらいです。
御簾もホンモノそっくりですよ。

ここはちょうど正面の反対側、廂(ひさし)という細長い、
今なら「廊下」ともいうべきスペースで、向こうまで突き抜けていて、
突き当たって右側に「行幸された帝」がおられます。
その「廂」に女性がズラリと並んでいます。

やっとまともにお顔の見えるお人形さんの登場です。
こんな感じのかわいい女房さんがあちこちにいまして、
場面によって食事の支度をしていたり姫様の身支度を整えたり、
出産の場面では、全員が白装束で立ち働いていたり、
共同作業で冊子を作っていたり…昔は印刷技術がありませんから、
ひたすら「書き写し」で当時流行の読み物などは書き写し、綴じて糊付け。
「本」を作ることまでも「女房たち」の大事な仕事だったのだそうです。
けっこう忙しかったんですねぇ。

ちょっとピンがきてなくてすみません、年若い女官たちが、
冊子を読みながら寝てしまったところ、でしょうか。

長い髪を入れる箱を枕元に置いていたというのは身分の高い女性だったんですね。
ついでのことに、当時の女官たちで「朱」の袴をはくのは「既婚者」、
未婚者はこの小豆色の上下だったそうです。なんかいかにもユニフォーム?
まぁこんな具合に、どこもかしこも「王朝絵巻」、
囲碁や食器などもちゃんと小さく作られていて、とてもかわいいですよ。
さて、ぐるりと回ると隣にもう一部屋、そこには原寸の十二単や、
楽器、双六(今の双六ではなく「バックギャモン」タイプ)などが置いてあり、
触るのも着るのも自由、そして奥には「御帳台(みちょうだい)」があります。
これは貴人のいわば「個室」、説明と実物はこちら、


まぁ貴賓ということも、寒さ対策もあったでしょうが、
ちょっと覗いてみましたがねぇ、閉所恐怖症では入ってられませんな。
たたみ二畳分のワンルームです。
小さなスペースに広がる平安の雅な世界、
そのほかにも時代衣装の絵ハガキもあり、絵ハガキばかり、
何枚も買ってしまいました。
さて、ここでじっくり時間をかけてしまった私ですが、
実はこの博物館の同じ通りに、コメントを下さるotyukun様の工房があります。
今回は、ギリギリまで予定がわかりませんでしたので、
失礼ながらアポなし、タダの通りすがりのお客としてお伺いしてみよう、と
そんな風に思っておりました。
ところがお伺いすると奥様が出ていらして、ブログ拝見しまして…と申しますと、
わざわざ外出なさっておられるご主人様にご連絡してくださいました。
たまたますぐそばまで戻っておられたご主人様と、お会いすることができました。
落ち着いた品のいい、いかにも仕事が命…という感じの方でした。
すばらしい染めの反物や帯を拝見させていただきまして、
かわいい小物を知り合いと自分用のお土産に買わせていただいて失礼しました。
突然お訪ねしましたのに、快くお話しを聞かせてくださって、
ありがとうございました。なおこちらが「京町家染工房遊」さんHPです。
予約で工房見学や体験もできます。また小紋も染めていただけますよ。
お土産に買ったのは「デジカメ用巾着」、これ、このために染めたようです。
この巾着の記事は「遊」ブログの11月8日の記事に載っています。

さて、おいしいお茶も頂いて次の目的地へ向かうため、
乗り物はナニにするかなと考えながら、東本願寺の前の通り、
つまり「烏丸通」まででますと、本願寺前の街路樹がいい具合に色づいています。
写真を撮ろうと、構えたときに左ヒザの中で「メキッ」といういやな音が…。
実は左ひざに古傷があります。この音がしたときは、無理をすると
後でしばらく立ち座りが不自由になるんですー。
ちゃんとテーピングもしていたのですが、カメラを構えるのに、
変な格好をしたんですねぇきっと。しばらくじっとしていましたが、
やはりいかにも「お皿」がずれた、という感じの鈍痛が…。
ほんとにズレたわけじゃないんですが、そういう感じ、です。
やはり歩くのはあきらめて、お土産だけ買って早めに帰ることにしました。
ゆっくりゆっくり歩いていくと、工事中のビルがありまして、
こんなものを見つけました。


シャレてますね、「牛若丸と弁慶」に「舞妓さん」です。
舞妓さんの手前の竹垣もこまかいですねぇ。ホンモノみたい。
何枚かありましたが、みんな絵が違いました。
横浜ならせいぜい「ツタの柄」とか「おじぎしたおじさん」、
「ご迷惑をおかけしてます」とかナントカですね。
いいもの見つけていい気分で駅まで戻り、お菓子などのお土産を買って、
予定より二時間早い新幹線で帰宅しました。
ヒザは大丈夫です。今もテーピングはしていますが、
整体の先生によると「古傷」があったり、高齢になってくると、
ヒザまわりの筋肉や筋がのびたり、弾力がなくなって、
ヒザのお皿が下がるのだそうです。メキッってのはその音ですかね。
ともあれ今回の旅も収穫の多い、とても楽しい旅になりました。
追記 こちらが「風俗博物館」と「染工房 遊」さまの地図です。
駅のまん前の大きな通りをまっすぐ行くと、すぐに「東本願寺」、
そこを左折してまっすぐです。博物館まで20分くらい?

本日は、また長くなるかもぉ…先にごめんなさいです。
まずは、昨日行こうとして時間切れだったところ、
「風俗博物館」といいます。駅からがんばって歩ける距離です。
最初にここを知ったのは、まず「本」をみつけたことでした。
上の写真がその本です。「源氏物語と京都 六條院へ出かけよう」です。
正直なところを言いますと、表紙のセンスはイマイチかなぁと思ったのですが、
表紙カバーを裏返すと、こんな写真が…。貴族のお屋敷を上から見たところ、
実はこれが博物館の展示物です。

ちょっと部分拡大してみました。黒い紐のようなものが
十二単のお人形の「髪」ですね。
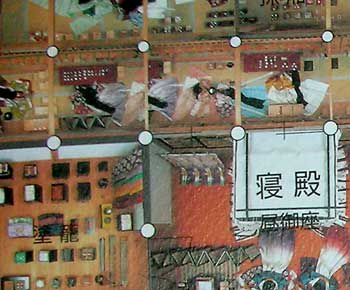
以前から「平安・雅の世界」についてもっと知りたいなぁと思っていましたので、
まず本を購入してみました。そしてこの雅な世界が四分の一スケールで、
具現化されて常設展示されていることを知ったわけで、
んじゃ行ってみるか…だったのです。
HPを調べたところ、博物館と言っても普通のビルのワンフロア、
ちょっと通り過ぎてしまいそうなビルだし、そんなに広くはないんだなと思い、
実を言うとそーんなに期待はしていませんでした。
でも、行ってよかったです。源氏物語や十二単などの衣装、それとお人形に
興味のある方にはお勧めです。
ちょっと説明致しますと、ここの博物館の館長さんは「井筒與兵衛」氏、
創業が1705年7月という、とんでもなく古いお店、
要するに「宗教関係・祭事関係」のさまざまな衣装や道具を作る会社、
僧侶・神主の衣装から、仏壇神前の飾り物、お祭関係(夜店じゃありませんよ、
京都のお祭ですから、それなりの氏子さんたちの衣装などです)
それに雅楽に使われる楽器などを扱っておられます。
京都ならではの御商売ですね。
で、ここの社長さんが「源氏物語の場面を具現化して平安貴族の暮らしぶりを
実際に見て、感じていただく」ということを考えられたわけです。
行ってみましたら、ビルの一階はその「店舗」でして、横のガラス戸から入り、
正面右のエレベーターで5階へ、扉が開くともう会場です。
さてその「四分の一スケール」ですが、まずはフロアいっぱいに
「光源氏の大邸宅 六條院」がありまして、左から順路でぐるりとまわります。
ありがたいことにここは「写真撮り放題」しかも「撮った写真を
個人ブログに載せてもよろしいでしょうか」とお尋ねしたら「かましまへん」と!
ではまず一枚目、こんな風にできていまして、
通路のところどころに、こうして上から見られるよう階段がついています。

大きな「邸」をぐるりとまわると、各場所がそれぞれに
源氏物語のさまざまな場面になぞらえて作られています。
家具や小道具衣装なども、全部四分の一で正確に作り上げられたものです。
こちらは衣装「襲の色目」をあらわしたものが並べられています。
四分の一ですから、高さ3~40センチくらいです。
御簾もホンモノそっくりですよ。

ここはちょうど正面の反対側、廂(ひさし)という細長い、
今なら「廊下」ともいうべきスペースで、向こうまで突き抜けていて、
突き当たって右側に「行幸された帝」がおられます。
その「廂」に女性がズラリと並んでいます。

やっとまともにお顔の見えるお人形さんの登場です。
こんな感じのかわいい女房さんがあちこちにいまして、
場面によって食事の支度をしていたり姫様の身支度を整えたり、
出産の場面では、全員が白装束で立ち働いていたり、
共同作業で冊子を作っていたり…昔は印刷技術がありませんから、
ひたすら「書き写し」で当時流行の読み物などは書き写し、綴じて糊付け。
「本」を作ることまでも「女房たち」の大事な仕事だったのだそうです。
けっこう忙しかったんですねぇ。

ちょっとピンがきてなくてすみません、年若い女官たちが、
冊子を読みながら寝てしまったところ、でしょうか。

長い髪を入れる箱を枕元に置いていたというのは身分の高い女性だったんですね。
ついでのことに、当時の女官たちで「朱」の袴をはくのは「既婚者」、
未婚者はこの小豆色の上下だったそうです。なんかいかにもユニフォーム?
まぁこんな具合に、どこもかしこも「王朝絵巻」、
囲碁や食器などもちゃんと小さく作られていて、とてもかわいいですよ。
さて、ぐるりと回ると隣にもう一部屋、そこには原寸の十二単や、
楽器、双六(今の双六ではなく「バックギャモン」タイプ)などが置いてあり、
触るのも着るのも自由、そして奥には「御帳台(みちょうだい)」があります。
これは貴人のいわば「個室」、説明と実物はこちら、


まぁ貴賓ということも、寒さ対策もあったでしょうが、
ちょっと覗いてみましたがねぇ、閉所恐怖症では入ってられませんな。
たたみ二畳分のワンルームです。
小さなスペースに広がる平安の雅な世界、
そのほかにも時代衣装の絵ハガキもあり、絵ハガキばかり、
何枚も買ってしまいました。
さて、ここでじっくり時間をかけてしまった私ですが、
実はこの博物館の同じ通りに、コメントを下さるotyukun様の工房があります。
今回は、ギリギリまで予定がわかりませんでしたので、
失礼ながらアポなし、タダの通りすがりのお客としてお伺いしてみよう、と
そんな風に思っておりました。
ところがお伺いすると奥様が出ていらして、ブログ拝見しまして…と申しますと、
わざわざ外出なさっておられるご主人様にご連絡してくださいました。
たまたますぐそばまで戻っておられたご主人様と、お会いすることができました。
落ち着いた品のいい、いかにも仕事が命…という感じの方でした。
すばらしい染めの反物や帯を拝見させていただきまして、
かわいい小物を知り合いと自分用のお土産に買わせていただいて失礼しました。
突然お訪ねしましたのに、快くお話しを聞かせてくださって、
ありがとうございました。なおこちらが「京町家染工房遊」さんHPです。
予約で工房見学や体験もできます。また小紋も染めていただけますよ。
お土産に買ったのは「デジカメ用巾着」、これ、このために染めたようです。
この巾着の記事は「遊」ブログの11月8日の記事に載っています。

さて、おいしいお茶も頂いて次の目的地へ向かうため、
乗り物はナニにするかなと考えながら、東本願寺の前の通り、
つまり「烏丸通」まででますと、本願寺前の街路樹がいい具合に色づいています。
写真を撮ろうと、構えたときに左ヒザの中で「メキッ」といういやな音が…。
実は左ひざに古傷があります。この音がしたときは、無理をすると
後でしばらく立ち座りが不自由になるんですー。
ちゃんとテーピングもしていたのですが、カメラを構えるのに、
変な格好をしたんですねぇきっと。しばらくじっとしていましたが、
やはりいかにも「お皿」がずれた、という感じの鈍痛が…。
ほんとにズレたわけじゃないんですが、そういう感じ、です。
やはり歩くのはあきらめて、お土産だけ買って早めに帰ることにしました。
ゆっくりゆっくり歩いていくと、工事中のビルがありまして、
こんなものを見つけました。


シャレてますね、「牛若丸と弁慶」に「舞妓さん」です。
舞妓さんの手前の竹垣もこまかいですねぇ。ホンモノみたい。
何枚かありましたが、みんな絵が違いました。
横浜ならせいぜい「ツタの柄」とか「おじぎしたおじさん」、
「ご迷惑をおかけしてます」とかナントカですね。
いいもの見つけていい気分で駅まで戻り、お菓子などのお土産を買って、
予定より二時間早い新幹線で帰宅しました。
ヒザは大丈夫です。今もテーピングはしていますが、
整体の先生によると「古傷」があったり、高齢になってくると、
ヒザまわりの筋肉や筋がのびたり、弾力がなくなって、
ヒザのお皿が下がるのだそうです。メキッってのはその音ですかね。
ともあれ今回の旅も収穫の多い、とても楽しい旅になりました。
追記 こちらが「風俗博物館」と「染工房 遊」さまの地図です。
駅のまん前の大きな通りをまっすぐ行くと、すぐに「東本願寺」、
そこを左折してまっすぐです。博物館まで20分くらい?





























源氏物語が好きで,当時の寝殿造はどうなっているか
とっても
目を大皿にしてしまいました^^
お人形もかわいらしくて,あいらしくて
いつか行ってみたいです。
紹介していただいて,ありがとうございます。
いいですね~ あぁご一緒したかったなぁ。
「京町家染工房遊」さんもお近くなんですね。
京都駅の近くならまた機会をみつけて行きたいと
思います。
それにしても、ヒザ大事にしてくださいね。
紅葉の見事なこと、陽花さんと楽しい時間がすごせたことでしょうね。
ピラミッドの「野菜カレー」も食べてみたいなー、
otyukunさんの工房も訪ねてみたい、
風俗博物館は絶対見てみたい!ですね。
あーー、しばらくご無沙汰の京都、
すべてを放っぽって、行きたいーーー。
(すでの逃避行動モードでしょうか(笑))
膝、お大事に。
あ、ところでとんぼさんもそろそろ「顔出し」で、
ご一緒しませんか(笑)。
この本もちょっとお高いですけれど、
おもいろいですよ。
私も現場では、目を大皿にしてました!
うろうろと戻ってみたり、思いっきりのぞきこんで頭ぶつけたり…。ちなみに、展示物は
手にとれるほど目の前ですよ。
ぜひ一度行ってみてください。
陽花様
ほんと、一日目にご一緒できなくてごめんなさい。
とても優雅な気分でした。
ヒザ、ありがとうございます。
テーピングとシップで、鈍痛は一日で取れました。
大丈夫です。ご心配かけてすみません。
みやざえもん様
東京朝一番で立てば「日帰り」コースですぞ!
おのおの方(ってだれよ)、おでかけめされい!
♪「あ~いのぉ 逃避行~」じゃなくてっ!
ピラミッドカレーは、最初野菜でご飯が見えない上、ルーが、あのアラジンのランプみたいなのじゃなくて
蓋のついた瀬戸物の壺で出てきたんです。
一瞬顔を見合わせて「これ、カレー?」でした。
ヒザ、ありがとうございます。大丈夫です。
顔出し…うぅ~~ん…みやざさんみたいに
シャープじゃないんですよぉ、この「オモテ」は。
ぼかし…くらいでいきますかね。
その2の、木を倒そうとしているところ・・・
お腹がよじれるほど笑えました、あれグッドです!
楽しい旅、ホントにホントに良かったですね!!!
遅れて居ますご免なさいデジプリやっと出来ました。
昭和16年戦火がしのびよる時代に刊行された「谷崎源氏物語」54帖全部が昔みたいに和紙綴じみたいな装丁で、当時1000部作られて、売り出されたのではなく、全部どなたかに贈呈されたのです。
桐の箱に一式入っています。番号がふられて、谷崎潤一郎の箱書きがしてあります。
じつは縁あって、先月手にはいりました。
値段もあって、まだ主人にも見せていません。
最近の宝ものです。
お~源氏物語と思いました。
是非行ってきたいと思っています。
ありがとうございました。
膝、同病ですね。ヒアルロンサンを注射してもらうと、楽になります。今では標準治療になって保険も利きます。ヒアルロンサン、飲めばどうでしょう?といいましたら、いいものですが、膝のところには血管ありません。飲んだんではそこには効かないですね、といわれました。
上野三人だと、真ん中をもーちょっと
不細工にして膨らませた感じ?(どんなカオじゃ!)
完全露出する勇気はありまへんなぁ…。
みやざさんや桔梗さんみたいに
シャープ、すっきりの顔立ちならいいんですけどねぇ
「反省ザル」はほんと写真見て自分で
「あれっ?こーなったわけ?」と思いましたよ。
デジプリ、楽しみにしてます。
ゆっくりなさってください。
蜆子様
それはそれは、本当に「お宝」ですね。
私は全部読んだということではないので、
ほんとお恥ずかしい…です。
ひたすら「風俗」にあこがれております。
ヒザはテーピングしておくと、
ほとんど大丈夫です。つまり「吊る」わけですね。
いずれにしても、ムリはきかなくなりましたねぇ。
しょっちゅう出かけているのに、京都は、まだまだ知らないところだらけ・・・
もっと、ぶらぶら歩きがしたいです。
ほんとに京都というところは
「見どころ」がゴロゴロという感じですね。
小さいところでも充実しています。
ナニをみるというわけでなくとも、
古い町家のある裏通りなどあるいているだけで、
なんかとてもリラックスできます。
不思議な町です。
工房さんも博物館も行きたいです。
特に工房の小紋は素敵なはんなりした色合い@@
いつかお誂えしたいですね。
疲れがたまると一番弱いところに出てくるのぢゃないかと最近思います。どうぞお大切に