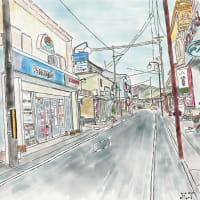わたらせ渓谷線ののりばがあります。
一度は乗ってみたいと考えていた線ですが、今回は乗れません。
群馬県桐生市と栃木県日光市を結ぶ全長約45kmのローカル線です。
紅葉の季節には、沿線沿いに素晴らしい風景が見れます。

私は、両毛線で足利駅を目指します。
足利駅に着きました。

初めて来ました。楽しみです。

黄色の線に沿って歩きます。
まず、足利まちなか遊学館を目指しました。
観光情報や観光地図をもらうのが目的です。
約20分ぐらい歩いて、着きました。
中に入って、観光情報をもらって、
それから、織物関係の機械や資料を見せてもらいました。



この機械は、ここの職員の方が実際に動かして見せてくださいました。
機械の動く様子、組紐のようなものができていくのが素晴らしいと思いました。


足利銘仙の着物が展示してあります。


ここから次に足利学校へ行きます。

前に見えるのが、足利学校の「入徳門」です。

図に従って、番号順に見学します。
「孔子像」です。

稲荷社。


ここからすぐ先に「学校門」があります。

1668年の創建です。足利学校のシンボル。
日本で唯一、「学校」の扁額がかけられている門。
この足利学校は日本最古の学校です。
次に「裏門」の方へまわりました。

すごい木ですね。樹齢はどれほどでしょうね。
裏門にやってきました。



次は「衆寮」の方へ。

衆寮です。

学生が勉強したり生活したりしたところだそうです。


次は、「木小屋」。


「土蔵」がありました。

書籍以外で大切なものを納めていた蔵です。
ここの先の方へ行って見ました。「方丈」の裏になります。



次に「庫裡」に行って、「書院」、「方丈」のある建物の中に入ります。

庫裡です。学校の台所で食事など日常生活が行われたところとなります。
ここから建物に入りました。
上杉憲実。

足利学校の歴史が明らかになるのは、上杉憲実(室町時代)が、書籍を寄進し庠主(学長)制度を設けるなどして学校を再興した頃からだそうです。

学校がありました。


奥の方へ進むと、庭園がありました。


徳川家康は足利学校をよく保護したようです。結びつきが強かったのですね。
徳川幕府歴代将軍の位牌がありました。


方丈から見た「南庭園」です。

むこうに「孔子廟」が見えます。

方丈の部屋の風景。

外へ出ます。
外から見た方丈です。

次に「孔子廟」に行きました。


「旧遺蹟図書館」です。

最後に天然記念物の大樹です。


素晴らしいものを見せてもらったという想いです。
満足しました。
次は、「鑁阿寺(ばんなじ)」に行きます。
次のブログで。