
ピアノ協奏曲の前回、私が一番華やかだと考えている、メンデルスゾーンの第1番を取り上げました。今回はその対極にくると思えるものです。と言っても華やかの反対語であろう地味という事ではなく、もうちょっと別の事を考えてみたいと思います。
その前回、メンデルスゾーンのこの曲は、自分の調子が50%以上の時に更に景気付けをするものだと申し上げました。この場合の調子というのは精神的なものの事を言います。では50%以下の時に聴くとどうなるか。なんかついていけなくてかえって落ち込んでしまうのです。私自身の経験なのですが、精神的な状態が極端に悪い時は、物事を楽しいとかおもしろいとかそういうふうに思う事が出来なくなります。ですからみんなが楽しく話をして笑っている輪の中にいる事などは、他の人とは逆にものすごく苦痛になります。自分は楽しめない訳ですから。そういった事と共通すると思うのですが、華やかな曲を落ち込んでいる時に聴くのは苦痛なものです。
じゃあそういった時はどういう曲なら聴けるか?という事になるのですが、自分自身のそういう心の状態に対して一緒にいてくれるような曲が良いと思えるわけです。ショパンのピアノ協奏曲第1番はそのような曲だと思います。

ある解説者がこの曲の旋律について「青白い」と表現していました。私もはじめて聴いた時、その表現がぴったりだと思いました。メンデルスゾーンは大変恵まれた環境にあった人のようですが、ショパンは健康面や環境面などに困難な事が多かったようです。この曲を書いた二十歳頃の、友人に宛てた書簡の中に次のようにあるとされます。「新しい協奏曲のアダージョ(第2楽章を指している)はホ長調である。ここでは僕は力強さなどは求めはしなかった。むしろ浪漫的な、静穏な、なかば憂鬱な気持ちで、楽しい無数の追憶を喚起させる場所を眺めるかのような印象を起こさせようとしたのだ。たとえば、美しい春の月明かりの夜のような」。 まあいろいろな事がこの曲の背景にはあるようです。
まあいろいろな事がこの曲の背景にはあるようです。
そういう曲であるわけなんですが、何でもない時にこの曲を聴いていて、「なんと憂鬱な曲なんだ」と思っていただけでした。けれども自分が激しく憂鬱な状態を経験して、その時にこの曲を聴いてみたところ、特に第1楽章がそういう状況の心の琴線にしっかりと共鳴してくれたように思えて、何かとてもありがたかったわけです。まあ私にとっては大変思い出深い曲ではありますね。
その第1楽章の一部の事だけ簡単に触れてみたいのですが、20分以上のこの楽章の最初は延々とオーケストラだけで進行しています。本当にP協奏曲なの?っていう感じです。5分経ったところでやっとピアノが、オケの主題だったのと同じ旋律を弾きだします。本当に青白い月明かりの夜のような旋律が続きます。
細かすぎて耳コピーではとてもじゃないけど途中から聴き取ることが出来なくなるものなのですが、少し後の方で出て来る大好きなピアノの旋律を楽譜にしておきます。不完全ですがそれで今回は終わりにさせていただきます。

ふうーっ、やっぱり音楽を言葉にするのは難しい。でも続けていくつもりです。
その前回、メンデルスゾーンのこの曲は、自分の調子が50%以上の時に更に景気付けをするものだと申し上げました。この場合の調子というのは精神的なものの事を言います。では50%以下の時に聴くとどうなるか。なんかついていけなくてかえって落ち込んでしまうのです。私自身の経験なのですが、精神的な状態が極端に悪い時は、物事を楽しいとかおもしろいとかそういうふうに思う事が出来なくなります。ですからみんなが楽しく話をして笑っている輪の中にいる事などは、他の人とは逆にものすごく苦痛になります。自分は楽しめない訳ですから。そういった事と共通すると思うのですが、華やかな曲を落ち込んでいる時に聴くのは苦痛なものです。
じゃあそういった時はどういう曲なら聴けるか?という事になるのですが、自分自身のそういう心の状態に対して一緒にいてくれるような曲が良いと思えるわけです。ショパンのピアノ協奏曲第1番はそのような曲だと思います。

ある解説者がこの曲の旋律について「青白い」と表現していました。私もはじめて聴いた時、その表現がぴったりだと思いました。メンデルスゾーンは大変恵まれた環境にあった人のようですが、ショパンは健康面や環境面などに困難な事が多かったようです。この曲を書いた二十歳頃の、友人に宛てた書簡の中に次のようにあるとされます。「新しい協奏曲のアダージョ(第2楽章を指している)はホ長調である。ここでは僕は力強さなどは求めはしなかった。むしろ浪漫的な、静穏な、なかば憂鬱な気持ちで、楽しい無数の追憶を喚起させる場所を眺めるかのような印象を起こさせようとしたのだ。たとえば、美しい春の月明かりの夜のような」。
 まあいろいろな事がこの曲の背景にはあるようです。
まあいろいろな事がこの曲の背景にはあるようです。そういう曲であるわけなんですが、何でもない時にこの曲を聴いていて、「なんと憂鬱な曲なんだ」と思っていただけでした。けれども自分が激しく憂鬱な状態を経験して、その時にこの曲を聴いてみたところ、特に第1楽章がそういう状況の心の琴線にしっかりと共鳴してくれたように思えて、何かとてもありがたかったわけです。まあ私にとっては大変思い出深い曲ではありますね。

その第1楽章の一部の事だけ簡単に触れてみたいのですが、20分以上のこの楽章の最初は延々とオーケストラだけで進行しています。本当にP協奏曲なの?っていう感じです。5分経ったところでやっとピアノが、オケの主題だったのと同じ旋律を弾きだします。本当に青白い月明かりの夜のような旋律が続きます。
細かすぎて耳コピーではとてもじゃないけど途中から聴き取ることが出来なくなるものなのですが、少し後の方で出て来る大好きなピアノの旋律を楽譜にしておきます。不完全ですがそれで今回は終わりにさせていただきます。

ふうーっ、やっぱり音楽を言葉にするのは難しい。でも続けていくつもりです。











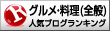
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます