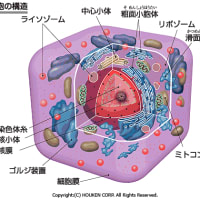2022年4月19日(火)くもりのち晴れ。
肌寒い一日だった。線路はいつも心惹かれる。

田んぼのあぜ道にタンポポが。フォローしている方のブログに西洋タンポポのことが書かれていましたので、さっそくよく見ましたところ、これは西洋タンポポでした。参考になりました。
外総苞片が完全に反り返っていますね。

発達障害がどういうものか、おおむねの概略は分かったような気がする。しかし、これは支援者等の立場に立って具体的に体験しないと、軽はずみに発言できないように感じた。
複雑で分かりにくいから、きめ細かい配慮や対策が必要だと理解できる。こうやって自分なりに調べて理解しようとしたから、ほんのわずかでも分かったことだ。
厚生労働省はかなり理解を示した姿勢を取っていると感じたが、自治体はどうだろうか?
自治体の取り組み
厚生労働省のサイトでは、各都道府県のホームページへのリンクや全国自治体マップ検索を掲載している。☞こちら
全国自治体マップ検索からは、市区町村のホームページへリンクしている。
さらに、支援に関する各都道府県独自の優れた取り組みについて、一覧で紹介している☞こちら。
厚生労働省では、厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業として「発達障害児とその家族に対する地域特性に応じた継続的な支援の実施と評価」という研究結果をもとに、提言「発達障害児とその家族に対する地域特性に応じた継続的な支援のあり方」を作成している。
これに基づいて、
・自治体を「政令指定都市」「中核市・特例市・特別区」「小規模市」「小規模町村」の4グループに分けていて、自治体規模に応じた支援システムの構築を行うよう指導している。
・地域特性に応じた発達障害のあるお子さんとそのご家族の支援体制づくりを促進することを目的とした冊子の紹介をしている。
提言は、ここからPDFで閲覧できる。
なるほど、体制はできているが、自治体によりばらつきもあるということだ。
本人や家族、支援者だけでなく、多くの人がこの発達障害のことをちゃんと理解しないといけないと思った。