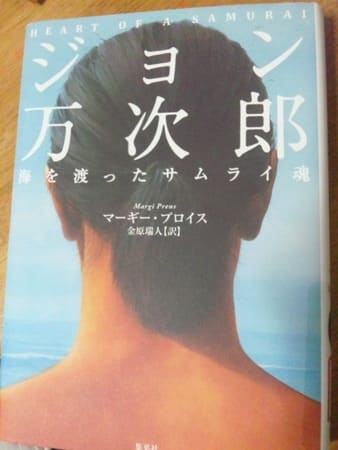帚木蓬生の「守教」、昨晩一気に読み終えました。
戦国時代に九州の農村でひっそり息づいたキリスト教の、
伝来から禁教の時代を乗り越えてふたたび信仰を公にするまでの300年の物語。
興味深いのは舞台が長崎や五島の島々ではなく、福岡の平野のど真ん中の農村であること。あんな開けっぴろげな場所で明治まで信仰を隠し続けることができた奇跡。
ぜったいに棄教はしない、この教えに悪いところはなにひとつないのだから。むしろ貧しく小さいものを労ってくれるたったひとつの教えなのだから。
信じて、教えを守り、まっすぐに慎ましく団結して生きていく村人。村人と信仰を守り抜くと決めた庄屋一族の覚悟。そして、村人の信仰を見て見ぬ振りを続けた周囲の村や寺院の心意気。度重なる小さな奇跡は何か大きな力によるものだと思わざるを得ない。
禁教の時代、4000人の信徒が殉教している。江戸は決して平和な時代ではなかった。幕府のしたことは最後の方ではもう意味を失っていた部分があって、ナチスのユダヤ人虐殺と大差ない。
あの時代、農村で搾取され虐げられた生活を耐えるのに、あの教えは必要だった。だからあれだけ一気に広まり根付いたんだと。
この物語には、直接的に悪者が登場しない。
責め苦も虐殺も、そんな時代だった、そう割り切っている。
なので、読後感が爽やかなのが救いだ。
秋に予約したこの本が、降誕節の今図書館から回ってきたのにも意味があるような気がしてくる。
自分はどうだろう。
慣れた仕事を辞めてまで敢えて奉仕職に就いた、あのときの思いを忘れていないか。
丁寧に暮らそう。と思った。