昨年は人生でファッションに一番お金をかけた年であった。それ以前があまりにも貧相な格好でそのギャップが大きかったために、服装に関してコメントされることが多かった。
しかし、今年は新しい服や靴などを買っても、コメントをもらうことがなくなった。それはある意味、僕に対するファッションに関するランク付けが固定されたということだと思う。つまり、この人はこういったレベルの身なりをしているというイメージが定着したということである。
プラスのコメントをもらえないのは残念だが、そもそもファッションというのは自分が着て満足すればいい。だから、他人の評価を基準に買っても意味がない。自分が好きな物を買い続けて、僕自身のスタイルを築いていけばいいのだ。
まあ、取り敢えず1ランクレベルが上がったことは確かだろう。これから先はそのレベルを維持しつつ、さらに上のレベルを目指してファッションセンスを上げていけばいいのかと思う。
基本的にいい服は高い。でも、いい服だからって僕に似合うわけではない。対費用効果を考えて、いつも小奇麗に、僕らしい服装をしていけばいいのだと思う。
どちらにしろ、いくら服の数を増やしたからといって、それに比例して僕自身が幸せを感じられるわけではない。物の数と幸せの大きさは比例しない。自分がこれが欲しいなと思ったものを、自分が本当に欲しい時に買えれば、これ以上の幸福はないのではないだろうかと思う。
僕が他人を見ていて気付いたのは、貧乏な人の家ほど物が多く、金持ちの家ほど物が少ないという事実である。恐らく貧乏な人は物が多いほど豊かだと錯覚しており、安いものばかりを買い揃える。結果、安いから大切に使わずにすぐ壊れ、物を大事に使うという教えを学ばずに育つ。
金持ちな人は、豊かさとは物の数ではなく、質の高いその物がもたらす利益を重視する。だから、高くても品質が良い物を買い、大事に使うので思い入れも強くなり、結果として物の数字体は少なくても豊かな生活が送れる。
「安物買いの銭失い」とはよく言ったもので、このようなお金に関する考え方に基づけば、貧乏人はいつまで経っても貧乏で、金持ちはさらにお金持ちになっていく。
貧乏人はお金のために働くが、金持ちは働いた結果の報酬としてお金をもらう。お金と仕事の間の授受行為自体は同じだが、それぞれの人の精神構造はまったく逆である。
貧乏人は一生働かなければならない。ワーキングプアとは言いえて妙である。もちろん、ワーキングプアを生み出すような日本の社会制度が間違っていることは確かだ。でも、ブルーワーカーとして人に使われ、消費社会に踊らされて、あまり必要でないものまで買って、一時的な幸せに固執したのだから、責任は本人にある。お金を使い切るのに頭を使う必要はないが、増やすのは大変である。
世の中を生きていく中で、必要な物質的なものは衣・食・住の3つ。あとは、健康、家族、愛する対象、仕事。物質的なものは欲を出せばきりがない。でも、3つともあるのであれば、それで満足すべきだ。
服を買うのはいい。新しい服を着ると気分も爽快だ。でも、何でも限度が必要である。「少欲知足」。欲を少なくして、足るを知る。何でも適度がいいのだ。
しかし、今年は新しい服や靴などを買っても、コメントをもらうことがなくなった。それはある意味、僕に対するファッションに関するランク付けが固定されたということだと思う。つまり、この人はこういったレベルの身なりをしているというイメージが定着したということである。
プラスのコメントをもらえないのは残念だが、そもそもファッションというのは自分が着て満足すればいい。だから、他人の評価を基準に買っても意味がない。自分が好きな物を買い続けて、僕自身のスタイルを築いていけばいいのだ。
まあ、取り敢えず1ランクレベルが上がったことは確かだろう。これから先はそのレベルを維持しつつ、さらに上のレベルを目指してファッションセンスを上げていけばいいのかと思う。
基本的にいい服は高い。でも、いい服だからって僕に似合うわけではない。対費用効果を考えて、いつも小奇麗に、僕らしい服装をしていけばいいのだと思う。
どちらにしろ、いくら服の数を増やしたからといって、それに比例して僕自身が幸せを感じられるわけではない。物の数と幸せの大きさは比例しない。自分がこれが欲しいなと思ったものを、自分が本当に欲しい時に買えれば、これ以上の幸福はないのではないだろうかと思う。
僕が他人を見ていて気付いたのは、貧乏な人の家ほど物が多く、金持ちの家ほど物が少ないという事実である。恐らく貧乏な人は物が多いほど豊かだと錯覚しており、安いものばかりを買い揃える。結果、安いから大切に使わずにすぐ壊れ、物を大事に使うという教えを学ばずに育つ。
金持ちな人は、豊かさとは物の数ではなく、質の高いその物がもたらす利益を重視する。だから、高くても品質が良い物を買い、大事に使うので思い入れも強くなり、結果として物の数字体は少なくても豊かな生活が送れる。
「安物買いの銭失い」とはよく言ったもので、このようなお金に関する考え方に基づけば、貧乏人はいつまで経っても貧乏で、金持ちはさらにお金持ちになっていく。
貧乏人はお金のために働くが、金持ちは働いた結果の報酬としてお金をもらう。お金と仕事の間の授受行為自体は同じだが、それぞれの人の精神構造はまったく逆である。
貧乏人は一生働かなければならない。ワーキングプアとは言いえて妙である。もちろん、ワーキングプアを生み出すような日本の社会制度が間違っていることは確かだ。でも、ブルーワーカーとして人に使われ、消費社会に踊らされて、あまり必要でないものまで買って、一時的な幸せに固執したのだから、責任は本人にある。お金を使い切るのに頭を使う必要はないが、増やすのは大変である。
世の中を生きていく中で、必要な物質的なものは衣・食・住の3つ。あとは、健康、家族、愛する対象、仕事。物質的なものは欲を出せばきりがない。でも、3つともあるのであれば、それで満足すべきだ。
服を買うのはいい。新しい服を着ると気分も爽快だ。でも、何でも限度が必要である。「少欲知足」。欲を少なくして、足るを知る。何でも適度がいいのだ。










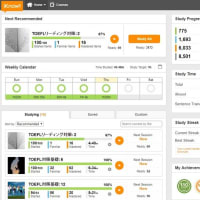



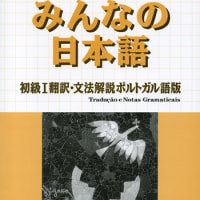
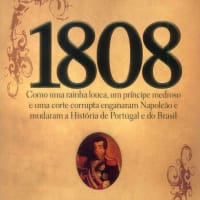
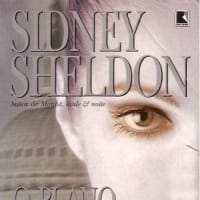



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます