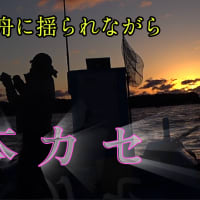君子は蓋(けだ)し闕如(けつじょ)たり
「子路 曰(い)わく、衛君(えいくん) 子を待ちて政を為さば、子 将に奚(なに)をか先にせんとする、と。子 曰(のたま)わく、必ずや名を正さんか、と。子路 曰(い)わく、是れ有るかな、子の迂(う)なるや。奚(いずくん)ぞ其れ正さん、と。子 曰(のたま)わく、野(や)なるかな、由や。君子〔教養人〕は其の知らざる所に於いては、蓋し闕如たり。名 正しからざれば、則ち言順(げんじゅん)ならず。言順ならざれば、則ち事成らず。事成らざれば、則ち礼楽(れいらく)興(おこ)らず。礼楽興らざれば、則ち刑罰中(あ)たらず。刑罰中たらざれば、則ち民 手足を錯(お)く所無し。故に君子〔教養人〕 之を名づくれば、必ず言う可(べ)し。之を言えば、必ず行なう可し。君子〔教養人〕は其の言に於いて、苟(いやし)くもする所無きのみ、と。」
■その意味は?
子路が尋ねた。
『衛国の国君が、先生を礼遇して政治を委ねられるとしますならば、先生は何から手をつけようとなされますか。』と。
孔子(先生)が答えられた。
『決まっている。名〔文字・記号〕を正すことだ。』と。
子路はさらに尋ねた。
『それですよ。先生のお考えは現実離れしています。どうして名を正すなどという〔悠長な〕ことでいいものですか。』と。
孔子(先生)が答えられた。
『現実的すぎるぞ、由〔子路〕よ。教養人たる者は、自分がよく知らないことについては、知らないままにすることだ。〔もし〕名〔文字・記号〕が正しくなければ、言〔ことば・筋・論理〕が妥当でない。言が妥当でないと、政事〔政治〕が達成されない。政事が達成されないと、礼楽〔規範・道徳〕が盛んとならない。礼楽が盛んとならないと〔むやみに処罰するばかりで行きすぎとなり〕、刑罰が当(とう)を得なくなる。刑罰が当を得なくなると、民は不安でゆっくりと手足を伸ばして安らかに暮らすことができなくなる。だからこそ、教養人は、〔正しく〕名づければ、主張〔言〕の筋を通すことができ、それができると政事〔が完成し、道徳が守られ妥当な刑罰を行なうこと〕ができる。〔このような関連があるのだから、由よ、教養人たる者は〕その発言においては、〔知らないことは知らないままにしておき〕軽はずみであってはならない。』と。
(加地伸行全訳注「論語」より)
■感想
普段、我々現代人が当然の如く用いる文字や言語というものには、 "本質=成り立ち" というものがある。その "本質=成り立ち" を知る〔感じる〕ことで、発する言葉にもより深みが増すものといえる。