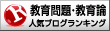われら、かの西山に登り薇をとる
世は暴をもって暴にかえ
その非を知らない
神農よ、虞(舜)よ、夏(禹)よ
これら聖人は、いまどこにもいない
どこに行けばよいのだ
ああ、ゆこう、命も衰えた
世は暴をもって暴にかえ
その非を知らない
神農よ、虞(舜)よ、夏(禹)よ
これら聖人は、いまどこにもいない
どこに行けばよいのだ
ああ、ゆこう、命も衰えた
この詩は、支那の古代歴史書『史記』に記されたもので、今から三千年以上もの昔、伯夷(はくい)・叔斉(しゅくせい)兄弟が辞世の詩として遺されたといわれている。
時は、暴君で名高い、殷(いん)の紂(ちゅう)王が天子となり世を治めていた時代で、人々は皆、殷の都を目指さずに、殷王朝の三公のひとり、西伯(さいはく)が治める周の国を目指していた。
このことに違和感を感じた兄弟は、 "民の心" が天子ではなく、その臣にすぎない西伯にあることを憂いていた。
「バカな!天子である紂王よりも、西伯に民心が寄せられているなど、あってはならないことだ」と。
なんにせよ、暴政を振るう天子の下では、民が心穏やかではなかったのだ。
そんな最中、周の国では西伯が死に、跡を継いだ発(武王)の下に、「紂王討て」の要望が次々に寄せられてきた。
しかし武王は、「天命はどこに帰するか、いまだわからぬ。」といって、なかなか起ちあがろうとはしなかった。
その内に、天子に対する民の心が、疑念から恐怖へと変わったことを知った武王は、ようやく発起することを決意し、殷の都へ兵を伴い出陣するのだった。
その道中、行軍する武王の下へと近づき、「父(西伯)が死んで葬らないうちに戦争をする、これを "孝" といえますか。臣の身で君主を殺そうとする、これで "仁" といえますか。」と、言いだす者が現れた。
伯夷と叔斉の兄弟である。
これに怒った武王の臣下は、兄弟ふたりを殺そうとするが、すかさず武王が臣下をおさえ、「殺すな。その者たちは "義人" である。」と命じるのだった。
やがて戦は武王が勝利することで、新たな天子となり、「天命は武王を選んだ」と囁かれるようになった。しかし、兄弟ふたりは、「誰がそれを決めたのか?」といって新しき天子を認めようとはしなかった。
しかし兄弟は
「天が殷を見棄てたのなら、殷の自滅を待つべきではなかったのか?しかし、殷の自滅を待っておれば、人民の苦しみがそれだけ長びくことになる。だが、 "義" はどうなるか。」
といった心の葛藤に苦しめられる日々を送る。
「天が殷を見棄てたのなら、殷の自滅を待つべきではなかったのか?しかし、殷の自滅を待っておれば、人民の苦しみがそれだけ長びくことになる。だが、 "義" はどうなるか。」
といった心の葛藤に苦しめられる日々を送る。
そして最後は
義のため、周の粟を食わず、首尾山にかくれ薇を採って之を食う。
といって、ふたりは周の国に仕えることをやめ、首尾山に篭ることを決意し、その後、ふたりが首尾山で、臨終の際に、辞世の詩として詠まれたのが、冒頭の詩である。
一方、『史記』の著者である司馬遷が、この詩を記した意図として、伯夷・叔斉に対する慈しみの気持ちが大きかったのではないか、と。
さらには、「ああ、ゆこう、命も衰えた」の、最後の一文に、伯夷・叔斉ふたりの、 "義の人" として、最期を迎えることの喜びが込められているようにも思えるのである。
"義に生きる" 喜び・・・
こうした詩が、語り継がれることの意味というものを、深く噛みしめてみたいですね
義のため、周の粟を食わず、首尾山にかくれ薇を採って之を食う。
といって、ふたりは周の国に仕えることをやめ、首尾山に篭ることを決意し、その後、ふたりが首尾山で、臨終の際に、辞世の詩として詠まれたのが、冒頭の詩である。
一方、『史記』の著者である司馬遷が、この詩を記した意図として、伯夷・叔斉に対する慈しみの気持ちが大きかったのではないか、と。
さらには、「ああ、ゆこう、命も衰えた」の、最後の一文に、伯夷・叔斉ふたりの、 "義の人" として、最期を迎えることの喜びが込められているようにも思えるのである。
"義に生きる" 喜び・・・
こうした詩が、語り継がれることの意味というものを、深く噛みしめてみたいですね
(●´ω`●)
【史記】伯夷と叔斉 義に生きる 【[History] Hakuju and Unsei live righteously】