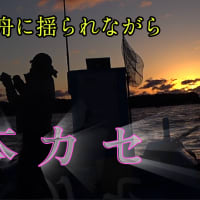わが国でも過去、「徳」なき時代はありました。
それは中央集権国家以前の、豪族が各地で覇を唱えていた時代であります。飛鳥時代前期には豪族が多数在り、現在でいうところの条例のようなものを豪族が制定し地域を支配していました。
そして支配するためには「力」が必要と考え、軍事力や政治力を強化するようになっていきました。そして他の豪族と争うことで、有力豪族が生き残る・・・。
ん?このような事は世界の至るところで聞く話しだと思わないでしょうか…?。
わが国もかつては、闘争に明け暮れるような時代があったのです。
このような闘争が絶えない理由には、これら豪族には「力」はあっても「徳」を持ち合わせていなかったからだと感じています。
そして、やがて豪族たちは、五殻豊穣を願うことで国民からの信を獲ていた皇室を利用しようと模索しはじめたのだと想像できます。
しかし、そのような豪族の思惑や乱れの中、わが国は巨大国家支那に呑まれようとしていましたが、のちに有力豪族・蘇我氏や推古天皇の台頭で聖徳太子が摂政となり、巨大国家に対抗できる国作りのために皇家を中心とした中央集権国家を樹立しようと模索することになります。
この時太子は、「力」の支配ではなく、「徳」による支配を重視されました。"聖徳太子"と云われる所以であります。
豪族にも「力」よりも「徳」を心掛けるよう説かれ、そして生まれたのが「冠位十二階」です。
十二の位は、豪族だけでなく、広く庶民からも出世出来る仕組みをとり、太子は世界で初めての民主主義憲法を制定し、さらなる中央集権国家への枠組みを作りはじめました。
ここに官民関係なく、日本人全て平等の精神、「和」の精神を樹立したのであります。
教育勅語の全文は明治期に、聖徳太子以前と以後のわが国の歴史などを深く考え、分りやすく書かれています。そして西洋一辺倒の流れを喰い止めることが出来ました。
経済力や科学力や軍事力一辺倒ではなく、さらに踏み込んで「徳」を重視することが大切であると考えた明治天皇…。
「徳」を身につけた者同士が集まり、さらに経済や科学を學び、国益に叶う議論をすることが本当の意味での「和」であると私は考えます。「力」のみの議論では豪族たちのように争うことしか出来ず、いずれ亡国への道を歩むことになるでしょう。
神武天皇から聖徳太子へ
聖徳太子から明治天皇へ
明治天皇から我々現代人へ…。
教育勅語を深く読むことで、永きに渡る日本の歴史を垣間見ることが出来るのは、まこと不思議なことであります。
それは中央集権国家以前の、豪族が各地で覇を唱えていた時代であります。飛鳥時代前期には豪族が多数在り、現在でいうところの条例のようなものを豪族が制定し地域を支配していました。
そして支配するためには「力」が必要と考え、軍事力や政治力を強化するようになっていきました。そして他の豪族と争うことで、有力豪族が生き残る・・・。
ん?このような事は世界の至るところで聞く話しだと思わないでしょうか…?。
わが国もかつては、闘争に明け暮れるような時代があったのです。
このような闘争が絶えない理由には、これら豪族には「力」はあっても「徳」を持ち合わせていなかったからだと感じています。
そして、やがて豪族たちは、五殻豊穣を願うことで国民からの信を獲ていた皇室を利用しようと模索しはじめたのだと想像できます。
しかし、そのような豪族の思惑や乱れの中、わが国は巨大国家支那に呑まれようとしていましたが、のちに有力豪族・蘇我氏や推古天皇の台頭で聖徳太子が摂政となり、巨大国家に対抗できる国作りのために皇家を中心とした中央集権国家を樹立しようと模索することになります。
この時太子は、「力」の支配ではなく、「徳」による支配を重視されました。"聖徳太子"と云われる所以であります。
豪族にも「力」よりも「徳」を心掛けるよう説かれ、そして生まれたのが「冠位十二階」です。
十二の位は、豪族だけでなく、広く庶民からも出世出来る仕組みをとり、太子は世界で初めての民主主義憲法を制定し、さらなる中央集権国家への枠組みを作りはじめました。
ここに官民関係なく、日本人全て平等の精神、「和」の精神を樹立したのであります。
教育勅語の全文は明治期に、聖徳太子以前と以後のわが国の歴史などを深く考え、分りやすく書かれています。そして西洋一辺倒の流れを喰い止めることが出来ました。
経済力や科学力や軍事力一辺倒ではなく、さらに踏み込んで「徳」を重視することが大切であると考えた明治天皇…。
「徳」を身につけた者同士が集まり、さらに経済や科学を學び、国益に叶う議論をすることが本当の意味での「和」であると私は考えます。「力」のみの議論では豪族たちのように争うことしか出来ず、いずれ亡国への道を歩むことになるでしょう。
神武天皇から聖徳太子へ
聖徳太子から明治天皇へ
明治天皇から我々現代人へ…。
教育勅語を深く読むことで、永きに渡る日本の歴史を垣間見ることが出来るのは、まこと不思議なことであります。
◇【聖徳太子】から学ぶ日本の心
[GREE日記 皇紀:2674年1月20日より]