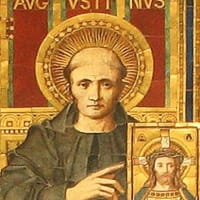『絶対主義の盛衰 世界の歴史9』社会思想社、1974年
4 イギリスの王政復古から名誉革命へ
1 チャールズ二世の帰国
イギリスでは護国卿オリバー・クロンウェルの死(一六五八)後、事態は共和制から王政復古にむかった。
一六六〇年五月二十五日、たくさんの人びとがドーバーの海岸に集まっていた。帰ってくるチャールズ二世(在位一六六〇~八五)を一目でも見るためである。
船から下りたった王の肉欲的な厚い唇、頑丈な鼻、人を茶化すような目は、今までのピューリタンになれていた国民感覚には、まったくそぐわないものであった。
チャールズは国王軍の敗北後大陸に走り、一六五〇年スコットランドからイギリスに侵入することに失敗してからは、王政復古まで亡命をつづけた。
彼は放縦な生活をおくり、オランダで若い女と関係して一人の庶子をもうけ、これをモンマス公(一六四九~八五)に叙した。のちのモンマスの乱の主人公である。
亡命中チャールズを忠実に補佐したのが、バイト(のちのクラレンドン伯、一六○九~七四)で、一六五八年大法官の称号をあたえられた。
チャールズの帰国前、イギリスでは四月に選挙が行なわれ、暫定議会が召集された。新議員には国王派や長老派が多く、九〇パーセントは、王の復位を支持していたといわれる。
この議会に対して、王の使者が復位のための条件を提示した。
これが「プレダの宣言」で、バイトの筆になり、王がオランダの同市で声明したものである。
この宣言はピューリタン革命中の行動に対する大赦、土地購入者の権利、信仰の自由の三点を確認し、しかも絶対君主の復活ではなく、王と議会という伝統的体制の復活を約束していた。
そこで議会はただちに宣言の受諾を決定し、王のイギリス上陸が実現したわけである。
復位した王は、三つの約束に忠実であったろうか。
大赦については、主としてチャールズ一世の裁判に参加したものが除外され、十三名が処刑された。
クロンウェルの墓が十二年目にあばかれて、遺体を刑場につるしたのち、首をウェストミンスター・ホールでさらしものにした。
革命中に没収された王や教会の土地は、もとにかえった。
国王派で土地を没収されたものは特別の請願もしくは普通の訴訟で、これをとりもどす権利をあたえられた。
しかし自発的に土地を売り払ったものには、補償がなかった。
土地をえた側では長老派は国王派が売り払った土地を手に入れていたので、所有権をみとめられた。
ところが独立派は王や教会の没収地を購入したので、無償で土地を旧所有者にかえさなけれぜならず、大打撃をうけた。
宗教問題では、王政復古に大きい役割を果たした長老派が期待をよせたが、王は彼らをイギリス国教会のなかへ包括しようとした。
しかし一六六一年五月ひらかれた議会は「騎士議会」とあだ名されたことからもわかるように、長老派が減少して国王派が大多数を占め、ピューリタンに竍する弾圧立法を行なった。
第一の「都市自治体法」(一六六一)は、「イギリス国教会の儀式にしたがって聖餐(せいさん)の聖礼典をうけないものは、都市の公職に任命もしくは選出されない」と規定している。
都市が、ピューリタンの勢力の中心であったからである。
第二の「礼拝統一法」(一六六二)によって、ピューリタニズムを国教とすることには終止符がうたれた。
すべての聖職者や教師に、国教の一般祈祷書の使用が命ぜられ、約二千名の聖職者が追放された。
第三の「宗教集合法」(一六六四)は、同一家族に属しない五名以上のものが、イギリス国教会の方式によらない宗教上の集会に出席することを禁止し、累犯(るいはん)者を七年間植民地に追放することにした。
最後に「五マイル法」(一六六五)が制定され、「本王国の法律に違反して非合法な宗教集会において説教しようとするものは、従来、牧師、副牧師、牧師補であった都市の五マイル以内にきてはならない」ことになった。
これは彼らを、支持者である大衆から隔離するものである。