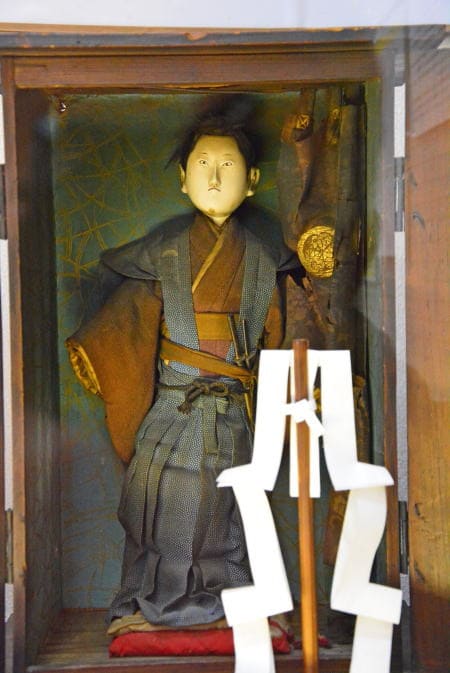本記事は自ホームページの旧記事をブログ用にリメイクしたものである
(2020/02/24 初回アップ、2023/05/29 再度アップ)。
5月10日は鳥海山に向かってみた。
いつもなら秋田市から向かうところだが、この日は横手市の実家からスタート。
ここから春には真っ白な富士山型の鳥海山が見える。
個人的にまだ登山しないが、もっと肉薄したくて南西方向に向かって走る。
湯沢市郊外から望んだ鳥海山。
ところが、いざ鳥海山に向かって進むと、前山に遮られてさっぱり見えなくなってしまう。
こちらは山形県境にある丁(ひのと)岳。
再びその姿を拝めるのは、旧・鳥海町の限られた場所だけになる。
笹子(じねご)峠より望んだ鳥海山。 


前山の沢筋に雪が残っているが、ブナの新緑はもう始まっている。
カタクリ群生地は成熟モードに達していた。
標高約400mの百宅(ももやけ)地区まで来ると、鳥海山は覆いかぶさるようにでかくなる。

この地では平地にもまだ雪が残っている

が、用水路の縁に早くも咲きだしているものがあった。
左側であちらを向いてるのがザゼンソウ。真ん中より右側がミズバショウ。
秋田ではミズバショウとザゼンソウは滅多に混生しない。
どちらかと言えば、ザゼンソウはミズバショウよりも乾き気味のところに多い。
ここのミズバショウは葉の赤いのがあってザゼンソウの苞と紛らわしかった。
ザゼンソウ
ザゼンソウ 

ミズバショウ
ミズバショウ

リュウキンカ
リュウキンカも含め、三種類が一緒に混じって咲くというのは珍しい。
キクザキイチゲは芽だしの真っ最中。ご覧のように咲きながら生長する。


ここには濃色のタイプが多かった。
先のミズバショウやザゼンソウの隣、やや乾いた場所に咲いていた。
これは 
アズマシロカネソウという小さな小さなキンポウゲ科。

丈は10センチに満たず、花も5ミリくらいととても小さく地味だが、葉が黄色っぽいので割と見つけやすい。
先のミズバショウ、ザゼンソウ、リュウキンカのすぐ近くの沢、水しぶきを浴びるような場所で咲いていた。
ここ百宅の地はやがてダム湖の底に沈む(※)。
当然だが、花たちも・・・。

百宅(ももやけ)地区の隣、猿倉地区からは富士山型の鳥海山の全体像が眺められる。
以上。
【追記】
2023年5月30日付の秋田魁新記事によると、
鳥海ダムは当初2028年完成の予定だったが、四年延長し、2032年度の完成をめざすと方針が変更になったとのこと。