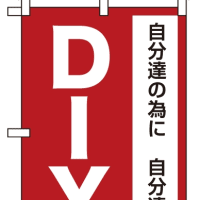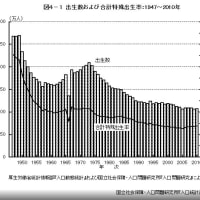これまで、ビルマと日本の歴史的な関わりについて明らかにするために、特に、アウン・サンと鈴木敬司・南機関の動きを中心に、ビルマが独立を達成するまでの流れについて説明を試みた。あくまでも、ビルマ独立の歴史に日本が深く関わっていることを伝えることが主旨であり、その是非について問うものではない。
だが、アウン・サンらは、日本政府や日本軍の対応に不満を抱き、結果的に反乱を起こしていることからしても、こうした日本の関わりはビルマにとって負の面が大きいのは否定できない事実であろう。スー・チーもアウン・サンの伝記の中で「日本による占領の物語は、幻滅と疑惑と苦痛の物語である…多くの人々は日本の兵士を解放者として歓迎していたが、その正体は、評判の悪かったイギリス人以上に悪質な圧政者だった」と述べている。
しかし、そんな中でも、少なくともアウン・サンら30人の志士にとって、鈴木敬司を始めとする南機関の日本人隊員がとった態度や行動については、評価できる部分も少なくないと言っても間違いないようである。結果として、鈴木敬司がアウン・サンらに約束した独立は果たされなかったが、鈴木敬司らは、軍上層部に何度も直談判し、時には命令に素直に従わずに、独立を実現しようとしたのである。
こうした、与えられた任務や命令の枠を超えた行動に鈴木敬司らを駆り立てたものは一体何か。今となっては関係資料から推測する他ないが、最も重要なのは、鈴木敬司らが目の当たりにした、アウン・サンらの独立に対する強靭な意志と行動力だったのでないか。もちろん、特に鈴木敬司にとっては、最初に独立の支援を約束してしまった以上、面目にかけても実現しなければならないという思いはあっただろう。しかし、そうした体裁を気にしての行動だけであれば、次第に不満が募っていった「30人の志士」らを従わせることは出来なかったのではないか。極秘の南機関の隊員として海南島での過酷な訓練等を共に行ううちに、言葉や文化、指導教官と訓練生という違いを乗り越えた、互いを同志として認めあう感情を共有するに至ったと言っても過言ではないのではないか。
実際、志士の一人であったボ・ミンガウンによれば、日本軍に対するBIAの不穏の動きについて問い質した鈴木敬司に対し、アウン・サンは、鈴木敬司がビルマにいる限り絶対に日本軍に反乱は起こさないと誓ったという。また、日本軍への武装蜂起を開始するにあたり、アウン・サンは元南機関員の救命を各部隊に指示し、そのお陰で、ビルマに唯一残っていた元南機関員の高橋八郎中尉は身柄を保護され、戦後、日本に無事帰還している。更には、日本軍への反乱に際し、志士の一人のミン・オンは、日本人への義に反するとして自決したと言われている。
こうした南機関とビルマの関わりは、アウン・サンの死で終わったわけではない。アウン・サンと共に闘った30人の志士の一人で、ウー・ヌ政権下の49年1月に軍の最高司令官に就任したネ・ウィンは、62年3月にクーデターを起こし、それから26年後の88年7月に民主化要求デモを受けて辞任するまで政権を握り続けた。そのネ・ウィンの辞任から約1か月後の8月、大集会で演説を行い、反政府運動のデビューを果たしたのがアウン・サンの娘のスー・チーだったというのは、歴史的な巡り合わせという他ないだろう。
そのデビューから2年ほど遡った86年4月。前述のように、当時、京都大学の研究員だったスー・チーは、浜名湖畔の旅館「小松屋」を訪れた。もちろん、父アウン・サンの足跡を辿るためである。その「小松屋」は既に無いが、同じくスー・チーが訪れた「ビルマゆかりの碑」(74年5月建立)は、今もなお、浜名湖畔の大草山で、アウン・サンと鈴木敬司が共に行動したことを記し続けている。


※大草山から浜名湖を望む石碑(2012年1月撮影)
地理的には必ずしも日本と近くはないビルマ/ミャンマー。しかし、歴史的には、様々な意味で日本はビルマと深い関わりがあり、今のミャンマーについて考える際、そのことを常に念頭に入れておくことが不可欠だろう。
(完)※敬称略
※この原稿は、私が榛葉賀津也・参議院議員の政策秘書時代(2009年3月)に書いたものです。

※スー・チー氏来日を報じる記事。鈴木敬司氏のご子息である鈴木邦幹氏の言葉も載っています(2013年4月14日静岡新聞)。
お読み下さり、ありがとうございます。