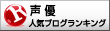以前、といってもかなり以前のことになりますが、私はモータースポーツライターをしていました。
そのことをいずれ書きます、と言っていましたので、今回と次回の記事でそれに関して触れます。
それには、ブログテーマのアルファロメオを少し離れて、フェラーリの話をしなければなりません。
なぜなら、私がわずか3年間の短い期間でしたが、モータースポーツジャーナリズムの世界に関わったのも…
スクーデリア・フェラーリがあってこそのことだったからです。

といってもアルファロメオとフェラーリには、切っても切れない関係というか、深い因縁があります。
フェラーリの創業者で、生前はレース部門でも、市販車製造部門でも絶対的権力を握っていた、エンツォ・フェラーリ。
彼は若いころアルファロメオのワークスレーシングチーム「アルファコルセ」のドライバーでした。

ハンドルを握っているのがエンツォ。彼の後ろの燃料タンクに「Alfa」と書いてあるのに注目です。
その後ドライバーからチームマネジャーになったエンツォは、アルファコルセを率いて数々の勝利を収めます。
エースドライバー、アントニオ・アスカーリの事故死をきっかけに、アルファコルセがレース活動から撤退すると…
エンツォは、アルファのセミ・ワークスチーム「スクーデリア・フェラーリ」を立ち上げて、ここでも成功します。

アルファのエンブレムとスクーデリア・フェラーリの紋章が同居しているところにご注目。
名エンジニア、ヴィットリオ・ヤーノと、名監督エンツォ・フェラーリ、そして…
伝説のレーサー、タツィオ・ヌヴォラーリら、最強のドライバー陣をそろえたアルファロメオのマシンは…
戦前のモータースポーツシーンで、まさに無双を極めました。
しかし1938年にアルファコルセがワークスチームとしてレースに復帰すると、翌年…
エンツォは会社の経営陣と対立し、チームを追われることになってしまいます。
しかもその後4年間は、アルファのイメージが付いた「スクーデリア・フェラーリ」という名前を…
いずれの場合においても、使ってはならないという屈辱的な誓約書まで書かされます。
アルファロメオへの復讐を誓ったエンツォは1940年、オリジナルのレーシングマシン、ティーポ815を製造…
ミッレミリアに参戦しますが成績は振るわず、第二次大戦の激化とともに、モータースポーツも事実上休止状態になります。
戦後、モータースポーツ再開に伴い、1947年にスクーデリア・フェラーリを再開させ、同時に…
自動車製造会社としてのフェラーリを設立します。
ただ当初、市販車製造部門は、エンツォにとってあくまでも、レース資金を稼ぐためのものでした。
当時、欧州のレース界では、ヨーロッパ選手権として1947年、新たに「F1レギュレーション」が導入されて始まったグランプリレースで…
アルファロメオ「ティーポ158」が3年間に渡って全戦無敗という、向かうところ敵なしの状況が続いていました。
1950年、初めて「F1世界選手権」として新たにスタートしたグランプリシリーズも…
アルファのティーポ158が全戦でポールポジション、ファステストラップ、優勝を独占するという圧勝に終わり…

スクーデリア・フェラーリがこのシーズンに投入した「125F1」は惨敗の結果となりました
捲土重来を期すフェラーリは、翌1951年には改良を重ねた「275F1」「340F1」を次々投入。

パワーでは、このシーズンのアルファの改良型マシン、ティーポ159Bに劣ったものの…
燃費でアドバンテージがあったため、給油のためのピットストップを減らせるというメリットがありました。
そしてこの年のF1第5戦、シルバーストーンサーキットで行われたイギリスグランプリで…
フロイラン・ゴンザレスの駆る「340F1」が、フェラーリにとって記念すべき、F1初勝利をもたらしました。

感極まって涙するエンツォ・フェラーリはこのときに、伝説的な…
「私は自分の母親を殺してしまった」
という言葉を口にしたと言われています。
スクーデリア・フェラーリは、アルファロメオを母体として、それを乗り越えるために生まれたチームであり…
エンツォのこの言葉は、まさに的を射たものだったといえるでしょう。
このシーズンは、結局アルファコルセの、F・M・ファンジオが年間チャンピオンドライバーになり…
そして生産者部門のコンストラクターズタイトルも、アルファロメオの手に渡りましたが…
アルファコルセは、本社の経営難から来る資金繰りの悪化で、この年を限りにF1GPから撤退しました。
一方スクーデリア・フェラーリは、現在まで一度も中断することなくF1世界選手権に参戦し続けている、唯一のチームとなっています。
こうした因縁を持っているフェラーリ。
そして、モータースポーツの世界で戦後最大のレジェンドとなっている、フェラーリ。
その歴史……というか、エンツォを含め、スクーデリア・フェラーリに関わった人々の、人物群像を描く…
雑誌連載の、取材と執筆をやってくれないか、というお話が私のところに来たのは、2003年の秋でした。
オファーしてくれたのは、私が、かつて週刊誌で働いていた頃の上司。
彼は「スポーツと人間」を扱う新しい月刊誌『VS. バーサス』という雑誌を創刊する準備をしていました。

そして、モータースポーツに関する長期連載のテーマとして…
当時M・シューマッハを擁して、何度目かの黄金時代を迎えていた…
スクーデリア・フェラーリを巡る、人物群像を掲載することを考えていました。
ただ雑誌のコンセプトとして資料や書き手の知識に頼るのではなく、あくまでも生の取材優先で…
取材者の足音と、対象者の「本音の声」が聞けるような記事、というものを求めていました。
私が若いころモータースポーツを自分でもやっていて、しかもイタリア語ができるライターということで…
白羽の矢を立ててくれた、ということのようです。
良い連載にするため、まる1年間の調査及び現場取材の時間と、潤沢な取材費を与えてくれるという好条件でした。
紙媒体が、スポンサーもなく海外取材をさせてくれるなんてこと自体、今ではもうあり得ない贅沢ですが…
当時としても、ほかにちょっとないぐらいの良いお話。お受けしない手はありませんでした。
1年の取材期間のうちに、数度にわたって、イタリアとドイツへ取材のため渡航しました。
その年の、フェラーリのニューマシン「F2004」の、プレス向けプレミア発表会への参加。
モンツァ(イタリアGP)、鈴鹿(日本GP)の各サーキット現場でのパドック取材。
マラネッロのフェラーリ工場と、フィオラーノのスクーデリア本拠地での現場取材。
そして、モデナ(マラネッロ、フィオラーノ含む)、マントヴァ、ミラノ、トリノ、その他の街での…
現在生きているスクーデリア・フェラーリ関係者や、既に故人となった関係者の家族への直接インタビュー。
現地のモータースポーツ史研究家などへの取材、文献資料集め、写真撮影(現地カメラマン同行)、などなどでした。
連載は、創刊第2号から11回にわたって同誌に掲載されました。

この連載が好評だったため、以後も同誌が休刊になるまでの数年間、私がモータースポーツ記事の取材・執筆を担当しました。
雑誌のメインスポンサーのひとつが日産自動車だったために、「NISMO」関係の取材が多かったです。
あとは、ブリヂストンタイヤの開発現場とか。
車とレースが大好きなので、これは今までしてきたあらゆる仕事の中でも、一番楽しかった物のひとつです。
次回の記事では、この取材でのこぼれ話をしたいと思います。