今朝の読売新聞の社会面に
司法修習生「給費制」復活
という記事がありました。
2011年に廃止されたこの制度の復活。
背景には「深刻な法曹離れ」があるとのことです。
医者のインターン制度も同じことが言われます。
研修医の給料では生活できない…。
でも、医師や弁護士はその後の所得は圧倒的に多い。
特に法曹の給費制は税金から賄われるため、批判も多かったようです。
しかしながら…。
このままでは富裕層しか法曹になれなくなる…。
そのような危機感から復活となったようです。
税理士試験の受験人数が激減していることといい、
法曹離れに拍車がかかっていることといい…。
今の時代、「一定の苦労をすること」に魅力がないのかもしれません。
モラトリアム期間。
これがどんどん長くなっている?
今、国家資格は、岐路に立っているのかもしれません。
金銭的な問題を解決するとか、問題を易しくして合格率を上げるとか、
そんな表面的な対応だけをしていては、「質」が下がるように思います。
今の時代に合わせて、「質」を確保しながら、改革していくことが必要なのではないかと思います。
しかし…。
どんな改革が必要なのか?
大変難しい…。
私見ですが、
「子供のころからの教育」と「若い人の働く意欲の向上」が
カギを握っているような気がしてなりません。
司法修習生「給費制」復活
という記事がありました。
2011年に廃止されたこの制度の復活。
背景には「深刻な法曹離れ」があるとのことです。
医者のインターン制度も同じことが言われます。
研修医の給料では生活できない…。
でも、医師や弁護士はその後の所得は圧倒的に多い。
特に法曹の給費制は税金から賄われるため、批判も多かったようです。
しかしながら…。
このままでは富裕層しか法曹になれなくなる…。
そのような危機感から復活となったようです。
税理士試験の受験人数が激減していることといい、
法曹離れに拍車がかかっていることといい…。
今の時代、「一定の苦労をすること」に魅力がないのかもしれません。
モラトリアム期間。
これがどんどん長くなっている?
今、国家資格は、岐路に立っているのかもしれません。
金銭的な問題を解決するとか、問題を易しくして合格率を上げるとか、
そんな表面的な対応だけをしていては、「質」が下がるように思います。
今の時代に合わせて、「質」を確保しながら、改革していくことが必要なのではないかと思います。
しかし…。
どんな改革が必要なのか?
大変難しい…。
私見ですが、
「子供のころからの教育」と「若い人の働く意欲の向上」が
カギを握っているような気がしてなりません。















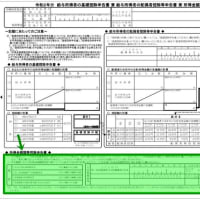
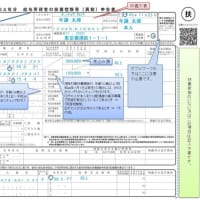









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます