*未読の方は「油彩技法、その秘訣」(2015-06-03 の記事) も読んでみて下さい。
油絵制作について具体的に言うと「常に中間の調子で描き進め、決定的な色彩にはしない」ということに尽きる。最終的な色合わせは、仕上げの段階でいいということだ。
これは皆さんお馴染みの石膏デッサンと同じ要領である。これを油絵でやればいいだけである。しかしながらこれが大変難しいのである。その難易度は極めて高い。
石膏デッサンとの決定的な違いは、油絵だと時間が経ってからその間違いに気づいても元に戻せないことである。石膏デッサンなら、間違ったところや気に入らないところを、練り消しゴムですぐに拭き取り、文字通り白紙に戻すことができるが、油絵制作ではそれができない。
確かに油絵具は乾くのが遅いので、乾く前なら容易に拭き取ることができるが、時間が経ち、指触乾燥してしまえばそれも無理である。その箇所を削り取ったり、上から白などの絵具を塗って修正することはできるが、石膏デッサンのように練り消しゴムで完全に元に戻せたり、練り消しゴムを軽く叩くように押しつけるだけでその濃度を落とせたりはしない。この差が極めて大きいのである。
加えて油絵具には厚みがあるので、無理やり削り取ってしまうと、そこだけ厚みがなくなり凹んでしまう。これは厚塗りはもちろんのこと、薄塗りでも人間の目には正確にわかってしまい、そこだけ厚みを戻そうとしても、不自然に見える結果になりがちだ。
さて話を戻すと、この「常に中間の調子で描き進める」ために、白や黒の絵具を混色して明度や彩度の上げ下げを行うわけだが、中間の調子で描き進めるには、モデリングかグレージング、またはスフマートのいずれかが必要になるからややこしくなる。
グレージングは明るい色の下地に色を薄く何層も重ねる方法。モデリングは暗い色の下地に、その暗い下地よりも明るい色で物の形を抜き出す方法。スフマートは暗い色の下地に、その暗い下地よりも明るい色を擦りつけて暈す方法。
換言すると、油絵の基本的な描き方は、画面を明るくして暗くするか、暗くして明るくするかの2つしかない。グレージングは前者で、モデリングとスフマートは後者である。
全体的に中間調で描き進めるには、こうした技法を使わないといけないので、事前に計算し、計画を立てておかないといけない。
画面のある個所をグレージングで描きたかったら、そこは明色にしておく必要があるし、画面全体をモデリングで描きたかったら、画面全体を暗色で塗っておかないといけない。「モナリザ」のように人の肌をスフマートで仕上げたかったら、そこは暗くしておく必要がある。
こうしたことを念頭に、画面全体を中間の調子で進めていくのだから、大変なのである。
話がややこしくなってしまった。要するに、油絵技法の極意とは、常に中間の調子で描き進めることで、石膏デッサンと同じ要領だということである。
平たく言えば、一気に決めず、画面全体を徐々に完成させていくということだ。当たり前の話なのだが、当たり前を当たり前のようにできれば一流なのである。そしてそれが皆なかなかできないものなのである。
付)「絵画制作記」カテゴリーの記事で、いつか油絵技法を総括したいと書きましたが、ようやくそれができてほっとしています。冒頭で触れた「油彩技法、その秘訣」と合わせて読んでもらえれば、油絵の描き方のこつを掴んだことになります。油絵の描き方を知りたい人や、油絵がうまく描けずに困っている方のお役に立てると思っております。
注)やや記事内容が雑記的になってしまい、申し訳ない。こうにしかなりませんでした。これは一重に私の文章力のなさです。できるだけ読みやすく努めたつもりですので、ご容赦を。
蛇足)私もぎこちないならがも、ようやく油絵を常に中間の調子で描き進めることができるようになりました。あとは枚数を描いてその精度を上げるだけです。がんばります。
油絵制作について具体的に言うと「常に中間の調子で描き進め、決定的な色彩にはしない」ということに尽きる。最終的な色合わせは、仕上げの段階でいいということだ。
これは皆さんお馴染みの石膏デッサンと同じ要領である。これを油絵でやればいいだけである。しかしながらこれが大変難しいのである。その難易度は極めて高い。
石膏デッサンとの決定的な違いは、油絵だと時間が経ってからその間違いに気づいても元に戻せないことである。石膏デッサンなら、間違ったところや気に入らないところを、練り消しゴムですぐに拭き取り、文字通り白紙に戻すことができるが、油絵制作ではそれができない。
確かに油絵具は乾くのが遅いので、乾く前なら容易に拭き取ることができるが、時間が経ち、指触乾燥してしまえばそれも無理である。その箇所を削り取ったり、上から白などの絵具を塗って修正することはできるが、石膏デッサンのように練り消しゴムで完全に元に戻せたり、練り消しゴムを軽く叩くように押しつけるだけでその濃度を落とせたりはしない。この差が極めて大きいのである。
加えて油絵具には厚みがあるので、無理やり削り取ってしまうと、そこだけ厚みがなくなり凹んでしまう。これは厚塗りはもちろんのこと、薄塗りでも人間の目には正確にわかってしまい、そこだけ厚みを戻そうとしても、不自然に見える結果になりがちだ。
さて話を戻すと、この「常に中間の調子で描き進める」ために、白や黒の絵具を混色して明度や彩度の上げ下げを行うわけだが、中間の調子で描き進めるには、モデリングかグレージング、またはスフマートのいずれかが必要になるからややこしくなる。
グレージングは明るい色の下地に色を薄く何層も重ねる方法。モデリングは暗い色の下地に、その暗い下地よりも明るい色で物の形を抜き出す方法。スフマートは暗い色の下地に、その暗い下地よりも明るい色を擦りつけて暈す方法。
換言すると、油絵の基本的な描き方は、画面を明るくして暗くするか、暗くして明るくするかの2つしかない。グレージングは前者で、モデリングとスフマートは後者である。
全体的に中間調で描き進めるには、こうした技法を使わないといけないので、事前に計算し、計画を立てておかないといけない。
画面のある個所をグレージングで描きたかったら、そこは明色にしておく必要があるし、画面全体をモデリングで描きたかったら、画面全体を暗色で塗っておかないといけない。「モナリザ」のように人の肌をスフマートで仕上げたかったら、そこは暗くしておく必要がある。
こうしたことを念頭に、画面全体を中間の調子で進めていくのだから、大変なのである。
話がややこしくなってしまった。要するに、油絵技法の極意とは、常に中間の調子で描き進めることで、石膏デッサンと同じ要領だということである。
平たく言えば、一気に決めず、画面全体を徐々に完成させていくということだ。当たり前の話なのだが、当たり前を当たり前のようにできれば一流なのである。そしてそれが皆なかなかできないものなのである。
付)「絵画制作記」カテゴリーの記事で、いつか油絵技法を総括したいと書きましたが、ようやくそれができてほっとしています。冒頭で触れた「油彩技法、その秘訣」と合わせて読んでもらえれば、油絵の描き方のこつを掴んだことになります。油絵の描き方を知りたい人や、油絵がうまく描けずに困っている方のお役に立てると思っております。
注)やや記事内容が雑記的になってしまい、申し訳ない。こうにしかなりませんでした。これは一重に私の文章力のなさです。できるだけ読みやすく努めたつもりですので、ご容赦を。
蛇足)私もぎこちないならがも、ようやく油絵を常に中間の調子で描き進めることができるようになりました。あとは枚数を描いてその精度を上げるだけです。がんばります。











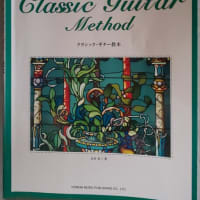





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます