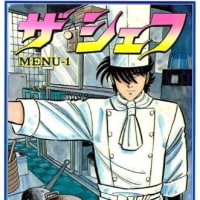最近の私個人の音楽方面での活動は、レコーディングのことで頭がいっぱい。
ユニット「時代屋」の活動は、4月中旬のライブ以後、休止中。
なので、たまには自分のユニット「時代屋」のことでも客観的に考えてみた。
音楽をやってる知り合いが、私のまわりには多い。
これまで、実際にその人たちのライブを見に行くことは、しばしばあった。
また、フォーク居酒屋などで、飛び入りで自作曲を歌うお客さんの歌を聴くことも多かった。
で、そういうのを見たり聴いたりしてると・・・
あ、この人の曲は、泉谷しげるファンが聴いたら好きになるだろうな・・とか
この人の楽曲は、中島みゆきファンが聴いたら好きになるだろうな・・とか
この人の楽曲は、拓郎ファンが聴いたら、きっと好きになるだろうな・・とか
この人の歌は、抒情派フォークが好きだった人が聴いたら、好きになるだろう・・とか
この人の音楽は、なぎらけんいちファンが聴いたら、好きになるだろうな・・とか
この人の曲はボサノバ好きが聴いたら好きになるだろうな・・とか
この人のレパートリーは、昭和歌謡が好きな人が聴いたら好きになるだろうな・・とか
この人の曲は憂歌団が好きな人が聴いたら好きになるだろうな・・とか
この人の演奏は、赤い鳥あたりが好きな人が聴いたらファンになるだろうな・・とか
この人の歌は、友部正人ファンが聴いたら気に入りそうだな・・とか
この人の歌は、井上陽水ファンが聴いたら好きになるだろうな・・とか
この人の曲は、アリスのファンが聴いたら好きになるだろうな・・とか
このグループは、PP&Mみたいな音楽が好きな人にぴったりだろうな・・とか
その他、松山千春、かぐや姫、さだまさし、長渕 剛、矢沢永吉、・・・ほか多数。
その他、その他。
そんな直感を持つことが多い。
だが・・こと、我々「時代屋」はどうなんだろう。
最近、そのへんのことが自分で掴めていないような気がしてならない。
時代屋の・・あるいは、私の曲をもしも・・もしも好きになってくれる人がいたとしたら、それはどんなミュージシャンが好きな人なんだろう。
それが分からなくなってきてる気がする。
「○○風」とか「○○スタイル」とか、そういうのではなくて。
正直・・我々「時代屋」には、アコースティックユニットとして手本とするスタイルやミュージシャンは・・いない。良くも悪くも(元々、私と相方はバンド時代から一緒にやってるし、いつベースやドラムが入ってもすぐやれるように、ギターパートだけでも作っておこう・・という考えが頭にあったからかもしれない)。
いや、この場合「悪くも」の要素のほうが強いのかもしれない。
もちろん、好きなミュージシャンや影響を受けたミュージシャンは、私にはたくさんいる。
でも、「時代屋」としては、手本としたり、目指しているユニット像は・・ない。
これでいいんだろうか。
「俺らは○○風・・と言われたくない、俺らは俺ら風なのだ」とか「俺らは独自の音楽をやっている」と、開き直ったり、突っ張ったりする人も世の中にはいるだろう。
でも、あくまでもそれは演奏側の独りよがりであるかもしれない。自己満足で終わる可能性も高い。
演奏者側の思いと、リスナー側の感じ方は微妙に違ったりもすれば、大きく異なる場合もある。
となると・・時代屋の曲は・・・だんぞうの曲は、どんなミュージシャンが好きな人になら、気に入ってもらうことができるのだろう。
そんなことを考えてしまうことがある最近の私。
「時代屋の曲、だんぞうの曲は、○○○○(←有名なミュージシャンの名前が入ります)の曲が好きな人には、気に入ってもらえるかもしれないよ。」
・・こういう表現をもらえない、あるいはそういう「例え」ができないのだとしたら、それは時代屋の・・私の楽曲の不利な点だと思うようになった。
仮に「○○風」じゃなくても、コンセプトが明確で分かりやすければ、時代屋を知ってる人が時代屋を知らない人に紹介する時、説明しやすいのではないか。
見知らぬ人に紹介してもらう時、そういう表現による「例え」、もしくは分かりやすいコンセプトがないと、不利なのではないだろうか。だいいち、紹介しづらいのでは。
ちなみに、「俺たちの音楽は、俺たちだけのスタイル」だとか「何かに例えないでくれ」などのツッパリは、今の私には無い。
この日記に書いたこと、・・実は今の「悩み」なのです。
・・って、今日のネタ、なんかネガティブな日記になってしまったかなあ。
でも・・本当は、「時代屋」というユニット名にちなんだ「楽曲の傾向」も、最近は出てきてるような気がするんだけど。
問題はそれが独りよがりになっていないかどうか・・なのです。
ちなみに写真は、数年前のもの。
ユニット「時代屋」の活動は、4月中旬のライブ以後、休止中。
なので、たまには自分のユニット「時代屋」のことでも客観的に考えてみた。
音楽をやってる知り合いが、私のまわりには多い。
これまで、実際にその人たちのライブを見に行くことは、しばしばあった。
また、フォーク居酒屋などで、飛び入りで自作曲を歌うお客さんの歌を聴くことも多かった。
で、そういうのを見たり聴いたりしてると・・・
あ、この人の曲は、泉谷しげるファンが聴いたら好きになるだろうな・・とか
この人の楽曲は、中島みゆきファンが聴いたら好きになるだろうな・・とか
この人の楽曲は、拓郎ファンが聴いたら、きっと好きになるだろうな・・とか
この人の歌は、抒情派フォークが好きだった人が聴いたら、好きになるだろう・・とか
この人の音楽は、なぎらけんいちファンが聴いたら、好きになるだろうな・・とか
この人の曲はボサノバ好きが聴いたら好きになるだろうな・・とか
この人のレパートリーは、昭和歌謡が好きな人が聴いたら好きになるだろうな・・とか
この人の曲は憂歌団が好きな人が聴いたら好きになるだろうな・・とか
この人の演奏は、赤い鳥あたりが好きな人が聴いたらファンになるだろうな・・とか
この人の歌は、友部正人ファンが聴いたら気に入りそうだな・・とか
この人の歌は、井上陽水ファンが聴いたら好きになるだろうな・・とか
この人の曲は、アリスのファンが聴いたら好きになるだろうな・・とか
このグループは、PP&Mみたいな音楽が好きな人にぴったりだろうな・・とか
その他、松山千春、かぐや姫、さだまさし、長渕 剛、矢沢永吉、・・・ほか多数。
その他、その他。
そんな直感を持つことが多い。
だが・・こと、我々「時代屋」はどうなんだろう。
最近、そのへんのことが自分で掴めていないような気がしてならない。
時代屋の・・あるいは、私の曲をもしも・・もしも好きになってくれる人がいたとしたら、それはどんなミュージシャンが好きな人なんだろう。
それが分からなくなってきてる気がする。
「○○風」とか「○○スタイル」とか、そういうのではなくて。
正直・・我々「時代屋」には、アコースティックユニットとして手本とするスタイルやミュージシャンは・・いない。良くも悪くも(元々、私と相方はバンド時代から一緒にやってるし、いつベースやドラムが入ってもすぐやれるように、ギターパートだけでも作っておこう・・という考えが頭にあったからかもしれない)。
いや、この場合「悪くも」の要素のほうが強いのかもしれない。
もちろん、好きなミュージシャンや影響を受けたミュージシャンは、私にはたくさんいる。
でも、「時代屋」としては、手本としたり、目指しているユニット像は・・ない。
これでいいんだろうか。
「俺らは○○風・・と言われたくない、俺らは俺ら風なのだ」とか「俺らは独自の音楽をやっている」と、開き直ったり、突っ張ったりする人も世の中にはいるだろう。
でも、あくまでもそれは演奏側の独りよがりであるかもしれない。自己満足で終わる可能性も高い。
演奏者側の思いと、リスナー側の感じ方は微妙に違ったりもすれば、大きく異なる場合もある。
となると・・時代屋の曲は・・・だんぞうの曲は、どんなミュージシャンが好きな人になら、気に入ってもらうことができるのだろう。
そんなことを考えてしまうことがある最近の私。
「時代屋の曲、だんぞうの曲は、○○○○(←有名なミュージシャンの名前が入ります)の曲が好きな人には、気に入ってもらえるかもしれないよ。」
・・こういう表現をもらえない、あるいはそういう「例え」ができないのだとしたら、それは時代屋の・・私の楽曲の不利な点だと思うようになった。
仮に「○○風」じゃなくても、コンセプトが明確で分かりやすければ、時代屋を知ってる人が時代屋を知らない人に紹介する時、説明しやすいのではないか。
見知らぬ人に紹介してもらう時、そういう表現による「例え」、もしくは分かりやすいコンセプトがないと、不利なのではないだろうか。だいいち、紹介しづらいのでは。
ちなみに、「俺たちの音楽は、俺たちだけのスタイル」だとか「何かに例えないでくれ」などのツッパリは、今の私には無い。
この日記に書いたこと、・・実は今の「悩み」なのです。
・・って、今日のネタ、なんかネガティブな日記になってしまったかなあ。
でも・・本当は、「時代屋」というユニット名にちなんだ「楽曲の傾向」も、最近は出てきてるような気がするんだけど。
問題はそれが独りよがりになっていないかどうか・・なのです。
ちなみに写真は、数年前のもの。