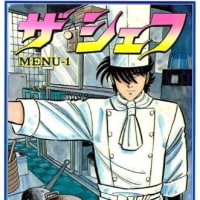「アイム・ノット・ゼア」を見て来た。
劇場に映画を見に行くのは、相当久しぶりだった。
これはトッド・ヘインズ監督作品で、ボブ・ディランの生き方や歌から触発されてできた映画で、ディランの色んな時代を、6人の役者が演じる・・という作品だ。一人二役を演じる人がいるので、都合7種類のディランが出て来る。
この手法がまず型破り。
で、しかも、ロックンロールに転向した頃の、一番かっこ良い時代のディランを、なんと女優が演じる・・というではないか。
これは見に行かないわけにはいかない。
行った劇場は渋谷のシネマライズという劇場。
以前「ノーディレクションホーム」という、ディランのドキュメント映画を見た時の劇場はかなり小ぶりな劇場だった。
そのイメージがあったので、今度も小ぶりな劇場なのかなと思ったが、案外大きかった。
スクリーンも大きかったし。
混み方はまずまず。
スカスカではない。
おそらく見に来てる客はほとんどがディランのファンだろう。
中にはトッド・ヘインズのファンもいるかもしれないが。
劇場に集まってきた客を見て、私はなにやら感慨深いものがあった。
「こんなにディランのファンがいるのか」と思うとね・・.
私が10代~20代の頃は、私の周りにはディランファンはほとんどいなかった。
知名度だけはあれど、ディランファンってのは少なかったのだ。ビートルズのファンはたくさんいたけどね。
ロックが好きで、ディランも嫌いではない・・・せいぜいその程度の人がたま~~にいるくらいだった。
だが今はどうだ。
90年代中盤ころからというもの、ディランの昔の未発表音源(海賊版として出回っていたものもある)が次々と正式に発売され、今ではディランの映画が次々と作られ、新作アルバムを出せばチャートを駆け上り、自伝も話題になり、しまいにはラジオのパーソナリティとしても人気を博す。過去の楽曲は再評価の的になり。
今やディランは、若いファンを増やしつづけている。
まさに不滅のスター・・って感じになっている。
エルビスが居ない今、今やアメリカのロック・アイコンの代表・・というふうに見なされている感もある。
映画館内には、明らかに若いころのディランを真似した若者の姿を何人も見かけた。ヘアースタイル、シャツなど。
そんな光景を見てると、本当に感慨深い。思わず、ため息をついてしまう自分がいた。ため息・・といっても、否定的な意味ではないので念のため(笑)。
映画は、6人のディランの分身のストーリーがけっこう入り組んでいる。
6人の役者が演じるディランの、それぞれの時代のストーリーがオムニバス形式で描かれてるのかと思ったら、そうではない。
ある意味「入り乱れている」。
ディランのエピソードをあれこれ知ってる人にとっては、
「あ、このシーンは、あれだ!」とか「この演出は、ディランのあれを題材にしてる」とかが分かって、見ててちょっとニヤッとさせられる。
あのエピソードを、こういう処理にしたか!・・などと思って見ると、けっこう楽しい。
「さて、このシーンは、ディランの何を題材にしたのでしょう?」みたいなクイズにして遊ぶことも可能なくらいに。
6人の役者の中では、ケイト・ブランシェットが演ずる「一番かっこいいディラン」が一番印象的で、この映画の事実上の「核」のような気がする。容姿もよく似ている。
この時代のディランは、日本人は「生」では見てなかったはず。
せいぜい「ドントルックバック」という映画で垣間みることができるくらいだ。
これを見て、あの頃のディランって、こんなにカッコよかったのか・・と実感する人は多いだろう。
ただ、ディランは決して「いい奴」ではない(笑)。それはこの映画でもしっかりと描かれている。
絶えずピリピリしてる感じだし、我がままでもあり、気まぐれでもあり、気難しくもあり、人に対して厳しくもあり、何かを用心してるようでもあり。でも、それらをひっくるめてトータル的に見ると、・・・やはりカッコいい。
この当時のディランを、一度生で見てみたかったなあ。ライブなどで。
少年役を演じた黒人少年マーカス・カール・フランクリンの歌のうまさには感心した。
シンボリックで抽象的に描かれてるなあと感じたのは、リチャード・ギア。
ディランの色んな側面を、それぞれ別の人が演じ、しかもそれをまぜこぜにすることで、今までになかった伝記(?)映画みたいになっている・・とでも言えそうだが、これは「単なる伝記」ではない。
混沌だと思う。ディランという混沌。だからこそ、「アイムノットゼア」なのではないだろうか。「アイム・ゼア」や「アイム・ヒア」じゃなく。
1つの見方で捉えきれる人物ではない・・・それがディランなのだ。そういうことが浮き彫りになっている気がする。
なまじ、一人の役者が全編通して演じるよりも、別の役者が別人としてそれぞれを演じるほうが、ビジュアル的に分かりやすい・・ということなのかもしれない。
でも、元はディラン一人。だから、それぞれの役者が演じるパートが組み合わさって、まぜこぜになっている。
私は、そんな見方をした。
伝記映画としてストーリーを把握しようとするとややこしいことになるし、むしろそういう見方はしないほうがいい。
こんな別々の要素が、1人のディランに重なり合い、混沌としている・・という描かれ方を、単純に楽しむほうが早いと思う。あまり深く考えすぎないことが肝要だと思う。
むしろ、1つ1つのシーンを楽しむように見たほうがいい。その方が発見もあるし、気づく要素は多いと思う。
そう考えると、決して難解ではない。
そうやって見れば、すごく印象的な作品だし、斬新だし、楽しめると思う。
ひとつだけ気になることが。
ドキュメント映画「ドントルックバック」の冒頭に、非常に有名なシーンがある。
プロモーションビデオのさきがけ・・・と評されてるシーンで、ディランの「サブタレニアンホームシックブルース」という曲が流れる中、ディランが路地裏みたいな場所に立って、歌詞の単語が書かれた画用紙(?)を曲に合わせて1枚づつめくって放り投げていくシーンがある。
てっきり、この「アイムノットゼア」でも、そのシーンが出てくるのかと思った。
パンフレットにも、ケイト・ブランシェットがそういうシーンを演じた写真が掲載されている。
だが・・・いつそのシーンが出てくるか・・と思って楽しみにして、ジ~~ッと画面を最初から最後まで見てたのだが、結局そのシーンは「アイムノットゼア」本編には出てこなかった。
もしや、私の見落とし・・・?????
いや、そんなことはない・・と思うんだがなあ。
パンフレットだけの演出だったのだろうか。それとも・・・??
劇場に映画を見に行くのは、相当久しぶりだった。
これはトッド・ヘインズ監督作品で、ボブ・ディランの生き方や歌から触発されてできた映画で、ディランの色んな時代を、6人の役者が演じる・・という作品だ。一人二役を演じる人がいるので、都合7種類のディランが出て来る。
この手法がまず型破り。
で、しかも、ロックンロールに転向した頃の、一番かっこ良い時代のディランを、なんと女優が演じる・・というではないか。
これは見に行かないわけにはいかない。
行った劇場は渋谷のシネマライズという劇場。
以前「ノーディレクションホーム」という、ディランのドキュメント映画を見た時の劇場はかなり小ぶりな劇場だった。
そのイメージがあったので、今度も小ぶりな劇場なのかなと思ったが、案外大きかった。
スクリーンも大きかったし。
混み方はまずまず。
スカスカではない。
おそらく見に来てる客はほとんどがディランのファンだろう。
中にはトッド・ヘインズのファンもいるかもしれないが。
劇場に集まってきた客を見て、私はなにやら感慨深いものがあった。
「こんなにディランのファンがいるのか」と思うとね・・.
私が10代~20代の頃は、私の周りにはディランファンはほとんどいなかった。
知名度だけはあれど、ディランファンってのは少なかったのだ。ビートルズのファンはたくさんいたけどね。
ロックが好きで、ディランも嫌いではない・・・せいぜいその程度の人がたま~~にいるくらいだった。
だが今はどうだ。
90年代中盤ころからというもの、ディランの昔の未発表音源(海賊版として出回っていたものもある)が次々と正式に発売され、今ではディランの映画が次々と作られ、新作アルバムを出せばチャートを駆け上り、自伝も話題になり、しまいにはラジオのパーソナリティとしても人気を博す。過去の楽曲は再評価の的になり。
今やディランは、若いファンを増やしつづけている。
まさに不滅のスター・・って感じになっている。
エルビスが居ない今、今やアメリカのロック・アイコンの代表・・というふうに見なされている感もある。
映画館内には、明らかに若いころのディランを真似した若者の姿を何人も見かけた。ヘアースタイル、シャツなど。
そんな光景を見てると、本当に感慨深い。思わず、ため息をついてしまう自分がいた。ため息・・といっても、否定的な意味ではないので念のため(笑)。
映画は、6人のディランの分身のストーリーがけっこう入り組んでいる。
6人の役者が演じるディランの、それぞれの時代のストーリーがオムニバス形式で描かれてるのかと思ったら、そうではない。
ある意味「入り乱れている」。
ディランのエピソードをあれこれ知ってる人にとっては、
「あ、このシーンは、あれだ!」とか「この演出は、ディランのあれを題材にしてる」とかが分かって、見ててちょっとニヤッとさせられる。
あのエピソードを、こういう処理にしたか!・・などと思って見ると、けっこう楽しい。
「さて、このシーンは、ディランの何を題材にしたのでしょう?」みたいなクイズにして遊ぶことも可能なくらいに。
6人の役者の中では、ケイト・ブランシェットが演ずる「一番かっこいいディラン」が一番印象的で、この映画の事実上の「核」のような気がする。容姿もよく似ている。
この時代のディランは、日本人は「生」では見てなかったはず。
せいぜい「ドントルックバック」という映画で垣間みることができるくらいだ。
これを見て、あの頃のディランって、こんなにカッコよかったのか・・と実感する人は多いだろう。
ただ、ディランは決して「いい奴」ではない(笑)。それはこの映画でもしっかりと描かれている。
絶えずピリピリしてる感じだし、我がままでもあり、気まぐれでもあり、気難しくもあり、人に対して厳しくもあり、何かを用心してるようでもあり。でも、それらをひっくるめてトータル的に見ると、・・・やはりカッコいい。
この当時のディランを、一度生で見てみたかったなあ。ライブなどで。
少年役を演じた黒人少年マーカス・カール・フランクリンの歌のうまさには感心した。
シンボリックで抽象的に描かれてるなあと感じたのは、リチャード・ギア。
ディランの色んな側面を、それぞれ別の人が演じ、しかもそれをまぜこぜにすることで、今までになかった伝記(?)映画みたいになっている・・とでも言えそうだが、これは「単なる伝記」ではない。
混沌だと思う。ディランという混沌。だからこそ、「アイムノットゼア」なのではないだろうか。「アイム・ゼア」や「アイム・ヒア」じゃなく。
1つの見方で捉えきれる人物ではない・・・それがディランなのだ。そういうことが浮き彫りになっている気がする。
なまじ、一人の役者が全編通して演じるよりも、別の役者が別人としてそれぞれを演じるほうが、ビジュアル的に分かりやすい・・ということなのかもしれない。
でも、元はディラン一人。だから、それぞれの役者が演じるパートが組み合わさって、まぜこぜになっている。
私は、そんな見方をした。
伝記映画としてストーリーを把握しようとするとややこしいことになるし、むしろそういう見方はしないほうがいい。
こんな別々の要素が、1人のディランに重なり合い、混沌としている・・という描かれ方を、単純に楽しむほうが早いと思う。あまり深く考えすぎないことが肝要だと思う。
むしろ、1つ1つのシーンを楽しむように見たほうがいい。その方が発見もあるし、気づく要素は多いと思う。
そう考えると、決して難解ではない。
そうやって見れば、すごく印象的な作品だし、斬新だし、楽しめると思う。
ひとつだけ気になることが。
ドキュメント映画「ドントルックバック」の冒頭に、非常に有名なシーンがある。
プロモーションビデオのさきがけ・・・と評されてるシーンで、ディランの「サブタレニアンホームシックブルース」という曲が流れる中、ディランが路地裏みたいな場所に立って、歌詞の単語が書かれた画用紙(?)を曲に合わせて1枚づつめくって放り投げていくシーンがある。
てっきり、この「アイムノットゼア」でも、そのシーンが出てくるのかと思った。
パンフレットにも、ケイト・ブランシェットがそういうシーンを演じた写真が掲載されている。
だが・・・いつそのシーンが出てくるか・・と思って楽しみにして、ジ~~ッと画面を最初から最後まで見てたのだが、結局そのシーンは「アイムノットゼア」本編には出てこなかった。
もしや、私の見落とし・・・?????
いや、そんなことはない・・と思うんだがなあ。
パンフレットだけの演出だったのだろうか。それとも・・・??