
最近はスーパーやコンビニなどでも、駄菓子が売られていたりする。
そう、かつては駄菓子屋で売られていたような、安くて、ばら売りされてる駄菓子が。
そういう商品を見ると、子供の頃に駄菓子屋にさんざんお世話になった(?)私としては懐かしくて、時には衝動買いしてしまうこともある。
だが、商品は確かに駄菓子でも、スーパーやコンビニのような「あかぬけた、店内照明が明るい環境」で売られていると、どうも「どこか違う」と思ってしまう。
やはり、駄菓子というものは、駄菓子屋で売られてこそ味わいがあるような気がする。
これは私がかつての駄菓子屋を知っているからこそであろう。
当時は街には駄菓子屋は普通にあった。
だが今は、ほとんど見かけない。
だから今の子供たちは、「駄菓子屋」と言われてもピンとこないだろう。
駄菓子自体は前述の通り、今でもスーパーやコンビニでも売られているから、今の子供たちも「駄菓子」という菓子は知っていても、かつてそれらが売られていた「駄菓子屋」がどんなものであったかは、分からないのではないだろうか。
では、私の思う「駄菓子屋」とは、一体どういうものだったか。どんな店であったか。
それを書いてみたい。
これは言わば、私にとっての「正しい駄菓子屋」である(笑)。←あくまでも、個人的なイメージではあるが。
- 経営者はお爺さんか、お婆さん。やや腰が曲がっている。
- 店は木造で、古臭い。築何十年もたっている。ボロ(←失礼)ければボロいほど、いい。しかも店の奥が経営者の住居になっている。
- 店は大通り沿いにあるのではなく、大通りから区画をへだてた狭い道(路地?)沿いにある。もしくは、民家が立ち並ぶ中の、とある民家が店になっている。
- 店の中は薄暗い。
- 経営者は普段は必ずしも店頭にいるわけではなく、客である子供が店に入ってきて、奥の住居スペースに向かって「すいませ~ん」と経営者に呼びかけると、奥の方から経営者であるお爺さんかお婆さんが、ゆっくり店頭にやってくる。無言でやってきたりもする。
- 経営者であるお爺さんやお婆さんは、決して愛想が良くはない。でも、それでいい。必ずしも愛想は良くなくてもいい。
- 店に入ると、食べ物が入った箱みたいなものが縦横に整然と並んでおり、その箱はフタがガラスで、中の商品が見える。お菓子の中には、紐付きの飴などもある。
- 食べ物だけでなく、玩具も売られている。
- 玩具は、パチンコ、銀玉鉄砲、メンコ、妖怪けむり、組み立て式紙飛行機、細長い紙に梱包された組み立て式でゴム動力のグライダー、プロノート(はがすと何回でも絵や文字をかける、1ページだけのノート)、柔らかめのブーメラン、シャボン玉、かんしゃく玉、などなど。
- 玩具でも、銀玉鉄砲やグライダーなどは、駄菓子屋の商品の中では高級品であり、そういうものは天井からつり下げられて高い位置にあり、売られている。
- 安い玩具・・例えば「妖怪けむり」などは柱の途中などから低めの位置につり下げられており、シャボン玉セットは、お菓子の箱などと並んで売られている。
- ドアは左右にずらして開けるタイプで、木製の骨組みにガラスばり。もちろん手動。ノブを手にとって、手前に引いて開けたり、奥に押して開けるタイプのドアではない。
- 入り口から入って、一番目につきやすい位置に、「スピードくじ付きのガム」が売られている。駄菓子屋では売れ筋商品だったのかもしれない。
- プラスチック製の透明なツボみたいなものに、ばら売りのせんべいが売られている。そのツボのフタは、なぜか銀色。
- 下手したら、お店の名前がはっきりしなかったりする。
- 基本的には安い商品しか売られてなかった。
とりあえず、すぐに思いつく要素をあげてみた。
私が子供の頃に通っていた駄菓子屋は、だいたい上記のような共通点があった。
それゆえ、上記にあげたような駄菓子屋こそが、私の中にある「正しい(?)駄菓子屋」像である。
まあ、本当にそれが「正しい」かどうかはともかく(笑)。
それに比べたら、スーパーやコンビニに売られている駄菓子の売り場の環境は、経営者は決してお爺さんやお婆さんという感じではない。
店舗は、古い木造の家という感じでもない。
また、店舗がある場所は、路地にあるという感じでもないし、むしろ車が通るような大きめの道沿いにある。
店内は明るい。
店のスタッフは、制服みたいなものを着た、比較的若い人が、レジに常駐している。
愛想は、まあ普通。決して愛想が悪いという印象はない。
ある意味、ビジネスライクな明るさがある場合もある。
店内では様々な商品が売られていて、駄菓子は、色んな商品の傍らに、比較的小さなスペースにまとめられているし、普通の商品と同列みたいな感覚で売られている。
ちなみに、玩具は・・少なくてもコンビニでは売られているイメージはない。
ドアは、店にもよるが、自動ドアだったりすることもある。
こんなことを考えると、私の「正しい駄菓子屋」と、今駄菓子が売られているスーパーやコンビニの環境は、対照的であるとさえいる。
だから、私はスーパーやコンビニで駄菓子が売られていても、たとえ駄菓子屋で売られていた商品と同じものだったとしても、なんというか・・あっけないというか、駄菓子という感じが希薄なのかもしれない。
単に「安いお菓子」程度の認識で。
駄菓子というのは、やはり垢ぬけないような環境の中で売られてこそ、感じがでる気がするのだ。
それと、スーパーやコンビニの駄菓子コーナーでは、駄菓子屋で売られていた「玩具」がないというのも、大きいのかもしれない。
駄菓子屋で売られていた玩具を、仮に便宜上「駄玩具」と呼ぶのなら、駄菓子屋には駄菓子だけでなく、駄玩具も売られていた・・という要素も大きい気はする。
いっそ、コンビニやスーパーで駄菓子を売るなら、その売り場は「安い商品」だけにして、照明も暗くして、売り場・・というか、駄菓子コーナーを「木造の小屋」みたいな売り場にして、なおかつ駄菓子だけでなく、駄玩具も売ればどうだろう?
さらに踏み込んで書くなら、そういうコーナーを設置するなら、普通のスーパーやコンビニよりも、むしろ「100円ショップ」の店内に設置したらどうだろう。
できれば店内の照明はあまり明るすぎない方がベター。
というのは、「100円ショップ」に行くと、店によっては(特に店内がさほど明るくない店)、私はたまに「古い駄菓子屋」に近いようなものを感じることがあるからだ。
ある意味「100円ショップ」は、「大人の駄菓子屋」みたいに思えることもあるからだ。
もちろん、店にもよるけれど。










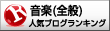


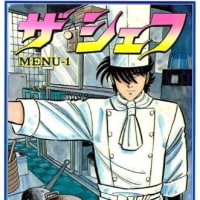














おっしゃってる意味での『正しい駄菓子屋』は、つげ義春先生の「ゲンセンカン主人」に出てくる店が、まさにそうでしょう。
まあ、ぼくが子供のころに住んでいた町(大阪市淀川区の繁華街から離れた古いそまつな住宅街ですが、、、)に、
それに近いお店がありましたね。
駄菓子のほかに、ビー玉とか、「おはじき」とか、「遊戯カ-ド類」とかプラモデルなんかも売ってました。
まあ、なつかしいですね。。。。。
☆ブログ掲載写真の駄菓子屋は、今、現存・営業中のお店なんですか?
あの時代の空気が、つげ作品にもたくさん詰め込まれていたんてしょうね。
ビー玉、おはじき、ありましたね!
遊戯カードというと、メンコを思い出します。
集めましたよ!
特に鉄人のメンコには熱中しました。
この日記の写真はネットで見つけた無料写真です。
あまりにこの日記のイメージにピッタリです。
私の中の駄菓子屋は、まさにこんな感じでした。
5円からお菓子が買えた…今では考えられませんね。
店によっては1円単位でも0Kな所もありました。
でも、親とか学校は駄菓子屋のお菓子は不潔だから
食べちゃダメっていうんですよね〜。
ま、確かに後年問題になったチクロなんていう代物がたっぷりと入ってたようではありますが(笑)
でも、あの毒々しいまでの色鮮やかさは、
子供心に大いにそそられたものです。
メンコ…当地ではパッチンと呼んでいました。
名刺大のものと少し判が小さくて厚みのある2種類がありました。
鉄人やアトムのようなメジャーどころから、
なんだかよくわからないキャラクターまで色々ありましたね。
それに版ズレが酷いものも平気で売られてました。
つげ義春氏と言えば、先日書店で氏を特集したムック本を目にしました。
青っぽい表紙で「SPECTATOR」とありました。
中は見る事ができませんでしたが、1冊まるまるつげ義春氏って感じでしたね。
透明のツボみたいなものに入っており、1枚1枚単品で買えました。
1円で買えたものもありましたが、それが何であったかはよく覚えてないんですが、もしかしたら小さなアメだったかもしれません。
親や先生は駄菓子屋を快く思ってはいなかったですね。
確かに店内はお世辞にもきれいとは言えなかったですし、衛生上の問題はあったと思います。
でも、子供にとっては、少ないおこづかいでやりくりするには、駄菓子屋の値段相場は貴重でした。
チクロ・・・ありましたね~。懐かしい言葉です。
メンコでは、丸いメンコもありました。しかも、名刺サイズのメンコより大きかったので、心強い存在でした。
印刷のズレ・・確かにありましたし、絵がヘタなメンコもありました。
偽物感満載でした(笑)。
つげ先生の本があるんですね。最近本屋に行ってないので、今度のぞいてみます。