「P.K.ディックとシミュラクラ」
世界観の一つに大地は象の背中の上に乗っており、その象がさらに大きな亀の上に乗っているというのがある。ヒンドゥー教か何であったか詳細は覚えていないが、描写されたいかにもオリエンタルな図柄と、そして何よりも決定的な次の一事で、その構造が強く印象に残った。亀はさらに互大なとぐろを巻いた蛇の上に乗っており、蛇は自らの尾を噛んで、己とその上に乗る世界を持上拝ているのである。蛇を支えているのは蛇自身なのであるそこでは蛇が自らのカで己とその上に乗る世界を支えられるかという快定的な矛盾を解消すれぱ世界は安定する。
そしてその決定的な矛盾は、象が大地を支えていると考える入々にあっては前提としない矛盾であるのだ。蛇の作る無限を閉し込める環が、人々を果てのない果てえの不安から解き放ってくれる。ディックの物語り世界にはその安定が無い。彼は大地が象の背中に乗っているとは考え難かったのだ。彼自身が物語り以上に狂気の世界に生きていたと考えるのは、大きな誤解であるに違いない。彼の押え難い理性、それが、本能的に閉ざされているべきはずの自明性の枠組みを崩し突き破ったとしても、彼は踏み応え、冷静な観察者である自分自身を見つづけていたに違いない、経済的な破綻、度重なる離婚と繰り返されると結婚、そしてドラックそれらはすべて彼のスマートではない生き方を示しているとは言え、彼が異常であることの証明にはならない。むしろ、正常に生きようとするものにとっての社会の異常性が彼に残酷にあたったのだ。ディックの描く世界に氾濫するシミュラクラとシミユラクラ粉いの登場人物たち。あやふやな町、あやふやな時間。何を確かなものにするのか、何が確かなものであるべきなのか。それらが実際の彼自身の時間においても,最も重大な関心事であったがために人とシミュラクを分かつものは共同し共感するする無意識下の理解であり、無意識であるがために隠しおおせない感情の存在であるはずだとディックは語っている。人間はどんなに強固であろうとも本質的には弱く傷つき易いものである。他者に対して強くあろうとするものは弱さを知らねぱならない。弱さは人問であれぽ誰もが共有しているものである。強さを際立たせることが、脆弱さをも露にする。シミュラクラにはそれがない。
映画「プレードランナー」のレプリカント達はディック描くシミユラクラとはかけ離れて人間的である。彼ら、其れらは人間と繋がる証明を求めていた、限られたライフスパンの延長をではなく、共有すべき感情をである。寿命はそのための期間でしかない。人間にもいずれ訪れる死は避けられないのだから。ディックが原作「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」で描かれたレイチェルは涙を流さない。表現形式としてのセックスは可能だが共有すべき愛を知り得ない。アパートメントの屋上から生きた子馬を投げ落とし復讐を(何に対して?)果たすのみだ。自分を人間のバウンティハンターだと信じ切っていたアンドロイドは、同類であるアンドロイドを抹殺するこで人間で在り続けようとした。アンドロイド達の間には共感の意識はなく論理を超えて感情は存在しない。シミュラクラは人間という形式にこだわり続けても決して人間であろうとはしない。デッカードをビルの屋上に追い詰めたレプリカントの語る思いは原作のイメージからは遠く離れ過ぎてしまっている。
アンドロイド、レプリカント、このSF的用語で語られるシミュユラクラは、在り得ないが故に非人間的なのだろう。空想科字小説の怪物としてディックは其れらを踏襲したのだろうか。
ディックは何篇かの昔通小説(まったくこの呼称はディック的て面自い。すでにシミユレーンョンである小説のシミュラクラ、シミュラクラのシミユラクラは本物であるのだろうか。)での評価を得ようと試みて失敗している。ジャンルとそれに介在する誤解と偏見が彼をいささか悩ませていたのは事実であろう。ソール・ベローは優れているがディックはただのパルプ小説作家なのである。彼の創リ出したアンドロイド達はSFというジャンルに押込められるだけでその象徴性を失い、ただの状況設定のための小道具に成り下がってしまう。何かが欠けたシミュラクラは、何かを失っている人間そのものである。解体された自己の一面かも知れない、共感できない、自らの頭の上に自らの足を置くもの。宙ぶらりんの男(そう言えば、ディックの作品の中にも「ハンギング・ストレンジヤー」というのがある)決して人間とは言えないシュミラクラは、シミユラクラであるが故に人間を映し出している。何重にも錯綜し全てがキップル化していく風景のなかで、ディックが捜していたものは人間そのものであったのではないか。
個人は世界の部分である。しかし、全体を知り得るのは個人よってである。(客観を認識しうる主観というのは、文法的には存在しても、気違いお茶会の帽子屋の言葉とあまり違わないように聞こえる)そして決定的な問題は、いずれにしても自己がここに在ることなのである。不確かな大地、曖昧な地平の上では人間は自分を自分で支えなけれぱならない。しかしそのために消費される工ネルギーは、まわりのすべてをキップル化し工ントロピーを極大へと加速する。誰もがそれを知っており、互いを、繋ぐ社会と組織をシュミレートするのだが、ディックにとってその現実世界こそがシュミレーションのためのシュミレーション、際限なく繰り返される無為に映じていたのではないか。その直感を彼に教えたもの、シミユレーションを終らせるための現実の大地を彼は求めていた。彼の物語ははその苦闘のシュユミレートとなって、また我々の手元にと現れる。
真理とは単純でなければならない。ディックは彼の足を置く居心地のよい大地、地球を求めており、その苦闘と希望とが彼の作品の根底を流れる思想となっているように思えてならない。機会を得、力が及べばいくつかの作品を通してP・K・ディックの(ダブルバインドされた)世界についても論じていきたい。
昔書いたものです
世界観の一つに大地は象の背中の上に乗っており、その象がさらに大きな亀の上に乗っているというのがある。ヒンドゥー教か何であったか詳細は覚えていないが、描写されたいかにもオリエンタルな図柄と、そして何よりも決定的な次の一事で、その構造が強く印象に残った。亀はさらに互大なとぐろを巻いた蛇の上に乗っており、蛇は自らの尾を噛んで、己とその上に乗る世界を持上拝ているのである。蛇を支えているのは蛇自身なのであるそこでは蛇が自らのカで己とその上に乗る世界を支えられるかという快定的な矛盾を解消すれぱ世界は安定する。
そしてその決定的な矛盾は、象が大地を支えていると考える入々にあっては前提としない矛盾であるのだ。蛇の作る無限を閉し込める環が、人々を果てのない果てえの不安から解き放ってくれる。ディックの物語り世界にはその安定が無い。彼は大地が象の背中に乗っているとは考え難かったのだ。彼自身が物語り以上に狂気の世界に生きていたと考えるのは、大きな誤解であるに違いない。彼の押え難い理性、それが、本能的に閉ざされているべきはずの自明性の枠組みを崩し突き破ったとしても、彼は踏み応え、冷静な観察者である自分自身を見つづけていたに違いない、経済的な破綻、度重なる離婚と繰り返されると結婚、そしてドラックそれらはすべて彼のスマートではない生き方を示しているとは言え、彼が異常であることの証明にはならない。むしろ、正常に生きようとするものにとっての社会の異常性が彼に残酷にあたったのだ。ディックの描く世界に氾濫するシミュラクラとシミユラクラ粉いの登場人物たち。あやふやな町、あやふやな時間。何を確かなものにするのか、何が確かなものであるべきなのか。それらが実際の彼自身の時間においても,最も重大な関心事であったがために人とシミュラクを分かつものは共同し共感するする無意識下の理解であり、無意識であるがために隠しおおせない感情の存在であるはずだとディックは語っている。人間はどんなに強固であろうとも本質的には弱く傷つき易いものである。他者に対して強くあろうとするものは弱さを知らねぱならない。弱さは人問であれぽ誰もが共有しているものである。強さを際立たせることが、脆弱さをも露にする。シミュラクラにはそれがない。
映画「プレードランナー」のレプリカント達はディック描くシミユラクラとはかけ離れて人間的である。彼ら、其れらは人間と繋がる証明を求めていた、限られたライフスパンの延長をではなく、共有すべき感情をである。寿命はそのための期間でしかない。人間にもいずれ訪れる死は避けられないのだから。ディックが原作「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」で描かれたレイチェルは涙を流さない。表現形式としてのセックスは可能だが共有すべき愛を知り得ない。アパートメントの屋上から生きた子馬を投げ落とし復讐を(何に対して?)果たすのみだ。自分を人間のバウンティハンターだと信じ切っていたアンドロイドは、同類であるアンドロイドを抹殺するこで人間で在り続けようとした。アンドロイド達の間には共感の意識はなく論理を超えて感情は存在しない。シミュラクラは人間という形式にこだわり続けても決して人間であろうとはしない。デッカードをビルの屋上に追い詰めたレプリカントの語る思いは原作のイメージからは遠く離れ過ぎてしまっている。
アンドロイド、レプリカント、このSF的用語で語られるシミュユラクラは、在り得ないが故に非人間的なのだろう。空想科字小説の怪物としてディックは其れらを踏襲したのだろうか。
ディックは何篇かの昔通小説(まったくこの呼称はディック的て面自い。すでにシミユレーンョンである小説のシミュラクラ、シミュラクラのシミユラクラは本物であるのだろうか。)での評価を得ようと試みて失敗している。ジャンルとそれに介在する誤解と偏見が彼をいささか悩ませていたのは事実であろう。ソール・ベローは優れているがディックはただのパルプ小説作家なのである。彼の創リ出したアンドロイド達はSFというジャンルに押込められるだけでその象徴性を失い、ただの状況設定のための小道具に成り下がってしまう。何かが欠けたシミュラクラは、何かを失っている人間そのものである。解体された自己の一面かも知れない、共感できない、自らの頭の上に自らの足を置くもの。宙ぶらりんの男(そう言えば、ディックの作品の中にも「ハンギング・ストレンジヤー」というのがある)決して人間とは言えないシュミラクラは、シミユラクラであるが故に人間を映し出している。何重にも錯綜し全てがキップル化していく風景のなかで、ディックが捜していたものは人間そのものであったのではないか。
個人は世界の部分である。しかし、全体を知り得るのは個人よってである。(客観を認識しうる主観というのは、文法的には存在しても、気違いお茶会の帽子屋の言葉とあまり違わないように聞こえる)そして決定的な問題は、いずれにしても自己がここに在ることなのである。不確かな大地、曖昧な地平の上では人間は自分を自分で支えなけれぱならない。しかしそのために消費される工ネルギーは、まわりのすべてをキップル化し工ントロピーを極大へと加速する。誰もがそれを知っており、互いを、繋ぐ社会と組織をシュミレートするのだが、ディックにとってその現実世界こそがシュミレーションのためのシュミレーション、際限なく繰り返される無為に映じていたのではないか。その直感を彼に教えたもの、シミユレーションを終らせるための現実の大地を彼は求めていた。彼の物語ははその苦闘のシュユミレートとなって、また我々の手元にと現れる。
真理とは単純でなければならない。ディックは彼の足を置く居心地のよい大地、地球を求めており、その苦闘と希望とが彼の作品の根底を流れる思想となっているように思えてならない。機会を得、力が及べばいくつかの作品を通してP・K・ディックの(ダブルバインドされた)世界についても論じていきたい。
昔書いたものです














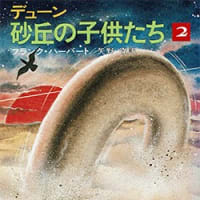


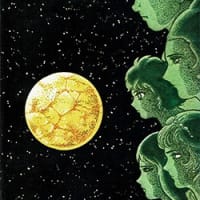

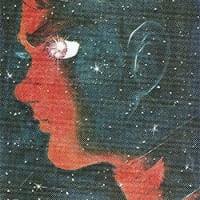







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます