「ヴァリス」につてい何を知っているのか?
さて2夜めにしても語る材料が揃わない
全然読み直す時間が無い
これは速読は無理である
からめ手から攻めるしかない
と思っていたが松岡正剛 千夜千冊の第八百八十三夜を紹介すれば良いのかとも思う
「ヴァリス」の解説は山ほどある
何をいまさら語るのか・・しかし、語らないわけにもいくまい
もともと自己完結のブログである
しかし、今夜もズルして松岡氏のブログから引用させていただく
ぜひ千夜千冊を読んでいただきたい
「・・・略
こうして『ヴァリス』の読み方にはいろいろの楽しみ方を変奏したほうがいいということになる。
第1には、おそらく最も知的な読み方が翻訳者の大滝啓裕が試みたように、ここに頻繁に登場してくる神秘思想を複合的に賞味することだろう。とくにシモンの知やグノーシス思想について、これほど興味深く採りこんだものはなく、それを啄むだけでも十分に楽しめる。
第2に、ディックの精神の軌跡を追いながら読むのは、正統SF派の読み方で、多くのSF読者が試みてきたはずだ。ただしこのためにはル・グインをはじめ60年代SFのエキスを浴びていなければならず、こうした免疫がないままに“ヴァリス三部作”から入ってしまうと、たいへんな混乱を生じるだろう。知がずたずたにされてしまうということもある。が、ディックが文学として認められるには、このような読者をこそ通過しなければならなくなっている。
第3に、もうちょっと気楽に読む気なら(これは実は不可能に近いのだが)、先にディックが書いたエッセイを読んでおくことだ。『フィリップ・K・ディックのすべて』(ジャストシステム社)というノンフィクション集成が刊行されているので、ここに収録されているディックの文章で地ならしをしておくといい。
リドリー・スコットが『模造記憶』と『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』を下敷きに、かの『ブレードランナー』を映画にしたのはよく知られている。しかしディックがこの短い原作が映画になりうることを1968年にとっくにノートとして発表していたことなどは、この『フィリップ・K・ディックのすべて』でなければわからない。
第4にの楽しみ方は、ディックへの入口を『高い城の男』か『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕』か『ユービック』にし、それからおもむろに『ヴァリス』を楽しむことだ。これならひょっとしてハリウッド映画のように読める。つまり『ヴァリス』という映画を見るつもりで読むとよい。
以上はむろん老婆心である。ディックはカフカともル・グインとも違うし、ボルヘスやエーコほどの幻想制御もしていないということを、また、ティモシー・リアリーやデレク・ジャーマンのポスト・ジェンダーふうの陽気をもちあわせていないということを、老婆心から語ってみたにずきない。
しかし、どんな読み方をしようとも、『ヴァリス』(と、その続編)が、今日考えられるかぎりの「宇宙と脳と神秘哲学をめぐる情報システム」を扱った最初で最大の唯一の文学思想的な試みであったことからは、読者は逃れようはないとも思うべきである。ぼくは面倒なのでここには書かないが、カルトを脱出するのはそんなに難しいことではないけれど、そんなことを考えるより、やはりいったんはディックの周到で狂気に満ちたPKDカルトに浸ることなのである。
そうすれば、これだけは請け合うが、読み終わったのちに、何が何だかわからない自分がそこにぽつんと取り残されるのを感じることだろう。が、
そのぽつんとした自分こそ、死を前にしたフィリップ・K・ディックが入念に仕上げたディックその人の虚無そのものなのだった。」
最後の段落がすべてかもしれない

「フィリップ・K・ディックのすべて―ノンフィクション集成」
ローレンス・スーチン著 飯田 隆昭訳 ジャスト・システム 1996年発行
松岡氏のブログでも紹介されている
ディックを理解するためには一読すべき本
帯の「ファン垂涎の書」という惹句がすごい
さて2夜めにしても語る材料が揃わない
全然読み直す時間が無い
これは速読は無理である
からめ手から攻めるしかない
と思っていたが松岡正剛 千夜千冊の第八百八十三夜を紹介すれば良いのかとも思う
「ヴァリス」の解説は山ほどある
何をいまさら語るのか・・しかし、語らないわけにもいくまい
もともと自己完結のブログである
しかし、今夜もズルして松岡氏のブログから引用させていただく
ぜひ千夜千冊を読んでいただきたい
「・・・略
こうして『ヴァリス』の読み方にはいろいろの楽しみ方を変奏したほうがいいということになる。
第1には、おそらく最も知的な読み方が翻訳者の大滝啓裕が試みたように、ここに頻繁に登場してくる神秘思想を複合的に賞味することだろう。とくにシモンの知やグノーシス思想について、これほど興味深く採りこんだものはなく、それを啄むだけでも十分に楽しめる。
第2に、ディックの精神の軌跡を追いながら読むのは、正統SF派の読み方で、多くのSF読者が試みてきたはずだ。ただしこのためにはル・グインをはじめ60年代SFのエキスを浴びていなければならず、こうした免疫がないままに“ヴァリス三部作”から入ってしまうと、たいへんな混乱を生じるだろう。知がずたずたにされてしまうということもある。が、ディックが文学として認められるには、このような読者をこそ通過しなければならなくなっている。
第3に、もうちょっと気楽に読む気なら(これは実は不可能に近いのだが)、先にディックが書いたエッセイを読んでおくことだ。『フィリップ・K・ディックのすべて』(ジャストシステム社)というノンフィクション集成が刊行されているので、ここに収録されているディックの文章で地ならしをしておくといい。
リドリー・スコットが『模造記憶』と『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』を下敷きに、かの『ブレードランナー』を映画にしたのはよく知られている。しかしディックがこの短い原作が映画になりうることを1968年にとっくにノートとして発表していたことなどは、この『フィリップ・K・ディックのすべて』でなければわからない。
第4にの楽しみ方は、ディックへの入口を『高い城の男』か『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕』か『ユービック』にし、それからおもむろに『ヴァリス』を楽しむことだ。これならひょっとしてハリウッド映画のように読める。つまり『ヴァリス』という映画を見るつもりで読むとよい。
以上はむろん老婆心である。ディックはカフカともル・グインとも違うし、ボルヘスやエーコほどの幻想制御もしていないということを、また、ティモシー・リアリーやデレク・ジャーマンのポスト・ジェンダーふうの陽気をもちあわせていないということを、老婆心から語ってみたにずきない。
しかし、どんな読み方をしようとも、『ヴァリス』(と、その続編)が、今日考えられるかぎりの「宇宙と脳と神秘哲学をめぐる情報システム」を扱った最初で最大の唯一の文学思想的な試みであったことからは、読者は逃れようはないとも思うべきである。ぼくは面倒なのでここには書かないが、カルトを脱出するのはそんなに難しいことではないけれど、そんなことを考えるより、やはりいったんはディックの周到で狂気に満ちたPKDカルトに浸ることなのである。
そうすれば、これだけは請け合うが、読み終わったのちに、何が何だかわからない自分がそこにぽつんと取り残されるのを感じることだろう。が、
そのぽつんとした自分こそ、死を前にしたフィリップ・K・ディックが入念に仕上げたディックその人の虚無そのものなのだった。」
最後の段落がすべてかもしれない

「フィリップ・K・ディックのすべて―ノンフィクション集成」
ローレンス・スーチン著 飯田 隆昭訳 ジャスト・システム 1996年発行
松岡氏のブログでも紹介されている
ディックを理解するためには一読すべき本
帯の「ファン垂涎の書」という惹句がすごい














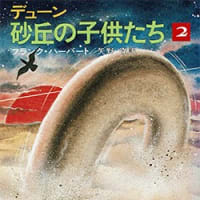


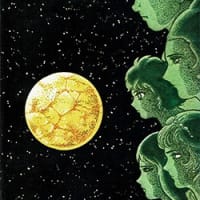

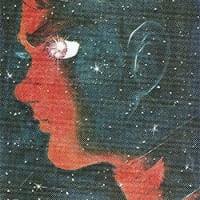







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます