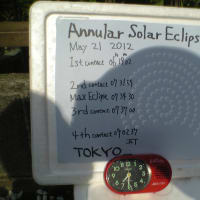さらには~
『困ります、ファインマンさん』も読む: 原書名:WHAT DO YOU CARE WHAT OTHER PEOPLE THINK?MR.FEYNMAN GOES TO WASHINGTON and others(Feynman,Richard;Leighton,Ralph)
ファインマン,R.P.【著】〈Feynman,Richard P.〉大貫昌子【訳】
1988年(文庫2001年)
原題に忠実なタイトルならば、第1話の「ひとがどう思おうとかまわない」(生い立ちと初恋の人であり最初の妻のアーリーンの思い出)になるところだろうが、「ご冗談でしょう」(これは原題に忠実)との連続性の点を考慮したのだろうか、「困ります」にして成功している。
「困りましたね、ファインマン先生」という小さな話が本書中にあるのだが、それは「いくらホテルが取れないといったって、大先生がそんなところに泊まられては困ります」というお話。
が、それよりも、「ファイマン氏、ワシントンにいく―チャレンジャー号爆発事故調査のいきさつ」(チャレンジャー号事故調査委員会の一員として、柔軟な発想でいかに原因を究明していったか、その顛末を語る)が、「困ります」の真髄であるように思う。
硬直した官僚的体質の大組織が無責任の連鎖で大事故を招いた(日本でも聞いたような展開があった?はまた別の話)過程を、米国各地を東奔西走して現場技術者への聞き取りから明らかにしていき、本論よりも余程真相に迫った付録の形で公開することが出来たプロセスが詳細に記載されている。
じつは、このとき先生はがんが転移しまくってもぐらたたき状態のお体。
NASA側に言わせれば、「そんなことまで突っ込んで明らかにされては困ります、先生」だったろう。
じつは低温になると問題の‘Oリング’が弾性を失うことはNASAの一部でも承知していて、それを打ち明けられた調査委員会メンバーのクティナ空軍大将(先生とは意気投合)が先生に、「キャブレターをいじりながらひょいと思いついたんですが」と電話で示唆する。
そのヒントでピンと来た先生はOリング問題の追及に掛かり、ロジャーズ委員会席上、シャトルの模型からはずしてきたリングをコップの氷水に突っ込んでみせるという簡単な実験で人々に真相を印象付ける。
動画(後で付加したと思われる解説画像つき?):youtube/Richard Feynman talks about the O ring
あとで振り返ってみると、大将は内部通報者を危険にさらさないよう、たくみに先生にヒントを与えていたのだと気付く…と「真相の真相」まで明らかにされる。
wiki/Space_Shuttle_Challenger_disaster
中尾政之教授の失敗百選
問題の付録:Personal Observations on Reliability of Shuttle by R. P. Feynman
本書中の1節の元の動画:youtube/「ものをつきとめることの喜び」1983年BBCインタビュー(1/5) ⇒ 2/5~5/5も続く。
おまけ:
ユダヤ移民の3代目が初代に捧げたオマージュ(故グールド博士の「ナチュラル・ヒストリー」誌連載エッセイの最終回):
naturalhistorymag/I Have Landed By Stephen Jay Gould
『困ります、ファインマンさん』も読む: 原書名:WHAT DO YOU CARE WHAT OTHER PEOPLE THINK?MR.FEYNMAN GOES TO WASHINGTON and others(Feynman,Richard;Leighton,Ralph)
ファインマン,R.P.【著】〈Feynman,Richard P.〉大貫昌子【訳】
1988年(文庫2001年)
原題に忠実なタイトルならば、第1話の「ひとがどう思おうとかまわない」(生い立ちと初恋の人であり最初の妻のアーリーンの思い出)になるところだろうが、「ご冗談でしょう」(これは原題に忠実)との連続性の点を考慮したのだろうか、「困ります」にして成功している。
「困りましたね、ファインマン先生」という小さな話が本書中にあるのだが、それは「いくらホテルが取れないといったって、大先生がそんなところに泊まられては困ります」というお話。
が、それよりも、「ファイマン氏、ワシントンにいく―チャレンジャー号爆発事故調査のいきさつ」(チャレンジャー号事故調査委員会の一員として、柔軟な発想でいかに原因を究明していったか、その顛末を語る)が、「困ります」の真髄であるように思う。
硬直した官僚的体質の大組織が無責任の連鎖で大事故を招いた(日本でも聞いたような展開があった?はまた別の話)過程を、米国各地を東奔西走して現場技術者への聞き取りから明らかにしていき、本論よりも余程真相に迫った付録の形で公開することが出来たプロセスが詳細に記載されている。
じつは、このとき先生はがんが転移しまくってもぐらたたき状態のお体。
NASA側に言わせれば、「そんなことまで突っ込んで明らかにされては困ります、先生」だったろう。
じつは低温になると問題の‘Oリング’が弾性を失うことはNASAの一部でも承知していて、それを打ち明けられた調査委員会メンバーのクティナ空軍大将(先生とは意気投合)が先生に、「キャブレターをいじりながらひょいと思いついたんですが」と電話で示唆する。
そのヒントでピンと来た先生はOリング問題の追及に掛かり、ロジャーズ委員会席上、シャトルの模型からはずしてきたリングをコップの氷水に突っ込んでみせるという簡単な実験で人々に真相を印象付ける。
動画(後で付加したと思われる解説画像つき?):youtube/Richard Feynman talks about the O ring
あとで振り返ってみると、大将は内部通報者を危険にさらさないよう、たくみに先生にヒントを与えていたのだと気付く…と「真相の真相」まで明らかにされる。
wiki/Space_Shuttle_Challenger_disaster
中尾政之教授の失敗百選
問題の付録:Personal Observations on Reliability of Shuttle by R. P. Feynman
本書中の1節の元の動画:youtube/「ものをつきとめることの喜び」1983年BBCインタビュー(1/5) ⇒ 2/5~5/5も続く。
おまけ:
ユダヤ移民の3代目が初代に捧げたオマージュ(故グールド博士の「ナチュラル・ヒストリー」誌連載エッセイの最終回):
naturalhistorymag/I Have Landed By Stephen Jay Gould