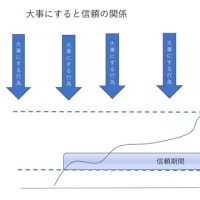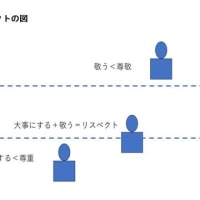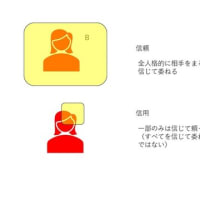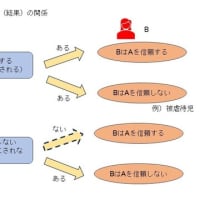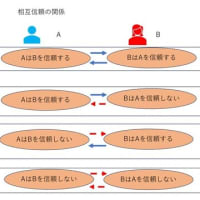今年のテーマは、自分的には、チーム学習です。
市立松戸高校勤務時代に、「学び方かの学びseason1-個人の学び編」を執筆し、生徒向けに補習したりしてきました。この資料については、ダウンロードコーナーにおいてあり、どなたでもダウンロードしてお使いいただけます。
さて、では、組織が学習していくときのセオリーにはどういったものがあるのでしょうか? 最近ではコーチングなどの本も個人向けから組織学習や企業エクゼクティブ向けの本が多くなってきました。時代の要請がそうさせているのでしょう。
組織学習では、ピーターセンゲの「最強組織の法則」p261のお話をちょっと紹介したいと思います。
***ここから引用
チーム学習のディシプリンでは、意見交換とディスカッションという二つの異なる対話方法をマスターする必要がある。意見交換では複雑で微妙な問題を自由かつ建設的に探究し、お互いの意見を十分に「聴き」、自分の考えを呈示する。対象的に、ディスっションでは、、さまざまな考えを述べたり弁護して、そのときに下さねばならない決定をサポートするにはどの考え方が最善かを探究する。意見交換とディスカッションには、潜在的に互いに補足し合うが、両者の違いを見分けて、意識して使い分けるチームは実際ほとんどない。
***ここまで引用
意見交換については、自由かつ建設的に探究するのですから、まずは、どのような意見がでてきたとしても、まずは受け止める受容の深さがメンバーに要求されます。普通、自分とは異なる意見に対してはすぐに反論したくなりますが、そうした場面でもうまく保留し、相手の意見や主張を構造としてとらえるような思考方法が必要となります。これは、そのような保留や相手のスタンスを洞察する力を経験から学ぶことで成長させられるのではないかという予感がしています。
一方で、組織では多種多様に出てきた案から、なんらかの決定を下さなくてはなりません。そうした決定の合意プロセスをいかになしていくのは、チーム学習として難しいところであり、探究の余地があるところで、まだまだ個人的には結論が出せまていません。
テレビの討論番組では、その道のプロや深い見解を持っている、あるいは実行力のある人々がそろって出てくるわけですが、他人の主張には耳を決して貸さなかったり、合意形成に向けて何か探究しっているなぁという風景は残念ながらほとんど見ることがありません。 こうした出演者がチームとして作用し、新たな政策などをその場で打ち出していくことができたらどんなに素晴らしいのになぁと思いながら、観ていますが。
私個人のテーマとしては、この部分をどのように教育で担うことができるのだろうかという点です。今後も深めていきたいと思います。
ブログで言わば公開で、こうした疑問を呈しているのも、不特定多数の読者の方に対しての情報共有・・・・ となっていればいいのですが・・・

市立松戸高校勤務時代に、「学び方かの学びseason1-個人の学び編」を執筆し、生徒向けに補習したりしてきました。この資料については、ダウンロードコーナーにおいてあり、どなたでもダウンロードしてお使いいただけます。
さて、では、組織が学習していくときのセオリーにはどういったものがあるのでしょうか? 最近ではコーチングなどの本も個人向けから組織学習や企業エクゼクティブ向けの本が多くなってきました。時代の要請がそうさせているのでしょう。
組織学習では、ピーターセンゲの「最強組織の法則」p261のお話をちょっと紹介したいと思います。
***ここから引用
チーム学習のディシプリンでは、意見交換とディスカッションという二つの異なる対話方法をマスターする必要がある。意見交換では複雑で微妙な問題を自由かつ建設的に探究し、お互いの意見を十分に「聴き」、自分の考えを呈示する。対象的に、ディスっションでは、、さまざまな考えを述べたり弁護して、そのときに下さねばならない決定をサポートするにはどの考え方が最善かを探究する。意見交換とディスカッションには、潜在的に互いに補足し合うが、両者の違いを見分けて、意識して使い分けるチームは実際ほとんどない。
***ここまで引用
意見交換については、自由かつ建設的に探究するのですから、まずは、どのような意見がでてきたとしても、まずは受け止める受容の深さがメンバーに要求されます。普通、自分とは異なる意見に対してはすぐに反論したくなりますが、そうした場面でもうまく保留し、相手の意見や主張を構造としてとらえるような思考方法が必要となります。これは、そのような保留や相手のスタンスを洞察する力を経験から学ぶことで成長させられるのではないかという予感がしています。
一方で、組織では多種多様に出てきた案から、なんらかの決定を下さなくてはなりません。そうした決定の合意プロセスをいかになしていくのは、チーム学習として難しいところであり、探究の余地があるところで、まだまだ個人的には結論が出せまていません。
テレビの討論番組では、その道のプロや深い見解を持っている、あるいは実行力のある人々がそろって出てくるわけですが、他人の主張には耳を決して貸さなかったり、合意形成に向けて何か探究しっているなぁという風景は残念ながらほとんど見ることがありません。 こうした出演者がチームとして作用し、新たな政策などをその場で打ち出していくことができたらどんなに素晴らしいのになぁと思いながら、観ていますが。
私個人のテーマとしては、この部分をどのように教育で担うことができるのだろうかという点です。今後も深めていきたいと思います。
ブログで言わば公開で、こうした疑問を呈しているのも、不特定多数の読者の方に対しての情報共有・・・・ となっていればいいのですが・・・