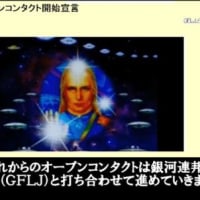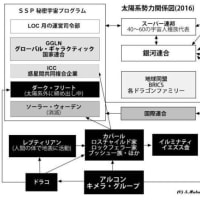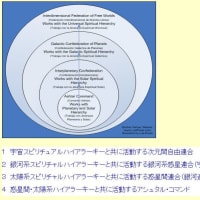【東京新聞2006年3月27日】
中国安徽省蚌埠市でこのほど、約7000年前の新石器時代の遺跡から、風景や人々の生活などを表現した文字のような絵や記号が大量に見つかった。新華社が26日までに報じた。
 専門家は、3000年以上前の中国最古の文字とされる「甲骨文字」を大きくさかのぼる漢字のルーツの1つとみている。絵や記号が刻まれているのが土器か陶器かは不明だが、同省考古研究所の研究者らによると600点以上あり、山や川、太陽、動植物、狩猟、養蚕など多様なテーマを描写。当時の衣食住の状況から、宗教、信仰まで示しているという。
専門家は、3000年以上前の中国最古の文字とされる「甲骨文字」を大きくさかのぼる漢字のルーツの1つとみている。絵や記号が刻まれているのが土器か陶器かは不明だが、同省考古研究所の研究者らによると600点以上あり、山や川、太陽、動植物、狩猟、養蚕など多様なテーマを描写。当時の衣食住の状況から、宗教、信仰まで示しているという。
中国では昨年も、寧夏回族自治区で1万年以上前のものとみられる大量の絵文字が見つかったと報じられている。
(以上:共同通信)


豊国(トヨクニ)文字の読み方
◆古代文字の真実[6]トヨクニ文字とサンカ文字と中国の絵文字
http://utukusinom.exblog.jp/9661239/
今回発見された中国古代の絵文字が、日本の神代文字の1つ豊国文字であるという解釈が発表されている。豊国文字を基につくられたとされるサンカ文字とも類似すると言われている。

これまでの通説では、漢字の起源と発達は、次のように説明されてきた。
殷(BC1700-BC1046)に於いて卜の結果を書き込むための使用された文字である。これを現在甲骨文字(亀甲獣骨文)と呼ぶ。秦(BC778-BC206)そして後の漢代(BC206-AD220)になると、下級役人を中心に使いにくい小篆の飾り的な部分を省き、曲線を直線化する変化が起こり、これが隷書となった。毛筆で書かれる木簡や竹簡に書き込む漢字から始まった隷書は、書物から石碑に刻まれる字にまで及んだ。この隷書を走り書きしたものは「草隷」と呼ばれたが、やがてこれが草書となった。一方で、隷書をさらに直線的に書いたものが楷書へ発達し、これをさらに崩して行書が生まれた。
今回の発見によって、これまで中国最古の文字と考えられてきた甲骨文字のはるか過去に別の絵文字が使われていたことが明らかにされたことによって、甲骨文字の起源が日本の神代文字にある可能性が高まった。日本では、漢字を移入するずっと以前からひらがなやカタカナの原型となる神代文字が使われており、それが世界各地に普及して、それぞれの民族の文字のルーツになったと推測することもできる。これまで最古の歴史書と考えられてきた古事記・日本書紀のはるか過去に神代文字で記述された古史古伝(こしこでん)の信ぴょう性が改めて高まったと言える。
☆F★
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・