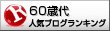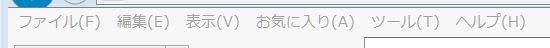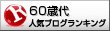親が亡くなると不動産の相続登記なんてことが発生するわけで、
言葉を聞いただけで面倒臭そう、なわけで、、。(^^;
かといって、何でも自分でしたがる難儀な性格は司法書士の手を煩わせたくないわけで、、。
ま、単に節約が好きなだけだけど。(笑)
いろいろネットで調べているウチにオンライン登記が割と簡単だとわかった。
多分もう二度とこんな事をすることもないとは思うが、備忘録的に書いておく。
何かのご参考になれば幸い。
まず、言葉でつまずく。(^^;
不動産の謄本って今じゃ、「登記事項証明書」と言うらしい。
全く同じものをさすわけではないが、効力は同じらしい。
その登記事項証明書そのものは不動産の相続登記に提出するわけでもないが
遺産分割協議書を作成するとき、正確に所在や名称を記す為にそれを見ながら書くわけ。
これを間違えると突き返される、らしい。(^^;
では、その登記事項証明書をどうやって入手するか。
当然、、当該法務局に出向けば手に入るが、そこはそれネットの時代、
オンラインで入手可能。
「オンライン登記」で検索すれば関連サイトが出てくるから指示に従って
ソフトのダウンロードをすれば法務局にアクセス出来る。
ふつうにパソコンを使っている人ならそんなに難しい作業ではない。
但し、サイトにアクセス出来るのは平日夜9時まで。夜中にパコパコとはいかない。(^^;
で、指示されるまま、必要事項を入力して送信すれば、しばらくして「納付」
という欄に料金が示される。
これまた、ネット送金すればいいわけ。
確か一通500円で送料込み。速達にして欲しければ別途料金。
殆ど二日後には目的の登記事項証明書が手に入る。
これとは別途に、不動産の評価額証明なるものを取る必要がある。
これは法務局ではなく物件管轄の市町村役場で入手。
ネットでその市町村のサイトに行けば、ちゃんと評価額証明の取り方や
申請書式が出てくる。ただ、郵送でも取れるがその場合料金は郵便為替と
指定されるようで、ほんの300円を送るのに郵便為替料金100円を支払うハメになる。(^^;
以上を集めて、今度は相続関係説明図なるものを作る。
これは、パソコンでオフィスを使っている人なら、難なく出来るはず。
それをPDF形式で保存しておく。
さらに、遺産分割協議書を作る。
これも、ネットに見本がいくらでもあるから、登記事項証明書を片手に
間違いの無いように記入する。そして関係者全員の実印を押して印鑑証明を準備。
当然、分割協議書を作る前には相続人全員の同意が得られていなければならない。(^^;
同時に準備するものとして、まず被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までを
記載した戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、当該物件を相続する人の住民票と申請者本人の
電子証明書などを入手しておく。電子証明書も役所で発行される。
これらの準備をして、先にDLした法務局のソフトを立ち上げ、不動産登記-相続の頁から
手続きを開始する。
この手続きをしたら二日以内に簡易書留で戸籍謄本などの書類を郵送するか持参する。
ま、ざっとこんな具合ですわ。って、まだ事の途中なんですけどね、当方は。(笑)
ん?面倒臭そう?
では、やはり司法書士さんに頼みましょう。(^^;
さて、本日の農事通信は、初なり胡瓜の花。
これ、どうせ大きくは成らない。雄花がまだ咲いてないもん。(^^;

お帰り前に、宜しければ応援のワンクリック↓をお願いします。m(_ _)m