「硝子のハンマー」で、物凄く論理的なミステリー(って、なんとなく頭痛が痛いみいな表現ですね)を見せられて、この人の書くホラーってどんなのだろうと興味を持って買ってきた本です。
イメージが重なるのは小林泰三ですが、彼のホラーは、意表をつくアイデアをスプラッタ仕立てにして見せるもので、オチがないのがホラーだとすると、小林泰三は、きっちりオチをつけながら怖がらせるために、生理的嫌悪感側に走ってしまったという感じがします。
逆に貴志祐介は、サイコのほうへ行ったようです。
主人公はエンパス能力を持つおそらく20代前半の女性由香里です。テレパスが思考を読むのに対し、エンパスというのは相手の感情を感じる能力だそうです。
舞台は阪神大震災直後の西宮。主人公は自分の能力を活かして、震災後のPTSDに襲われて生きる気力をなくした人を助けるボランティアに従事しています。
その由香里の前に現れたのが、多重人格の少女千尋。千尋の分裂した人格の中に非常に危険なものが存在することを察知した由香里は、彼女が通う高校のカウンセラーに警告を発し、手を引こうとするが...。
サイコホラーというのは、身近にいる人間が突然理解できない振る舞いを始めるというところに、恐怖の源泉を置いていると思います。
メインテーマである13番目の人格の正体は、とてもSF的な解釈がなされていて、そういう意味でも面白いのですが、クライマックスの後、そのまま終わってしまえば、単なるホラー風SFで終わってしまったでしょう。クライマックスシーンの後で、やっぱりきっちり謎解きをしてしまうとホラーの怖さが半減するなと思いながら、後日譚に入りましたが、ラストはやはり十分怖いですね。理に落としすぎないバランス感覚はさすがだと思いました。
同じようなしかしこちらはSFで筒井康隆の「家族八景」「七瀬ふたたび」があります。非常にペシミスティックな小説で、高校生の頃の僕はかなり大きな影響を受けました。貴志祐介もこの小説(あるいはこの小説によって提示されたテーマ)を意識しているように感じているシーンはありましたが、そのテーマに対しては、あえて救いを用意していることに、共感しました。まあ、こちらはこの小説の本来のテーマでもないし、そういうところでは家族八景から30年経ったんだなあという感慨と時代の成熟を感じました。
イメージが重なるのは小林泰三ですが、彼のホラーは、意表をつくアイデアをスプラッタ仕立てにして見せるもので、オチがないのがホラーだとすると、小林泰三は、きっちりオチをつけながら怖がらせるために、生理的嫌悪感側に走ってしまったという感じがします。
逆に貴志祐介は、サイコのほうへ行ったようです。
主人公はエンパス能力を持つおそらく20代前半の女性由香里です。テレパスが思考を読むのに対し、エンパスというのは相手の感情を感じる能力だそうです。
舞台は阪神大震災直後の西宮。主人公は自分の能力を活かして、震災後のPTSDに襲われて生きる気力をなくした人を助けるボランティアに従事しています。
その由香里の前に現れたのが、多重人格の少女千尋。千尋の分裂した人格の中に非常に危険なものが存在することを察知した由香里は、彼女が通う高校のカウンセラーに警告を発し、手を引こうとするが...。
サイコホラーというのは、身近にいる人間が突然理解できない振る舞いを始めるというところに、恐怖の源泉を置いていると思います。
メインテーマである13番目の人格の正体は、とてもSF的な解釈がなされていて、そういう意味でも面白いのですが、クライマックスの後、そのまま終わってしまえば、単なるホラー風SFで終わってしまったでしょう。クライマックスシーンの後で、やっぱりきっちり謎解きをしてしまうとホラーの怖さが半減するなと思いながら、後日譚に入りましたが、ラストはやはり十分怖いですね。理に落としすぎないバランス感覚はさすがだと思いました。
同じようなしかしこちらはSFで筒井康隆の「家族八景」「七瀬ふたたび」があります。非常にペシミスティックな小説で、高校生の頃の僕はかなり大きな影響を受けました。貴志祐介もこの小説(あるいはこの小説によって提示されたテーマ)を意識しているように感じているシーンはありましたが、そのテーマに対しては、あえて救いを用意していることに、共感しました。まあ、こちらはこの小説の本来のテーマでもないし、そういうところでは家族八景から30年経ったんだなあという感慨と時代の成熟を感じました。










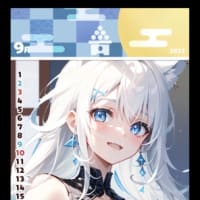









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます