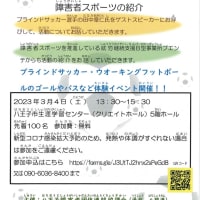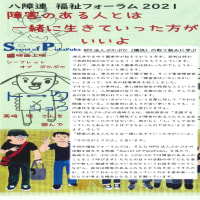八障連通信335号をアップします。
八障連通信335号【PDF版】はこちらから
八障連通信335号音声版です。
・事務局通信Vol.48音声版はこちらから
・編集部より音声版はこちらから
・お知らせ掲示板音声版はこちらから
・2018年定期総会に向けて音声版はこちらから
・連載コラム vol.17 『自分の言葉で考える』音声版はこちらから
注釈 馬場村塾について
・医療法及び医師法改正案の閣議決定・国会上程に関する緊急声明について音声版はこちらから
・会費振込先音声版はこちらから
音声版協力(南大沢音訳の会こだま)
ここからは八障連通信335号本文です。
【事務局通信 Vol.48】
新年度が始まり、単価改正があり、初めての請求が終了したと頃だと思いますが、各事業所の皆様、いかがでしょうか。各事業にはそれぞれの役割があると思われますが、今回の単価改正はそれぞれの事業所によって大きな変化があったと思われます。単価改正により、今までの収入を維持するため、新たなサービスを設けたりと、各事業所におきましては大変ご苦労されていると思われます。また、今まで無償で行っていた支援が認められ加算対象になったりなど、今後この様なサービス・単価の変更により時間を追う毎に問題点などの不具合が出てくると思われます。その変更がもとでサービスを利用されている方や、サービスを提供されている事業者に不安をもたらすのであれば、八障連はそれらの問題について、行政への改善要望など皆様の声を出来る限り届けていきたいと考えております。そのために、今年度も市の福祉部や必要な担当課などと懇談会を持ち、市議会の議員の方々とも問題共有をし、場合によっては代替えのサービスの構築など提案していきたいと考えております。
しかし、これらの問題に取り組むためには、皆様の声は欠かせないので、日々の業務でお忙しいとは思いますが、ぜひ現場の声を聞かせてください。また、八障連として多くのニーズに対応するために、活動にご理解をいただき、ご協力していただける方を引き続き受け入れさせていただきたいと考えております。障がい当事者の方や、各施設の職員さんなど八障連の活動
にご興味のある方、ぜひご協力をいただき活動をしていきたいと考えております。最初から事務局となると抵抗があるということであれば、会議に参加をしてどのような話し合いをしているのか知っていただくことからでも構いません。活動自体はなかなかできないけど、八障連でこのような活動をしてもらえないかなど提案もいただきたいと思いますので、みなさまよりご意見ご要望など、お待ちしております。(文責/立川)
【編集部より】
今国会に「医療法及び医師法改正案」が上程されていますが、これに関し、全国「精神病者」集団から緊急声明が発せられていますので、全文掲載しました。ご存知の通り、日本における精神科医療は他国と比べると突出して「隔離型」です。統計は少し古いですが 2014 年度の OECD(経済協力開発機構)がまとめた報告書では、人口十万人あたりの精神科病床数は加盟国平均が「六十八床」に対し、日本は約四倍弱の「二百六十床」に上ると指摘されています。
また近年「重度かつ慢性」という規定が登場して、厚労省の補助事業では現在長期入院している患者の約 6 割が「重度かつ慢性」に該当するとされ、国の 2018 年度障害福祉計画の策定の議論の中では、「重度かつ慢性に該当しない長期入院精神障碍者の地域移行を目指す」とされています。こうした背景を踏まえて今国会に上程されている「医療法及び医師法改正案」を読むと「緊急声明」が指摘するような問題点が浮かび上がってきます。「モリ・カケ」や「セクハラ」問題で国会は紛糾していますが、「医療法・医師法」改正案の動きにも注目していきたいものです。
【お知らせ掲示板】
✦八障連の総会は 5 月 19 日(土)となります。多くの会員の参加をお願いいたします。その際は必ず「総会議案書」をご持参ください。また同封の総会出欠はがきは、必ず 5/14 までにお出しください。(運営委員会)
【2018定期総会に向けて 八障連代表 杉浦 貢】
おかげさまで、代表を務めて 3 年目を迎えさせていただくことができました。八障連の正式名称は『八王子障害者団体連絡協議会』であり、所属団体としては『特定非営利活動法人 E-SMILE』の訪問介護事業所 COLORS から出てきている形になっていますが...個人としての思いは法人として、事業所として、というよりは...八王子に暮らす一人の市民として、障害当事者として...福祉サービスの利用者として何が発信できるのか、についてずっと考え続けて来た気がします。
保健、医療、福祉、教育、労働などの分野で様々な人や機関と連携し、相談支援体制の充実などを図り、本人の意向に基づいた必要な支援を...という、設立当初から八障連が目指してきた理念は現在、「八王子市障害者地域自立支援協議会」という形で具体化され、かつての八障連が地域に対して担ってきた役割も、自立支援協議会に移行しつつあります。では、八障連の役割は、もう終わってしまったのでしょうか。私も、他の運営委員も、この数年この課題について考えてきました。
八障連は規模も大きく、歴史の長い団体ですが...近年ではイベント等を開催しても、実働で参加できる運営委員のも少なくなっており、計画を立ててもなかなか思うような活動ができない点も悩ましいところです。残念ながら、2018 年度は今までの活動を縮小するようなことになると思います。 しかし、世の中の激しいその陰に隠れてつい見落とされがちな...生きづらさ、暮らしにくさを抱えている一人一人の障害当事者の小さな悩みにも寄り添っていける団体でありたいと考えてきました。
目が見える。耳が聞こえる。手足が動く。字が読める。計算ができる。毎日を明るく楽しく過ごせる。...何かが『できる』というときには、必ずそれが『うまくできない』と言う人が必ずいるのだということ...障害の無い人に福祉の実情を理解してもらう試みだけではなくて、障害当事者同士が他障害を理解する機会を作ること。また、自分たちの身の回りを支え、力を貸してくれる人々...いわゆる支援者や家族といった人たちが、どんな気持ちで自分たちの傍(かたわら)にいるのか、もっと極端に言ってしまえば『支援者は利用者の召使いではない』ということ。大きく語るならば、異なる立場の人の人を繋(つな)ぐ役割を果たすということ
は、いかに八障連が小さくなろうと、必要な仕事だと思うのです。
団体の顔、代表としての立場であるなら新年度の総会に向けた言葉としてはもっと明るく、前向きな指針を述べるべきでしょう。しかし、目の前は見えず、ゆく道もなかなか定まらない状態では、希望より不安の方が大きい...というのが、偽らざる本音です。一つだけ、みなさんにお約束できることがあるとするなら、どんな場合にも諦めない、前に進むことをやめない、ということでしょうか。頼りないとお叱(しか)りなる方もおられることと思います。情けないと呆(あき)れる方もおられるでしょう。私自身、これまで八障連を支えてこられた諸先輩に比べて、自分はなんと力がないのかと落ち込んでしまうこともよくあります。加盟団体のみなさまにお願いがあります。日中の業務がお忙しい、ということもあるでしょう。日々、利用者さんと向き合うということも、大切なお仕事ですし、並大抵のことではないということも、よく分かっているつもりです。ほんの微力...短い時間で構いません。どうぞ八障連にみなさんのお力をお貸しください。一緒に、三年先、五年先の八王子の福祉について、身近なところから考えてみようではありませんか。
来たる 5 月 19 日には、前年度の活動を総括し、新年度の活動の指針となる総会を行う予定です。ぜひ多くの方にご参加によって、八障連を見守っていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 (文責 杉浦)
【連載コラム vol.17 『自分の言葉で考える』 ハーネス八王子 鈴木 由紀子】
4月 30 日の午後、私は古い友人の一人を誘って「馬場村塾(ババソンジュク)」というイベントに初めて出かけて大きな刺激を受けた。以下、その日の感想を書いてみる。
私がまず関心を持ったのは「馬場村塾」という名前の付け方である。「○村塾」と聞いて私がすぐに思い浮かべるのは、江戸時代末期、現在の山口県萩市で吉田松陰が主催した「松下村塾(ショウカソンジュク)」。そこから明治期の日本を支えた志士たちが出たことで有名である。しかし馬場村塾は、東京都新宿区の高田馬場駅周辺で、2015 年 4 月から、ほぼ毎月 1
回のペースで行われている「多様性を育てる」ことを目的とした勉強会だという。高田馬場駅周辺には、点字図書館や点字出版書など視覚障害関連の施設や企業、それに東京都盲人会連合のような当事者の活動拠点が多く集まっている。それらの施設や企業の職員の有志が提案してこのイベントを企画しているそうで、その試みは画期的なことだと思われる。
馬場村塾の集まりでは、まずテーマに基づく講師が講演をし、その後参加者全体で意見交換をしながら、内容についてみんなで考えるという創造的な場である。
4 月 30 日の講師は、橋本宗明(ハシモト・ムネアキ)さんの 86 年のあゆみを教えていただく会。橋本さんは元全日本視覚障害者協議会会長、元ロゴス点字図書館館長などとして大きなお仕事を成し遂げた方。視覚障害者の生活環境、社会環境の改善に大きな役割を果たしたキーパーソンである。静かだが熱のこもったその話しぶりに、橋本さんの真っすぐな生き方と、い
つも目の前のことに真剣に取り組もうとするお姿がにじみ出ていると思いながら、そのお話に耳を傾け続けた。
1 時間強のお話の中で私が特に興味深かったのは、経営難を抱えたロゴス点字図書館の立て直し役を任せられたときの体験談である。当時その図書館には借金もあり、職員の給料も十分に払えない。その状況を立て直してほしいという注文である。
そこで橋本さんを中心とした図書館の職員たちは、社会福祉法人格を取るのに必要なだけの資金と蔵書(点字書や音訳図書)を何とかして集め、東京都から人件費などの補助を受けながら運営するという計画を立てた。匿志家(とくしか)の助けや、幸運な寄付の申し出もあり、必要な財産は、思いのほか順調に集まった。ところが、そのころ東京都内には点字図書館がすでに 3 施設あり、4 施設目の点字図書館の存在理由を、東京都の担当者に十分わかるように論証せよと言われたという。そこで橋本さんは、ご自身の若いころから積み重ねた知識や物事の考え方を使って、ひたすらその論理を組み立てたそうだ。
橋本さんが 14 歳のとき、日本が第二次世界大戦に敗れた。そのため、それまでの価値観がすべて一度にひっくり返されて、親も信じられないほど、非常に苦しんだ。そのころ同時に、失明と結核という病気にも苦しめられていた。それで「どうして、こんなつらい目に遭(あ)うのだろう。どうして生きる意味があるのか」と考えた。しかし、やがて、人生には十分に生きる意味があり、前向きに生きようと考えるようになった。そこで、新たな図書館構想においても、十分に教育が受けられない視覚障害者が人生について、世界について考えるヒントを与えるような本をどんどん作って、希望のある、明るい生き方をしてもらいたい。そのために「考える図書館」を運営したいと述べたという。東京都の福祉局の担当者にそのように説明したら理解してもらえて、やがて、その図書館に社会福祉法人格が与えられ、現在に至っている。私の聞き漏(も)らしたこともありそうだが、おおよそ、このような経緯を話してくださった。
お話の最後のほうで、橋本さんから私たちに特に伝えたいこととして、誰かの言葉を受け売りするのでなく、自分の言葉で、正面から向き合って考えるべきである。そのようにして、自分なりの確かな答えを導き出せたなら、相手を納得させられるだけの合理的な説明もできるはずだとも述べた。普段忙しさを理由にして、考えることを面倒くさがったり、逃げていたりする私に、その日の橋本さんの言葉が鋭く響いた。
《馬場村塾について》
「視覚障害」に関係する施設や団体・企業などが多く集まる高田馬場で、世代を超えた交流の場を増やそうと、2015年4月、「馬場村塾」が結成されました。主な活動として、月1回開かれる視覚障害当事者や支援団体・企業など関係者によるプレゼンで、聴講後には参加者を交えて意見交換などを行っています。(http://nichimou.org/welfare/180416-jouhou-2/より引用しました。問い合わせ等はこのサイトへ。 編集部)
【医療法及び医師法改正案の閣議決定・国会上程に関する緊急声明】
3 月 13 日、医療法及び医師法改正案が閣議決定されました。医療法及び医師法改正案に係る全国「精神病」者集団の声明をご紹介します。電気ショック治療のために地方の医師を確保したり、長期在院者が入院する病床をそのままにして医師を動員したりと、非常に問題が多い法案だと思います。既に 3 月 8 日に立憲民主党が法案のヒアリングを実施し、複数の反対意見があがったようです。
本日 3 月 13 日、医療法及び医師法改正案が国会に上程されました。医療法及び医師法改正案自体は、医師の偏在を解消するための計画の策定を趣旨としたものです。これだけだと医師の少ない過疎地の医療などの解消に向かっているように聞こえますが、実際には、必ずしもそれだけではありません。
法案概要資料によると医師偏在指標は、医療計画の基準病床値に基づき設定することとなっており、この医療計画の基準病床値(精神病床)の算出根拠にこそ看過できない重大な問題があります。第 7 期医療計画の基準病床値(精神病床)は、1 年以上の長期入院者(認知症を除く)の約 7 割が「重度かつ慢性」であるため退院できないとする係数aを採用します。また、それらの者は係数bといって修正型電気ショックとクロザピンの計画的普及によって解消されることとされています。修正型電気ショックとクロザピンは侵襲性が高いため、私たち精神障害者の多くが怖れているものです。
このことから医療法及び医師法改正案に基づく医師確保計画は、日本の多すぎる精神病床を減らさずにして、1年以上長期在院者の約 7 割を入院させ続ける前提で病棟の人員として“足りない”医師を増やすための計画ということになります。あるいは、修正型電気ショックをするための麻酔科医が田舎にはいないから医師確保計画で麻酔科医を増やすだとか、クロザピンをするための血液内科医が田舎にはいないから医師確保計画で血液内科医を増やすだとかが現実の話しとして浮上してきます。
こうした算定式による医療計画を前提とした全ての政策は、他の関連法案によって追認されるべきではありません。
障害者基本法における障害は、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用と認められるようになりました。しかし、「重度かつ慢性」の基準は、精神科病院に長期在院している人の置かれている不条理を当該精神障害者の機能障害に原因を帰責しようとするものであり、ひいては精神科医療従事者が研鑽して実践の水準をあげる機運を下げ、多くの人が指摘する国策の誤りについて容認することにもつながります。
そして、「重度かつ慢性」とされた長期在院患者は、今後も精神科病院において長期在院を余儀なくされることになりかねません。たとえ実際に精神障害者が重度で慢性症状を呈しているとしても地域で暮らす権利があることを確認し 、こうした係数の採用を前提としたあらゆる施策が見直されるべきであることを強く主張します。
2018 年 3 月 13 日 全国「精神病」者集団
八障連通信335号本文はここまで
八障連通信335号【PDF版】はこちらから
八障連通信335号音声版です。
・事務局通信Vol.48音声版はこちらから
・編集部より音声版はこちらから
・お知らせ掲示板音声版はこちらから
・2018年定期総会に向けて音声版はこちらから
・連載コラム vol.17 『自分の言葉で考える』音声版はこちらから
注釈 馬場村塾について
・医療法及び医師法改正案の閣議決定・国会上程に関する緊急声明について音声版はこちらから
・会費振込先音声版はこちらから
音声版協力(南大沢音訳の会こだま)
ここからは八障連通信335号本文です。
【事務局通信 Vol.48】
新年度が始まり、単価改正があり、初めての請求が終了したと頃だと思いますが、各事業所の皆様、いかがでしょうか。各事業にはそれぞれの役割があると思われますが、今回の単価改正はそれぞれの事業所によって大きな変化があったと思われます。単価改正により、今までの収入を維持するため、新たなサービスを設けたりと、各事業所におきましては大変ご苦労されていると思われます。また、今まで無償で行っていた支援が認められ加算対象になったりなど、今後この様なサービス・単価の変更により時間を追う毎に問題点などの不具合が出てくると思われます。その変更がもとでサービスを利用されている方や、サービスを提供されている事業者に不安をもたらすのであれば、八障連はそれらの問題について、行政への改善要望など皆様の声を出来る限り届けていきたいと考えております。そのために、今年度も市の福祉部や必要な担当課などと懇談会を持ち、市議会の議員の方々とも問題共有をし、場合によっては代替えのサービスの構築など提案していきたいと考えております。
しかし、これらの問題に取り組むためには、皆様の声は欠かせないので、日々の業務でお忙しいとは思いますが、ぜひ現場の声を聞かせてください。また、八障連として多くのニーズに対応するために、活動にご理解をいただき、ご協力していただける方を引き続き受け入れさせていただきたいと考えております。障がい当事者の方や、各施設の職員さんなど八障連の活動
にご興味のある方、ぜひご協力をいただき活動をしていきたいと考えております。最初から事務局となると抵抗があるということであれば、会議に参加をしてどのような話し合いをしているのか知っていただくことからでも構いません。活動自体はなかなかできないけど、八障連でこのような活動をしてもらえないかなど提案もいただきたいと思いますので、みなさまよりご意見ご要望など、お待ちしております。(文責/立川)
【編集部より】
今国会に「医療法及び医師法改正案」が上程されていますが、これに関し、全国「精神病者」集団から緊急声明が発せられていますので、全文掲載しました。ご存知の通り、日本における精神科医療は他国と比べると突出して「隔離型」です。統計は少し古いですが 2014 年度の OECD(経済協力開発機構)がまとめた報告書では、人口十万人あたりの精神科病床数は加盟国平均が「六十八床」に対し、日本は約四倍弱の「二百六十床」に上ると指摘されています。
また近年「重度かつ慢性」という規定が登場して、厚労省の補助事業では現在長期入院している患者の約 6 割が「重度かつ慢性」に該当するとされ、国の 2018 年度障害福祉計画の策定の議論の中では、「重度かつ慢性に該当しない長期入院精神障碍者の地域移行を目指す」とされています。こうした背景を踏まえて今国会に上程されている「医療法及び医師法改正案」を読むと「緊急声明」が指摘するような問題点が浮かび上がってきます。「モリ・カケ」や「セクハラ」問題で国会は紛糾していますが、「医療法・医師法」改正案の動きにも注目していきたいものです。
【お知らせ掲示板】
✦八障連の総会は 5 月 19 日(土)となります。多くの会員の参加をお願いいたします。その際は必ず「総会議案書」をご持参ください。また同封の総会出欠はがきは、必ず 5/14 までにお出しください。(運営委員会)
【2018定期総会に向けて 八障連代表 杉浦 貢】
おかげさまで、代表を務めて 3 年目を迎えさせていただくことができました。八障連の正式名称は『八王子障害者団体連絡協議会』であり、所属団体としては『特定非営利活動法人 E-SMILE』の訪問介護事業所 COLORS から出てきている形になっていますが...個人としての思いは法人として、事業所として、というよりは...八王子に暮らす一人の市民として、障害当事者として...福祉サービスの利用者として何が発信できるのか、についてずっと考え続けて来た気がします。
保健、医療、福祉、教育、労働などの分野で様々な人や機関と連携し、相談支援体制の充実などを図り、本人の意向に基づいた必要な支援を...という、設立当初から八障連が目指してきた理念は現在、「八王子市障害者地域自立支援協議会」という形で具体化され、かつての八障連が地域に対して担ってきた役割も、自立支援協議会に移行しつつあります。では、八障連の役割は、もう終わってしまったのでしょうか。私も、他の運営委員も、この数年この課題について考えてきました。
八障連は規模も大きく、歴史の長い団体ですが...近年ではイベント等を開催しても、実働で参加できる運営委員のも少なくなっており、計画を立ててもなかなか思うような活動ができない点も悩ましいところです。残念ながら、2018 年度は今までの活動を縮小するようなことになると思います。 しかし、世の中の激しいその陰に隠れてつい見落とされがちな...生きづらさ、暮らしにくさを抱えている一人一人の障害当事者の小さな悩みにも寄り添っていける団体でありたいと考えてきました。
目が見える。耳が聞こえる。手足が動く。字が読める。計算ができる。毎日を明るく楽しく過ごせる。...何かが『できる』というときには、必ずそれが『うまくできない』と言う人が必ずいるのだということ...障害の無い人に福祉の実情を理解してもらう試みだけではなくて、障害当事者同士が他障害を理解する機会を作ること。また、自分たちの身の回りを支え、力を貸してくれる人々...いわゆる支援者や家族といった人たちが、どんな気持ちで自分たちの傍(かたわら)にいるのか、もっと極端に言ってしまえば『支援者は利用者の召使いではない』ということ。大きく語るならば、異なる立場の人の人を繋(つな)ぐ役割を果たすということ
は、いかに八障連が小さくなろうと、必要な仕事だと思うのです。
団体の顔、代表としての立場であるなら新年度の総会に向けた言葉としてはもっと明るく、前向きな指針を述べるべきでしょう。しかし、目の前は見えず、ゆく道もなかなか定まらない状態では、希望より不安の方が大きい...というのが、偽らざる本音です。一つだけ、みなさんにお約束できることがあるとするなら、どんな場合にも諦めない、前に進むことをやめない、ということでしょうか。頼りないとお叱(しか)りなる方もおられることと思います。情けないと呆(あき)れる方もおられるでしょう。私自身、これまで八障連を支えてこられた諸先輩に比べて、自分はなんと力がないのかと落ち込んでしまうこともよくあります。加盟団体のみなさまにお願いがあります。日中の業務がお忙しい、ということもあるでしょう。日々、利用者さんと向き合うということも、大切なお仕事ですし、並大抵のことではないということも、よく分かっているつもりです。ほんの微力...短い時間で構いません。どうぞ八障連にみなさんのお力をお貸しください。一緒に、三年先、五年先の八王子の福祉について、身近なところから考えてみようではありませんか。
来たる 5 月 19 日には、前年度の活動を総括し、新年度の活動の指針となる総会を行う予定です。ぜひ多くの方にご参加によって、八障連を見守っていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 (文責 杉浦)
【連載コラム vol.17 『自分の言葉で考える』 ハーネス八王子 鈴木 由紀子】
4月 30 日の午後、私は古い友人の一人を誘って「馬場村塾(ババソンジュク)」というイベントに初めて出かけて大きな刺激を受けた。以下、その日の感想を書いてみる。
私がまず関心を持ったのは「馬場村塾」という名前の付け方である。「○村塾」と聞いて私がすぐに思い浮かべるのは、江戸時代末期、現在の山口県萩市で吉田松陰が主催した「松下村塾(ショウカソンジュク)」。そこから明治期の日本を支えた志士たちが出たことで有名である。しかし馬場村塾は、東京都新宿区の高田馬場駅周辺で、2015 年 4 月から、ほぼ毎月 1
回のペースで行われている「多様性を育てる」ことを目的とした勉強会だという。高田馬場駅周辺には、点字図書館や点字出版書など視覚障害関連の施設や企業、それに東京都盲人会連合のような当事者の活動拠点が多く集まっている。それらの施設や企業の職員の有志が提案してこのイベントを企画しているそうで、その試みは画期的なことだと思われる。
馬場村塾の集まりでは、まずテーマに基づく講師が講演をし、その後参加者全体で意見交換をしながら、内容についてみんなで考えるという創造的な場である。
4 月 30 日の講師は、橋本宗明(ハシモト・ムネアキ)さんの 86 年のあゆみを教えていただく会。橋本さんは元全日本視覚障害者協議会会長、元ロゴス点字図書館館長などとして大きなお仕事を成し遂げた方。視覚障害者の生活環境、社会環境の改善に大きな役割を果たしたキーパーソンである。静かだが熱のこもったその話しぶりに、橋本さんの真っすぐな生き方と、い
つも目の前のことに真剣に取り組もうとするお姿がにじみ出ていると思いながら、そのお話に耳を傾け続けた。
1 時間強のお話の中で私が特に興味深かったのは、経営難を抱えたロゴス点字図書館の立て直し役を任せられたときの体験談である。当時その図書館には借金もあり、職員の給料も十分に払えない。その状況を立て直してほしいという注文である。
そこで橋本さんを中心とした図書館の職員たちは、社会福祉法人格を取るのに必要なだけの資金と蔵書(点字書や音訳図書)を何とかして集め、東京都から人件費などの補助を受けながら運営するという計画を立てた。匿志家(とくしか)の助けや、幸運な寄付の申し出もあり、必要な財産は、思いのほか順調に集まった。ところが、そのころ東京都内には点字図書館がすでに 3 施設あり、4 施設目の点字図書館の存在理由を、東京都の担当者に十分わかるように論証せよと言われたという。そこで橋本さんは、ご自身の若いころから積み重ねた知識や物事の考え方を使って、ひたすらその論理を組み立てたそうだ。
橋本さんが 14 歳のとき、日本が第二次世界大戦に敗れた。そのため、それまでの価値観がすべて一度にひっくり返されて、親も信じられないほど、非常に苦しんだ。そのころ同時に、失明と結核という病気にも苦しめられていた。それで「どうして、こんなつらい目に遭(あ)うのだろう。どうして生きる意味があるのか」と考えた。しかし、やがて、人生には十分に生きる意味があり、前向きに生きようと考えるようになった。そこで、新たな図書館構想においても、十分に教育が受けられない視覚障害者が人生について、世界について考えるヒントを与えるような本をどんどん作って、希望のある、明るい生き方をしてもらいたい。そのために「考える図書館」を運営したいと述べたという。東京都の福祉局の担当者にそのように説明したら理解してもらえて、やがて、その図書館に社会福祉法人格が与えられ、現在に至っている。私の聞き漏(も)らしたこともありそうだが、おおよそ、このような経緯を話してくださった。
お話の最後のほうで、橋本さんから私たちに特に伝えたいこととして、誰かの言葉を受け売りするのでなく、自分の言葉で、正面から向き合って考えるべきである。そのようにして、自分なりの確かな答えを導き出せたなら、相手を納得させられるだけの合理的な説明もできるはずだとも述べた。普段忙しさを理由にして、考えることを面倒くさがったり、逃げていたりする私に、その日の橋本さんの言葉が鋭く響いた。
《馬場村塾について》
「視覚障害」に関係する施設や団体・企業などが多く集まる高田馬場で、世代を超えた交流の場を増やそうと、2015年4月、「馬場村塾」が結成されました。主な活動として、月1回開かれる視覚障害当事者や支援団体・企業など関係者によるプレゼンで、聴講後には参加者を交えて意見交換などを行っています。(http://nichimou.org/welfare/180416-jouhou-2/より引用しました。問い合わせ等はこのサイトへ。 編集部)
【医療法及び医師法改正案の閣議決定・国会上程に関する緊急声明】
3 月 13 日、医療法及び医師法改正案が閣議決定されました。医療法及び医師法改正案に係る全国「精神病」者集団の声明をご紹介します。電気ショック治療のために地方の医師を確保したり、長期在院者が入院する病床をそのままにして医師を動員したりと、非常に問題が多い法案だと思います。既に 3 月 8 日に立憲民主党が法案のヒアリングを実施し、複数の反対意見があがったようです。
本日 3 月 13 日、医療法及び医師法改正案が国会に上程されました。医療法及び医師法改正案自体は、医師の偏在を解消するための計画の策定を趣旨としたものです。これだけだと医師の少ない過疎地の医療などの解消に向かっているように聞こえますが、実際には、必ずしもそれだけではありません。
法案概要資料によると医師偏在指標は、医療計画の基準病床値に基づき設定することとなっており、この医療計画の基準病床値(精神病床)の算出根拠にこそ看過できない重大な問題があります。第 7 期医療計画の基準病床値(精神病床)は、1 年以上の長期入院者(認知症を除く)の約 7 割が「重度かつ慢性」であるため退院できないとする係数aを採用します。また、それらの者は係数bといって修正型電気ショックとクロザピンの計画的普及によって解消されることとされています。修正型電気ショックとクロザピンは侵襲性が高いため、私たち精神障害者の多くが怖れているものです。
このことから医療法及び医師法改正案に基づく医師確保計画は、日本の多すぎる精神病床を減らさずにして、1年以上長期在院者の約 7 割を入院させ続ける前提で病棟の人員として“足りない”医師を増やすための計画ということになります。あるいは、修正型電気ショックをするための麻酔科医が田舎にはいないから医師確保計画で麻酔科医を増やすだとか、クロザピンをするための血液内科医が田舎にはいないから医師確保計画で血液内科医を増やすだとかが現実の話しとして浮上してきます。
こうした算定式による医療計画を前提とした全ての政策は、他の関連法案によって追認されるべきではありません。
障害者基本法における障害は、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用と認められるようになりました。しかし、「重度かつ慢性」の基準は、精神科病院に長期在院している人の置かれている不条理を当該精神障害者の機能障害に原因を帰責しようとするものであり、ひいては精神科医療従事者が研鑽して実践の水準をあげる機運を下げ、多くの人が指摘する国策の誤りについて容認することにもつながります。
そして、「重度かつ慢性」とされた長期在院患者は、今後も精神科病院において長期在院を余儀なくされることになりかねません。たとえ実際に精神障害者が重度で慢性症状を呈しているとしても地域で暮らす権利があることを確認し 、こうした係数の採用を前提としたあらゆる施策が見直されるべきであることを強く主張します。
2018 年 3 月 13 日 全国「精神病」者集団
八障連通信335号本文はここまで