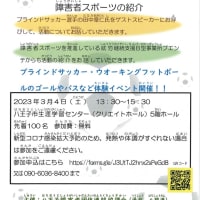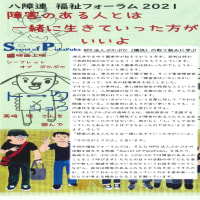もう12月ですね。通信304号のアップを忘れておりました。申し訳ありません。
師走のお忙しい時期とはなりますが、305号と同時にアップさせていただきます。
八障連通信304号【PDF版】はこちらから
これより通信本文となります。
【事務局通信 Vol.19】
9月17日の例会は「まゆだま」さんの活動報告が行われました。その内容については本号にも寄稿いただいておりますが、多くは、もともと肉親である親御(おやご)さんが中心となり活動をしていたところへ障害者自立支援法施行という法改正から必要に迫られて、まゆだまさんも2011年6月に外部の方を理事長に向かえNPO法人を設立した経緯があります。行政が描く体系化された通所サービスのイメージが不確実な中、苦心の末に就労継続支援B型事業としてスタートされましたが、利用者の高齢化や重度障害の方が多い現状から生活介護を中心とした事業所へ転換を図られます。また保護者のニーズと今後を考えるときに相談支援事業や移動支援、グループホームの必要性に着目され、行動に移された経過をお聞きしました。とりわけ、グループホーム設立の過程をお聞きすると、障害者差別禁止条例等の法令が世界レベルから日本国の地方自治体である八王子という生活の場、住まう地域まで波及しているにもかかわらず、依然として障害者への差別が存在する現実を思い知らされました。法整備が何もない時代に、生きていく必然性から生まれた親御さん方々の努力により日中の通い場所である社会参加の場が生まれましたが、今度は法整備によりまた試練を余儀なくされました。しかし弛(ゆる)みなく「必要」なことに対応して新たな事業を創造していく現理事長をはじめ、スタッフや関係者の方々の活動に敬意を払います。例会では様々な意見や質問がありましたが、相談支援事業所「まゆにっと」の名の由来から日戸美代子元八障連代表の話題があがりました。草創期の八障連を支えた人物であり、八王子の地域福祉発展に貢献された方でありますが、懐(なつ)かしい思い出話にも花が咲きました。また席上では、偏見(へんけん)について、更には就労に力点を置いている現障害者支援政策の補完的要素を担う地域生活支援事業が自治体によって大きな違いがある現状があると意見がありました。精神障害の方への支援についても施策の影響による隔(へだ)たりや偏見について意見など現状報告がありました。事業所設置に関わる関係行政機関との折衝(せっしょう)など福祉分野に限らず、「住まう」ことに関連したあらゆる行政、地域などの環境要因について意見交換されました。
お知らせしているとおり、今年度も福祉課や市議会議員の皆様方との懇談会を開催いたします。誤解や偏見は、まず知ってもらうことから第一歩が始まります。私たちに即しても、まず知ることからすべては始まります。他の障害の状況を知る機会がある八障連の活動に感謝しつつ、多くの皆様の活動への参加をお待ちしております。(文責/事務局有賀)
【今後のスケジュール】
10月15日(木)18時より八王子市役所・802会議室で、障害福祉課との懇談会を開催します。ぜひご参加ください。
なお、障害福祉課との懇談会に向けて「要望書」を提出しています。通信(本号)に掲載しておりますので、ご参照ください。
市障害福祉課との懇談会
10月15日(木) 18:00~20:00 八王子市役所 802会議室
七法人学習会
10月31日(土) 14:00~16:30 東浅川保健福祉センター集会室
八障連知的学習会
12月12日(土) 14:00~16:30 クリエイトホール 第2学習室
【要望書】
障害者福祉課御中
八王子障害者団体連絡協議会
代表 杉浦 貢
2015年10月15日八王子市障害者福祉課懇談会のテーマについて
日頃は当会の活動へのご協力をいただき、誠にありがとうございます。また恒例となっております当会との懇談の場をいただいたことを感謝申し上げます。今回の懇談会での主なテーマについてお伝えいたします。当日は地域福祉の更なる発展のために、種々課題について意見交換と課題共有を共々に行い、よりよい街づくりへの機会になればと考えております。
1) 日中活動系施設等運営安定化事業補助金について
財政が難しい状況にある中で、家賃補助を運営安定化目的として死守していただいたことで、新法移行に苦慮する団体、特に通所系事業所にとっては心強い補助事業であります。市より補助事業についての変更を検討しているご説明がありましたが、どのような補助の在り方になるか事業所としては関心の高いところであります。新法移行から運営が安定している事業所もあれば、1日の利用者数によって給付費(運営費)が左右する法形態によって、利用者数の確保の難しさから運営が厳しい事業所もあります。現行の補助がなくなることで、最大で180万円がなくなることになります。これは非常勤職員を雇える金額ともなります。マンパワーの削減や運営の弱体化にならないよう、また運営が安定していない事業所もある現状を考慮していただき、来年度以降も安定化事業の存続をお願いいたします。
2) 視覚障害者の方々が使用する点字ディスプレイ購入の補助について
パソコンなどのデータを点字で確認できる点字ディスプレイは視覚障害の方にとって有用なものとなります。現状、市では視覚障害者及聴覚障害の重度重複障害者 のみが日常生活用具給付の対象となっております。視覚障害のみでも日常生活用具給付対象となるようお願い致します。
3) 地域活動支援センターの運営費について
現在、八王子市では地域活動支援センターⅢ型として「わくわく」「パオ」の2か所が委託を受けて活動されています。新法移行後に就労継続支援B型事業所は工賃増額が義務つけられ、授産事業が活発に変化している事業所が増えていると思います。一方、そうした作業活動にはなじまない障害状態の方々のニーズは存在します。また重度の方や「わくわく」のような就業している障害者へ離職率を防ぐための必要なサービスを展開している事業所もあります。そうした活動を支える運営費は職員確保には厳しい現状があります。給付事業サービスの狭間にあるニーズに応えることが地域支援事業では可能です。ぜひ地域活動支援センターの運営強化をお願い致します。
以上、どうぞよろしくお願い致します。
【9月例会報告 NPO法人まゆだま報告】
9月17日の例会では、NPO法人「まゆだま」さんより報告をいただきました。34年前にさかのぼる「まゆだま」の創設時から現在に至る経過の中で遭遇した困難、またそれを乗り越えての今後の方向性等を語っていただきました。例会での活動報告をふまえ、細野理事長よりコンパクトにまとめていただいたレポートを執筆していただきました。以下掲載します。(編集部)
「NPO法人 まゆだまのいま」理事長 細野 満里
NPO法人まゆだまの生い立ちは、八王子養護学校(現八王子特別支援学校)の卒業生の保護者により、我が子の「親亡き後も地域で安心な暮らしを」を目標に授産事業を34年前に立ち上げたことに遡(さかのぼ)ります。
開設当初は保護者宅の庭先に施設を設け、後に八王子共同通所センターを経て現在の長沼通所センターへ移りました。「みんながだいじ、わたしもだいじ、明日のために ともに あゆもう」を理念として、創設者の思いを繋(つな)ぐため現在は生活介護事業所まゆだまを運営しています。
まゆだまでは、利用者様の特性やニーズにお応えするために授産事業として段ボールの組み立て作業、内職、ショッパー配達、公園清掃、資源回収などを行い、また自主製品制作にも取り組んでいます。
地域で豊かに暮らせることを目標に、余暇活動や行事を計画的に行っています。利用者様の個別支援に沿って、無理のない範囲で行うため参加希望制にしています
今年度は、お花見、プール、クリスマス、バレンタインデーなどを余暇活動とし、福祉祭り、ふれあい運動会、手作り作品展への参加や旅行、忘年会、新年会などを行事として計画しています。
現在、利用者様は67歳の方から20歳までと幅も広く、長い方では、30年になる方も通所しています。そのため開設当初のような一元的な支援では利用者様のニーズに応えられなくなってきており、職員の日々の苦労も多く、ケース会議や研修を重ねて少しでも利用者様の思いを尊重して支援できるように努力をしています。
保護者様の高齢化に伴い、利用者様の休日の過ごし方も単一的となり生活のパターン化が目立つようになってきたため、昨年度から移動支援事業すてっぷを立ち上げ、生活介護事業所の余暇活動等と連携(れんけい)して利用者様の精神面の健康維持などに取り組み始めました。まだ利用者数は少ないですが、なるべく多くのニーズに応えるために、ヘルパーの確保や保護者様のご理解を深めていただけるよう努めている最中です。また、地域で豊かに生活するために利用者様に何が必要なのか、どのような社会資源を活用すれば良いのかを利用者様ご自身や保護者様始め、地域で生活されている障害者の皆様と一緒に考え、提案するお手伝いができればと、5月に相談支援事業所まゆにっとを開設しました。担当職員も様々な事業所の見学や情報を取り入れて相談支援ができるよう努力をしておりますので、団体会員皆様の連携をぜひよろしくお願いいたします。
今年度は、かねてからの計画でありますグループホーム創設の事業を行っています。親亡き後も地域で豊かに生活を続けられるために、どのような形のグループホームが良いのか明確な答えはまだありません。
しかも創設ということで、地域の方々のご理解、建設資金等困難続きではありますが、ひとつずつ前へ進めています。 ハンディキャップを抱えて社会に出る我が子のスタート台として出発したまゆだまです。その思いを紡(つむ)いでいくには、いまだ未熟な法人運営です。八障連会員の皆様とも連携をして成長させていただけることを願っております。今後ともよろしくお願い致します。
(NPO法人まゆだま理事長 細野満里)
【連載コラム 『日々のなかから、』 <より良い学びとは2> Vol.37 八障連代表 杉浦 貢】
義務教育の9年間で、健常者の中のたった一人の障害者…という自分の立ち位置に、精神的な疲労を感じてしまった私は、高校になって養護学校を選びます。
思春期になると誰もが、自分と他人との差を感じ、コンプレックスを自覚するようになるものと思います。
私の場合も、とても苦しかった記憶があります。歳を取ってしまえばどうという事もない小さな悩みであっても、子どものうちに悩みの出口を探すのは、とても難しいことですよね。
他の人がスイスイやってのけることが、どうして自分にはできないのだろう。どうして自分だけが、人より劣っているのだろう。そして何より、トイレに行きたいとき、階段による教室移動の時に…どうして介助のために、家から母が呼ばれるのだろう…。
『障害の有無に関わらず、共に学ぶ』両親のそんな願いとは裏腹に、私の苦痛は増していきました。
養護学校でなら、もっとのんびり学べるかもしれない。そんな甘い考えで、短絡的な道を選んでしまいました。今現在は学校現場の雰囲気も変わり、すべての児童生徒が学びやすくなっていることを願いますが、そこに待っていたのは、さらなる差別と格差の実態だったのです。
学校が悪い。先生が最低だ。というつもりはありません。あの頃の時代の空気が、そういう物だったのでしょう。 私が進学した頃は、まだまだ『頑張れ、負けるな』という精神論が幅をきかせていた時代でした。それでも、古い価値観を否定する声は少しずつあがり始めていたのですが、学校現場の支流となるには、まだ少し時間が必要でした。
今でも忘れられないのが『杉浦、お前は障害が軽いから、何でもできるし、何でも判るだろ、他の友達の分も頑張るんだぞ』という先生の言葉です。
重度の知的障害があったり、私よりもさらに手足の自由がきかなかったり、内臓等に難しい疾患を抱えている子どもたちは、将来の可能性も限られてしまっている。
その子たちの未来を私が背負え…そう言われてしまったのです。
冗談ではない…当時の私はその先生に噛(か)みつきました。もちろん、どんなに重い障害を抱(かか)えていようと、どの子も大切な仲間であることに変わりはない。できることなら何とかしてあげたい。だけど、自分だってまだ子どもなのだ。自分一人の将来だってまだ不安なのに、それ以上の物まで背負えるものか。
だいたい障害が重ければ重いほど選べる未来が少なくなるような社会を作ってきたのは先生のような無神経な大人だ。出来る子ばかりチヤホヤして、出来ない子を(勉強の面では)見捨ててきた。普通の高校生と同じように過ごせないことは、障害児の責任ではないし、普通に過ごせないからこそ、ここにいる。たとえどんなに落ちこぼれた子、重度の子であっても、その子なりの美点はあるはずなのに、そういう所には目を向けず、型にはまった機械的な授業しかしない。自分だって頭悪いくせに、偉そうに説教垂(た)れるな。たしかそんなことを言った気がします。我ながら青臭いですね。
くれぐれもお断りしておきますが、これは高校生当時の私の言葉です。今では、大人には大人の苦労があることもちゃんと知っていますし、その先生だけが悪いのではないと思っています。それでもこうした話題を持ち出したのは、あの頃の時代の空気がそうだった。あの頃はこの先生のような考え方こそが普通であったと言いたいからなのです。
普通校で挫折した私が、養護学校に入ったとたん、訳も分からず持ち上げられる。私自身の本質には特になんの変化もないのに、周りの評価で待遇が決まる。一体これはなんなのだろうか。 割り切れない重いが黒雲のように、私の心を覆(おお)っていきました。(次回に続きます。)
通信本文はここまで。
師走のお忙しい時期とはなりますが、305号と同時にアップさせていただきます。
八障連通信304号【PDF版】はこちらから
これより通信本文となります。
【事務局通信 Vol.19】
9月17日の例会は「まゆだま」さんの活動報告が行われました。その内容については本号にも寄稿いただいておりますが、多くは、もともと肉親である親御(おやご)さんが中心となり活動をしていたところへ障害者自立支援法施行という法改正から必要に迫られて、まゆだまさんも2011年6月に外部の方を理事長に向かえNPO法人を設立した経緯があります。行政が描く体系化された通所サービスのイメージが不確実な中、苦心の末に就労継続支援B型事業としてスタートされましたが、利用者の高齢化や重度障害の方が多い現状から生活介護を中心とした事業所へ転換を図られます。また保護者のニーズと今後を考えるときに相談支援事業や移動支援、グループホームの必要性に着目され、行動に移された経過をお聞きしました。とりわけ、グループホーム設立の過程をお聞きすると、障害者差別禁止条例等の法令が世界レベルから日本国の地方自治体である八王子という生活の場、住まう地域まで波及しているにもかかわらず、依然として障害者への差別が存在する現実を思い知らされました。法整備が何もない時代に、生きていく必然性から生まれた親御さん方々の努力により日中の通い場所である社会参加の場が生まれましたが、今度は法整備によりまた試練を余儀なくされました。しかし弛(ゆる)みなく「必要」なことに対応して新たな事業を創造していく現理事長をはじめ、スタッフや関係者の方々の活動に敬意を払います。例会では様々な意見や質問がありましたが、相談支援事業所「まゆにっと」の名の由来から日戸美代子元八障連代表の話題があがりました。草創期の八障連を支えた人物であり、八王子の地域福祉発展に貢献された方でありますが、懐(なつ)かしい思い出話にも花が咲きました。また席上では、偏見(へんけん)について、更には就労に力点を置いている現障害者支援政策の補完的要素を担う地域生活支援事業が自治体によって大きな違いがある現状があると意見がありました。精神障害の方への支援についても施策の影響による隔(へだ)たりや偏見について意見など現状報告がありました。事業所設置に関わる関係行政機関との折衝(せっしょう)など福祉分野に限らず、「住まう」ことに関連したあらゆる行政、地域などの環境要因について意見交換されました。
お知らせしているとおり、今年度も福祉課や市議会議員の皆様方との懇談会を開催いたします。誤解や偏見は、まず知ってもらうことから第一歩が始まります。私たちに即しても、まず知ることからすべては始まります。他の障害の状況を知る機会がある八障連の活動に感謝しつつ、多くの皆様の活動への参加をお待ちしております。(文責/事務局有賀)
【今後のスケジュール】
10月15日(木)18時より八王子市役所・802会議室で、障害福祉課との懇談会を開催します。ぜひご参加ください。
なお、障害福祉課との懇談会に向けて「要望書」を提出しています。通信(本号)に掲載しておりますので、ご参照ください。
市障害福祉課との懇談会
10月15日(木) 18:00~20:00 八王子市役所 802会議室
七法人学習会
10月31日(土) 14:00~16:30 東浅川保健福祉センター集会室
八障連知的学習会
12月12日(土) 14:00~16:30 クリエイトホール 第2学習室
【要望書】
障害者福祉課御中
八王子障害者団体連絡協議会
代表 杉浦 貢
2015年10月15日八王子市障害者福祉課懇談会のテーマについて
日頃は当会の活動へのご協力をいただき、誠にありがとうございます。また恒例となっております当会との懇談の場をいただいたことを感謝申し上げます。今回の懇談会での主なテーマについてお伝えいたします。当日は地域福祉の更なる発展のために、種々課題について意見交換と課題共有を共々に行い、よりよい街づくりへの機会になればと考えております。
1) 日中活動系施設等運営安定化事業補助金について
財政が難しい状況にある中で、家賃補助を運営安定化目的として死守していただいたことで、新法移行に苦慮する団体、特に通所系事業所にとっては心強い補助事業であります。市より補助事業についての変更を検討しているご説明がありましたが、どのような補助の在り方になるか事業所としては関心の高いところであります。新法移行から運営が安定している事業所もあれば、1日の利用者数によって給付費(運営費)が左右する法形態によって、利用者数の確保の難しさから運営が厳しい事業所もあります。現行の補助がなくなることで、最大で180万円がなくなることになります。これは非常勤職員を雇える金額ともなります。マンパワーの削減や運営の弱体化にならないよう、また運営が安定していない事業所もある現状を考慮していただき、来年度以降も安定化事業の存続をお願いいたします。
2) 視覚障害者の方々が使用する点字ディスプレイ購入の補助について
パソコンなどのデータを点字で確認できる点字ディスプレイは視覚障害の方にとって有用なものとなります。現状、市では視覚障害者及聴覚障害の重度重複障害者 のみが日常生活用具給付の対象となっております。視覚障害のみでも日常生活用具給付対象となるようお願い致します。
3) 地域活動支援センターの運営費について
現在、八王子市では地域活動支援センターⅢ型として「わくわく」「パオ」の2か所が委託を受けて活動されています。新法移行後に就労継続支援B型事業所は工賃増額が義務つけられ、授産事業が活発に変化している事業所が増えていると思います。一方、そうした作業活動にはなじまない障害状態の方々のニーズは存在します。また重度の方や「わくわく」のような就業している障害者へ離職率を防ぐための必要なサービスを展開している事業所もあります。そうした活動を支える運営費は職員確保には厳しい現状があります。給付事業サービスの狭間にあるニーズに応えることが地域支援事業では可能です。ぜひ地域活動支援センターの運営強化をお願い致します。
以上、どうぞよろしくお願い致します。
【9月例会報告 NPO法人まゆだま報告】
9月17日の例会では、NPO法人「まゆだま」さんより報告をいただきました。34年前にさかのぼる「まゆだま」の創設時から現在に至る経過の中で遭遇した困難、またそれを乗り越えての今後の方向性等を語っていただきました。例会での活動報告をふまえ、細野理事長よりコンパクトにまとめていただいたレポートを執筆していただきました。以下掲載します。(編集部)
「NPO法人 まゆだまのいま」理事長 細野 満里
NPO法人まゆだまの生い立ちは、八王子養護学校(現八王子特別支援学校)の卒業生の保護者により、我が子の「親亡き後も地域で安心な暮らしを」を目標に授産事業を34年前に立ち上げたことに遡(さかのぼ)ります。
開設当初は保護者宅の庭先に施設を設け、後に八王子共同通所センターを経て現在の長沼通所センターへ移りました。「みんながだいじ、わたしもだいじ、明日のために ともに あゆもう」を理念として、創設者の思いを繋(つな)ぐため現在は生活介護事業所まゆだまを運営しています。
まゆだまでは、利用者様の特性やニーズにお応えするために授産事業として段ボールの組み立て作業、内職、ショッパー配達、公園清掃、資源回収などを行い、また自主製品制作にも取り組んでいます。
地域で豊かに暮らせることを目標に、余暇活動や行事を計画的に行っています。利用者様の個別支援に沿って、無理のない範囲で行うため参加希望制にしています
今年度は、お花見、プール、クリスマス、バレンタインデーなどを余暇活動とし、福祉祭り、ふれあい運動会、手作り作品展への参加や旅行、忘年会、新年会などを行事として計画しています。
現在、利用者様は67歳の方から20歳までと幅も広く、長い方では、30年になる方も通所しています。そのため開設当初のような一元的な支援では利用者様のニーズに応えられなくなってきており、職員の日々の苦労も多く、ケース会議や研修を重ねて少しでも利用者様の思いを尊重して支援できるように努力をしています。
保護者様の高齢化に伴い、利用者様の休日の過ごし方も単一的となり生活のパターン化が目立つようになってきたため、昨年度から移動支援事業すてっぷを立ち上げ、生活介護事業所の余暇活動等と連携(れんけい)して利用者様の精神面の健康維持などに取り組み始めました。まだ利用者数は少ないですが、なるべく多くのニーズに応えるために、ヘルパーの確保や保護者様のご理解を深めていただけるよう努めている最中です。また、地域で豊かに生活するために利用者様に何が必要なのか、どのような社会資源を活用すれば良いのかを利用者様ご自身や保護者様始め、地域で生活されている障害者の皆様と一緒に考え、提案するお手伝いができればと、5月に相談支援事業所まゆにっとを開設しました。担当職員も様々な事業所の見学や情報を取り入れて相談支援ができるよう努力をしておりますので、団体会員皆様の連携をぜひよろしくお願いいたします。
今年度は、かねてからの計画でありますグループホーム創設の事業を行っています。親亡き後も地域で豊かに生活を続けられるために、どのような形のグループホームが良いのか明確な答えはまだありません。
しかも創設ということで、地域の方々のご理解、建設資金等困難続きではありますが、ひとつずつ前へ進めています。 ハンディキャップを抱えて社会に出る我が子のスタート台として出発したまゆだまです。その思いを紡(つむ)いでいくには、いまだ未熟な法人運営です。八障連会員の皆様とも連携をして成長させていただけることを願っております。今後ともよろしくお願い致します。
(NPO法人まゆだま理事長 細野満里)
【連載コラム 『日々のなかから、』 <より良い学びとは2> Vol.37 八障連代表 杉浦 貢】
義務教育の9年間で、健常者の中のたった一人の障害者…という自分の立ち位置に、精神的な疲労を感じてしまった私は、高校になって養護学校を選びます。
思春期になると誰もが、自分と他人との差を感じ、コンプレックスを自覚するようになるものと思います。
私の場合も、とても苦しかった記憶があります。歳を取ってしまえばどうという事もない小さな悩みであっても、子どものうちに悩みの出口を探すのは、とても難しいことですよね。
他の人がスイスイやってのけることが、どうして自分にはできないのだろう。どうして自分だけが、人より劣っているのだろう。そして何より、トイレに行きたいとき、階段による教室移動の時に…どうして介助のために、家から母が呼ばれるのだろう…。
『障害の有無に関わらず、共に学ぶ』両親のそんな願いとは裏腹に、私の苦痛は増していきました。
養護学校でなら、もっとのんびり学べるかもしれない。そんな甘い考えで、短絡的な道を選んでしまいました。今現在は学校現場の雰囲気も変わり、すべての児童生徒が学びやすくなっていることを願いますが、そこに待っていたのは、さらなる差別と格差の実態だったのです。
学校が悪い。先生が最低だ。というつもりはありません。あの頃の時代の空気が、そういう物だったのでしょう。 私が進学した頃は、まだまだ『頑張れ、負けるな』という精神論が幅をきかせていた時代でした。それでも、古い価値観を否定する声は少しずつあがり始めていたのですが、学校現場の支流となるには、まだ少し時間が必要でした。
今でも忘れられないのが『杉浦、お前は障害が軽いから、何でもできるし、何でも判るだろ、他の友達の分も頑張るんだぞ』という先生の言葉です。
重度の知的障害があったり、私よりもさらに手足の自由がきかなかったり、内臓等に難しい疾患を抱えている子どもたちは、将来の可能性も限られてしまっている。
その子たちの未来を私が背負え…そう言われてしまったのです。
冗談ではない…当時の私はその先生に噛(か)みつきました。もちろん、どんなに重い障害を抱(かか)えていようと、どの子も大切な仲間であることに変わりはない。できることなら何とかしてあげたい。だけど、自分だってまだ子どもなのだ。自分一人の将来だってまだ不安なのに、それ以上の物まで背負えるものか。
だいたい障害が重ければ重いほど選べる未来が少なくなるような社会を作ってきたのは先生のような無神経な大人だ。出来る子ばかりチヤホヤして、出来ない子を(勉強の面では)見捨ててきた。普通の高校生と同じように過ごせないことは、障害児の責任ではないし、普通に過ごせないからこそ、ここにいる。たとえどんなに落ちこぼれた子、重度の子であっても、その子なりの美点はあるはずなのに、そういう所には目を向けず、型にはまった機械的な授業しかしない。自分だって頭悪いくせに、偉そうに説教垂(た)れるな。たしかそんなことを言った気がします。我ながら青臭いですね。
くれぐれもお断りしておきますが、これは高校生当時の私の言葉です。今では、大人には大人の苦労があることもちゃんと知っていますし、その先生だけが悪いのではないと思っています。それでもこうした話題を持ち出したのは、あの頃の時代の空気がそうだった。あの頃はこの先生のような考え方こそが普通であったと言いたいからなのです。
普通校で挫折した私が、養護学校に入ったとたん、訳も分からず持ち上げられる。私自身の本質には特になんの変化もないのに、周りの評価で待遇が決まる。一体これはなんなのだろうか。 割り切れない重いが黒雲のように、私の心を覆(おお)っていきました。(次回に続きます。)
通信本文はここまで。