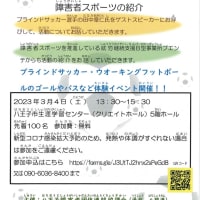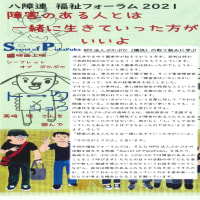八障連通信311号をアップします。
八障連通信311号【PDF版】はこちらから。
ここからは通信本文です。
【事務局通信 Voj.24】
早いもので、新体制から1年を経過して、定期総会の時期が近づいてまいりました。平成27年度にどのような活動をしてきたかなど振り返り報告をまとめました。また平成28年度の活動についても運営委員会で検討し、新たな年度はどのように活動をしていくか事業計画(案)を作成いたしました。『定期総会議案書』として今号に同封されていますので、ご覧いただければと思います。
活動の内容をまとめていく中で考えたことは、今年度も八障連は問題、課題などの発信の場としての役割を担っていき、皆さんに活用していいただければという思いでした。定期総会には是非多くの皆様のご参加とご意見をお願いできればと思います。振り返れば、ここ数年担い手不足の課題が常に存在していますが、少子高齢化が進んでいる渦中では、この課題は継続しそうです。
問題や課題などに取り組むためには、現状の事務局体制では難しいところもあり、もう少し人材がほしいところでもあります。通常業務を行うなか、いろいろな活動に協力することは非常に難しいことではあるのですが、少しの時間でもいいので、お手伝いをいただける方がいらっしゃいましたら是非お願いをしたいと思います。
今後も制度の変更なども続くと予想されます。その中で埋もれていかないためにも、八障連という媒体をフルに活用してより良い環境を作っていきたいと思いますので、ご協力お願いいたします。(事務局 立川)
【告知板】
・2016年度の総会(5月21日開催)に向けて、運営委員会で講論を重ね、総会議案書にまとめました。本号に同封しておりますので是非ご検討ください。総会にて活発な議論を期待しております。また総会に向けて『出欠はがぎ』を同封しています。5月31日㈮までに必ずお出しください。よろしくお願いいたします。(事務局)
・情報発信したという会員団体の投稿を引き続き募集しております。投稿先cxb0172@nifty.com八障連通信掲載希望とお書きください。(編集部)
【今後のスケジュール】
ワークセンター総会 5月21日(土) 10時~12時 八王子労政会館
八障連定期総会 5月21日(土) 13時30分~16時30分 八王子労政会館
みんな違ってみんないい 5月29日(日) 10時30分~ 浅川河川敷
八障連運営委員会 6月23日(木) 18時~20時 クリエイトホール
【福祉フォーラム「風は生きよという」上映会開催さる】
3月19日、八王子労政会館にて福祉フォーラムを開催。人工呼吸器を使いながら地域で自立生活をする重度障害者のドキュメンタリー映画、『風は生きよという』の上映会を行いました。
この映画は、呼吸器ユーザーグループ「呼ネット」の副代表海老原弘美さんの、仕事も含めた自立生活の映像が全体的なベースとなり、北海道、東京、大阪でそれぞれに自分の思う人生を送る10代から約50歳の3名の方が登場します。それぞれの地域で一人暮らしや家族と一緒に暮らしている日常の生活が映し出されているのですが、暮らしや思い、家族の証言などでつづられていました。
映像の中では特に「音」を効果的に使っていました。それは「風の音」「鳥のさえずり」そして「呼吸器から出てくる音」などです。
それぞれの当事者と町の人々との間に生まれるコミュニケーションが無脚色で淡々と映されていて、風のようなさわやかさの中にも、静かな力強さが心に残る映画でした。
この映画のメッセージである「日常の尊さ」で、「たくさんの支援が必要だからこそ、多くの人と出会え、自由に動くことが出来ないからこそ、生きていることに感謝する」を、呼吸するための道具である人工呼吸器を使用している当事者だからこそ伝えている内容でした。
フォーラムの後半、上映会の後に、映画の中に出演している海老原さんご本人からお話をしていただきました。その中で印象的だったことは、「生きている価値は何か?」と言う問いについてお話をされたことです。
『働けるか働けないかということで生きる価値を判断してしまい、社会に役に立つことで人の価値を測る世の中になっている。そのなかで「尊厳死」の問題が出てきて、法制化しようという動きもあり、そんな動きに対して、人工呼吸器ユーザーは反対の運動をしています。人工呼吸器を使って生きている人の価値は何かを問いた時に、価値があるかないかで考えても答えが出ないのではないでしょうか―。』 そして、例えとして、屋久島の杉の話をされていました。『屋久杉を見るために大勢の人たちが屋久島まで行き、樹齢数千年の杉を見て感動し、元気をもらい、生きる意味を感じ、それぞれの人たちの心を癒してくれるのです。ただの「杉」ですが、その杉の価値は見る人達が決めているのです。人の価値もそのように、自分が生きている価値があるかどうかを判断するのではなく、周りの人たち、世の中の人達が判断することではないでしょうか―。』
この映画を見た、いち障害当事者として杉浦は考えます。いわゆる安楽死や緩和医療、ホスピスなどの医療もまた否定されるべきではありません。それはそれで必要かつ重要なことだと思います。それが病院であれ在宅であれ、医療の現場においては治療の方法や、終末期ケアに関しては患者本人の意思、家族の意思、それら相互の関係、環境や経済状況などによってそれぞれに異なるでしょう。
一方で、重度の障害者の中には地域サービスの未整備もあって、家族の介護に依存しなければ生きていけない人たちもいます。その人たちは、家族への遠慮から手厚い看護や介護、治療を選択しにくい状況にあります。こうした人たちにとって、この法律ができることは治療を停止して、不本意な死を選ばざるをえない無言の選択を強いることにならないでしょうか?
死と生は本来ひとつの価値であり、そのことに関して社会的コストといった功利的な理由や、医師の免責の理由や、家族の負担といった理由や、あるいは国家の財政的な理由などによって人の死を法律によって拘束したり、収奪することはできません。
いかに生きるかと同じように、いかに死ぬかについても、どこかの誰かから受ける無言の圧力によってではなく、最期まで自分の望むようにさせて欲しい。全ての医療はあくまで、本人のためのものであって欲しい。私はそう願わずにはいられません。(文責/杉浦)
【八障連例会に参加した4年を振り返って思うこと 八王子聴覚視覚障碍者サポートセンター 伊藤薫】
八障連の例会に初めて参加したのは、2012年7月19日でした。実はこの時、私はとても気後れするような、ちょっと不安な気持ちで初出席していました。というのは、例会は19時から、運営委員会が18時からと聞いていたので、仕事の後一旦帰宅して夕食の準備をしてから、19時少し前にクリエイトホールへ到着すると、すでに例会が始まっている雰囲気で、(初回から遅刻、しまった!)と思ったのです。そしてさらに、周りはどうやら男性ばかりのようで、おばさんといえども、さみしいような心細いような気持ちになっていました。例会の後半になって、自己紹介の時間を取ってくださり、知っている方が何名か同席していて、私以外にも女性がおられたことがようやく分かり、殆ど視力がない私は、ここでちょっとほっとしたのでした。そして、みなさんも仕事の後、時間をやりくりして徐々に集まって人が増えていたということも分かってきてさらにほっとすると同時に、障害の種類や団体・事業所の垣根を超えて協力し合っていることに、団体としての強さや温かさを感じました。
この時の主な議題は、「わらじの会」を迎えてのフォーラムの振り返り、対市予算要望の検討に関することでした。当時の簡単なメモを読み返してみると、市への要望に関連して、
・災害時の障害者用の避難所について情報を開示してほしい。
・小児メディカルクリニックの土曜の開院要望について。
・家賃補助の減額問題。
・狭間の新体育館、大横福祉センターの建て替えに設計から関わり、提案を行うこと。
・日中一時支援の単価、委託料が低く、運営が難しい状況。
・次年度からの、総合支援法への移行について、市の考え方を聞きたい。
などがありました。今も課題となっていることがあり、八障連として交渉が続けられています。
八王子では全国に先駆けて、知的障害、精神障害の方を中心とした、障害者地域生活支援拠点整備のモデル事業がスタートしています。また子供たちへの障害理解教育についても八王子独自に具体的な教材や授業の検討も今後行われます。八障連はその動向にも注目して、提案や参画をしていくことになるでしょう。
この春の八障連フォーラムでは、呼吸器ユーザーのドキュメンタリー「風は生きよという」を、字幕と音声ガイドでの情報保証のあるバリアフリー上映会として行い、反響を得ました。障害の垣根を越えた連携でこのような上映会が行われるのは、全国でも貴重な活動です。今年11月で結成30周年となる八障連。八障連の担当は終えますが、まだまだ学ばせていただきながら、繋がっていきたいと思います。
<編集部より>
伊藤様は今期で八障連担当を終えることになりました。任期中は、八障連例会参加のみならず、八障連通信の「コラム欄」を執筆していただき、貴重なご意見をいただきました。担当を終えることは誠に残念ですが、今後もなにかトピック・ご意見等がございましたら、ぜひ八障連通信を活用して、情報発信していただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。(編集部)
【連載コラム B型肝炎闘病記 パオ 小濱 義久 闘病史 その4】
入2院予約窓口で告げられたように、ちょうど2ヵ月あまり経った1983年4月初旬の木曜日だったか金曜日だったか、来週の月曜日に入院できますかという電話が突然入った。電話と言うものはいつも突然来るものだが、心の準備と言うものがあるでしょと思わず自分に突っ込みを入れていた。自由に生活できるのは、あと3,4日しかないと強く感じた。勤務体制や入院時に持って行く物などの準備は一応整えてはいたが、気持ちまでは整えていなかった。精神科においては、強制入院などしばしば患者さんの意思を無視した形で突然の入院が強行される。うろたえる彼らの気持ちの一端を味わった気がした。
分院は東急田園都市線の梶ヶ谷駅から歩いて15分位の所にあった。4階建てのコの字型に建てられた箱型の病棟は、古さばかり目立ち何の飾り気もなかった。病棟面積の3~4倍はありそうな広い敷地が周りに広がっていた。まさに療養所という雰囲気そのものだった。一画に庭が整備され、いろんな樹木が植えられているようで、病棟の周りを巡る小道も作られていた。季節毎に長期入院者の心を慰めてくれる花々がきっと咲いてくれるはずだ。正面玄関前には大きな池があり、鯉たちが気持ち良さそうに泳いでいた。金魚もいた。咲き残っていた桜の花が、暖かい日差しとともに私を迎え入れてくれた。
~3週間、長くても1ヶ月のつもりの入院が3か月に及ぶことになるとはその時は考えもしなかったし、ましてや有給消化から、病気休暇へ変更になり、その後疾病療養給付金をもらって過ごすことになるとは全く想定外の話であった。なんと1年間も、勤務していた病院を休むことになったのである。数か月に一度診断書を提出し、給付期間を延長していくのだが、最後の方では認めてもらえるのだろうかととても不安になり、給付金が貰えなければどうしようかと精神的に幾分不安定になったことを今でも昨日のことのように覚えている。(続く)
通信本文はここまで。
八障連通信311号【PDF版】はこちらから。
ここからは通信本文です。
【事務局通信 Voj.24】
早いもので、新体制から1年を経過して、定期総会の時期が近づいてまいりました。平成27年度にどのような活動をしてきたかなど振り返り報告をまとめました。また平成28年度の活動についても運営委員会で検討し、新たな年度はどのように活動をしていくか事業計画(案)を作成いたしました。『定期総会議案書』として今号に同封されていますので、ご覧いただければと思います。
活動の内容をまとめていく中で考えたことは、今年度も八障連は問題、課題などの発信の場としての役割を担っていき、皆さんに活用していいただければという思いでした。定期総会には是非多くの皆様のご参加とご意見をお願いできればと思います。振り返れば、ここ数年担い手不足の課題が常に存在していますが、少子高齢化が進んでいる渦中では、この課題は継続しそうです。
問題や課題などに取り組むためには、現状の事務局体制では難しいところもあり、もう少し人材がほしいところでもあります。通常業務を行うなか、いろいろな活動に協力することは非常に難しいことではあるのですが、少しの時間でもいいので、お手伝いをいただける方がいらっしゃいましたら是非お願いをしたいと思います。
今後も制度の変更なども続くと予想されます。その中で埋もれていかないためにも、八障連という媒体をフルに活用してより良い環境を作っていきたいと思いますので、ご協力お願いいたします。(事務局 立川)
【告知板】
・2016年度の総会(5月21日開催)に向けて、運営委員会で講論を重ね、総会議案書にまとめました。本号に同封しておりますので是非ご検討ください。総会にて活発な議論を期待しております。また総会に向けて『出欠はがぎ』を同封しています。5月31日㈮までに必ずお出しください。よろしくお願いいたします。(事務局)
・情報発信したという会員団体の投稿を引き続き募集しております。投稿先cxb0172@nifty.com八障連通信掲載希望とお書きください。(編集部)
【今後のスケジュール】
ワークセンター総会 5月21日(土) 10時~12時 八王子労政会館
八障連定期総会 5月21日(土) 13時30分~16時30分 八王子労政会館
みんな違ってみんないい 5月29日(日) 10時30分~ 浅川河川敷
八障連運営委員会 6月23日(木) 18時~20時 クリエイトホール
【福祉フォーラム「風は生きよという」上映会開催さる】
3月19日、八王子労政会館にて福祉フォーラムを開催。人工呼吸器を使いながら地域で自立生活をする重度障害者のドキュメンタリー映画、『風は生きよという』の上映会を行いました。
この映画は、呼吸器ユーザーグループ「呼ネット」の副代表海老原弘美さんの、仕事も含めた自立生活の映像が全体的なベースとなり、北海道、東京、大阪でそれぞれに自分の思う人生を送る10代から約50歳の3名の方が登場します。それぞれの地域で一人暮らしや家族と一緒に暮らしている日常の生活が映し出されているのですが、暮らしや思い、家族の証言などでつづられていました。
映像の中では特に「音」を効果的に使っていました。それは「風の音」「鳥のさえずり」そして「呼吸器から出てくる音」などです。
それぞれの当事者と町の人々との間に生まれるコミュニケーションが無脚色で淡々と映されていて、風のようなさわやかさの中にも、静かな力強さが心に残る映画でした。
この映画のメッセージである「日常の尊さ」で、「たくさんの支援が必要だからこそ、多くの人と出会え、自由に動くことが出来ないからこそ、生きていることに感謝する」を、呼吸するための道具である人工呼吸器を使用している当事者だからこそ伝えている内容でした。
フォーラムの後半、上映会の後に、映画の中に出演している海老原さんご本人からお話をしていただきました。その中で印象的だったことは、「生きている価値は何か?」と言う問いについてお話をされたことです。
『働けるか働けないかということで生きる価値を判断してしまい、社会に役に立つことで人の価値を測る世の中になっている。そのなかで「尊厳死」の問題が出てきて、法制化しようという動きもあり、そんな動きに対して、人工呼吸器ユーザーは反対の運動をしています。人工呼吸器を使って生きている人の価値は何かを問いた時に、価値があるかないかで考えても答えが出ないのではないでしょうか―。』 そして、例えとして、屋久島の杉の話をされていました。『屋久杉を見るために大勢の人たちが屋久島まで行き、樹齢数千年の杉を見て感動し、元気をもらい、生きる意味を感じ、それぞれの人たちの心を癒してくれるのです。ただの「杉」ですが、その杉の価値は見る人達が決めているのです。人の価値もそのように、自分が生きている価値があるかどうかを判断するのではなく、周りの人たち、世の中の人達が判断することではないでしょうか―。』
この映画を見た、いち障害当事者として杉浦は考えます。いわゆる安楽死や緩和医療、ホスピスなどの医療もまた否定されるべきではありません。それはそれで必要かつ重要なことだと思います。それが病院であれ在宅であれ、医療の現場においては治療の方法や、終末期ケアに関しては患者本人の意思、家族の意思、それら相互の関係、環境や経済状況などによってそれぞれに異なるでしょう。
一方で、重度の障害者の中には地域サービスの未整備もあって、家族の介護に依存しなければ生きていけない人たちもいます。その人たちは、家族への遠慮から手厚い看護や介護、治療を選択しにくい状況にあります。こうした人たちにとって、この法律ができることは治療を停止して、不本意な死を選ばざるをえない無言の選択を強いることにならないでしょうか?
死と生は本来ひとつの価値であり、そのことに関して社会的コストといった功利的な理由や、医師の免責の理由や、家族の負担といった理由や、あるいは国家の財政的な理由などによって人の死を法律によって拘束したり、収奪することはできません。
いかに生きるかと同じように、いかに死ぬかについても、どこかの誰かから受ける無言の圧力によってではなく、最期まで自分の望むようにさせて欲しい。全ての医療はあくまで、本人のためのものであって欲しい。私はそう願わずにはいられません。(文責/杉浦)
【八障連例会に参加した4年を振り返って思うこと 八王子聴覚視覚障碍者サポートセンター 伊藤薫】
八障連の例会に初めて参加したのは、2012年7月19日でした。実はこの時、私はとても気後れするような、ちょっと不安な気持ちで初出席していました。というのは、例会は19時から、運営委員会が18時からと聞いていたので、仕事の後一旦帰宅して夕食の準備をしてから、19時少し前にクリエイトホールへ到着すると、すでに例会が始まっている雰囲気で、(初回から遅刻、しまった!)と思ったのです。そしてさらに、周りはどうやら男性ばかりのようで、おばさんといえども、さみしいような心細いような気持ちになっていました。例会の後半になって、自己紹介の時間を取ってくださり、知っている方が何名か同席していて、私以外にも女性がおられたことがようやく分かり、殆ど視力がない私は、ここでちょっとほっとしたのでした。そして、みなさんも仕事の後、時間をやりくりして徐々に集まって人が増えていたということも分かってきてさらにほっとすると同時に、障害の種類や団体・事業所の垣根を超えて協力し合っていることに、団体としての強さや温かさを感じました。
この時の主な議題は、「わらじの会」を迎えてのフォーラムの振り返り、対市予算要望の検討に関することでした。当時の簡単なメモを読み返してみると、市への要望に関連して、
・災害時の障害者用の避難所について情報を開示してほしい。
・小児メディカルクリニックの土曜の開院要望について。
・家賃補助の減額問題。
・狭間の新体育館、大横福祉センターの建て替えに設計から関わり、提案を行うこと。
・日中一時支援の単価、委託料が低く、運営が難しい状況。
・次年度からの、総合支援法への移行について、市の考え方を聞きたい。
などがありました。今も課題となっていることがあり、八障連として交渉が続けられています。
八王子では全国に先駆けて、知的障害、精神障害の方を中心とした、障害者地域生活支援拠点整備のモデル事業がスタートしています。また子供たちへの障害理解教育についても八王子独自に具体的な教材や授業の検討も今後行われます。八障連はその動向にも注目して、提案や参画をしていくことになるでしょう。
この春の八障連フォーラムでは、呼吸器ユーザーのドキュメンタリー「風は生きよという」を、字幕と音声ガイドでの情報保証のあるバリアフリー上映会として行い、反響を得ました。障害の垣根を越えた連携でこのような上映会が行われるのは、全国でも貴重な活動です。今年11月で結成30周年となる八障連。八障連の担当は終えますが、まだまだ学ばせていただきながら、繋がっていきたいと思います。
<編集部より>
伊藤様は今期で八障連担当を終えることになりました。任期中は、八障連例会参加のみならず、八障連通信の「コラム欄」を執筆していただき、貴重なご意見をいただきました。担当を終えることは誠に残念ですが、今後もなにかトピック・ご意見等がございましたら、ぜひ八障連通信を活用して、情報発信していただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。(編集部)
【連載コラム B型肝炎闘病記 パオ 小濱 義久 闘病史 その4】
入2院予約窓口で告げられたように、ちょうど2ヵ月あまり経った1983年4月初旬の木曜日だったか金曜日だったか、来週の月曜日に入院できますかという電話が突然入った。電話と言うものはいつも突然来るものだが、心の準備と言うものがあるでしょと思わず自分に突っ込みを入れていた。自由に生活できるのは、あと3,4日しかないと強く感じた。勤務体制や入院時に持って行く物などの準備は一応整えてはいたが、気持ちまでは整えていなかった。精神科においては、強制入院などしばしば患者さんの意思を無視した形で突然の入院が強行される。うろたえる彼らの気持ちの一端を味わった気がした。
分院は東急田園都市線の梶ヶ谷駅から歩いて15分位の所にあった。4階建てのコの字型に建てられた箱型の病棟は、古さばかり目立ち何の飾り気もなかった。病棟面積の3~4倍はありそうな広い敷地が周りに広がっていた。まさに療養所という雰囲気そのものだった。一画に庭が整備され、いろんな樹木が植えられているようで、病棟の周りを巡る小道も作られていた。季節毎に長期入院者の心を慰めてくれる花々がきっと咲いてくれるはずだ。正面玄関前には大きな池があり、鯉たちが気持ち良さそうに泳いでいた。金魚もいた。咲き残っていた桜の花が、暖かい日差しとともに私を迎え入れてくれた。
~3週間、長くても1ヶ月のつもりの入院が3か月に及ぶことになるとはその時は考えもしなかったし、ましてや有給消化から、病気休暇へ変更になり、その後疾病療養給付金をもらって過ごすことになるとは全く想定外の話であった。なんと1年間も、勤務していた病院を休むことになったのである。数か月に一度診断書を提出し、給付期間を延長していくのだが、最後の方では認めてもらえるのだろうかととても不安になり、給付金が貰えなければどうしようかと精神的に幾分不安定になったことを今でも昨日のことのように覚えている。(続く)
通信本文はここまで。