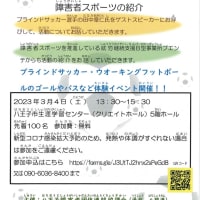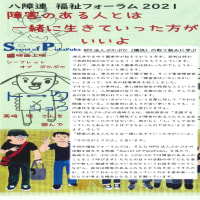八障連通信310号です。
八障連通信310号【PDF版】はこちらから。
ここより、八障連通信310号本文です。
【事務局通信 Vol.23】
桜が咲き誇る新年度を迎えました。4月を迎えて新しい出会いや別れもあったかと思います。八障連も新体制となり、皆様のご協力を頂きながら何とか一年が経とうとしています。3月は特にイベントも多く、第4回の知的障害者の地域生活について考える学習会では実際に単身生活をされている当事者の方のお話が聞けました。反響も大きく席が足りなくて立ったままの方も多く、関心の高さが知れました。詳細は別途報告で。福祉フォーラムでは「風は生きよという」の上映会を行い、一般市民から福祉関係者、医療関係者、これから上映を考えている方、高校生など幅広い来場となりました。また今回はバリアフリー上映会でもあり、視覚障害の方も多く来ていただけました。jilが推進している映画ということもあり、機材、セッティングなどもjilの完全協力のもと行いました。この場を借りて担当していただいたjilの皆様と手伝っていただいたご家族の方へお礼申し上げます。
第2部では海老原宏美さんのトークショーがあり、映画の内容を補完するとともに障害者の何気ない日常をお話ししていただきました。何気ない日常の中から多くのメッセージがあり、来場された方は何かしらを持って帰られたのでないかと思います。話は変わりますが、障害者福祉課から平成28年度予算についてお話を3役で聞きました。高齢化が待ったなしに進む中で、予算は膨れ上がる一方という状況を背景に、地域活動支援センターの委託費増額はなかなか厳しい状況は変わらないようです。具体的な地域ニーズをより鮮明にしていく必要はあるようです。点字ディスプレイについては近隣他市の状況もみて、極めて前向きな検討が行われているようです。視覚障害の方々の情報格差の是正が期待されます。いわゆる家賃補助については、平成28年度は現行通りとなりましたが、平成29年度は制度自体の変更を準備されるようです。確かに無制限に全ての事業所へ負担し続けるのは現実的ではないかもしれませんが、障害特性などで運営が厳しいところ、必要なサービスがなくならない配慮がされるよう注視していく必要はあります。もうすぐ定期総会を迎えますが、より一層の皆様のご協力と参加をお願いします。(文責/有賀)
【告知板】
✦ 2016 年度の総会(5 月21 日開催予定)に向けて、4 月21 日(木)の運営委
員会より、2015 年度の活動を振り返りと2016 年度の活動方針の討論に入りま
す。ご注目ください。(運営委員会)
✦ 「結の会」さんより近況報告の投稿がありました。本号に掲載しましたのでぜひ
ご一読ください。また情報発信したいという会員団体の投稿を引き続き募集して
おります。投稿先 cxb01672@nifty.com 八障連通信掲載希望とお書きくださ
い。(編集部)
【今後のスケジュール】
八障連運営委員会 4月21日(木) 18時~20時 クリエイト第1学習会
八障連定期総会 5月21日(土) 13時30分~16時30分 八王子労政会館第1会議室
ワークセンター総会 5月21日(土)9時30分~12時 八王子労政会館
【第4回 知的に障害のある人の地域生活を考える学習会報告
グループホームと一人暮らしでは、何がどうちがうのか?】
立ち見が出るほどの大盛況でした
知的に障害のある方の地域生活というと今はグループホームというのが、一般的かと思いますが、地域では、一人暮らしをしている方もいらっしゃいます。3月12日クリエイトホール第2学習室で行われた第4回目の学習会では、八王子市で一人暮らしをしている田丸俊彦さんとその支援をしているヒューマンケア協会の関島裕美さんペアと多摩市で一人暮らしをしている山崎隆司さんとその支援をしているたこの木クラブの横田彰敏さんペアにお話を伺いました。当日は、定員70名のところ立ち見が出るほどの大盛況でした。
実家のそばに暮らすという田丸さんの新しい選択
ひと口に一人暮らしといっても、親御さんをはじめとする環境によってそうせざるを得なくて始まる一人暮らしと自分から望んで始まる一人暮らしがあること、八王子では、残念ながらせざるを得なくて始まった方が多いことを知りました。そんな中、10年ほど前から実家のすぐそばにアパートを借りて実家と両立させて暮らす田丸さんのライフスタイルは、自宅か独立かという二者択一だった自立観に対して、新しい選択肢として注目されます(最近は、お母さんが実家で一人になったため、実家で寝るようにしているそうで、これも高齢化する親との関係性として、新しい選択肢かもしれません)。
仲間に触発されてはじまった山崎さんの一人暮らし
一方の山崎さんは、周りの仲間が先に一人暮らしをはじめる様子を見て、自分も自立したいと希望してはじまったそうです。田丸さんは、ヘルパーさんは入っておらず、ガイヘルを時々使うぐらいとのことでしたが、山崎さんは、毎朝8時にはヘルパーさんが来られて、朝食や洗濯を済ませ、作業所に通い、夕方から夜の9時ぐらいまではまたヘルパーさんと過ごすそうです。他の仲間は24時間ヘルパーさんがついている方も多いそうです。今回、その様子をよりリアルに知っていただけるようにと映像の提供をお願いしたところ、田丸さんは、ご自分で自分の部屋の様子を撮ってきてくれました。そのほとんどは、音の出ていないテレビ番組に、BGMとして田丸さんの好きなアイドルの歌が流れているといったもので、一見生活の様子とは遠い感じがしましたが、そこには田丸さんの世界、世界観がはっきりと感じられましたし、生活の拠点が実家に移りつつある田丸さんにとっては、一人暮らしの中心はこういった誰にも遠慮の要らない一人の時間の過ごし方なのかなと後で納得しました。一方、山崎さんの映像は、支援者の横田さんが、自分とは異なるヘルパーさんが入ったある朝の様子を詳細に撮ってくださったもので、山崎さんが洗濯物を洗濯機に入れる様子やヘルパーさんが朝食を作り、それを食べる山崎さんの様子から、その生活の雰囲気がよくわかりました。また、撮影した横田さんが、自分が入った時とは山崎さんの様子が全くちがうことに驚かれたり、当日の支援者の方も、カメラが回っている今日はいつもの山崎さんとはかなりちがうといったお話があったりして、今回の撮影を通して、意外な発見があったようです。
大切なのは「できるできないよりも、一人暮らしをしたいという思い」
最後の質疑応答の際、「どういった基準で一人暮らしができるかどうかを判断するのですか?」という質問に、関島さんが、「何々ができなければ、ということはないです」「できるできないよりも、その人が本当に一人暮らしをしたいのかどうか、その思い、覚悟が大切です」と答えてくださいました。会場の方は、ちょっと驚いていましたが、今回の学習会で、一番大切だったのは、この点だったと思います。私たちはつい、何々ができるから自立できる、何々ができないから自立できない、と考えてしまいがちですが、できないことは誰かに手伝ってもらえばいい、しかし、こうしたいという気持ち、意思は、だれかに代わってもらうわけにはいきません。最後になりましたが、田丸さん、関島さん、そして多摩市からわざわざおいでくださった山崎さん、横田さんをはじめとする「たこの木クラブ」の皆々様、どうもありがとうございました。 (文責/土居)
【《会員近況報告》
八王子市の「監査」を受けました -しばらく勘弁ですねー NPO 法人:結の会 (市川翔吾)】
去年の12月10日になりますが、結の会は、八王子市の実地検査、所謂監査を受けました。監査というものは、突然八王子市からの郵送でこの日に行いますと通達が来ます。それも実施日の10日ほど前にやってくるものですから、かなりあたふたします。
以前、小耳にはさんだ話によると、労災申請が立て続けにあった事業所に監査が入ったと聞いていたので、何か少し目に付くようなことがあった場合監査が入りやすいのかなと思っていました。ただ、結の会の場合、特に思い当たる節もないですし、何故だろう?もしかして、請求関係でミスでもあったのだろうか?と若干ドギマギしていましたが、市の方に聞いたところ、平成27年4月より八王子市が中核市に移行したことにより、市内の福祉施設全てを順番にまわっているとのことでした。
監査にあたっては、まず通達書と一緒に準備書類一覧というものが記されており、それらを当日までに用意・整理しておかなければなりません。年末の忙しい時期とも重なり、これがなかなか大変な作業でした。ひとつひとつ用意して不備がないかなど確認し、しっかり説明できるように準備しました。
そんなこんなで、監査当日、市の指導監査課の職員の方3名がやってきました。最初に施設内を案内しながら設備面などのチェックが入ります。そして、用意した書類を渡して、それを市職員の方がひたすらチェックします。私たちは、別室で仕事をしながら待機していて、何かあれば呼ばれるので、書類についての説明を行います。ですので、当日は監査に関して、思っているほど対応するというようなことはありませんでした。最後に口頭で改善点などの指摘を受けます。後日、改めてその結果が書面で送られてきました。
結果については、概ね良好で、書面などもよく整備されていますとのことでしたが、大きく2点ほど是正してくださいとの指摘を受けました。ひとつは、「虐待防止・人権意識向上のための研修を実施していないので是正すること」。もうひとつは、「サービス提供の記録をしていないので是正すること」でした。「虐待防止~」については早速、規定を整備し、それについてのミーティングも定期的に行い、研修計画もたてました。「サービス提供の記録~」については、全くやっていないということはなく、毎日の作業内容の記録や、大なり小なり様子の変化やトピックがあればその都度記録するというスタイルでやってきました。今回は、更に毎日の細やかな様子の記録、毎度メンバーからの確認をもらってくださいとのことでした。これが、一見単純で簡単なことのようにも思えますが、現場で実際やるとなるとなかなか厳しく、日常業務や日々ただでさえ多くなっていく事務仕事を行っていくなかでは、メンバーと関われる時間がますます減り、事務量・残業は増えていくという負のスパイラルに入り込んでいき本末転倒なことになりかねないわけです。もちろん、サービス提供の記録はとても大切で必要なものであると思います。これについては、もう少しうまいやり方があるのではないかと模索しながら導き出せればと思います。
今回の監査を受けては、自立支援法という大きな波に飲み込まれることなく、自分たちのスタンスとバランスを崩さず、法と程よい距離感でうまく付き合いながら、結で働くメンバー・職員がよりよく過ごせるようにと気をひきしめるよい機会になりました。ただ、監査はしばらく勘弁ですね。(結の会通信77号より転載)
【連載コラム B 型肝炎闘病記 パオ 小濵 義久 闘病史 その3】
昨年の11 月に肝臓癌の再発があり、2 週間足らずの入院生活を2 回にわたって挿入させてもらったが、今回から34 年前の肝臓での初めての入院体験に戻ることにする。
その2」で、初診時に入院手続きをして帰ったという話を書いたが、その時に肝臓での入院は都心の虎の門にある本院ではなく、川崎市の梶ヶ谷にある分院にと言われ、入院のしおりとともに分院の地図が描かれているパンフレットも渡された。都心の喧騒(けんそう)の中での入院生活よりは、郊外での方がのんびりしていて良いかなと感じた。一方、母が入退院を繰り返していた郊外の結核療養所の風景も脳裏をよぎり、なんかなぁ~という感情も湧いた。
そ 当時、私は精神病院に勤めていて、忙しい毎日を送っていた。入院、外来ともに担当患者さんがおり、いくつもの治療活動を担っていた。いつ入院になるか、またどれくらいの入院期間になるかも分からないという状況は最悪だった。取り敢えず、新患は持たないことと、私の居ない間他のスタッフに担当してもらうべく担当患者さんの割り振りを行い、日常業務はなるべく少なくするように努めた。私がいなくても業務がスムーズに行われるようにフェードアウトしていくことにしたのである。
精神病院というのは未だに劣悪な環境に置かれていて、WHO(世界保健機構)から何度も改善勧告を日本は受けている。先進国の中では最悪の環境であり、20年も30年も遅れている。
過日、八王子労政会館で精神医療をテーマにした「むかしMattoの町があった」という映画の上映会があったが、イタリアで精神病院が全廃されて行く過程をドキュメンタリータッチで描いたものだ。大熊一夫さんが第一回バザ-リア賞を受賞した折にイタリアから持ち帰った映画で、字幕作製のカンパに私も協力している。
日本での精神病院平均在院日数は未だ350日を越しており、日本以外の先進各国ではすべて100日以下であり、30日を下回る国も数か国ある。精神科特例と言ってスタッフの数が少なくても良い(医者は三分の一、看護、薬剤は二分の一)という法律を持つのも日本特有のことである。1960年に当時日本医師会会長だった故武見太郎が「精神病院のことを牧畜業者」と指弾(しだん)した状況は、一部は改善されたものの、今もってあらかた変わっていない。
のような状況の中、精神医療改革運動に携(たずさ)わりながら、ある精神
病院の改革に取り組んでいた6年目の途中に戦列を離れることになった。超忙しい毎日だったから、暫(しば)しの休養という意味では有り難いものでもあった。(続く)
通信本文はここまで。
八障連通信310号【PDF版】はこちらから。
ここより、八障連通信310号本文です。
【事務局通信 Vol.23】
桜が咲き誇る新年度を迎えました。4月を迎えて新しい出会いや別れもあったかと思います。八障連も新体制となり、皆様のご協力を頂きながら何とか一年が経とうとしています。3月は特にイベントも多く、第4回の知的障害者の地域生活について考える学習会では実際に単身生活をされている当事者の方のお話が聞けました。反響も大きく席が足りなくて立ったままの方も多く、関心の高さが知れました。詳細は別途報告で。福祉フォーラムでは「風は生きよという」の上映会を行い、一般市民から福祉関係者、医療関係者、これから上映を考えている方、高校生など幅広い来場となりました。また今回はバリアフリー上映会でもあり、視覚障害の方も多く来ていただけました。jilが推進している映画ということもあり、機材、セッティングなどもjilの完全協力のもと行いました。この場を借りて担当していただいたjilの皆様と手伝っていただいたご家族の方へお礼申し上げます。
第2部では海老原宏美さんのトークショーがあり、映画の内容を補完するとともに障害者の何気ない日常をお話ししていただきました。何気ない日常の中から多くのメッセージがあり、来場された方は何かしらを持って帰られたのでないかと思います。話は変わりますが、障害者福祉課から平成28年度予算についてお話を3役で聞きました。高齢化が待ったなしに進む中で、予算は膨れ上がる一方という状況を背景に、地域活動支援センターの委託費増額はなかなか厳しい状況は変わらないようです。具体的な地域ニーズをより鮮明にしていく必要はあるようです。点字ディスプレイについては近隣他市の状況もみて、極めて前向きな検討が行われているようです。視覚障害の方々の情報格差の是正が期待されます。いわゆる家賃補助については、平成28年度は現行通りとなりましたが、平成29年度は制度自体の変更を準備されるようです。確かに無制限に全ての事業所へ負担し続けるのは現実的ではないかもしれませんが、障害特性などで運営が厳しいところ、必要なサービスがなくならない配慮がされるよう注視していく必要はあります。もうすぐ定期総会を迎えますが、より一層の皆様のご協力と参加をお願いします。(文責/有賀)
【告知板】
✦ 2016 年度の総会(5 月21 日開催予定)に向けて、4 月21 日(木)の運営委
員会より、2015 年度の活動を振り返りと2016 年度の活動方針の討論に入りま
す。ご注目ください。(運営委員会)
✦ 「結の会」さんより近況報告の投稿がありました。本号に掲載しましたのでぜひ
ご一読ください。また情報発信したいという会員団体の投稿を引き続き募集して
おります。投稿先 cxb01672@nifty.com 八障連通信掲載希望とお書きくださ
い。(編集部)
【今後のスケジュール】
八障連運営委員会 4月21日(木) 18時~20時 クリエイト第1学習会
八障連定期総会 5月21日(土) 13時30分~16時30分 八王子労政会館第1会議室
ワークセンター総会 5月21日(土)9時30分~12時 八王子労政会館
【第4回 知的に障害のある人の地域生活を考える学習会報告
グループホームと一人暮らしでは、何がどうちがうのか?】
立ち見が出るほどの大盛況でした
知的に障害のある方の地域生活というと今はグループホームというのが、一般的かと思いますが、地域では、一人暮らしをしている方もいらっしゃいます。3月12日クリエイトホール第2学習室で行われた第4回目の学習会では、八王子市で一人暮らしをしている田丸俊彦さんとその支援をしているヒューマンケア協会の関島裕美さんペアと多摩市で一人暮らしをしている山崎隆司さんとその支援をしているたこの木クラブの横田彰敏さんペアにお話を伺いました。当日は、定員70名のところ立ち見が出るほどの大盛況でした。
実家のそばに暮らすという田丸さんの新しい選択
ひと口に一人暮らしといっても、親御さんをはじめとする環境によってそうせざるを得なくて始まる一人暮らしと自分から望んで始まる一人暮らしがあること、八王子では、残念ながらせざるを得なくて始まった方が多いことを知りました。そんな中、10年ほど前から実家のすぐそばにアパートを借りて実家と両立させて暮らす田丸さんのライフスタイルは、自宅か独立かという二者択一だった自立観に対して、新しい選択肢として注目されます(最近は、お母さんが実家で一人になったため、実家で寝るようにしているそうで、これも高齢化する親との関係性として、新しい選択肢かもしれません)。
仲間に触発されてはじまった山崎さんの一人暮らし
一方の山崎さんは、周りの仲間が先に一人暮らしをはじめる様子を見て、自分も自立したいと希望してはじまったそうです。田丸さんは、ヘルパーさんは入っておらず、ガイヘルを時々使うぐらいとのことでしたが、山崎さんは、毎朝8時にはヘルパーさんが来られて、朝食や洗濯を済ませ、作業所に通い、夕方から夜の9時ぐらいまではまたヘルパーさんと過ごすそうです。他の仲間は24時間ヘルパーさんがついている方も多いそうです。今回、その様子をよりリアルに知っていただけるようにと映像の提供をお願いしたところ、田丸さんは、ご自分で自分の部屋の様子を撮ってきてくれました。そのほとんどは、音の出ていないテレビ番組に、BGMとして田丸さんの好きなアイドルの歌が流れているといったもので、一見生活の様子とは遠い感じがしましたが、そこには田丸さんの世界、世界観がはっきりと感じられましたし、生活の拠点が実家に移りつつある田丸さんにとっては、一人暮らしの中心はこういった誰にも遠慮の要らない一人の時間の過ごし方なのかなと後で納得しました。一方、山崎さんの映像は、支援者の横田さんが、自分とは異なるヘルパーさんが入ったある朝の様子を詳細に撮ってくださったもので、山崎さんが洗濯物を洗濯機に入れる様子やヘルパーさんが朝食を作り、それを食べる山崎さんの様子から、その生活の雰囲気がよくわかりました。また、撮影した横田さんが、自分が入った時とは山崎さんの様子が全くちがうことに驚かれたり、当日の支援者の方も、カメラが回っている今日はいつもの山崎さんとはかなりちがうといったお話があったりして、今回の撮影を通して、意外な発見があったようです。
大切なのは「できるできないよりも、一人暮らしをしたいという思い」
最後の質疑応答の際、「どういった基準で一人暮らしができるかどうかを判断するのですか?」という質問に、関島さんが、「何々ができなければ、ということはないです」「できるできないよりも、その人が本当に一人暮らしをしたいのかどうか、その思い、覚悟が大切です」と答えてくださいました。会場の方は、ちょっと驚いていましたが、今回の学習会で、一番大切だったのは、この点だったと思います。私たちはつい、何々ができるから自立できる、何々ができないから自立できない、と考えてしまいがちですが、できないことは誰かに手伝ってもらえばいい、しかし、こうしたいという気持ち、意思は、だれかに代わってもらうわけにはいきません。最後になりましたが、田丸さん、関島さん、そして多摩市からわざわざおいでくださった山崎さん、横田さんをはじめとする「たこの木クラブ」の皆々様、どうもありがとうございました。 (文責/土居)
【《会員近況報告》
八王子市の「監査」を受けました -しばらく勘弁ですねー NPO 法人:結の会 (市川翔吾)】
去年の12月10日になりますが、結の会は、八王子市の実地検査、所謂監査を受けました。監査というものは、突然八王子市からの郵送でこの日に行いますと通達が来ます。それも実施日の10日ほど前にやってくるものですから、かなりあたふたします。
以前、小耳にはさんだ話によると、労災申請が立て続けにあった事業所に監査が入ったと聞いていたので、何か少し目に付くようなことがあった場合監査が入りやすいのかなと思っていました。ただ、結の会の場合、特に思い当たる節もないですし、何故だろう?もしかして、請求関係でミスでもあったのだろうか?と若干ドギマギしていましたが、市の方に聞いたところ、平成27年4月より八王子市が中核市に移行したことにより、市内の福祉施設全てを順番にまわっているとのことでした。
監査にあたっては、まず通達書と一緒に準備書類一覧というものが記されており、それらを当日までに用意・整理しておかなければなりません。年末の忙しい時期とも重なり、これがなかなか大変な作業でした。ひとつひとつ用意して不備がないかなど確認し、しっかり説明できるように準備しました。
そんなこんなで、監査当日、市の指導監査課の職員の方3名がやってきました。最初に施設内を案内しながら設備面などのチェックが入ります。そして、用意した書類を渡して、それを市職員の方がひたすらチェックします。私たちは、別室で仕事をしながら待機していて、何かあれば呼ばれるので、書類についての説明を行います。ですので、当日は監査に関して、思っているほど対応するというようなことはありませんでした。最後に口頭で改善点などの指摘を受けます。後日、改めてその結果が書面で送られてきました。
結果については、概ね良好で、書面などもよく整備されていますとのことでしたが、大きく2点ほど是正してくださいとの指摘を受けました。ひとつは、「虐待防止・人権意識向上のための研修を実施していないので是正すること」。もうひとつは、「サービス提供の記録をしていないので是正すること」でした。「虐待防止~」については早速、規定を整備し、それについてのミーティングも定期的に行い、研修計画もたてました。「サービス提供の記録~」については、全くやっていないということはなく、毎日の作業内容の記録や、大なり小なり様子の変化やトピックがあればその都度記録するというスタイルでやってきました。今回は、更に毎日の細やかな様子の記録、毎度メンバーからの確認をもらってくださいとのことでした。これが、一見単純で簡単なことのようにも思えますが、現場で実際やるとなるとなかなか厳しく、日常業務や日々ただでさえ多くなっていく事務仕事を行っていくなかでは、メンバーと関われる時間がますます減り、事務量・残業は増えていくという負のスパイラルに入り込んでいき本末転倒なことになりかねないわけです。もちろん、サービス提供の記録はとても大切で必要なものであると思います。これについては、もう少しうまいやり方があるのではないかと模索しながら導き出せればと思います。
今回の監査を受けては、自立支援法という大きな波に飲み込まれることなく、自分たちのスタンスとバランスを崩さず、法と程よい距離感でうまく付き合いながら、結で働くメンバー・職員がよりよく過ごせるようにと気をひきしめるよい機会になりました。ただ、監査はしばらく勘弁ですね。(結の会通信77号より転載)
【連載コラム B 型肝炎闘病記 パオ 小濵 義久 闘病史 その3】
昨年の11 月に肝臓癌の再発があり、2 週間足らずの入院生活を2 回にわたって挿入させてもらったが、今回から34 年前の肝臓での初めての入院体験に戻ることにする。
その2」で、初診時に入院手続きをして帰ったという話を書いたが、その時に肝臓での入院は都心の虎の門にある本院ではなく、川崎市の梶ヶ谷にある分院にと言われ、入院のしおりとともに分院の地図が描かれているパンフレットも渡された。都心の喧騒(けんそう)の中での入院生活よりは、郊外での方がのんびりしていて良いかなと感じた。一方、母が入退院を繰り返していた郊外の結核療養所の風景も脳裏をよぎり、なんかなぁ~という感情も湧いた。
そ 当時、私は精神病院に勤めていて、忙しい毎日を送っていた。入院、外来ともに担当患者さんがおり、いくつもの治療活動を担っていた。いつ入院になるか、またどれくらいの入院期間になるかも分からないという状況は最悪だった。取り敢えず、新患は持たないことと、私の居ない間他のスタッフに担当してもらうべく担当患者さんの割り振りを行い、日常業務はなるべく少なくするように努めた。私がいなくても業務がスムーズに行われるようにフェードアウトしていくことにしたのである。
精神病院というのは未だに劣悪な環境に置かれていて、WHO(世界保健機構)から何度も改善勧告を日本は受けている。先進国の中では最悪の環境であり、20年も30年も遅れている。
過日、八王子労政会館で精神医療をテーマにした「むかしMattoの町があった」という映画の上映会があったが、イタリアで精神病院が全廃されて行く過程をドキュメンタリータッチで描いたものだ。大熊一夫さんが第一回バザ-リア賞を受賞した折にイタリアから持ち帰った映画で、字幕作製のカンパに私も協力している。
日本での精神病院平均在院日数は未だ350日を越しており、日本以外の先進各国ではすべて100日以下であり、30日を下回る国も数か国ある。精神科特例と言ってスタッフの数が少なくても良い(医者は三分の一、看護、薬剤は二分の一)という法律を持つのも日本特有のことである。1960年に当時日本医師会会長だった故武見太郎が「精神病院のことを牧畜業者」と指弾(しだん)した状況は、一部は改善されたものの、今もってあらかた変わっていない。
のような状況の中、精神医療改革運動に携(たずさ)わりながら、ある精神
病院の改革に取り組んでいた6年目の途中に戦列を離れることになった。超忙しい毎日だったから、暫(しば)しの休養という意味では有り難いものでもあった。(続く)
通信本文はここまで。