こちらから、メールを送信出来ます。
彼はかなり、マメにファンメールは見てくれます。
サッカーに関心のある方こそ、送ってあげて下さい。
こんばんは ツネ。
しばらくまた、日にち空いて悪かったな。
オレは過去を振り返る事に、最近はまっている。
小学校1・2年の時分に、母親がお菓子を棚の上に隠されてしまっていた。
今思い出したけど、母方の親や父方の親もよく小包にお菓子を一緒に入れて送ってくれた。
オレは長男だったから、親戚一同からは結構気を遣ってもらって育ったと母も妹が小学校高学年くらいに成長してからシミジミ話していた。
何故ならオレの写真やらなにやらは、結構残ってたりする。
しかし父親の気まぐれで残されている成長の記録は、妹に対しては圧倒的に少ない。
親戚からの贈り物で構成される雛人形なども、妹のものは質素だ。
こういった生まれながらの格差というのは、誰にも起こりうるものだ。
だが格差は埋められるものであっても、記憶の中にある過去の格差は一生残るものだ。
それはその人のパーソナリティーなり、性癖なり、コンプレックスとなって色濃く現れるものだ。
オマエが虫が苦手なのも、過去の記憶からくるものである。
母親や周りの兄弟が虫が苦手な場合、その周りとの反応の格差を埋めるために強制的に刷り込まれる形で虫嫌いになる。
現状のオマエが虫に殺される訳でもないし、虫に出くわしたところで明日のコンディションに響くようならプロとしてどうかとも思う。
つまりどんな出来事に遭遇しても、未来の自分に本当に影響が出るかどうかを慎重に判断しろと言いたい。
人間の思考形態は二つあると思う、一つは日常の思考。
もう一つは、言語下の思考である。
いい文章が書ける人間が、必ずしも日常での思考もそうであるかと言えば必ずしも一致しないであろう。
文章を書くのは訓練だが、その人の心血が注がれた文章を読みやすく作るにはある程度の才能も必要とされる。
それは、言葉の選び方であったり。
文章の区切り方であったり、人から指図を受けてどうなるものでもない。
オレは結構自分の感覚を大事にして、生きている。
だから自分が弱ってる時や、疲れてる時に感覚が働かなくて困るという気持ちもよく分かる。
ただそれでは、どうだろう?
感覚に頼るだけでは、安定した成果は望めない。
サッカーは、点で合わせるスポーツである。
点と点の距離は、走力と始動の早さで相手よりも早く移動しなければならない。
そしてサッカーにおいて、点を抑える事をチームが意識した場合どうなるか。
ポジションは自然と流動的になる、CBがあがったり。
左SBが、右サイドでボールを受けたり。
それは何故チョイスされるか?
ノーマークでボールを受けたり、ノーマークにさせない為である。
勿論マークとは、相手からボールを奪い取ってビルドアップやチャンスメイクに繋げられる視野と技量と度量が同時に求められる。
そして奪い取る事を信じて、周りがサポートと同時に一時も攻撃の準備も怠らない。
そういうチームが鋭い出足と、素早い展開を可能にする。
そのために、ポジションは関係ないチームは形成される。
ただ、それだけの事。
動けるやつが動いてるのではなく、動くポイントを察知した人間が始動する。
それを背中を見て感じ取って、周りが流動的にバックアップしているだけである。
ここでひらめいた
日本人は過去のこれまで受けた指導で、ポジションを固執したり。
早め、早めの勝負に持ち込む姿勢を「勝ち急ぐな」と言われてないか。
3年前に浦和の試合を観戦していて、平川が左サイドバックをやっていた。
自陣からドリブルで相手を抜きにかかった様子を見て、観戦していたワタシより一回りは年をとっていそうな男性がこう言った。
「なんでそんな所で、勝負するんだ」
これは一つの意見だが、今思うとこういった思考が日本のサイドバックに怖さを失わせてるのではないか?
オレは自陣でサイドバックがボールを持った場合、相手のマークについたプレーヤーの初動を見てイケそうなら勝負を要求する。
しかけていく姿勢は、当時前線に君臨したエメルソンにも伝わるし。
そういった後方から仕掛けていく姿勢というのは、当時の浦和からすれば生命線の様に感じられていた。
オレはサッカーの指導を受けた事が無いし、プレー経験も無い。
だからかもしれないが、その瞬間に沿ったプレーの選択という物が取れるのかもしれない。
過去の己の苦い経験や、誤った刷り込みが無いからだ。
それに加えてオレの、言ったもん勝ちという強いコーチング意欲がオレを突き動かしているからだ。
サッカーに興味を持った93年以降から、チームと個人の噛み合わせをずっと模索していた。
そう今は、過去を振り返って考えている。
チームには何人かのスタープレーヤーと、縁の下の力持ちが居る事はだいたい分かる。
そしてサッカーは11人だけでなく、ベンチプレーヤーも含めてやるものだと理解した時。
縁の下の力持ちの存在も、試合の行方に関わっている事に気付かされた。
それが、守備力である。
エスパルスのシジマールの無失点記録が、少年サンデーの表紙をめくってすぐのカラーページに記されてあった事がオレにそれを強く刷り込ませ印象付けさせた。
続きついては、次回語ろう。














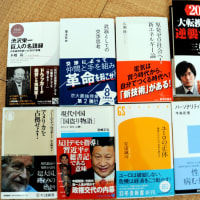





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます