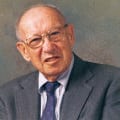今日のマコなり社長のインサイドストーリーズから
・論理と感情を行き来しながら、自分にしかできない価値を出していこう!
・任せるということは、任せた相手がどのような結果を出してもどのような問題を起こそうとも責任を取るということである。責任を取るとは、部下がやったことを自分がやったことと同じと受け止めることを意味する。
・権限委譲とは、部下が起こした問題の全ての責任を負うこと。すなわち委譲された全ての責任を持つことと言える。
・社員のひとりが違法行為をしてしまったときに、私が逮捕されるわけではない。それは、個人として裁かれる問題である。しかし、会社が提供しているサービスでお客様に損害を与えてしまったのであれば、それはそのような人を採用した会社の責任であり、トップの責任でもある。会社の活動の中で起きたことは全てトップの責任である。
・組織の運営の仕方にセオリーはある。組織がピラミッド構造であることを前提としている以上、正攻法は存在する。正攻法はあるが、他の組織の在り方は組織によってかなり異なる。
・お客様に価値を提供するために、どのような組織だったらいちばん良いのかを考え抜いて、最適化されていたとしても、正解はひとつだけではない。
・セオリーとは、激辛料理のお店を作るよりは、皆カレーが好きだからカレーのお店のほうが多くの人がおいしいと言ってくれる可能性が高いということであり「激辛料理を出すのが正解なのか。チャーハンを出すのが正解なのか」という議論をすることではない。
・プロセスコントロールをしないことが良いかどうかは、お客様に価値提供ができているかどうかで測るべきである。セオリーの話で言うと、権限委譲したからにはプロセスをコントロールしないというのもセオリーである。理由の1つ目は、意味がないから。自分の思い通りに動かない他人という存在を事細かく全て指示して動かすのであれば、それは自分が手を動かしているのと同じになってしまう。理由の2つ目は、できるようになるのが遅くなるから。はじめはみんな理解が浅いので、なぜそれが便利なのかや良いやり方なのかが分かっていない。前提としている考え方から自分なりの良いやり方を生み出すことができなければ、変化に適応できない。さらに、腹落ちしていないため、ルールや指示されたやり方をやらなくなるという場合がある。
・人は、自分で「なぜこのようにやるのだろうか」と考えてみたときに初めて、複数の選択肢や膨大な前提条件から自分なりの答えを導き出そうとする。
・プロセスを全て奪って具体的な指示をしてしまうと、学びを減らしてしまう。ここで言う学びとは「知る」「分かる」「できる」「習得する」である。この学びの段階を浅くしてしまう。
・プロセスコントロールの問題点は「そもそも意味がない」「部下が学ばなくなる」ことである。
★部下に対しては、数字の目標もしくは「これができるようになる」というなにかしら目標を置いて、後は口を出さないのがいちばん良いのかというと、それは違う。そこには2つの観点がある。ひとつは、目標のレベルである。上司が数字だけを追わせるとどのようになるかというと、なにからやって良いのかが分からず大抵の人は溺れてしまう。その対策は丁寧にWhyから説明すること、前提から説明することである。一度言って分かると思うほうが間違っている。何十回も繰り返していくことで、私がこれまで学んできた知識や経験、価値観が部下にもインストールされていく。タイミングを見て毎回同じことを言うことが大切である。いつから言い始めたのか分からないくらい同じ指摘を、同じ人に何度も言わなければならない。これは、仕組みであり文化である。そのようにしなければならない。それが教育である。
・最初から決まっていることや、一貫して伝えていることをできないときに指摘することはプロセスコントロールではない。プロセスコントロールとは、まるで代わりに仕事をやってあげるかのように全て決めて指示をすることである。結果を出す方法は、ひとつではないので、決められたこと以外に関しては、自由に創意工夫や想像力を発揮すべきであるので、プロセスコントロールをコントロールするという考え方が正しい。
・一般的に仕事のプロセスで決まっていることは、仕事の意思決定の中の10分の1もない。他の90%は、自分の判断で進められるところがある。
・リーダーもメンバーも良い意味で利用することで、ギブ&テイクの関係を築きながらお互いに成長することができる。しかし。部下の成長や学びよりも、短期的な成果を大事にしなければならない場面もある。場面に応じて、どのようにすれば長期的に仕事や会社が良くなっていくのかを考えて、プロセスコントロールをコントロールしていこう!