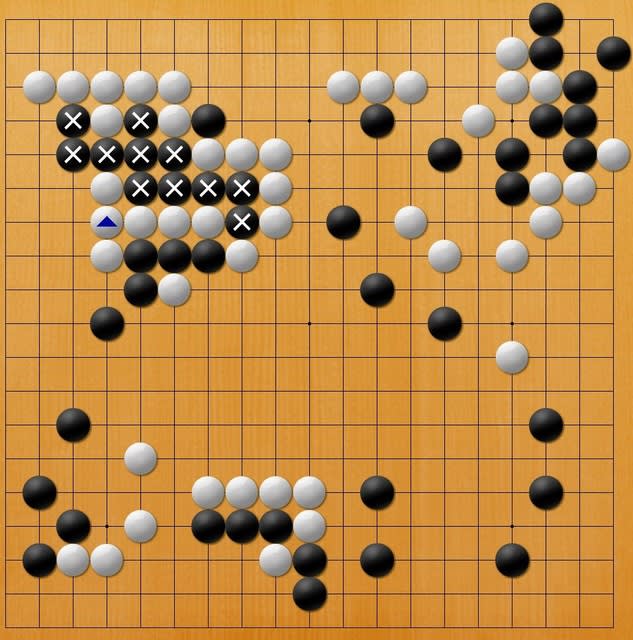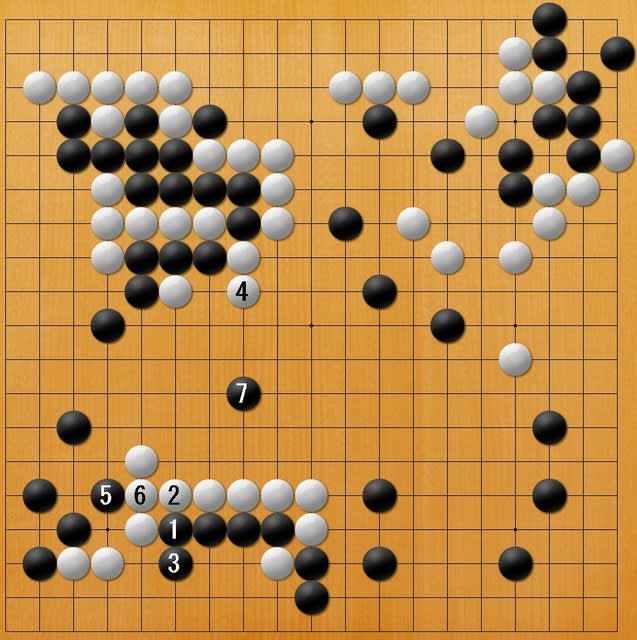皆様こんばんは。
まずはお知らせです。
Facebookに仕様変更があり、gooブログとの連携ができなくなりました。
以前はブログを投稿すると、自動的にFacebookにもリンクが貼られるようにできていましたが、これからは手動になります。
私のことですから、うっかり忘れることもあるでしょう・・・。
さて、本題に移りましょう。
以前、11路盤が欲しいというお話をしましたが・・・。
読者の方から、作っているところがあるという情報を頂きました。
その中の1つに、株式会社アルプレートというところがあります。
今回、そちらで作っている11路盤をモニター使用させて頂くことになりました。
ご紹介しましょう。
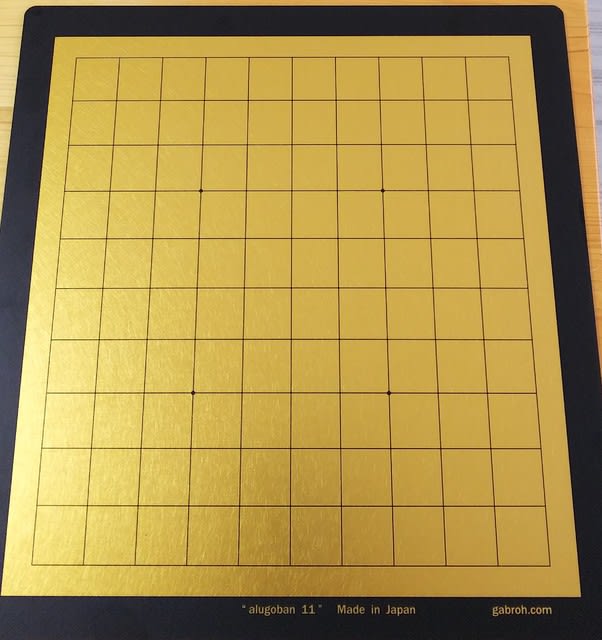
こちらです!
私の写真の腕は25級レベルなので伝わりづらいかと思いますが、ピカピカ光っています。
なんと、アルミ製碁盤なのです。
普段私達は木製の碁盤で対局しますが、他にもプラスチックやガラス、紙、布などで作られたものもあります。
しかし、アルミ製の碁盤を見たのは初めてです。
https://twitter.com/alplate">こちらのブランドで、様々なアルミ製の碁盤や将棋盤を作っているとか。
厚さは約1~2mmという、極薄設計となっています。
カフェなどに置くのにちょうど良さそうですね。
おしゃれで場所も取りません。
モニター使用ということで、課題も考えてみましょうか。
金属なので、木の碁盤と同じ感覚でやってしまうと、かなり大きな音になってしまうということがあります。
初心者の子供(5歳)が試してくれていますが、元気一杯に打たれるとちょっと心配になります(笑)。
この対策としては、まずは石を打ちつけるのではなく、そっと置くことです。
志田達哉か芝野虎丸になりきってください(笑)。
もう1つは、相性の良い石を選ぶことです。
手持ちの蛤碁石で試しましたが、35号よりも32号の方が、また黒石よりも白石の方が打ちやすいです。
なるべく薄い方が良いのではないでしょうか。
材質としても、蛤はベストではない気がします。
平べったくて滑りにくいものが良いでしょう。
何はともあれ、11路盤が手に入って嬉しいです。
これで指導方法の幅が広がります。
また、指導対局では既に試していますが、普通に19路盤を打てる人が打ったらどうなるかを考えてみました。

<1図>
例えばこんな進行を想定できます。
これは、9路よりに13路の方が近い雰囲気ですね。
1局を布石、中盤、終盤に分けることができそうです。
余談ですが、この図はKiinEditorにて作成しました。
KiinEditorは2路盤から19路盤まで対応しているのです。
えっ、2路盤? と思われるかもしれませんが・・・。
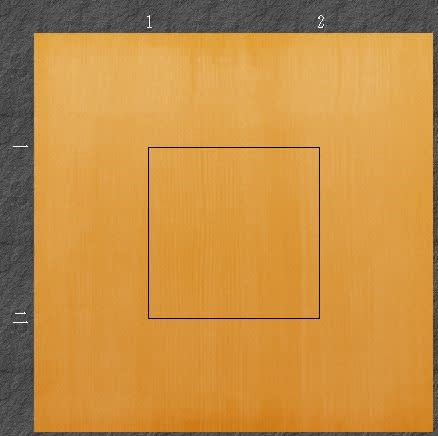
<2図>
これも一応、囲碁と言えないことはありません。
相手が間違えれば、2眼作れる可能性もありますからね。
上手くいかなかった場合は、不毛な争いになりますが・・・(笑)。
まずはお知らせです。
Facebookに仕様変更があり、gooブログとの連携ができなくなりました。
以前はブログを投稿すると、自動的にFacebookにもリンクが貼られるようにできていましたが、これからは手動になります。
私のことですから、うっかり忘れることもあるでしょう・・・。

さて、本題に移りましょう。
以前、11路盤が欲しいというお話をしましたが・・・。
読者の方から、作っているところがあるという情報を頂きました。
その中の1つに、株式会社アルプレートというところがあります。
今回、そちらで作っている11路盤をモニター使用させて頂くことになりました。
ご紹介しましょう。
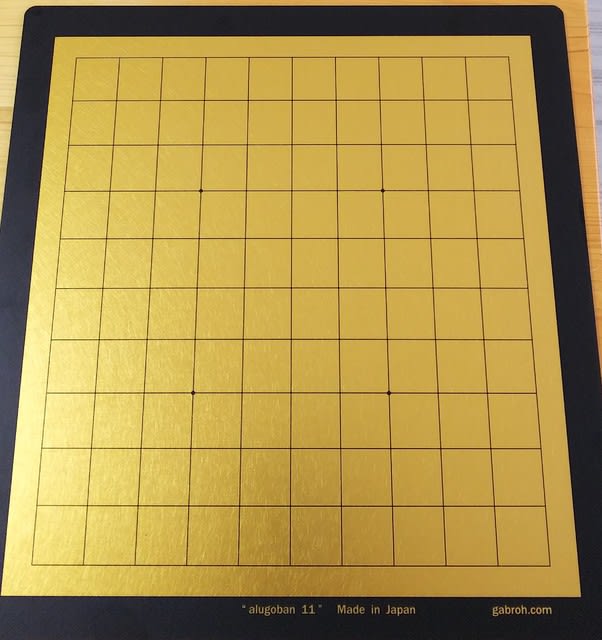
こちらです!
私の写真の腕は25級レベルなので伝わりづらいかと思いますが、ピカピカ光っています。
なんと、アルミ製碁盤なのです。
普段私達は木製の碁盤で対局しますが、他にもプラスチックやガラス、紙、布などで作られたものもあります。
しかし、アルミ製の碁盤を見たのは初めてです。
https://twitter.com/alplate">こちらのブランドで、様々なアルミ製の碁盤や将棋盤を作っているとか。
厚さは約1~2mmという、極薄設計となっています。
カフェなどに置くのにちょうど良さそうですね。
おしゃれで場所も取りません。
モニター使用ということで、課題も考えてみましょうか。
金属なので、木の碁盤と同じ感覚でやってしまうと、かなり大きな音になってしまうということがあります。
初心者の子供(5歳)が試してくれていますが、元気一杯に打たれるとちょっと心配になります(笑)。
この対策としては、まずは石を打ちつけるのではなく、そっと置くことです。
志田達哉か芝野虎丸になりきってください(笑)。
もう1つは、相性の良い石を選ぶことです。
手持ちの蛤碁石で試しましたが、35号よりも32号の方が、また黒石よりも白石の方が打ちやすいです。
なるべく薄い方が良いのではないでしょうか。
材質としても、蛤はベストではない気がします。
平べったくて滑りにくいものが良いでしょう。
何はともあれ、11路盤が手に入って嬉しいです。
これで指導方法の幅が広がります。
また、指導対局では既に試していますが、普通に19路盤を打てる人が打ったらどうなるかを考えてみました。

<1図>
例えばこんな進行を想定できます。
これは、9路よりに13路の方が近い雰囲気ですね。
1局を布石、中盤、終盤に分けることができそうです。
余談ですが、この図はKiinEditorにて作成しました。
KiinEditorは2路盤から19路盤まで対応しているのです。
えっ、2路盤? と思われるかもしれませんが・・・。
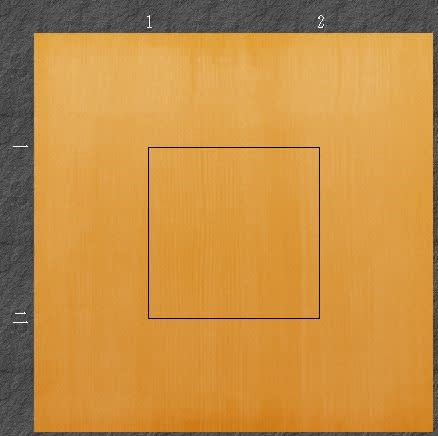
<2図>
これも一応、囲碁と言えないことはありません。
相手が間違えれば、2眼作れる可能性もありますからね。
上手くいかなかった場合は、不毛な争いになりますが・・・(笑)。