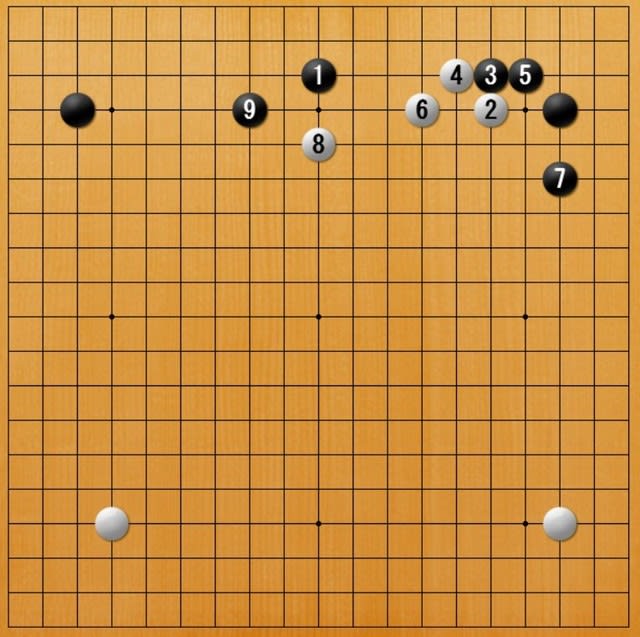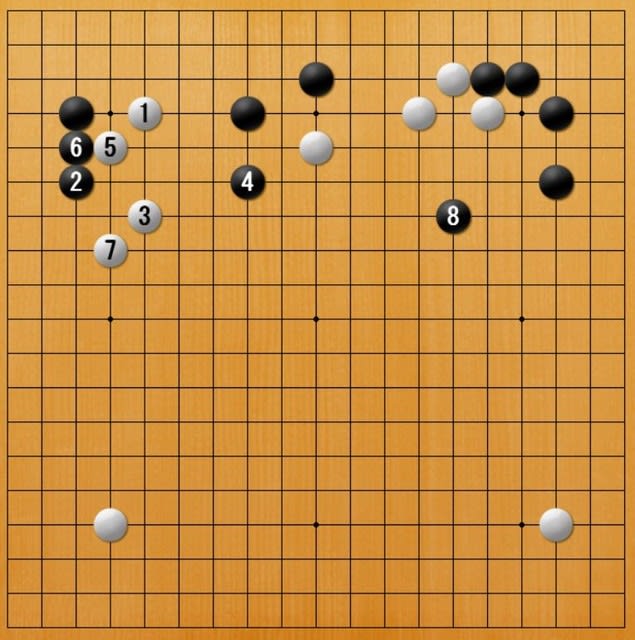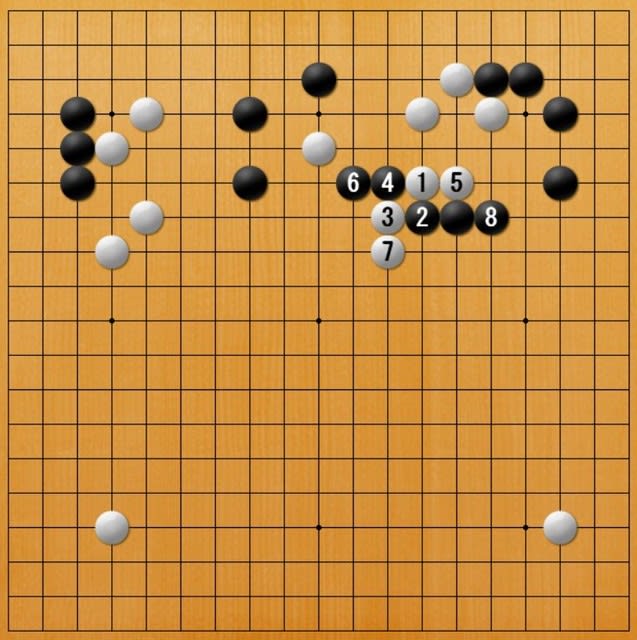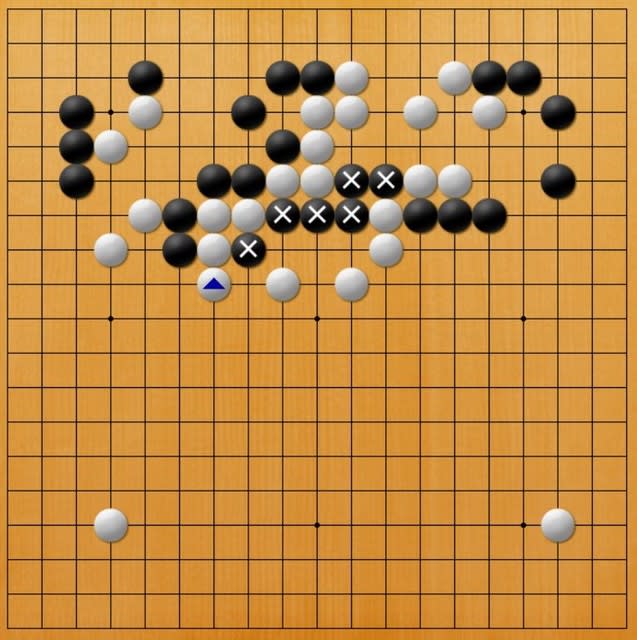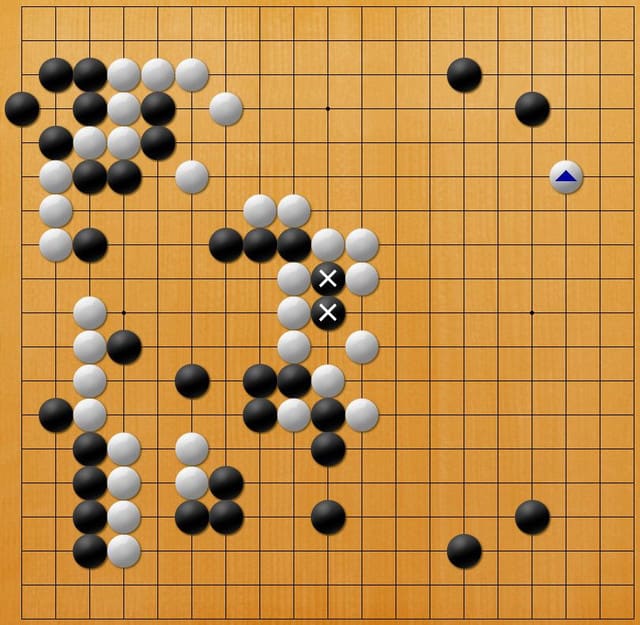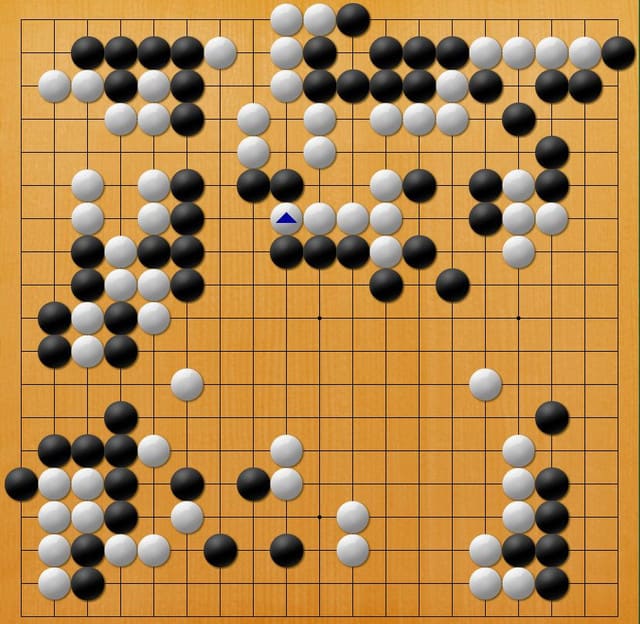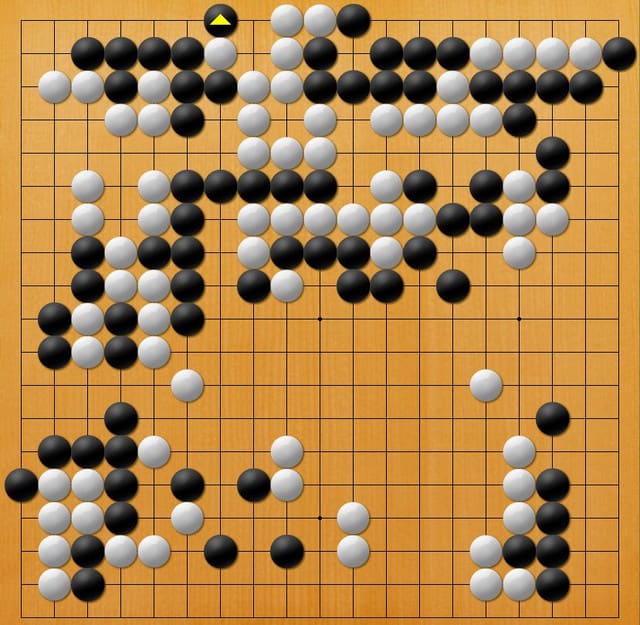<本日の一言>
件名「アドレス変更」
本文「再度登録お願いします。」
・・・どちら様でしょうか?
非常にモヤモヤしますが、迷惑メールなのでしょうね。
</本日の一言>
皆様こんばんは。
本日は棋士紹介シリーズの第6回です。
<小池芳弘四段(公式プロフィール)>
平成10年(1998年)7月6日生まれの20歳です。
長年棋士をやっていそうな雰囲気を漂わせていますが、そんなに若かったのですね。
小池四段はTwitterの日本棋院若手棋士アカウントを何度か担当していますが、しばしば本質を突くかのような鋭い発言をします。
将来なかなかの論客になるのではないかと睨んでいるのですが、いかがでしょうか。
さて、小池四段は昨年19連勝という素晴らしい記録を残しました。
年間成績は36勝12敗で、7割5分の勝率は全棋士中3位でした。
好成績の秘訣は、体力があることではないかと思います。
体力と言っても、運動のための体力ではありません。
囲碁の体力です。
棋士の対局は朝10時頃から始まって夕方に終わることが多く、持ち時間の長い碁では夜10時、11時まで長引くこともあります。
また、1局の持ち時間が短くても、同じ日に何局も打ったり、連日対局するような場合もあります。
長丁場の戦いで集中力を持続させられるかどうかは、勝負に大きく影響します。
棋風は典型的なじっくりタイプですね。
勝負が長引くことを全く恐れていないのでしょう。
さて、今回ご紹介するのは2016年8月18日の棋聖戦Cリーグ、片岡聡九段との対局です。
片岡九段も、若い頃からじっくりタイプとして有名でしたね。
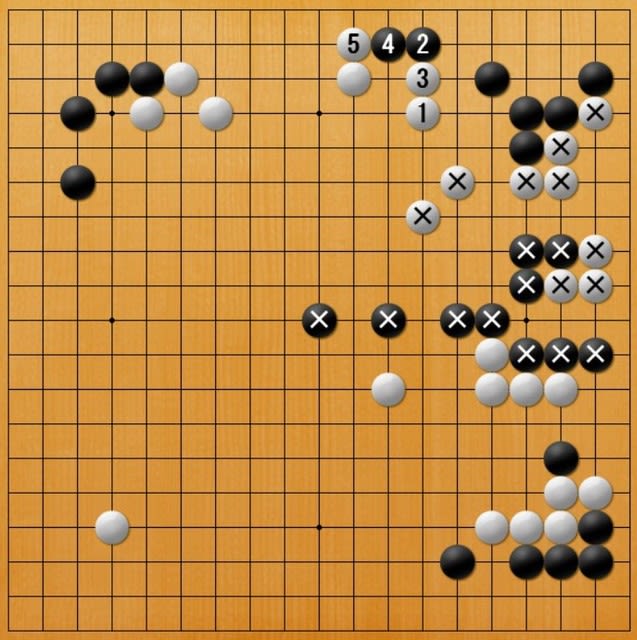
1図(実戦)
片岡九段の黒番です。
黒×が弱いですが、白×も心配です。
慌てて攻めかかったりすると、反撃を受けて苦しくなるでしょう。
そこで、実戦は白1~5としっかりつながりました。
この打ち方は当然と言えば当然ですね。
しかし、対局していると色々と雑念が生じ、あらぬ方向に石が行ってしまうこともあります。
その点、小池四段はやるべきことを淡々とこなしていく印象があります。
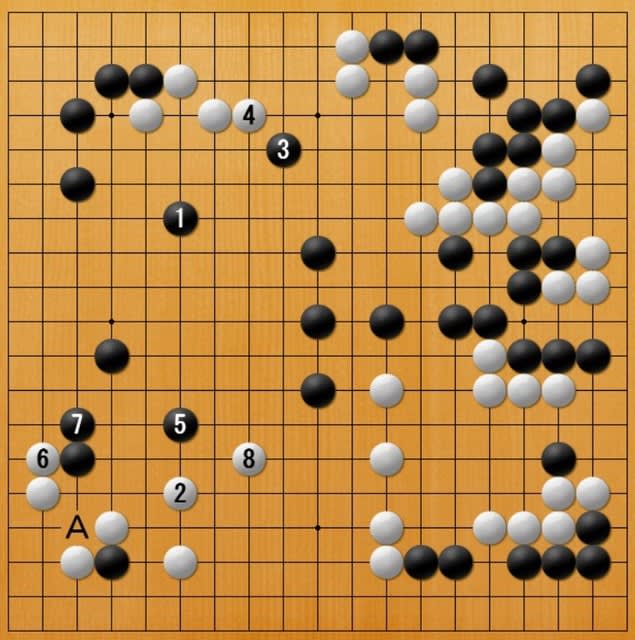
2図(実戦)
黒1と左辺を広げられましたが、慌てず騒がず白2と守りました。
黒Aなどの手を防いだものですが、実に落ち着いていますね。
無理に左辺に入っていかなくても、十分やれるとみているのです。
若い頃はつい力に頼った無茶をしてしまいがちですが、小池四段はそのようなことには無縁かもしれません。
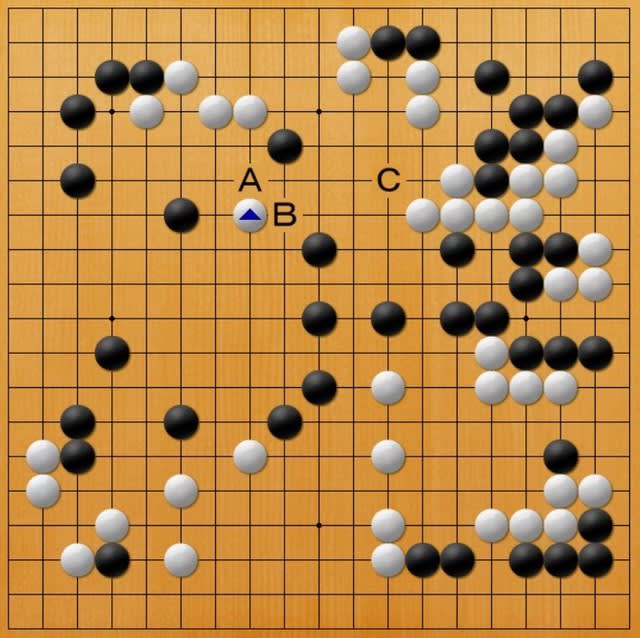
3図(実戦)
無茶はしませんが、ぎりぎりの踏み込みは決行します。
白△が鋭い手でした。
この後、黒A、白B、黒Cと対応され、怖い感じもありますが・・・。

4図(実戦)
しかし、小池初段(当時)は読みきっていたのでしょうね。
次に黒A、白B、黒Cがありそうですが、白D、黒E、白Fの反撃で右辺黒が危ないということでしょう。
深く読むことで、戦いのリスクを小さくしています。
本局は小池初段の白番半目勝ちでした。
件名「アドレス変更」
本文「再度登録お願いします。」
・・・どちら様でしょうか?
非常にモヤモヤしますが、迷惑メールなのでしょうね。
</本日の一言>
皆様こんばんは。
本日は棋士紹介シリーズの第6回です。
<小池芳弘四段(公式プロフィール)>
平成10年(1998年)7月6日生まれの20歳です。
長年棋士をやっていそうな雰囲気を漂わせていますが、そんなに若かったのですね。
小池四段はTwitterの日本棋院若手棋士アカウントを何度か担当していますが、しばしば本質を突くかのような鋭い発言をします。
将来なかなかの論客になるのではないかと睨んでいるのですが、いかがでしょうか。
さて、小池四段は昨年19連勝という素晴らしい記録を残しました。
年間成績は36勝12敗で、7割5分の勝率は全棋士中3位でした。
好成績の秘訣は、体力があることではないかと思います。
体力と言っても、運動のための体力ではありません。
囲碁の体力です。
棋士の対局は朝10時頃から始まって夕方に終わることが多く、持ち時間の長い碁では夜10時、11時まで長引くこともあります。
また、1局の持ち時間が短くても、同じ日に何局も打ったり、連日対局するような場合もあります。
長丁場の戦いで集中力を持続させられるかどうかは、勝負に大きく影響します。
棋風は典型的なじっくりタイプですね。
勝負が長引くことを全く恐れていないのでしょう。
さて、今回ご紹介するのは2016年8月18日の棋聖戦Cリーグ、片岡聡九段との対局です。
片岡九段も、若い頃からじっくりタイプとして有名でしたね。
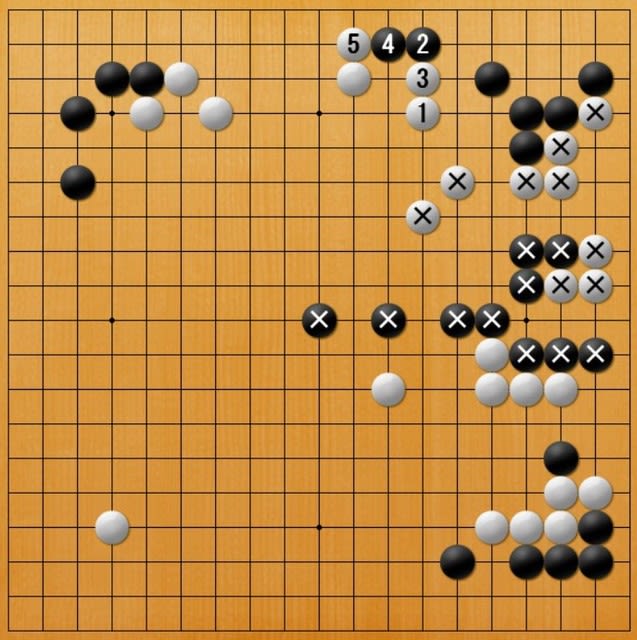
1図(実戦)
片岡九段の黒番です。
黒×が弱いですが、白×も心配です。
慌てて攻めかかったりすると、反撃を受けて苦しくなるでしょう。
そこで、実戦は白1~5としっかりつながりました。
この打ち方は当然と言えば当然ですね。
しかし、対局していると色々と雑念が生じ、あらぬ方向に石が行ってしまうこともあります。
その点、小池四段はやるべきことを淡々とこなしていく印象があります。
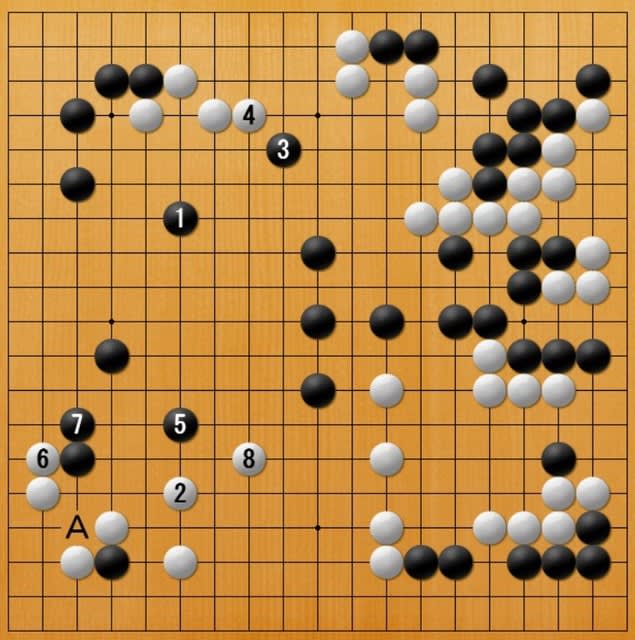
2図(実戦)
黒1と左辺を広げられましたが、慌てず騒がず白2と守りました。
黒Aなどの手を防いだものですが、実に落ち着いていますね。
無理に左辺に入っていかなくても、十分やれるとみているのです。
若い頃はつい力に頼った無茶をしてしまいがちですが、小池四段はそのようなことには無縁かもしれません。
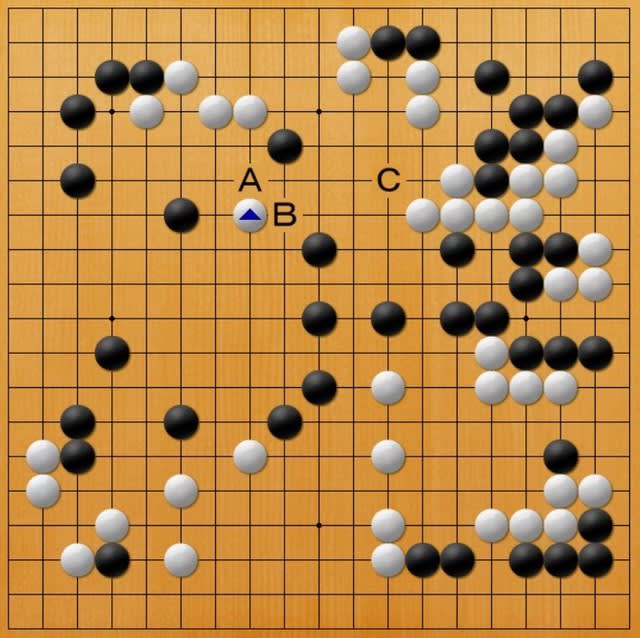
3図(実戦)
無茶はしませんが、ぎりぎりの踏み込みは決行します。
白△が鋭い手でした。
この後、黒A、白B、黒Cと対応され、怖い感じもありますが・・・。

4図(実戦)
しかし、小池初段(当時)は読みきっていたのでしょうね。
次に黒A、白B、黒Cがありそうですが、白D、黒E、白Fの反撃で右辺黒が危ないということでしょう。
深く読むことで、戦いのリスクを小さくしています。
本局は小池初段の白番半目勝ちでした。