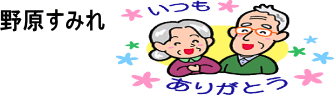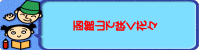去年の今頃の光景 コマツナ
ブログは 毎朝4時頃 更新努力しています
更新は 私が「元気で自遊人」している便りです
お忙しい時の訪問は 「ナナメ読み」や「スルー」していただければと思います
毎日の「挨拶訪問」 お待ちしていま~~~~~~す
 ホームページ田舎都会通信
ホームページ田舎都会通信
昨日 渡島半島東部に位置する古部丸山に登りました
太平洋噴火湾の山裾 雪は少ないが厳寒
国道道端の光景は 凍りつくような寒さを表現していました

普段は一直線に落ちる滝水ですが
昨日は風に流され 苦悩する光景に見えました

右側の面に風で散らばった滝水が降りそそぎ
針で刺されたような痛々しさが伝わってきます

滝つぼ
やる度胸はないが 修験場にピッタシカンカン

点灯
転倒注意信号
ここはコンビニの店頭

豪雪地帯の今時期は
ガンコな氷にお手上げです

歩道もテッカテカ
スケートリンク顔負けの氷盤です

厚い氷は 岩盤のように固い
じょうずな転び方教室 あるといいなあ

気温が緩むと 水たまりにも要注意
お出かけは 格好を気にしないで長靴 これが一番

転倒がイヤなら
お出かけセーブか 室内で花観賞をするのが好さそう





 古部丸山①
古部丸山①

函館市東部にある標高691.1m 古部丸山
北海道三角点選定第1号の山です
24日の記録を3回シリーズで紹介します
絵紙林道地先に車を止めリーダーの注意を受け出発進行
冬山はベテラン指導者に連れて行ってもらうのが 一番
安心して登れます
AM 8:20

山仲間 今回の参加者は22人
AM 8:30

根開けが始まっている

先週は最初かんじきを履かないで歩いてみた
しかし 埋まったりして疲れが倍増でした
かた雪の時節とは言え 「埋まると足を痛めるよ」などなど
指導者の注意をよく聞くことが大事なことを実感した反省から
今回は 歩き始めからかんじきのお世話になることにした
AM 8:45

雪の下は 雪融けが始まっているよう
AM 8:52

寒さの厳しさ 伝わってきます
AM 8:56

見えた 山頂
喜びも束の間 596ピークでした
テッペンはピークを下り 再度登ったところにあるそう
AM 9:00

AM 9:15

林道とお別れ


AM 9:28

林間の中を 迷わず案内してくれる指導者の知識と経験に
感心しながら登ると 私の場合 疲れが半減です

休憩時間は情報交換の場
AM 9:38


大先輩のご教示によれば ネズミの足跡だそう
私は生まれて初めて目にした光景です


見た目より傾斜はきつい
ジクザクしながら高度を上げます
AM 9:45

小枝がうるさくて困る
リュックなどにひっかかると 脱出は簡単でないこともあります
AM 10:05

林間から見えていた山並み ようやく展望が開けました
向って左が恵山 右は海向山
明日2回目へ続く
AM 10:10





 パチリ 貴州省
パチリ 貴州省
 中国一の低所得省
中国一の低所得省




 箱根・彫刻の森⑤
箱根・彫刻の森⑤
箱根登山鉄道・彫刻の森駅から歩いて数分の美術館
森林浴を楽しみながら アートを観賞できる
握手をしよう


 行雲流水
行雲流水 難しい結婚
難しい結婚
接木をしたことがあるが 樹種によっては難しいね
相性がよくないと門前払いをされる
森を歩くと 枝と枝とが結婚しそうな光景を目にします
枝と枝が擦り合い 接木とは違って簡単に合体できそうに思えるが 現実は簡単ではなさそう
写真の木の合体を見ると イヤイヤだった苦労の跡が伝わってくる
人間はうまくいかないと 何歳であっても離婚や再婚できる自由があります
しかし樹木にはそういう選択肢はないので お気の毒



基本給アップ 家族元気の源です
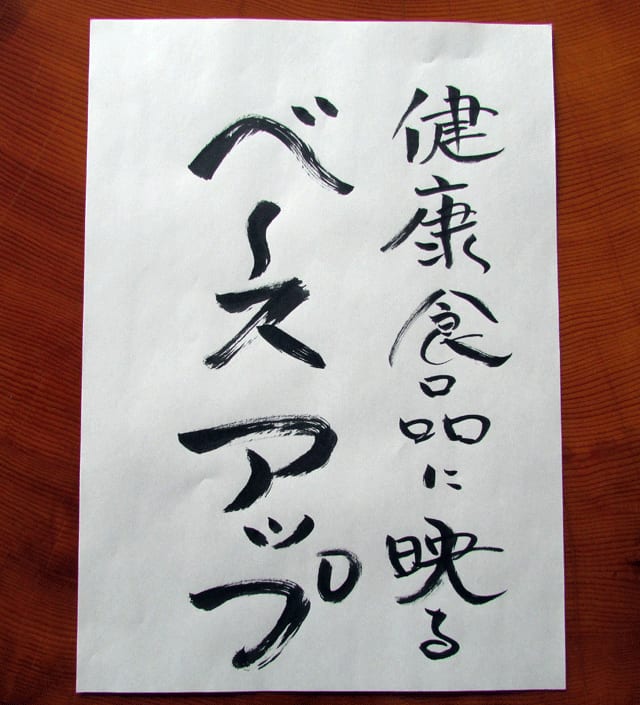
 写真家 稲場祐一 作品館
写真家 稲場祐一 作品館
函館山で咲く花々標高334m 温暖な気候の函館山は約650種の植物が謳歌