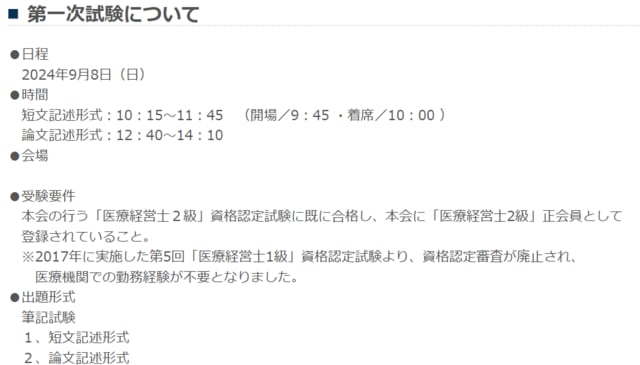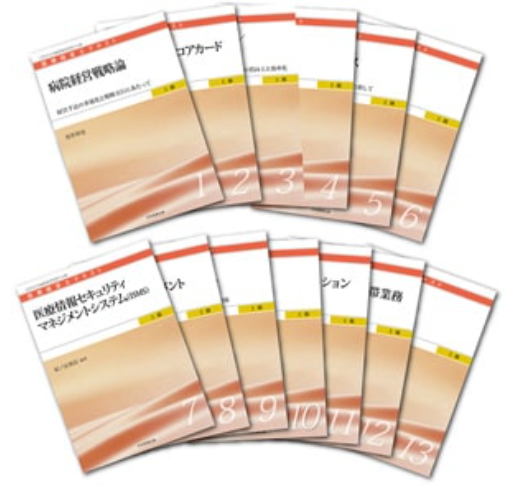みなさま、こんにちは。
昨日は、下記の⑻と⑼についてお話ししました。
⑻ 短文問題を書いて解答する 時間・字数の感覚を得る
⑼ 論文問題を書いて解答する 時間・字数の感覚を得る (ChatGPTを利用は6月までに)
⑽ 論文問題について、自分問題を作成する 箇条書きで解答 ポイントを絞る
⑾ 総まとめ 苦手分野の 繰返し
短文問題も論文問題も、もちろん「長先生の予想問題集」のことです。
論文問題の詳しい書き方については、この問題集の序文に説明してくださっているので、必ず参考にしましょう。
ただ、論文の骨組みは大事だと思いますが、下書きの段階で「これについて5行書く…」とまで、考える余裕が私にはないので、
・出題に対しての結論そのもの
・出題に関する要旨やキーワード
など、予備用紙(実際の試験でも用意されています)に、思いつくこと全てを、箇条書きかワードで書き出します。
次に、関連性のあるもの同士を結び付けて、骨組み(書く順番)を作っていく感じです。
例えば「2035年に向けて『健康長寿の実現』のための具体策を論じよ。400字」という問題。
問題文が長ければ長いほど、それだけ与えられる情報も多いのですが、
たったこの1行から400字の論文を書くとは、「えっ?」となります。
医療知識もあり社会問題にも明るい方なら、瞬く間にさまざまなキーワードが浮かんでくるのでしょうが…。



論文問題で使える言葉をメモ書きしておきました。時々見て、言葉の説明や関連がわかるよう、また思い出しやすくするため。
ヒントは、「2035年」と「健康長寿」のみです。
2035年問題とは? 高齢者問題とは? 健康で長生きするためには? と、必死に思い出します。
そこから、浮かんでくる言葉、箇条書きの要旨や自分の意見を、どんどん書いていきます。
高齢者急増、少子高齢化、労働人口減少、介護人材不足、医療費増大、年金制度のあやうさ、定年延長、ボランティア・就労、
社会・コミュニティとつながること大事、健康へのリテラシー高める、生活習慣病、食事・運動・禁煙、高齢者の予防医療、
口腔・栄養・リハビリ・ワクチン接種 … などなど。
それらを、自分なりに分類し、書くべき順番=組み立てを考えます。
まずは、書き出しの文章。
私は、大抵、問題文を利用した一文で始めることにしています。
この問題でしたら、「2035年に向けて、健康長寿の実現のために、( )つの具体策が考えられる。」です。
( )には、書き綴った後、いくつの具体策を書けたかによって、その数を記入します。
ちなみに、「チャットGPT」に「2035年に向けて健康長寿の実現のための具体策を論じよ。400字」と尋ねると、
最初の答えは以下の通りでした!
ご参考まで。
2035年に向けて健康寿命を実現するためには、以下の具体策が考えられます。
まず、予防医療の強化が重要です。定期的な健康診断や早期の疾病発見、生活習慣病予防のための教育が必要です。健康管理アプリやウェアラブルデバイスを活用し、個々の健康状態をリアルタイムで把握できる仕組みを導入することも効果的です。
次に、生活習慣の改善が求められます。バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、基本的な健康習慣の促進が必要です。地域社会や職場で健康促進活動を展開し、健康的なライフスタイルを支援することが重要です。
また、高齢者の社会参加を促進することも大切です。ボランティア活動や地域コミュニティへの参加を通じて、心身の健康を維持する機会を提供することが、精神的な充足感や社会的なつながりを強化します。
さらに、医療と福祉の連携を強化し、包括的なケアを提供する体制の整備が求められます。高齢者向けの医療・福祉サービスを統合し、より効率的で質の高い支援を提供することが、健康寿命の延伸に寄与します。
これらの施策を総合的に実施することで、2035年に向けて健康寿命の延伸を実現することが可能です。
⑼と⑽については、また明日にでも。















 「
「