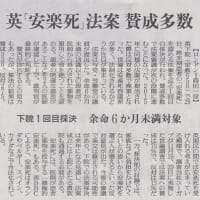一昨日の読売新聞の切り抜きです。
「小1の壁」とは,小学生になった子供の預け先が見つからず,親の就労が困難になる,という問題です。
かつては保育園の待機児童が問題になりましたが,今度は学童保育がカバーしていない朝の時間の子供の居場所が問題になっているのです。
学童は放課後に児童を受け入れる機関ですから,朝は対応していません。
よって,親が出勤した後に,子供は登校時間まで自宅で過ごし,登校時間になったら玄関の鍵を閉めて学校へ行くのです。
親はこうした事態を避けるために出勤時間の変更を迫られる。
その結果,自分のキャリアに影響を及ぼすことになると記載されています。
このため,一部の自治体では朝7時から子供が登校できる事業を始めたそうです。
さらに民間の学童では,夜遅くまで子供を預かるところもあります。
親の都合で早朝に家を出て夜遅くまで家に帰ることができない子供のことを考えないのだろうか。
こども家庭庁は,これから地域の取り組みや親の要望を把握すると言ってるけど,まずは子供の思いを聞くべきでしょう。
ボクだったら絶対にそんな生活は嫌だと答えるでしょう。
ボクには夏休み,冬休み,春休みも早朝から学童に行かせるなんて考えられません。
幸いなことに,ボクの両親は子供第一に考えてくれていたし,今も我が一族は子供が小学生高学年になるまでは手元で育てています。
岸田さんは「こども真ん中」という政策をたびたび口にするけど,こども家庭庁は親の都合を子供に押し付ける政策を勧めているんです。
親が子供よりも自分のキャリアを優先する気持ちがボクには理解できません。
子供が小学校高学年になるまでは手元で育てる。
それは子供にとっても親にとってもかけがえのない時間なんです。