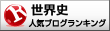山梨県北杜市、韮崎市、南牧村、伊那市は縄文時代の太陽観測天文台であった

金生遺跡・大配石は太陽暦観測施設で

立春、立秋の日の出を観測している
冬至の日の出は大配石で観測し、配石の北限としている

この立地で冬至の日の入りを観測できる

発掘時の大配石の詳細図 ↑立秋の男根型石棒 ↑立春の石棒石組
それぞれの石棒を囲む石組が見える 東の先端部は長いので省略した
このような状況から
縄文時代には太陽暦が完成していて、その記録は供献土器として残されたと考えている、
縄文土器の他の文明と隔絶した画期的特徴とされる、波状突起口縁の土器が存在していて、
この記録には
太陽暦の開発経緯と太陰暦の開発経過が、土器に造形して記録として残されていた。
縄文時代前期には濃厚可能となっていた
縄文時代には太陽暦がこれまで無いとされていたが、それは
ストーンサークルや木柱列などからは、太陽暦や太陰暦の形跡が見えないからであるが、
その時代には既に暦は完成していて、社会に実装されていたからであると考えるなら不思議では無い。
写真はお借りしています
引用ーーーーーーーーーーーーーー
山内丸山遺跡の天文台説ですが、以前、NHKの特集番組でも見たことがありますが、一般的な見張り台説、祈祷所説、
灯台説などがあります。船舶による地域交流に起因する灯台説は有力とのことでした。
天文台説も可能性としてはあると思いますが、純粋な太陽暦の存在に結びつける論は疑問があります。
ちなみに、「1年が365日と1/4」は450日ではなく、365.2422日を意味してます。0.2422超過分を補正するのが、現代のうるう年補正です。
太陽暦が確実に確認できるのはエジプトでナイル川の氾濫を予測するために生まれたもので、紀元前3000年位と言われています。三内丸山遺跡は6000~4000年前の遺跡ですから、太陽暦を運用していたとすれば、エジプトに先行する可能性出も出てきます。これは状況証拠でしかないですが、ピラミッドの方位設定技術など、他の文化度から類推して、日本の縄文時代における純粋な太陽暦の保有には疑問を感じます。それは、日本が弥生時代を経て古墳時代、飛鳥時代に入っても太陽暦を持たなかったことからも推測できると思いますね。
ーーーーーーーーーーーーーー
ここでは國學院大學の「縄文学研究室」の見解を取り上げてみる。同研究室が取り上げた具体的な夏至、冬至、春分、秋分に関わる遺跡は以下の通りである。
【石倉貝塚】
北海道函館市の後期の環状列石。
中央と南東の立石を結ぶ線の延長線上から冬至に日の出。
また、中央と南西の配石群を結ぶ線の延長線上に冬至の日没。
水野正好 1996(石倉貝塚の報道のコメント):
「縄文人が冬至などを意識していたと立証するには材料が乏しい。この遺跡が偶然一致しただけで、全国的なものではない。」とある。
【三内丸山遺跡】
青森県青森市の前期・中期の集落跡。国史跡。
大型木柱遺構の方向と夏至の日の出・冬至の日の入線がほぼ一致。
【小牧野遺跡】
青森県青森市の後期の環状列石。国史跡。
現在馬頭観音となっている配石と中央とを結ぶ線が夏至の日の出線と一致。
【大湯環状列石】
秋田県鹿角市の後期の環状列石。国特別史跡。
万座と野中堂の日時計状特殊組石を結ぶ線が夏至の日没線。
【伊勢堂岱遺跡】
秋田県鷹巣町の後期の環状列石。
環状列石C:外環のまとまりが30度づつ区切られており、その区切りが、中心-直列石のラインを中心に磁北ライン・夏至の日の出ラインなどと重なる。
【樺山遺跡】
岩手県北上市の後期の配石墓群。国史跡
春分・秋分の日、前塚見山に日が沈む。
【天神原遺跡】
群馬県安中市の晩期の環状列石。
中央から3本の立石を結ぶ線の延長線に妙義山(三峰)を望み、春分・秋分には妙義山に日が沈む。
また、冬至には大桁山に日が沈む。
【砂押遺跡】
群馬県安中市の中期の環状集落。
環状集落の中央広場からみると、冬至に大桁山に日が沈む。
【野村遺跡】
群馬県安中市の中期の環状列石。
この場所から見ると冬至に妙義山に日が沈む。
【寺野東遺跡】
栃木県小山市の後期の遺跡。国史跡。
環状盛土の中の円形盛土と中央の石敷台状遺構とを結ぶ線上に冬至の日の入を望む。
【田端遺跡】
東京都町田市の後期~晩期の環状積石遺構。都史跡。
冬至には、丹沢の主峰蛭が岳に日が沈む。
【水口遺跡】
山梨県都留市の中期の環状列石。
春分の日没が地蔵岳に落ちる。
【牛石遺跡】
山梨県都留市の中期の環状列石。
春分の日没が三つ峠山に落ちる。
【大柴遺跡】
山梨県須玉町の中期~後期の環状列石。
夏至には金峰山から日が昇る。
【アチヤ平遺跡】
新潟県朝日村の環状列石を伴う拠点集落。
夏至の日、朝日岳から日が昇る。
【極楽寺遺跡】
富山県上市町の早期~前期の攻玉遺跡。
冬至には大日山(立山連峰の1峰)から日が昇る。
【不動堂遺跡】
富山県朝日町の中期の集落。国史跡。
冬至には朝日岳と前朝日の間(鞍部)から日が昇る。
【チカモリ遺跡】
石川県金沢市の後期の遺跡。国史跡。
ウッドサークルの入口?が、冬至の日の出の方向を向いている。
以上、環状列石や環状木柱列等と二至二分の関連を説いているが、何やら「こじつけ」の感もある。一般に、環状列石は日本でもはたまた外国でも「大規模な共同墓地」と考えられており、環状木柱列は「祭祀場」と考えられている。暦学者はそうはさせじと「大型のストーン・サークルには墓の痕跡がないものも多く、十分に説得力のある学説とは言えないようです。
近年ではむしろ、小林達雄氏(國學院大學文学部名誉教授)に代表される考古学者たちのように、環状列石を日の出・日の入りを観測する装置とみなす説が有力になっています。」と曰っている。
REPORT THIS AD
★まとめ
まず、環状列石だが、一説に「ストーンサークルの密集域が円筒土器文化圏(東北北部)と重なっていること、円筒土器は遼河文明と関連していること、遼河文明と関連する三内丸山遺跡からもストーンサークルが発見されていることから、日本にストーンサークルをもたらしたのはY染色体ハプログループNに属すウラル系遼河文明人と考えられる。しかし、ウラル系遼河文明人にはストーンサークルを造る文化はなく、東アジアにストーンサークルを伝播させた集団はY染色体ハプログループR1bに属す集団と考えられる。」と言う。
日本のストーンサークルの起源も元を正せばヨーロッパあるいは中央アジア北東部からシベリア南部(アファナシェヴォ文化)と言うことになるようだ。
はっきりしないことを蒸し返しても建設的なものにはならないので、環状列石や環状木柱列の日本での建造目的は食糧確保のための建造物と考える。「日本での」と断ったのはこれらの建造物が日本で自然発生的に生じたもので外国から入って来たものかは疑問である。
北東北の環状列石が古いと言っても講学上の最古のものは縄文時代前期の阿久遺跡(あきゅういせき。長野県諏訪郡原村)にある環状集石群と考えられている。
この種の遺跡の特徴として
1.なにがしかの二至二分の日の出や日の入りと関わっていること。
2.墳墓を伴うことが多いこと。
3.日本では本体サークルの補完、補正などに利用されたと思われる、日時計状組石や四本柱の環状木柱列(本体は十本。真脇遺跡)などがある。
1.二至二分(夏至、冬至、春分、秋分)の日の出や日の入りが見える場所については、やはり季節の春夏秋冬を知るために、環状列石や環状木柱列が造られたのであろう。これは農業、漁業、林業の基本であり、縄文農業がどれほどであったかは解らないがやはり縄文時代にも農業があったと思われる。こういう意味では環状列石や環状木柱列は春、夏、秋、冬の四季しか解らないものではあったが、やはりカレンダー的要素の強いものではなかったか。
古代人が太陽の位置に興味を抱いたのは太陽の位置により気温が異なり、人間はもとより多くの生物がその行動を左右されるからであろう。太陽の位置を観測すると言うことはとりもなおさず現今のカレンダー(暦)を意識したものではないか。これは日本だけでなく世界的なものである。(ナブタ・プラヤの遺跡<エジプト>は、北回帰線近くに位置し、夏至の前後3週間ほどの間、正午の太陽は天頂に昇り、直立物は影を射さなくなる。研究者たちは、ナブタ・プラヤのストーン・サークルは、夏至前後に天頂を通る太陽の運行に対応した物だっただろう、と推測している。特別な石材は、夏至前後の季節を確認するための観測道具だった、とみなされ「カレンダー・サークル」の名で呼ばれている。)上述の石倉貝塚の水野正好(奈良大学名誉教授。物故者)と言う人が述べていることにも一理はあるが「この遺跡が偶然一致しただけ」と言うのも他の一致した遺跡はどうなるのだ、と言うことなのだが。
2.墳墓を伴うこともこれらの墳墓が当初より計画的にストーン・サークルの内や外に配置されていたものかは不明である。意外と後世になって墓地が不足し環状列石の内や外に墳墓を造築したのではないか。副葬品が豪華なものもあるので、最初から墓地という説も根強い。
3.補完、補正装置としての日時計状組石や四本柱の環状木柱列は、本体の環状列石や環状木柱列を毎年のカレンダーとして間に合わせるべく、諸々の誤差(例、地球の公転と一日24時間としたときの誤差)を正すべく使用されたと思われる。
そこで環状列石と環状木柱列であるが、環状列石が先に出現し、環状木柱列が縄文時代後半に出現したのではないかと考える。
環状木柱列の主な遺跡としては、
チカモリ遺跡 石川県 柱8~10本、柱列環直径6~8mが8基
真脇遺跡 石川県 柱10本、環直径7.4m、6度立替 トーテムポールのような木柱
井口遺跡 富山県 柱10本、柱列環直径8m
桜町遺跡 富山県 柱10本、柱列環直径6m
米泉遺跡 石川県 柱8本、柱列環直径5.5m、中央に鮭の骨を含む穴
若緑ヒラ野遺跡 石川県 柱10本、柱列環直径約7m
古沢A遺跡 富山県 柱4本を方形配置、2棟並ぶ
正楽寺遺跡 滋賀県 柱6本、環直径6m
寺地遺跡 新潟県 柱4本方形配置
矢瀬遺跡 群馬県 半截材(直径50センチメートル前後の巨木を半切)の方形木柱列は割面が向き合う6本の立柱 四角形に配列されて立てられた部分(方形木柱列)
西鯉遺跡 福井県 環状木柱列遺構 縄文後期前半。クリの半裁材を使用した径約10m の大型円形建物 西日本と東日本の縄文晩期の境界になる
以上より、柱数は10本が最も多く、ほかに4、6、8本がある。形状は環状がほとんどで柱が4本になると方形配置と解されている。柱の用途は「不明」とするものがほとんどだが、方形、円形にせよ建物の構造材と解する向きも多い。地域的には北陸の豪雪地帯が多い。年代的には縄文時代後半に集中している。
柱の本数が偶数なのは何らかのバランス(例、左右対称)をとろうとしたからではないか。柱の用途も建物が方形ならともかく、円形では中央部に支えとなる柱(大黒柱か)がないようなので、建物の構造材というのは考えられない。当時の積雪量がどのくらいかは解らないが、豪雪の荷重に耐えられない。そこで考えられるのは、二至二分に関心が強かったと思われる縄文人にとってはそれを正確に知る装置が必要だったと思われる。その装置はどのようなものだったかとチカモリ遺跡を例にとりながら私見を説明すると、
同遺跡は10本柱の環状木柱列と「4本の柱」の表示のある木柱列がある。私見では10本柱の方は年間カレンダー(暦)で、4本柱の方はその補正装置と考える。当時の日本は三内丸山遺跡の「6」から真脇遺跡の「10」になるまで相当年数がかかったようで、とても365などという数字には到達していなかったと思われる。また、他の民族では年と日の概念の間に月の満ち欠けによる「月」を導入したが、我が国ではそういうこともなく、年を主体としていたようだ。
年には二至二分があり、それは4本柱の方形木柱列ではかり、年を十等分し「単位1」を36日(縄文人の好きな6の二乗かも知れない)とし、4年に一度21日(毎年5日が少ないのと4年に一度の正規の閏日を足す。)の閏月を10本の環状木柱列の玄関と称するところに挿入したのではないか。我がご先祖さまは背伸びしたことが嫌いでできる範囲で暦を作成したものと思われる。
水野正好奈良大学名誉教授のように「縄文人にはそんな能力はない」と言われればそれまでだが、私見では日本人の特性は堅実に物事を処理するところにあったと思われ、日本プロパーな暦を作出したのではないか。