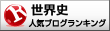天文学は中根元圭の「暦算全書」から 1728年
中根元圭が「暦算全書」に訓点をほどこしたのが最初ですから、 これ以前に日本には天文学はなかったのです。 だから中根元圭が日本で最初の天文学者なのです。という。
暦の歴史は 554 百済の暦博士固徳王保孫、暦法をもたらす。からとなるようですが。
立春を年の初めとする暦はこの歴史から見えてこないのは何故なのか

縄文、弥生、古墳、現代へと続いた暦の歴史は歴史時代より前から続いてきた伝統なのか
歴史時代に入るとともに、この歴史は消えてしまったのだろうか。
引用ーーーーーー
古代の日本には天文学があったか?
この答えは単純で「日本には天文学と称するものは単になかった」なのです。
これは ティコ・ブラーエの観測装置を読んだ結果から明らかとなりました。
観測装置には色々ありますが、 方位角四分儀であれば天体の高度と方位角がわかり、 ここから天体の赤緯と赤経を求めるには三角法が必要です。 また赤緯と赤経から黄緯と黄経を求めるには再び三角法が必要です。 また、これらの逆の計算をするにも三角法が必要となります。
正確な一年を理解するには太陽の黄道上における位置 (黄経) を知ることが必要となり、 この位置の決定には三角法が必要なのです。 従って、暦を作るには三角法が必要なのです。 古代中国にはインド人やイスラム圏の人が天文学者として採用されており、 彼らの著した本もあり、その中には三角法が紹介されていたのです。
日本では三角法が知られたのは、 中根元圭が「暦算全書」に訓点をほどこしたのが最初ですから、 これ以前に日本には天文学はなかったのです。 だから中根元圭が日本で最初の天文学者なのです。 三角法がないと天文学が成立しないから、 プトレマイオスもアルマゲストの第一章で三角法を導入しているのです。
最初は日の出、日の入りの時刻はアストロラーベや渾天儀がないと無理だと考えていたのですが、 太陽の黄道上の位置が分かれば、赤緯と赤経が決定でき、 ここから、与えられた時刻における太陽の高度と方位角が決定できます。 これをするには、面倒な三角法の計算が必要ですが、 アナログ的な方法を採用しなくても何とか計算が可能です。(逆三角関数も必要ですから、正確な三角法の表が是非とも必要です。) 無論、古代には太陽の見かけ上の動き (楕円であること) を 正確に理解できていたわけではありませんが、 三角法がなければ何も計算ができなくなり、また観測結果を理解することもどだい無理となります。
日食や月食の予測に関しても、当然三角法が必要です。 例えば、食が起きるのは月が黄道面を横切る時ですから、月の動きを黄緯と黄経で記述できないといけないのです。 また日食や月食が起きる場合の方位と高度を予測するには更に別に三角法が必要となる。 だから三角法なしの天文学などあるはずがないのです。
日本には古来天文学者がいたとされているのですが、これは全部まったくの嘘です。 ただの占い師というべきです。
ーーーーーー
第一章 暦の歴史
年表
時代 西暦 年号 事項
古墳 553 欽明14 百済に暦博士・暦本を求める。
554 欽明15 百済の暦博士固徳王保孫、暦法をもたらす。
飛鳥 604 推古12 初めて元嘉暦を用いる。
689 持統3 この年の暦が現存最古の元嘉暦
(奈良県明日香村石神遺跡出土の木簡)。
692 持統6 元嘉暦と儀鳳暦を併用。
697 文武元 元嘉暦を廃し儀鳳暦を用いる。
奈良 729 天平元 この年の暦が現存最古の具注暦
(静岡県可美村城山遺跡出土の木簡)。
746 天平18 この年の暦が紙に書かれた現存最古(正倉院蔵の具注暦断簡)。
763 天平宝字7 儀鳳暦を廃し大衍暦を用いる(施行は翌年)。
780 宝亀11 この年の、漆紙に書かれた具注暦断簡が多賀城跡から出土。
784 延暦3 1月1日、初めて朔旦冬至の賀を行なう。