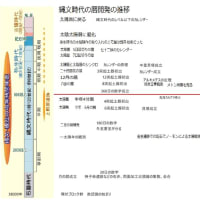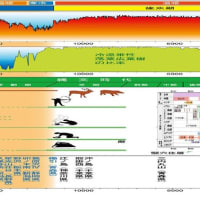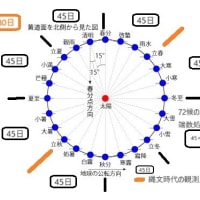写真はお借りしました
金生遺跡から出た土偶 異形の土偶とされている。
土偶は見ていると殆どが異形である。
確かに人、それらしいものもある、それはうずくまる土偶で祈るような、出産するようなと見えるもの。
人体としては女性の首から下の特徴を象ったのものが殆ど、しかしそれにしては正確に人を表現しようとしているとはとても思えない。
人を象るのに顔が無い、そんなことは無いだろう。
最後には三角のかめんを被ったような土偶まで現れた。そして仮面まで出ている。

写真はお借りしました
縄文人の想念が示されていて、そのものの形を正確に具象表現出来ているとは思えない。表現できないものを表そうとしている様で、対象物の精神性が示されているもののように思う。
芸術作品では無い。
手足のような形はあるものの、それは祈りとか思念を表現するために補足されているものと思う。
何かの対象物を表現しているのだろうけれど、その形にとして見えているもので無く、その精霊を表現しようとしているように見える。
仏像だって人を表そうとしているのでは無く、仏様の精神を現わすもの、しかし人のような形を取っている。
中空土偶は栗を表すという人が居た。そう思ってみていると、そのように思えなくも無い。
そう言われて金生遺跡の中空土偶を見ていると、手足も無いような形で、毬から出てきた栗を示すものかと見えてきた、手も足もそのように見える様には作られていない。
栗の実りの悪化に対する不安な思いを表現しようとしていたのだろうか、不安が表現されているように見えてきて、いたたまれないような気分にさせられてしまう。
表現しようとしていた対象物が何なのか、正確には分らないが、それの実りを祈っていたものだろうと思う。
山クルミの精の土偶というのはよく分る。

サトイモを表す土偶は表現が凄すぎる。

栗の精はこんなに成るのだろうか

写真はお借りしました
引用ーーーーーー
土偶を「人体」の表現と捉えてしまうと、その異形ともいえる造形から稚拙さを感じ、「やはり原始時代には技術が未発達だったのだろう」と思うかもしれない。
だが、著者の説に従い「植物を人体化したもの」として見ると、「対象物の特徴をうまく捉えた上で人体にも見えるようにする」といった高度な芸術表現ともみなせる。「人はなぜ歌い、踊るのか」を論じた『野生の声音』(夜間飛行)には、旧石器時代の人々は、現代よりも自由に発声し、高度な歌唱技術を持っていたとの指摘がある。そして、その歌唱技術は、言語や西洋音楽理論が発達するにつれ失われていったのだという。
古代人類の能力は劣っているわけでも、未熟でもないのだろう。斬新な発想や表現を身につけるには、あらゆる先入観や知識をいちど取り払い、古代人類のシンプルな感性や思考に立ち返って見るのもいいかもしれない。
ーーーーーー
この本が発売された2021年5月にユネスコの諮問機関が北海道・北東北の縄文遺跡群を世界遺産へ登録することを勧告しました。いよいよ縄文時代が日本文化として世界に向けて発信されようとしています。ところが北海道・北東北の縄文遺跡群をはじめ、日本列島の各地域に存在する遺跡群では、どのように食料が獲得されていたのか、はっきり分かっていません。たとえば、縄文時代に農耕が始まっていたのか、いつまで狩猟採集にだけ頼っていたのかさえはっきり分かっていません。つまり、生活の実態がよくわかっていないのです。研究者の中には弥生時代からが日本文化であって、それ以前は文化ではないとさえ公言する人もいます。
++++そうなのか
それでは私たちはどうでしょうか。祖先がどういう人間だったのかということに真剣に向き合う機会がありません。研究者も議論を戦わせる土俵がありません。どうせわかるわけがないとか、証明のしようがないとか、簡単に言ってみればわからないものはわからないという状況が続いています。
この状況が続くかぎり、私たちはいつまでたっても祖先の本当の姿を知ることはできません。そんな状況をよそに、縄文は世界に向かって文化遺産としての価値を問われているのです。
++++そうなのか
それが「土偶を読む」が生まれた土壌であり理由です。私たちは、私たちにとって最もわかりやすい情報を求めています。そして私たちの祖先のイメージが欠落し続けている限り、別の情報が私たちの望む形で現れ、私たちが信じたいことを投影し続けるでしょう。
竹倉氏は「土偶を読む」で自ら立てた仮説的推論を解明したと述べています。
仮説的推論とは、その推論によって、どれだけ目の前に起きていることを説明できるかということが重要であることは言うまでもありません。竹倉氏もそのことに言及したうえで、関東と東北の膨大な量の土偶から幾つか事例を選択し、仮説による説明を加え、その結果解明したと述べています。
しかし、仮説的推論とは、目の前に起きている出来事の中からどれだけ説明可能な事例があるかではなく、説明のつかない事例までもが、その推論によって説明可能になるのかが問われるのです。
例えば、引力が存在しているという仮説的推論は、落下しているものにも静止しているものにも同じように引力が働いていることを説明します。引力は落下しているものだけに適用されるのではありません。静止しているものにも適用されます。
つまり仮説的推論は、なぜ同じ現象が起きていないかということを「説明できなければならない」のです。そう見えるものだけに仮説が適用され、そう見えないものに同じ仮説が適用できないのであれば仮説的推論ではありません。
ですから竹倉氏は「土偶を読む」によって土偶の仮説を提起したのみにとどまり、食材に見えない土偶を含めて、いかに多くの事例を推論を適用して説明できるかということを示す必要があるのです。
もし、それができないのであれば「土偶を読む」は仮説的推論でなく印象論です。印象論は論証が不要なので、何かを解明したということにはなりません。
この本は提起としては面白く、文章力も表現力もあり読ませます。それだけに、竹倉氏の今後の土偶の論証に注目したいと思います。
ーーーーーー
縄文時代にはすでに広範な食用植物の資源利用が存在していた。しかも地域によっては、トチノミなどの堅果類を“主食級”に利用していた社会集団があったこともすでに判明している。ということは、そうした植物利用にともなう儀礼が行われていたことは間違いないのであるが、なぜか縄文遺跡からは植物霊祭祀が継続的に行われた痕跡がまったくといっていいほど発見されていないのである。一方、それとは対照的に、動物霊の祭祀を行ったと思われる痕跡は多数見つかっている。
ではなぜ、最重要と思われる植物霊祭祀の痕跡は見つかっていないのだろうか。
「植物霊祭祀の痕跡が見つかっていない」のではなく、本当はすでに見つかっているのに、われわれがそれに気づいていないだけだとしたらどうだろうか。
実はこれこそが私の見解なのだ。
つまり、「縄文遺跡からはすでに大量の植物霊祭祀の痕跡が発見されており、それは土偶に他ならない」というのが私のシナリオである。このように考えれば、そしてこのように考えることによってのみ、縄文時代の遺跡から植物霊祭祀の痕跡が発見されないという矛盾が解消される。
ーーーーーー
土偶の正体、ひらめきを得た森での「事件」
「土偶は女性モチーフ」の認識が覆った!驚きの新説(後編)
2021.4.25(日)
竹倉 史人
椎塚土偶(左、所蔵:大阪歴史博物館)と星形土偶(右、所蔵:辰馬考古資料館)
ギャラリーページへ
縄文時代に作られた土偶は、女性や妊婦をかたどったものだ、というのが多くの人の認識だろう。「そうではない」という驚きの新説を提唱したのが、人類学者の竹倉史人氏だ。前編では、「土偶は植物の精霊をかたどったものである」という結論に至った過程を紹介した。後編ではいよいよ具体的な土偶の解読に取りかかる。(JBpress)
前編
日本考古学史上最大の謎「土偶の正体」がついに解明
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/65038
※土偶(どぐう)とは:縄文時代に作られた素焼きの人形。1万年以上前から制作が始まり、2000年前に姿を消した。現在までに2万点近い土偶が発見されている。なお、埴輪(はにわ)は、古墳にならべるための土製の焼き物。4世紀から7世紀ごろに作られたもので、土偶とは時代が異なる。
(※)本稿は2021年4月に発行された『土偶を読む 130年間解かれなかった縄文神話の謎』(竹倉史人著、晶文社)より一部抜粋・再編集したものです。
私が直感していたことは、「土偶と植物とは関係がありそうだ」という抽象的なレベルの話ではない。もっと直接的で、具体的な仮説が私の頭の中を駆け巡っていた。それは、「土偶は当時の縄文人が食べていた植物をかたどったフィギュアである」というものだ。
土偶の姿が「いびつ」なものに見えるのは、勝手に私たちが土偶=人体像であると思い込んでいるからではないのか。いびつなのは土偶のかたちではなく、われわれの認知の方なのではないか。ヴィジョンを獲得した日以来、私の目には、遮光器土偶はある根茎植物をかたどった精霊像にしか見えなくなっていた。そして私は、土偶には様式ごとに異なるモチーフが存在し、そのモチーフはすべて植物なのではないかと考えるようになっていた。
ハート形土偶の造形的特徴とは
最初に私にその姿を開示したのは、これまで「ハート形土偶」と呼ばれてきた土偶である(図1)。
図1 群馬県吾妻郡東吾妻町郷原で出土したハート形土偶(所蔵:東京国立博物館)
ギャラリーページへ
土偶は「食用植物をかたどっている」というのが私の仮説である。したがって、私の仮説によれば、このハート形の頭をした土偶も何らかの植物をかたどっているということになる。そこで私は、とりあえず「ハート形土偶」の造形について細かく分析してみることにした。
ーーーーーー
土偶には二つの大きな謎がある。一つは「土偶は何をかたどっているのか」というモチーフの問題。ざっとみただけでも、妊娠女性説、地母神説、目に見えない精霊説、はたまた宇宙人説に至るまで、考古学の内外からじつに多様な意見が開陳されていることがわかった。そしてもう一つが「土偶はどのように使用されたのか」という用途の問題。豊穣のお祈り、安産祈願のお守り、病気治療など、こちらも様々な意見が主張されてきたようだ。
土偶のモチーフは「食用植物」だと宣言したい
しかし、土偶のモチーフや用途をめぐっては諸説あるものの、いずれも客観的な根拠が乏しく、研究者のあいだでも統一的な見解が形成されていないのである。少し大げさな言い方をすれば、自分たちのルーツにあたる先祖の精神性を、そしてその神話を余すことなく体現しているであろう土偶について無知であるということは、われわれ自身についても無知であるということを意味している。それでいいのか。
そこで私は宣言したい。――ついに土偶の正体を解明しました、と。
結論から言おう。土偶は縄文人の姿をかたどっているのでも、妊娠女性でも地母神でもない。〈植物〉の姿をかたどっているのである。それもただの植物ではない。縄文人の生命を育んでいた主要な食用植物たちが土偶のモチーフに選ばれている。
19世紀末にイギリスの人類学者ジェームズ・フレイザーが著した『金枝篇』で私が特に注目したのは「栽培植物」にまつわる神話や儀礼である。植物の栽培には必ずその植物の精霊を祭祀する呪術的な儀礼が伴うことを、フレイザーは古今東西の事例をあげて指摘している。
なぜか縄文遺跡から「植物霊祭祀」が見つからない
近年の考古研究の進展によって、北海道を除く東日本では、すでに縄文中期(およそ5500年前)あたりから、縄文人が従来の想定よりもはるかに植物食に依存していた実態が浮かび上がってきた。しかもかれらは単なる採集だけでなく、ヒエなどの野生種の栽培化、里山でのクリ林やトチノキ林などの管理、マメ類の栽培などを行っていたことも判明しつつある。
ということは、そうした植物利用にともなう儀礼が行われていたことは間違いないのであるが、なぜか縄文遺跡からは植物霊祭祀が継続的に行われた痕跡がまったくといっていいほど発見されていないのである。
だが、「植物霊祭祀の痕跡が見つかっていない」のではなく、本当はすでに見つかっているのに、われわれがそれに気づいていないだけだとしたらどうだろうか。実はこれこそが私の見解なのだ。つまり、「縄文遺跡からはすでに大量の植物霊祭祀の痕跡が発見されており、それは土偶に他ならない」というのが私のシナリオである。
縄文文化を代表する「遮光器土偶」の謎
土偶と聞けば誰もが思い出す土偶の代名詞的な存在であり、縄文文化を象徴するアイコン、遮光器土偶の謎に迫っていこう。
遮光器土偶は、およそ3200年前~2700年前にかけて、約500年間にわたって東北地方を中心に製作された土偶である。国立歴史民俗博物館の「土偶データベース」で検索すると、「遮光器土偶」は550点がヒットする。
私の仮説に従えば、縄文晩期前葉の東北地方に遮光器土偶が出現したということは、その時期に当地で何らかの食用植物の組織的な栽培が開始されたことを意味している。そして晩期後葉において遮光器土偶が消失したということは、やはりその時期に至って、何らかの理由によってその食用植物の栽培が放棄されたことを意味している。
++++そうなのか
私は造形的に優れた遮光器土偶を分析対象としてピックアップした。宮城県大崎市の恵比須田から発見された遮光器土偶(恵比須田土偶)である。
恵比須田土偶の(紡錘形の)腕の側部には突起が造形されている。一見するとただの粘土粒のようにも見えるが、よく見ると側部の突起は明らかに何らかの意匠が施されていることがわかる。突起は上下に開き、中からは丸みを帯びたフォルムがのぞいている。
放置していた親イモの形は「遮光器土偶の頭部」にそっくり
私は、これはある植物の「芽」をかたどったものであると考えた。では、紡錘形の「腕」の側面から出芽する植物とは何であろうか――結論から言うとそれは「サトイモ」である。つまり、遮光器土偶はサトイモの精霊像であり、その紡錘形に膨らんだ四肢はサトイモをかたどっていたというのが私の結論となる。
根茎類であるサトイモは地下で成長し、植え付けられた種イモから「親イモ」、「子イモ」、「孫イモ」と増殖していくが、遮光器土偶の場合はそのまま頭部に「親イモ」が、手足に「子イモ」が配置されたということになる。
サトイモを自分で栽培すれば何か新しい発見があるかもしれないと思い、私は毎年畑を借りてサトイモを“養育”している。2019年の秋にサトイモを収穫した際には、水道で泥を洗い流してから子イモを取り外し、そのまま部屋にしばらく放置しておいた。何日後だったかは定かではないが、ふと親イモを見ると――そこにあったのはまさに遮光器土偶の頭部であった。大きな目のように見える部分は、子イモを取り外した跡である。
++++そうなのか
また、通常サトイモを地中から掘り出して収穫する際、地上部に伸びていた芋茎(サトイモの葉柄)を親イモの上部で切断する。すると、そこには綺麗な渦巻き模様が現れるということで、遮光器土偶の体表の紋様は、芋茎の断面の渦巻きをモチーフにしたものであると私は考えている。
無防備なサトイモたちを「守護」する存在
じつは遮光器土偶は全身が真っ赤に塗られていた。これはベンガラと呼ばれる塗料で、酸化鉄を主体とする自然顔料である。赤色は血液を連想させることから、こうした場合の赤色塗装は生命力の賦活や魔除けのために行われたと考えるのが自然だろう。
サトイモの精霊が宿る遮光器土偶に期待される効果とは、貯蔵中のサトイモ(種イモを含む)を魔的な力から守護することであったと考えられる。
サトイモは5度以下になると低温障害を起こし芋が腐敗しやすくなるため、縄文時代においても東北地方では土中保存されていたはずである。しかし、かなりの頻度で貯蔵中のサトイモは腐敗する。病魔があらゆるところに出没し、隙あらば人間や植物の身体への侵入を狙っていることを考えれば、長期にわたって土の中で眠っている種イモたちはあまりにも無防備である。何か種イモを守護する存在が必要ではないか。それが遮光器土偶だったというわけである。
傷つきやすい無防備なサトイモたちを警護するのであれば、なるべく“派手”な風体の方が望ましい。体表にびっしりと紋様を入れ、さらにベンガラで真っ赤に塗彩すれば、魔も怯むなかなかの迫力である。遮光器土偶に装着された巨大な眼の仮面もまた、魔的な存在へ睨みを利かせるためのものだったのかもしれない。土中で瞼を大きく開けることはできないが、中央に線刻された細い亀裂の奥から、サトイモの精霊は鋭い眼光を放っていたのであろう。