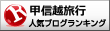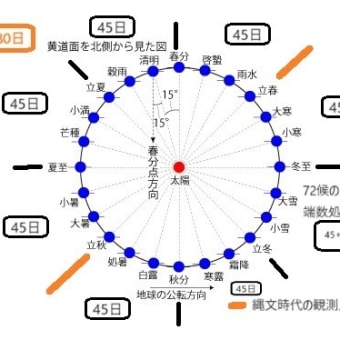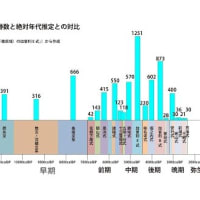草創期は定住を安定させるため生業開発に集中していたと考える。
先ずは手近にある植物の実を利用することから始めて、マメ類を選択したのでは無いか。
その過程で小さなマメを集めるために、籠に代わる容器として土器を造ることを発明した。
まもなくマメ類の栽培に着手して、収穫することが出来るようになったものと思う。
そして生業としてある程度上手く育てて、成果を得ることが出来るようになったのでは無いか。それは集落にとって大きな成果で、それは豆粒文土器を造って祝っていたことから想定できるものと考える。

その内に弓矢猟が出来るようになり、それは先ず弓に張る強い弦となる材料を見つけることが出来たのではないか。同時に矢柄と石鏃も開発して始まったものと思う。
その後も弦の強化開発は進められ、弓の弦はより細くより強いものが開発されていった。それがその後の隆起線文土器系として供献土器が造られた。

さらに弦の強化と細くする努力は続けられて、その経過は、多縄文、回転縄文として記録された。
石鏃についても同様に開発は進められ、その開発努力は爪形文土器として祝われ、供献土器が造られた。
弦の強化努力はついに魚釣りの釣り糸を開発するまでに繋がったものと考える。
魚釣り漁の釣り糸 テグスの開発 は撚糸文土器として記録された。

縄文土器の縄の模様というのは、この弓の弦の強化開発と、釣り糸 テグス開発の経過を記録したものであり、生業開発の記録であると思う。
蛇は豆作り農耕の過程で、作物や穀物を食い荒らすネズミを捕る猫の代わりでは無いだろうか。
このように元々は実用性があったはずだろうと思う、イノシシは畑を食い荒らす害獣だったとしても、食料としての有用性、蛇は猫の代わりのねずみ取りなど、マメ栽培には有用生物だったのではないか。縄文土器で深鉢の口縁部の把手に、イノシシとヘビが対峙するモチーフのものがあるというので、それはそのことを示すものでは無いだろうか。この造形は具象的で、ここまではヘビ信仰などの抽象的な思想が入っているとは思えない。


その後については土偶からも、具象的造形から、なんだか分らないものに変化してしまったことが見えている。
とにかく土偶が何を表現しているのか分らなくなってしまっている。

縄文土器の歴史はこのように理解出来るものと考える。
図はお借りしました
引用ーーーーーーーーーーーーーー
2022年12月12日
縄文土器~「縄」はいったい何を表しているのか?
火焔型土器に象徴される「縄文土器」。これら縄文土器の多くに表されている「縄」の文様は、いったい何を表しているのか。さまざまな説がありますが、ここに迫ってみたいと思います。
(大島直行氏『月と蛇と縄文人』を参考にさせていただいております)
画像はhttps://mag.japaaan.com/archives/164704/3からお借りしました。
民俗学者の吉野裕子氏は、神社の注連縄(しめなわ)が蛇の交尾している姿が象徴的に表されているとしています。
私は、これまでの人生で、実際に蛇が交尾している様子を見たことがありません。蛇は、ハブの場合、2匹(または3匹)がしっかりと絡み合って交尾するそうです。絵を見てみると、まさに注連縄とそっくりですね。(下絵は安田喜憲氏より)
吉野氏は、蛇の脱皮や冬眠が「不死」や「再生」を連想させること、さらに男性性器に似た形態に対して、縄文人が「生命の旺盛さ」を感じ取ったのだと考えています。そして、「蛇に対する思いは縄文時代に限ったことではなく、その後も表面から隠されながら命脈を保ちつづけ、地下水のように日本文化の諸相の底を縫って流れ、現代に及んでいる」と指摘しています。
そういえば、あの岡本太郎氏も、「縄文土器にふれて、わたしの血の中に力がふき起るのを覚えた。濶然と新しい伝統への視野がひらけ、我国の土壌の中にも掘り下げるべき文化の層が深みにひそんでいることを知ったのである。民族に対してのみではない。人間性への根源的な感動であり、信頼感であった」と述べています。
ルーマニアに生まれた20世紀最大の宗教学者であるミルチャ・エリアーデ氏も、吉野氏とほぼ同様の見解を持っています。加えて、蛇は女性が身ごもるための水、すなわち精液を「月」から運んでくるのだと考えました。
(「月」に対して縄文人はどのように捉えていたのかについては、とても興味があります。今後も追求していきたいと思っています)
これらのことから、縄文人は「不死」「再生」の象徴である蛇を崇めており、きつく絡み合う蛇の交尾の様子を「縄」で模倣し、土器の表面に「縄文」として表現したものと推測されます。
大島氏は、「縄文土器に長きにわたって『縄文』が描かれ続けたのは、縄文人にとって不死や再生が重要な観念として確立されていたからでしょう。それをシンボライズするものとして選ばれたのが蛇だったのです。そして、縄の撚り(より)によってレトリックされたのです」と結論づけられています。
現代の日本では、「蛇」と聞くと何か「怖いもの」というイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。縄文時代は、産まれて間もなく死んでしまうことも多かった時代。病魔との闘いの中で生命力を求める思いを、現代とは比べようもないぐらい強烈に感じていたのでしょうね。
FacebookTwitterEmailLineMeWe共有
投稿者 kita-kei : 2022年12月12日 List
ーーーーーーーーーーーーーー
また、山梨の金生遺跡からは、直径1m、深さ80cmほどの穴から、すべて焼かれた138個体のイノシシの下顎が出土したが、そのうち115体が幼体、つまりウリボウのものだったという。ウリボウばかり115頭捕獲するのは難しいことから、当時(縄文後・晩期)すでにイノシシの家畜化が行われていたのではないかと推測される。
一方、下顎の骨を焼かずに埋納した遺構が、福島の大畑貝塚、岩手の宮野貝塚で出土し、焼いた骨を細かく砕き地上に散骨することが縄文後期から晩期に多く見られる。
このようにイノシシの葬送には、焼かずに下顎を埋納、焼いた下顎を埋納、焼いたのちに細かく砕いた散骨(部位不明)の各様式があった。
後代の弥生時代にも下顎の埋納があり、現代に至っても宮崎県西都市の銀鏡(しろみ)の神社ではイノシシにまつわる神楽が12月14日のししとぎり祭りから翌15日のししば祭りにかけて行われ、その時までに狩られたイノシシの頭を奉納し、ししとぎ祭りでは1体を残しすべて解体し参加者で食べ、明けたししとば祭りで残りの一体を川原で火を焚き供養したのち山に埋納するという。ししとぎり祭りで豊穣を祈り、ししとば祭りで鎮魂する意味を持つのだそうだ。ちなみに地元の猟師の言い伝えでは、イノシシが増えるとマムシは減ると言われ、またイノシシの牙を身に着けているとマムシに噛まれないのだという。イノシシはマムシが大好物で、マムシを見つけると踏み殺し食べてしまうからというのがその理由である。
縄文土器で深鉢の口縁部の把手に、イノシシとヘビが対峙するモチーフのものがあるが、マムシの被害から身を守る祈りが込められていたのだろう。
ところで、北海道にイノシシは生息していなかったが、東北地方から移送する試みはあったようである。しかし定着するには至らず、その後イノシシに対する葬送儀礼をもとに熊のイオマンテの儀礼が完成したという。
ーーーーーーーーーーーーーー
■7.「縄文」土器の「縄」と「しめ縄」の意味するところ
そもそも「縄文」土器の縄模様も、縄文人の死生観を明かしています。この縄模様が一万年ほどにもわたって、土器に付けられ続けたからには、よほど確たる理由があるに違いありません。
縄文土器には、よく蛇がそれとわかるデザインで登場します。蛇は冬眠をします。冬の間に冬眠し、春になると目覚める。それはあたかも死から蘇ったように縄文人たちは捉えたことでしょう。そこから蛇は「再生」のシンボルと捉えられました。
その蛇が交合する様は、まさに神社のしめ縄のように二匹が絡み合います。いえ、逆にしめ縄は蛇の交合を象徴していると考えられています。その交合の様を縄で模倣し、その縄を土器の表面に押しつけて「縄文」をつけたのです。
土器は煮炊きによって食べ物の種類を大きく広げ、気化熱で内部の温度を下げることで食べ物の保存を可能にしました。人々のいのちを支える有り難い道具でした。その土器に「縄文」をつけることで、中にいれる食物に「再生」の力を伝え、それを食べることによって「再生」の力を我が身に取り込む。
それは家族の健康長寿と子孫の繁栄を願う、という祈りだったのではないでしょうか。現代の我々が神社で神に祈るのは、無病息災、安産、七五三での子供の元気な成長、というような事でしょう。しめ縄のもとで、そのような祈りをする我々の心は、1万年も縄文土器を作り続けてきた縄文人の心に、思いのほか近いのではないでしょうか。
円環的死生観、精霊信仰、そして神社での祈り。我々日本人の「三つ子の魂」は、縄文時代に形成されたのです。
(文責 伊勢雅臣)