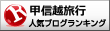追加しました。
火焔土器、火焔式土器の作られていた地域では土器の口縁に作られる突起は神秘数 4に成るとしていた。
その時は北陸地方の海岸沿いにある天神山式土器の存在は気が付いていませんでした。
見たものは有ったかと思うが、目の前は火焔式土器の輝きで、周りはスコトーマになっていた。
北陸地方には同じような時期に天神山式土器というものが作られていた。
この土器は全て見たわけでは無いので、また見落としがあるかも知れないが、大変興味深い状況になって居た。
基本的に神秘数 6、3で僅かに 4の雰囲気があるという感じだった。
土器の形をよく見ると、火焔式土器に引けを取らないと言われているのももっともだと思う。
土器の見付かっている範囲は

突起としては 6突起波状口縁の土器が基本となっているかのように見える。

4突起口縁の土器は 3突起が付いた突起を重ねて置いたかのように見えている。

神秘数 4はベースにあるが、6と3が強調されているかのようだ。写真が分かり難いかと思いますが、じっと目を凝らして見てください、これを作った人は縄文人です。
海辺にある地域なので月の影響を感じているから潮の満ち干の影響を良く知っていたと思う。
追加しました。
波状突起神秘数 8 の先端に
これは神秘数 6突起なのか、 4突起+2突起なのか
どう解釈したら良いものだろうか

この土器では神秘数 3 なしで
8、6、4、2 が出ているようだ。
八節の暦に半年一年暦 6回の月の満ち欠けを重ねているのだろう。太陽暦と太陰暦が重ねられていたことを示しているものと考える。
図と写真はお借りしました