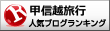松本盆地の弘法山古墳の墳丘主軸と方位
弘法山古墳の墳丘軸線は鉢伏山の方角を向いているので、
再現シミュレーションをおこなった結果、弘法山古墳は冬至の日の出方位に後方部の正面を向けていることがわかったといいます。
弘法山古墳の前方部に立って後方部側を見据えたとき、鉢伏山は冬至の日の出として拝まれる形になるはずという。
観測記録は無いので確認できないのですが、二至の方向を向いていることに成っていたようです。
この地域でも、古墳人は観測が簡単な二至、太陰太陽暦を用いていたのでしょう。
弘法山古墳や中山古墳群を営んだ人々の本拠地だと目されている遺跡には、東海や北陸地域の土器が多量に持ちこまれていたので、これらの土地からの移住者が多かったと推測されている。
縄文時代の金生遺跡 立春を起点とする現地人の持つ太陽暦は、松本に入った古墳人により廃止されたのでしょうか。
纏向石塚古墳は立春の三輪山に古墳の前方を向けていましたが、弘法山古墳 前方後方墳ですが これは行燈山古墳が後円部を冬至方向に向けていたのと同じ方向でした。

行燈山古墳 冬至の方向
箸墓古墳は後方部から見て、後円部を夏至に向けていたのでそれとは異なっていた。
図はお借りしました
引用ーーーーーー
2.松本盆地でも再現された「坐東朝西」の景観設計
そして邪馬台国時代の松本盆地でも、奈良盆地とまったく同じランドスケープ・デザインが再現されたことがわかります。
現在の南松本駅の西には出川西遺跡があり、この時代の中心的な集落遺跡であることが松本市教育委員会の長年の調査の結果、明らかにされました(直井2013他)。
この遺跡には東海や北陸地域の土器が多量に持ちこまれましたので、これらの土地からの移住者も多かったと推測されますし、弘法山古墳や中山古墳群を営んだ人々の本拠地だと目されます。
そして相互の位置関係をみれば、先にみた奈良盆地の様相とよく似ていることがわかります。出川西遺跡第10調査地点からみた西暦250年における年間の日の出・日の入りの推計範囲を図5に示しました。夏至の日の出は袴越山(標高1,753m)付近から、冬至の日の出は伏鉢山(標高1,929m)付近からとなります。弘法山古墳や中山古墳群はその中央前面に位置しますので、日向の嶺の前景にあたる低丘陵を墓域に定めた様相だとみることができるでしょう。「坐東朝西」の景観設計にほかなりません。
大和東南部古墳群がここでは中山古墳群となり、奈良盆地における高橋山は松本盆地では袴越山に転
北條講演資料 2
じ、三輪山は伏鉢山になぞらえられた、といえるのです。
3. 弘法山古墳の墳丘主軸と方位
さらに弘法山古墳の墳丘軸線は伏鉢山の方角を向いています。そこで改めて再現シミュレーションをおこなった結果、弘法山古墳は西暦250年の冬至の日の出方位に後方部の正面を向けることがわかりました。ダイヤモンド伏鉢山は、弘法山古墳の前方部に立って後方部側を見据えたとき、冬至の日の出として拝まれたはずなのです(図6)。この事実はとくに重要です。冬至の日の出は全世界で重視されました。
古代ローマでは太陽の復活を祈る祭りがクリスマスに転嫁されたことが知られています。そもそも暦の起点は冬至であったともいわれます。
祭りの催行時としてこれほど相応しい日取りはありません。ですから弘法山古墳に葬られた人物は、まず間違いなく「冬至の王」としてこの日の朝に完了する葬送祭のもとで葬られ、魂の復活を予祝されたはずだと考えられるのです。