
鑁阿寺の堀(四方が堀で囲まれています)

太鼓橋(栃木県指定有形文化財)

本堂(国宝)

多宝塔(栃木県指定有形文化財)


経堂(国指定重要文化財)

梅の花と鐘楼(国指定重要文化財)
金剛山仁王院法華坊鑁阿寺(「足利氏宅跡(鑁阿寺)」国の指定史跡、日本100名城の一つ)、続きです。
鑁阿寺(足利市)のホームページはこちらです。
足利氏継承に纏わることの概略をまとめてみました。
●足利氏と鑁阿寺
清和天皇を祖とする清和源氏の棟梁、源義家(八幡太郎義家)の四男、源義国が下野国足利荘(栃木県足利市)を領有し、義国の次男、源義康がこの地に館を構え、足利と名乗ったことにより、足利氏の祖とされています。1196年(建久7年)、二代・足利義兼が館内に大日如来を奉納した持仏堂と堀内御堂などを建てたのが始まりで、三代・義氏が堂塔伽藍を建立し、鑁阿寺を足利一門の氏寺としたそうです。
源義康(足利義康)の異母兄、義重は、新田氏(上野国新田荘)の祖とのことです。
●鎌倉時代
源義康(足利義康)の子、義兼は1180年(治承4年)の源頼朝による平家追悼の挙兵に参陣し、1192年(建久3年)の鎌倉幕府開府後も有力御家人として、また、源氏一門としても有力な地位にあったようです。
※鎌倉幕府は1185年に成立していたという説もあるようです。
征夷大将軍・源頼朝と足利義康は、縁戚関係(従弟)とのことです。
足利義康の子・義兼は、源頼朝の妻(北条政子)の妹・北条時子を妻に迎え、また、足利氏はこの後も北条氏と縁戚関係を結んでいたようです。
1219年(承久元年)1月、第3代征夷大将軍・源実朝が暗殺され、頼朝の遠縁に当たる摂関家の藤原頼経が征夷大将軍に就きました。北条氏の実権は、更に強化され、執権政治が続きました。
●鎌倉幕府・北条得宗家滅亡
1333年(元弘3年/正慶2年)、後醍醐天皇の挙兵に呼応し、足利高氏(尊氏)が京都の六波羅探題を滅ぼし、高氏(尊氏)の子・足利義詮、新田義貞、関東の御家人が倒幕軍に加わり、第14代執権・北条高時の一族は東勝寺合戦に敗れ、滅亡しました。約150年間の鎌倉時代が幕を閉じました。
●室町時代
1338年(暦応元年)、足利尊氏が北朝の光明天皇によって征夷大将軍に任じられていますが、室町幕府の成立は建武式目が制定された1336年(建武3年)との説もあるようです。
足利尊氏は鎌倉に東国を統括する鎌倉府を設置し、子の基氏を派遣しました。足利基氏は鎌倉公方として、鎌倉を中心とした関東を支配したそうです。鎌倉公方は足利基氏の子孫が世襲しましたが、幕府と対立し、また、関東管領の上杉氏とも対立していたそうです。第四代鎌倉公方・足利持氏は第六代征夷大将軍・足利義教との戦いに敗れ、自害し、鎌倉公方家は滅亡しました。
後に、足利義政により、足利持氏の子・成氏が再興を許され、第五代鎌倉公方となりました。足利成氏は関東管領上杉氏と対立、鎌倉を放棄し、下総古河に移り、古河公方と称したそうです。
1458年(長禄2年)、第8代征夷大将軍足利義政は対立する古河公方足利成氏への対抗措置として、異母兄の足利政知を鎌倉公方として送りました。しかし、鎌倉には入ることが出来ず、伊豆堀越に留まり、堀越公方(堀越の鎌倉公方)家の始まりとなりました。1495年(明応4年)、今川軍による堀越御所攻めで、第2代堀越公方は追放されました。2代で滅んだ堀越公方ですが、その血統は将軍家に受け継がれ、第11代・足利義澄から第15代・足利義昭までの征夷大将軍は堀越公方の血筋とのことです。また、平島公方家により、現在も血筋は継承されているそうです。
第二代古河公方足利政氏の次男・足利義明から始まる小弓公方(下総国千葉郡小弓)は、1538年(天文7年)に北条氏・千葉氏の連合軍に攻められ、義明は討死、遺族は里見氏を頼って安房に逃れ、滅亡しました。古河公方と小弓公方との分裂状態は無くなりました。
第五代古河公方・足利義氏が1583年(天正11年)に死去し、古河公方の権威も失墜していたこともあり、再興されることもなく、1455年から約130年間続いた家は断絶となりました。
関東の政(まつりごと)を掌っていた足利氏が姿を消し、北条、上杉、武田氏などが群雄割拠、世はまさに戦国時代のさ中でした。
室町幕府は守護大名による合議制政権で、将軍の権力基盤は脆弱であり、守護大名も台頭する守護代や有力家臣の強い圧力を受けていました。また、家督継承をめぐる争いも数多く勃発していたようです。1467年(応仁元年)に起きた応仁・文明の乱以降は、守護の支配下にあった守護代、国人などの武装勢力などが実権を握り、戦国の時代へと移っていきました。
室町幕府の征夷大将軍は、初代足利尊氏から第15代義昭までの約250年に渡り、在位が続きました。
●安土桃山時代から江戸時代以降
1573年(元亀4年)、第15代征夷大将軍・足利義昭が織田信長により、京都から追放され、室町幕府は滅亡しました。15年後の1588年(天正16年)、足利義昭は関白豊臣秀吉に従って参内し、将軍職辞任、准三宮に宣下され、秀吉からは厚遇されていたそうです。
豊臣秀吉は、第五代古河公方・足利義氏の娘と小弓公方の子孫・足利国朝を婚姻させ、下野国喜連川に領地を与えました。後に、足利氏から喜連川氏に改め、江戸時代には5000石の禄高でありながら、10万石格の国主大名として、江戸幕府による特別な処遇を受け、幕末まで存続しました。明治維新後、足利姓に戻り、当主は華族、子爵にもなったそうです。
阿波の国では、室町幕府第11代征夷大将軍足利義澄の次男・足利義維(義冬)の末裔、平島公方(阿波公方)が阿波国平島庄(現在の阿南市那賀川町)に館を構えていました。一族からは足利義栄が第14代征夷大将軍に就いていますが、在任中に入京することもできなかったとのことです。第九代平島公方・義根は、約270年間居住した館を1805年(文化2年)に退去し、京へ移ったそうです。平島公方家は、足利氏初代・源義康からの血筋を絶やさず、現在まで継承しているそうです。
他にも、継承されている武家の家系はあるようです。
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
>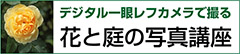
写真家が教える『デジタル一眼レフカメラで撮る 花と庭の写真講座』
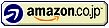
Nikon デジタル一眼レフカメラ D610
※掲載内容等について、変更することがあります。ご了承をお願いいたします。

太鼓橋(栃木県指定有形文化財)

本堂(国宝)

多宝塔(栃木県指定有形文化財)


経堂(国指定重要文化財)

梅の花と鐘楼(国指定重要文化財)
金剛山仁王院法華坊鑁阿寺(「足利氏宅跡(鑁阿寺)」国の指定史跡、日本100名城の一つ)、続きです。
鑁阿寺(足利市)のホームページはこちらです。
足利氏継承に纏わることの概略をまとめてみました。
●足利氏と鑁阿寺
清和天皇を祖とする清和源氏の棟梁、源義家(八幡太郎義家)の四男、源義国が下野国足利荘(栃木県足利市)を領有し、義国の次男、源義康がこの地に館を構え、足利と名乗ったことにより、足利氏の祖とされています。1196年(建久7年)、二代・足利義兼が館内に大日如来を奉納した持仏堂と堀内御堂などを建てたのが始まりで、三代・義氏が堂塔伽藍を建立し、鑁阿寺を足利一門の氏寺としたそうです。
源義康(足利義康)の異母兄、義重は、新田氏(上野国新田荘)の祖とのことです。
●鎌倉時代
源義康(足利義康)の子、義兼は1180年(治承4年)の源頼朝による平家追悼の挙兵に参陣し、1192年(建久3年)の鎌倉幕府開府後も有力御家人として、また、源氏一門としても有力な地位にあったようです。
※鎌倉幕府は1185年に成立していたという説もあるようです。
征夷大将軍・源頼朝と足利義康は、縁戚関係(従弟)とのことです。
足利義康の子・義兼は、源頼朝の妻(北条政子)の妹・北条時子を妻に迎え、また、足利氏はこの後も北条氏と縁戚関係を結んでいたようです。
1219年(承久元年)1月、第3代征夷大将軍・源実朝が暗殺され、頼朝の遠縁に当たる摂関家の藤原頼経が征夷大将軍に就きました。北条氏の実権は、更に強化され、執権政治が続きました。
●鎌倉幕府・北条得宗家滅亡
1333年(元弘3年/正慶2年)、後醍醐天皇の挙兵に呼応し、足利高氏(尊氏)が京都の六波羅探題を滅ぼし、高氏(尊氏)の子・足利義詮、新田義貞、関東の御家人が倒幕軍に加わり、第14代執権・北条高時の一族は東勝寺合戦に敗れ、滅亡しました。約150年間の鎌倉時代が幕を閉じました。
●室町時代
1338年(暦応元年)、足利尊氏が北朝の光明天皇によって征夷大将軍に任じられていますが、室町幕府の成立は建武式目が制定された1336年(建武3年)との説もあるようです。
足利尊氏は鎌倉に東国を統括する鎌倉府を設置し、子の基氏を派遣しました。足利基氏は鎌倉公方として、鎌倉を中心とした関東を支配したそうです。鎌倉公方は足利基氏の子孫が世襲しましたが、幕府と対立し、また、関東管領の上杉氏とも対立していたそうです。第四代鎌倉公方・足利持氏は第六代征夷大将軍・足利義教との戦いに敗れ、自害し、鎌倉公方家は滅亡しました。
後に、足利義政により、足利持氏の子・成氏が再興を許され、第五代鎌倉公方となりました。足利成氏は関東管領上杉氏と対立、鎌倉を放棄し、下総古河に移り、古河公方と称したそうです。
1458年(長禄2年)、第8代征夷大将軍足利義政は対立する古河公方足利成氏への対抗措置として、異母兄の足利政知を鎌倉公方として送りました。しかし、鎌倉には入ることが出来ず、伊豆堀越に留まり、堀越公方(堀越の鎌倉公方)家の始まりとなりました。1495年(明応4年)、今川軍による堀越御所攻めで、第2代堀越公方は追放されました。2代で滅んだ堀越公方ですが、その血統は将軍家に受け継がれ、第11代・足利義澄から第15代・足利義昭までの征夷大将軍は堀越公方の血筋とのことです。また、平島公方家により、現在も血筋は継承されているそうです。
第二代古河公方足利政氏の次男・足利義明から始まる小弓公方(下総国千葉郡小弓)は、1538年(天文7年)に北条氏・千葉氏の連合軍に攻められ、義明は討死、遺族は里見氏を頼って安房に逃れ、滅亡しました。古河公方と小弓公方との分裂状態は無くなりました。
第五代古河公方・足利義氏が1583年(天正11年)に死去し、古河公方の権威も失墜していたこともあり、再興されることもなく、1455年から約130年間続いた家は断絶となりました。
関東の政(まつりごと)を掌っていた足利氏が姿を消し、北条、上杉、武田氏などが群雄割拠、世はまさに戦国時代のさ中でした。
室町幕府は守護大名による合議制政権で、将軍の権力基盤は脆弱であり、守護大名も台頭する守護代や有力家臣の強い圧力を受けていました。また、家督継承をめぐる争いも数多く勃発していたようです。1467年(応仁元年)に起きた応仁・文明の乱以降は、守護の支配下にあった守護代、国人などの武装勢力などが実権を握り、戦国の時代へと移っていきました。
室町幕府の征夷大将軍は、初代足利尊氏から第15代義昭までの約250年に渡り、在位が続きました。
●安土桃山時代から江戸時代以降
1573年(元亀4年)、第15代征夷大将軍・足利義昭が織田信長により、京都から追放され、室町幕府は滅亡しました。15年後の1588年(天正16年)、足利義昭は関白豊臣秀吉に従って参内し、将軍職辞任、准三宮に宣下され、秀吉からは厚遇されていたそうです。
豊臣秀吉は、第五代古河公方・足利義氏の娘と小弓公方の子孫・足利国朝を婚姻させ、下野国喜連川に領地を与えました。後に、足利氏から喜連川氏に改め、江戸時代には5000石の禄高でありながら、10万石格の国主大名として、江戸幕府による特別な処遇を受け、幕末まで存続しました。明治維新後、足利姓に戻り、当主は華族、子爵にもなったそうです。
阿波の国では、室町幕府第11代征夷大将軍足利義澄の次男・足利義維(義冬)の末裔、平島公方(阿波公方)が阿波国平島庄(現在の阿南市那賀川町)に館を構えていました。一族からは足利義栄が第14代征夷大将軍に就いていますが、在任中に入京することもできなかったとのことです。第九代平島公方・義根は、約270年間居住した館を1805年(文化2年)に退去し、京へ移ったそうです。平島公方家は、足利氏初代・源義康からの血筋を絶やさず、現在まで継承しているそうです。
他にも、継承されている武家の家系はあるようです。
>
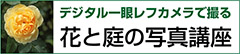
写真家が教える『デジタル一眼レフカメラで撮る 花と庭の写真講座』
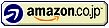
Nikon デジタル一眼レフカメラ D610
※掲載内容等について、変更することがあります。ご了承をお願いいたします。

























