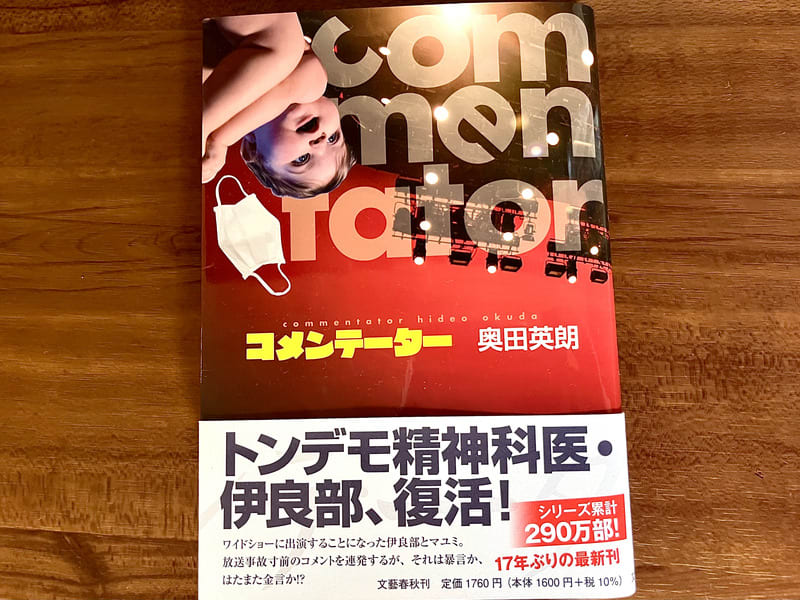大きな耳を持ったキツネが主人公。
キツネは、大きな音が苦手でもありました。
穴を掘って、掘って、地中深くに静かに暮らしていました。
住んでいる森は大きな音でいっぱいだったから。
大きな音にいつもびくびくしている自分が見られるのを恥ずかしく思ってもいました。
そんなある日、キツネは静かなところを探そうと勇気を出して森に出かけました。
意外と身近なところにあるんじゃないかなあ?
すると、見つかりました。あちらにもこちらにも。
「どくのあるベニテングタケのかさのした」
「そっととじためのおく」
「はっぱのうえでそろりとうごくガガンボ」
「よつばのクローバーがはさまれたほんのページ」
「ひとやすみしているちょうちょのしょっかくのさきっちょ」
「めがさめてしんしんとゆきのふるあさ」
キツネは、さらに見つけた。
「おもいでのなか」
「すずらんのかおり」
「まっくらなところ」
「ひるまのひかり」
「だれかによんでもらうおはなし」
「ゆらゆらゆれるいなほ」
「やさしいことばのなか」
「ひんやりしたまどガラス」
キツネは、さらに地中深く掘っていきました。
すると、大きな岩にぶつかり、その上からダンプカーのとても大きな音が響いてきました。
キツネは泣いてしまいました。大きな声をあげて。
すると、地中のお隣から「しずかにしてくれー!」と言ってミミズが顔を出しました。
ミミズもまた大きな音が苦手なのでした。
そこでキツネは、地中から出て、森で叫びました。
「しずかにしてくれー! おおきなおとは もう たくさん」
それから、森は大きな音をあまり出さなくなりました。
大きな音が苦手だった他の生き物たちと、キツネは仲良くなりました。
特にミミズとは友達になって、楽しくおしゃべりするようになりました。
そんなお話です。
この絵本を読んで、あー私にもあったなあと、思いつくままに「しずかなところ」を書き出してみました。
「打ち鳴らされたゴング」
「黒板に書き付けられたチョークからこぼれる粉」
「日記帳の空白に下された万年筆のインク」
「コーヒーから立ち上る湯気と香り」
「ピッチャーマウンドとホームベースの間」
「映画館の照明が消えるとき」
「親しくなった人とする食事」
「マラソンのゴールテープ」
「走って風になれたとき」
「開店前の本屋」
「屋根を軽々と越えていく虹」
「本を開いた人の耳」
「つやつやして甘酸っぱいリンゴのかけら」
「絵の前」
「音楽の奥」
「真夏の夜のよく冷えたスイカ」
「風に揺れるコスモスの細くしなやかな茎」
「お昼寝」
まだまだありそうです。
「しずかなところ」は、「物理的な静寂」だけを意味しなかった。その発見が、この絵本の最大のメッセージだと思います。
「しずかなところ」は、「美しいところ」「私を感じられるところ」「大事なところ」「夢中になれるところ」「落ち着くところ」「感心するところ」でもありました。
「しずかなところ」が一つでも多く見つかると、私たちは生きやすくなります。
「しずかでないところ」で生きなければならない人たちに、この絵本は大きな支えとなってくれそうです。
レーッタ・ニエメラ 文/島塚絵里 絵・訳/岩波書店/2024
キツネは、大きな音が苦手でもありました。
穴を掘って、掘って、地中深くに静かに暮らしていました。
住んでいる森は大きな音でいっぱいだったから。
大きな音にいつもびくびくしている自分が見られるのを恥ずかしく思ってもいました。
そんなある日、キツネは静かなところを探そうと勇気を出して森に出かけました。
意外と身近なところにあるんじゃないかなあ?
すると、見つかりました。あちらにもこちらにも。
「どくのあるベニテングタケのかさのした」
「そっととじためのおく」
「はっぱのうえでそろりとうごくガガンボ」
「よつばのクローバーがはさまれたほんのページ」
「ひとやすみしているちょうちょのしょっかくのさきっちょ」
「めがさめてしんしんとゆきのふるあさ」
キツネは、さらに見つけた。
「おもいでのなか」
「すずらんのかおり」
「まっくらなところ」
「ひるまのひかり」
「だれかによんでもらうおはなし」
「ゆらゆらゆれるいなほ」
「やさしいことばのなか」
「ひんやりしたまどガラス」
キツネは、さらに地中深く掘っていきました。
すると、大きな岩にぶつかり、その上からダンプカーのとても大きな音が響いてきました。
キツネは泣いてしまいました。大きな声をあげて。
すると、地中のお隣から「しずかにしてくれー!」と言ってミミズが顔を出しました。
ミミズもまた大きな音が苦手なのでした。
そこでキツネは、地中から出て、森で叫びました。
「しずかにしてくれー! おおきなおとは もう たくさん」
それから、森は大きな音をあまり出さなくなりました。
大きな音が苦手だった他の生き物たちと、キツネは仲良くなりました。
特にミミズとは友達になって、楽しくおしゃべりするようになりました。
そんなお話です。
この絵本を読んで、あー私にもあったなあと、思いつくままに「しずかなところ」を書き出してみました。
「打ち鳴らされたゴング」
「黒板に書き付けられたチョークからこぼれる粉」
「日記帳の空白に下された万年筆のインク」
「コーヒーから立ち上る湯気と香り」
「ピッチャーマウンドとホームベースの間」
「映画館の照明が消えるとき」
「親しくなった人とする食事」
「マラソンのゴールテープ」
「走って風になれたとき」
「開店前の本屋」
「屋根を軽々と越えていく虹」
「本を開いた人の耳」
「つやつやして甘酸っぱいリンゴのかけら」
「絵の前」
「音楽の奥」
「真夏の夜のよく冷えたスイカ」
「風に揺れるコスモスの細くしなやかな茎」
「お昼寝」
まだまだありそうです。
「しずかなところ」は、「物理的な静寂」だけを意味しなかった。その発見が、この絵本の最大のメッセージだと思います。
「しずかなところ」は、「美しいところ」「私を感じられるところ」「大事なところ」「夢中になれるところ」「落ち着くところ」「感心するところ」でもありました。
「しずかなところ」が一つでも多く見つかると、私たちは生きやすくなります。
「しずかでないところ」で生きなければならない人たちに、この絵本は大きな支えとなってくれそうです。
レーッタ・ニエメラ 文/島塚絵里 絵・訳/岩波書店/2024