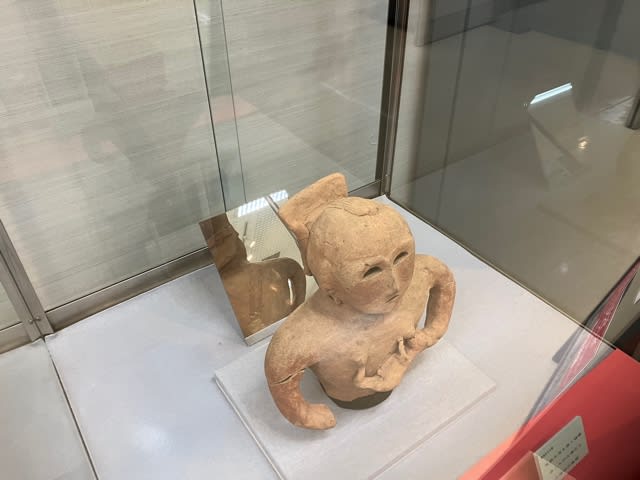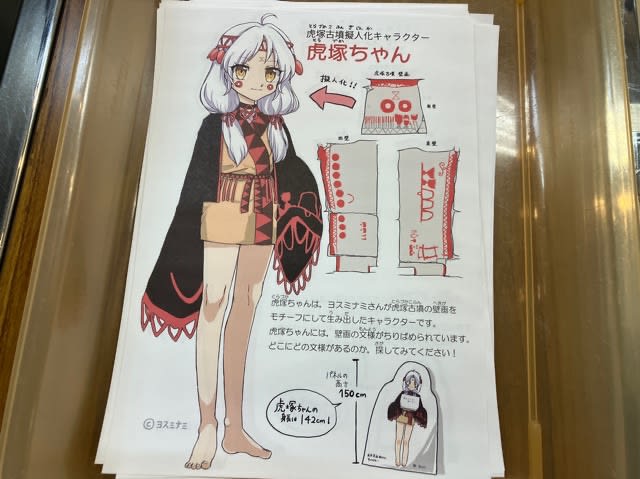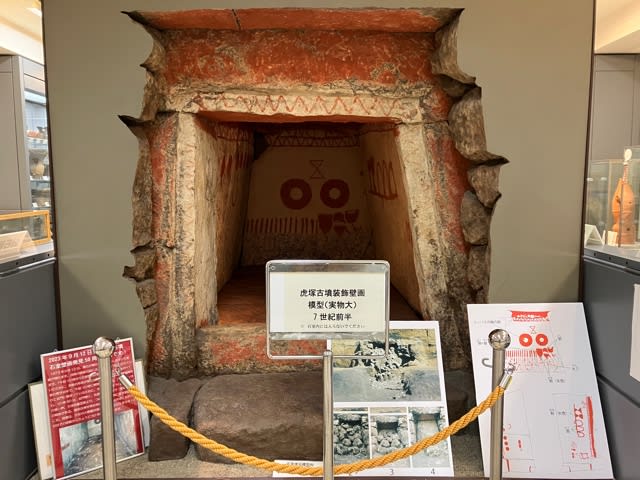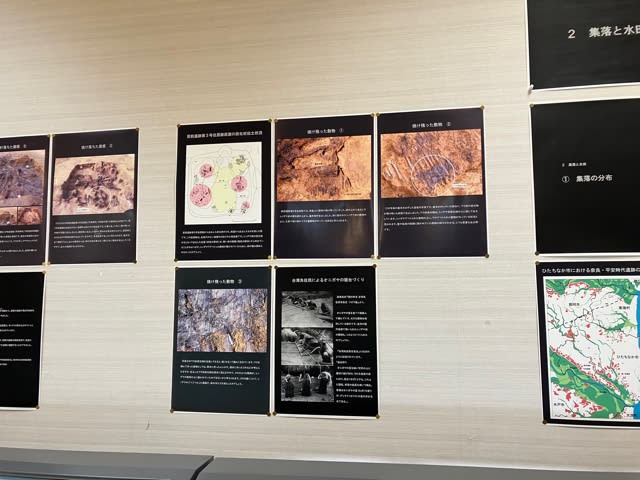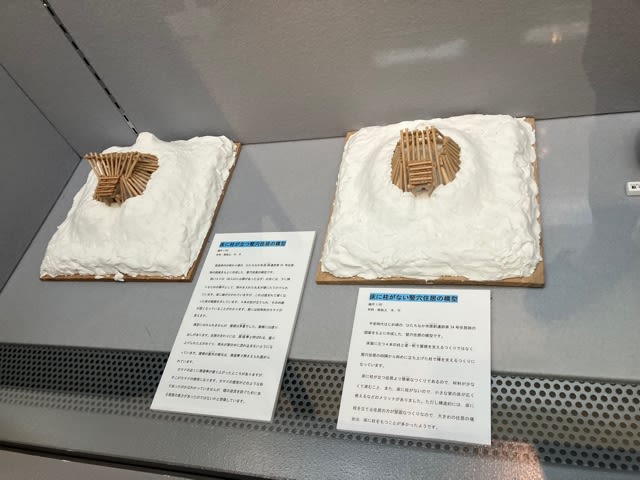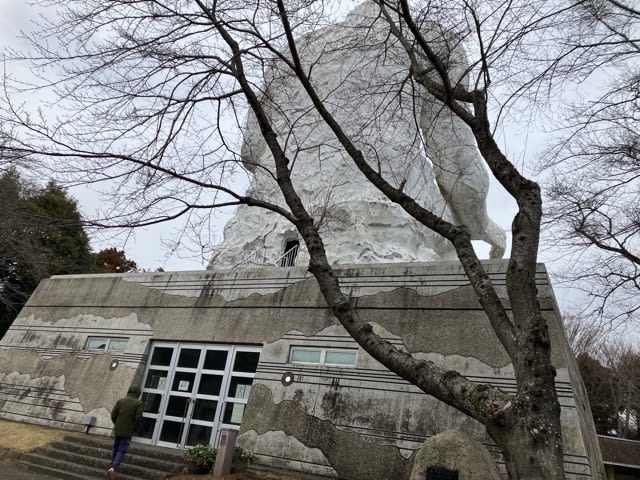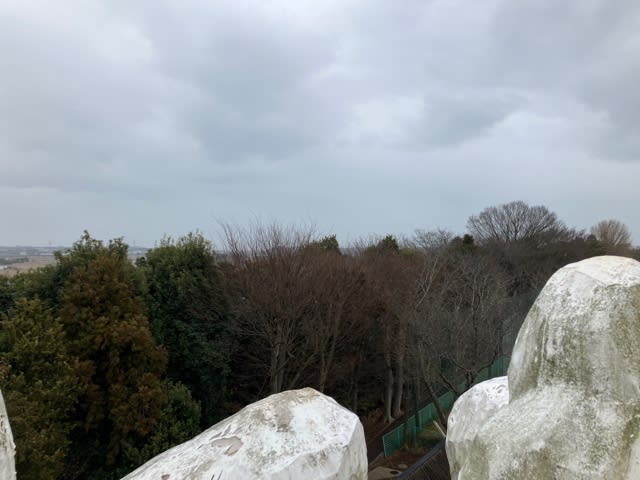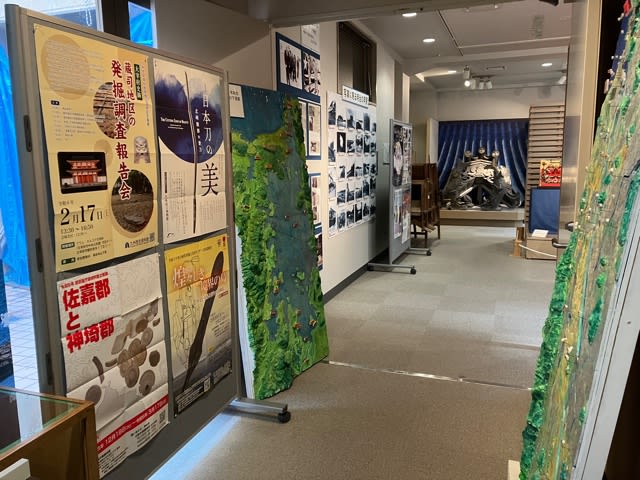まさか!

大串貝塚の断層面観覧施設は鍵が閉まっていた。
Σ(゚д゚lll)
のぞいてみる。
わざわざ係の人を呼ぶのはさすがに申し訳ないけど、ちょっと残念。
もどりますか。
林をてくてく。

ご注意ください


もどろう、とにかく。
近くの学校の鐘が鳴る。ちょうど12時なのだ。
貝塚があったということは、この辺まで海が来てたということだよね。
またお会いしましたね!




天井にこのぐらい隙間が空いてたら煙で家の中がもくもく
と言うこともないのだろうか。
天井部分が開け閉めできたとか?

水戸市埋蔵文化財センター
縄文くらしの四季館

ほ、やっと屋内。



これこれ!

偉い人の副葬品より何倍も心おどる。
日常を垣間見るときの
ひとの生活にお邪魔するような。

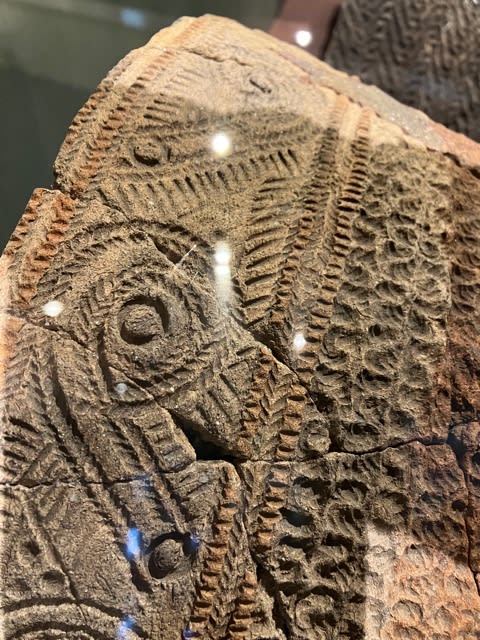
模様にうっとり。



さわってみたくなるし、やってみたくなるのはDNAにかきこまれているから?(笑)



弥生時代の遺跡から住居跡が10軒発見され、弥生土器とともに「紡錘車」という土製品が出土している。
紡錘車とは、植物の繊維を同じ太さの糸にするために、ねじりながら糸を巻きとる作業に用いられる道具らしい。
バラエティにとんだかたちや文様がある。
コマみたいにまわると違うかたちがみえてくるのかな?




使い勝手はさておき、すごくおしゃれだ。
平安時代の人面墨書土器
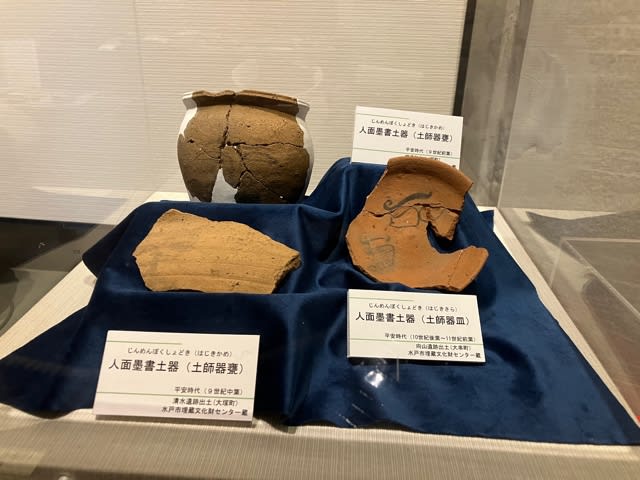
墨で顔が書いてある。
キャラクターのお茶碗なら、ドラえもんのやつが家にあるw
この地にも人間が3万年前から訪れていた跡を知ることができました。
このあと、12:45 さか天パークへ。
買ったものは
いいだこ、サザエ、真イカ、イカの塩辛。
発泡スチロール箱にいれてもらって、あと
干し芋も!
14:00 守谷パーキングエリアに寄る。
新しいのかな?広くて広すぎず、きれいなとこ。
ここでも、たくさんお土産を買いました。
何気なく積んであったおせんべいも二袋ほど買った。
14:30出発
東京にもどってから、入院している親戚のおばさんとこ寄って
おせんべいをお土産に渡したら、
大好物で以前はよく取り寄せたものだと感極まっていた。
将門煎餅(まさかどせんべい)
ありがとう茨城県アゲイン。