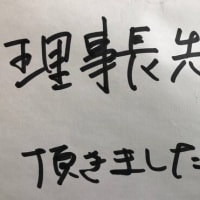1989年に出版された「豊かさとは何か」には強い衝撃を受けた。経済学者にも市井に通じた暮らしの分かる人がいるんだと思った。当時は世界第二位の経済大国で、あり余る資金が何処に消えて行ったのか今でも謎である。その証拠は大都市に溢れている。暉峻名誉教授が言うように、近代的ではあるがみすぼらしいコンクリートの積み木細工ばかりである。うさぎ小屋とは言わないが、かつて地方で茅葺き屋根の下に暮らした時分と比較したら雲泥の差がある。
効率化と飽くなき利益追求という単純な命題に猪突猛進した結果、都会ではバラックの建物を見栄えのいいようにしただけのコンクリートの無機質な世界と化している。今や少子化で八割減が続くというのに、SFの世界のようなリニア新幹線や高速道路網など、ただただ槌音を響かせ続けている。
人の豊かさとは何か?半年で壊される万博のパビリオンに何千億円を惜しげもなく注ぎ込む神経はなんなのだろう。目玉がない中で、大金を豪華なトイレに流し込む行為は、まさにバブルの申し子の成せる技なのだろうか?時代は明らかに変わったのかもしれない。70年代80年代生まれの世代が引っ張る社会である。高齢者は己の健康を案じて、ただじっと眺めるしかないのかもしれない。そう思いながらも、社会に流されてきた己も同じように、罪深さの一端を感じずにはおられない。