結局の処、
蘇我氏の血族というしがらみが、あったということである。と、思う。
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Soga_faminy_tree.svg
蘇我氏が乙己の変(大化の改新のきっかけになる変)にて、滅亡。
そして、藤原氏の登場。
持統天皇末年頃に少壮官僚であった藤原不比等は、文武天皇元年(697年)8月に持統天皇の譲位により即位した軽皇子(文武天皇)に娘の藤原宮子が夫人となっており、中央政界に台頭する。これと同時に藤原朝臣姓の名乗りが不比等とその子孫に限定されており、不比等は鎌足の後継者として認められて「藤原氏 = 不比等家」が成立する。藤原不比等は、下毛野古麻呂らとともに大宝律令を編纂して律令制度の確立に貢献した。さらに宮子が首皇子(後の聖武天皇)を産むと、皇子の後宮にも娘の光明子(後の光明皇后)を入れて、天皇の姻戚としての地位を確立した。文武天皇以降、天皇のほとんどの后・妃が藤原氏の娘となる[3]。
天武天皇・天智天皇あたりになると、
蘇我氏のしがらみからぬけでていて、
天皇の正統性を確約しようとしたように思えるのが、
古事記・日本書記の編纂である。
この天皇の発生の元々が高天原族=ヘブライ人と考えていくと
それに見合った史書をつくろうとしたのではないか?と思える。
ところが、ここに消し去れない人物が出てくる。
饒速日という天孫が、神武天皇に帰順したのは、
まあ、消し去ったというわけではないが、
横にどかすことは出来たと言ってよいと思う。
ところが、消し去れなかったのが
素戔嗚だったと思う。
何故、消し去れなかったかと考えると、
今でも、そうだろうけど、
500年くらい前の話ならば、
実際にまだ、生きている。
消し去ろうにも、いろいろ、証拠が残りすぎているわけである。
そこで、素戔嗚という人物をどうあつかうか、と、言う事に成ってくるのだと思う。
(だが、出雲風土記では、素戔嗚にあたる人物がいない・・という話も聞いている)
素戔嗚という名前からして
疑問であるが、
これが、のちに
牛頭大王と同一視されたり
蘇民将来の話に出てくるのは武塔神だったり、素戔嗚だったりするのだが
蘇の民(子孫)だから、疫病にかからない。
と、いうその「蘇」は、どこの国だ?と言う事に成る。
温(おん)または蘇(そ)は、古代中国周代の国家。領域は現在の河南省焦作市温県。
紀元前650年に温(蘇)は狄によって、滅ぼされた
『日本書紀』における八岐大蛇の記述がある一書第4では、天から追放された素戔嗚尊は、新羅の曽尸茂梨(そしもり)に降り、この地吾居ること欲さず「乃興言曰 此地吾不欲居」と言い息子の五十猛神(いそたける)と共に土船で東に渡り出雲国斐伊川上の鳥上の峰へ到った(「遂以埴土作舟 乘之東渡 到出雲國簸川上所在 鳥上之峯」)後、八岐大蛇を退治した。
新羅の曽尸茂梨(そしもり)に降りたと記述されていることから、元々は新羅の神ではないかと考えられていた。
奇妙だと思う。
ウィキのとおりであるのなら
天照大神と兄弟(姉弟)であるわけで、
天照大神も新羅の神ではないか?ということになるやもしれぬことを
書く。
元々は新羅の神ではないかと考えられていた。
と、ある部分の主語がぬけているので曖昧模糊だが
古の人、日本書紀を読んだ人、全般にわたって
また、その話を聞いた人までもが、あてはまってくる。
奇妙な書き方はほかにもいくつかあるが、
単純に蘇の人・新羅の神?であるとするのなら
日本書紀側は
姉弟とは、書かないだろう。
どう考えても、
出雲王国をつくりあげた人物を
他の国の人であるという風にかけなかった理由があるだろう。
それが、ひとつに、ヘブライ人が天皇家になったからであり
ヘブライ人が侵略をくりかえしたという事実をひた隠しにしなければならなかった。
と、いうことでもあろう。
このために、素戔嗚という架空人物をつくりあげたとも考えられる。
なぜ、そこまでしなければならなかったか?
だが、
それ以前の経緯というものがみえてきていない。
ーーー続くーーー











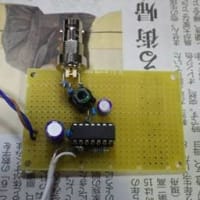


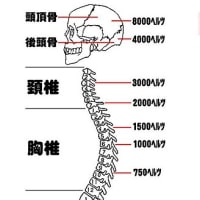



グーグルで検索するとヒットするので無料で読めます。
お楽しみくださいませ。
貴作品、ざっと、眺めて来ましたが
主人公(探偵?)現代の人間が、藤原不比等に対して
興味を持っていく、そのあたりの導入部が、うまくいってない気がします。
このため、一緒に秘密をしっていこうという共感をひきだしきれずにいるとも思えます。
文章的にも、テンポの良さがなく、
文章表現も発展途上がみえて、
小説としては、読みつらいです。
できるならば、読んでくれという宣伝行為でなく、
自分の言葉で
不比等のことをこうとらえているという書き込みが欲しかったですね。
相手に伝わりやすく、かつ、興味を抱いてもらえる書き方として
コメント欄でも、文章修行ができるのではないかと思えます。