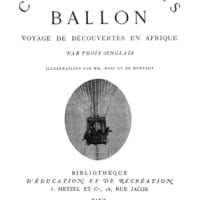(『二千七百の夏と冬』荻原浩著/双葉文庫)

 「ファンタジーにはしたくなかったので、言葉一つにも縛りを設け、
「ファンタジーにはしたくなかったので、言葉一つにも縛りを設け、
動植物も当時の日本列島に実在したものだけを書く」ようにしたと著者は言ってるけど
(『週刊ポスト2014年8月1日号【著者に訊け】荻原浩氏 縄文時代小説『二千七百の夏と冬』より)
やっぱりファンタジー小説。
ファンタジーというくくりを「曖昧さ」「絵空事」という解釈で捉えてないかなー。
そうだとすると、ちょっと違うよと言いたい。
アメリカの作家、ジーン・アウルの『大地の子エイラ』シリーズは
太古の昔を描いた壮大なファンタジー・ノベル。
とても面白い。
それの日本版のようなもので、縄文時代と弥生時代の過渡期を描いたもの。
こちらも、とても面白い。
 2011年、北関東のダム建設工事の掘削作業中に、
2011年、北関東のダム建設工事の掘削作業中に、
若い縄文人男性の人骨が発見された。
それだけなら、よくある話だけど
そのすぐ隣で、十代半ばと推定される渡来系弥生人の女性の人骨が発見されたのだ。
二体の人骨は、右手を相手の左手と重ねるように、つまり手を握り合い、
向き合った姿で横たわっていた。
 縄文人の男性と弥生人の女性は、なぜそのような姿でその場所に埋まっていたのか?
縄文人の男性と弥生人の女性は、なぜそのような姿でその場所に埋まっていたのか?
約二千七百年前の人骨。
しかも、驚くことに縄文人男性のもう片方の手には、
稲のプラント・オパール(植物珪酸体)が握られていた。
農耕が始まったのは弥生時代からではなかったのか?
こういう謎が提示されて物語は始まる。
古人骨発掘の情報は、現代に生きる地方支局の新聞記者により
そのつど挿入される。
 縄文時代の物語に思わず引き込まれ、ついつい読み進んでしまう。
縄文時代の物語に思わず引き込まれ、ついつい読み進んでしまう。
とくに陽の色をした巨大なクムゥ(おそらく熊)との闘いのシーンは圧巻で
いかにも縄文時代の狩り、あるいは獣との格闘はこんなふうだったのかと
納得させられる臨場感がある。
「鳥の巣の卵」と書いて「たぶん」とルビをふったり、
「生肉と焼き肝」を「ぜたいく」と読ませたり、
「神の決めた日」で「こんにちは」のルビ。
そういう著者の造語も、リアリティを増幅させて面白い。
 新聞記者に対して、発掘を進める地元の国立大准教授が言うように
新聞記者に対して、発掘を進める地元の国立大准教授が言うように
人間の寿命が仮に90年だとすると、人が人生を30回繰り返せば
2700年ぐらいになってしまうのだ。
そう遠い昔でもないのかもしれない。
実際、縄文時代から弥生時代に変わる過渡期に
縄文人の若者と弥生人の少女が出会って
恋をすることだったあったのかも。
 物語の最後で、謎は解き明かされる。
物語の最後で、謎は解き明かされる。
ちょっと心を打たれる展開。
そうかそうか。
縄文人の若者ウルクは、力強く、懸命にその社会を生きたんだ。
そして二人は二千七百の夏と冬を、命を終えたときのままの姿で経て
現代に物語を届けてくれた。
と、ジーンとくるのだ。