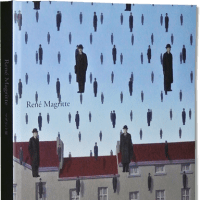□■□■----------------------------------------------■□■□
夜の訪問者について。
ぼくは心底びっくりしたのだ
□■□■----------------------------------------------■□■□
夜になって、僕はいいかげん疲れて自分のマンションに帰ってきた。
出張取材で地方に行ってたのだけど、早朝から移動するし、
夜は夜で飲み会なんだから、けっこうバテる。
まあ、いつものことだから、どうってことはない。かな?
一人暮らしとはいえ、自分の部屋に帰ってくるのは悪くない。
鍵を回す感触が、なんとなく嬉しい。
僕は昔から家に帰るのが好きだった。
あたりまえか…。みんな、そう?
ドアを開けて入る瞬間のこもった家の匂いが好きだ。
空気が重量を増していて、無音の空間。
って、なんだよ。
この匂い。
違うだろ。
これ、ポップコーンの匂いだろう!
僕は慌てた。
「誰かいるの?」と声をかけてみた。
いるはずないじゃないか。僕以外に鍵を持っているやつなんか…。
…レディバード!
急いで靴を脱ぎ、部屋に入り、電気をつけた。
僕は呆然とした。
「きみ、誰?」
そこにいたのは、小さいレディバードではなく、背がひょろひょろっと伸びた、
栗色の縮れ毛の髪の少年だった。
洗いざらしのコットンのシャツにサスペンダーのついた短めのズボン。
裸足。
古いアメリカの西部劇にでも出てきそうな、そんな少年だ。
僕がいつも寝そべってテレビを見るソファーの背に腰を下ろし、
座るべきところに脚を置いて、片手に油紙で包んだポップコーン、
もう片手はポップコーンをつまんで、
まさに口に放り込もうとしていたところだった。
普通に食べればいいのに、ひょいっと投げて口に入れている。その瞬間、
見事にポップコーンは口からそれて、下に落ちた。
「やあ、お帰り」
少年は少しばかり不敵な笑みを浮かべて、そう言った。
はっきり言っておくけど、日本人じゃない。
だけど日本語を喋る。
まじまじと少年を見て、見たことある気がするけれど誰だろう、と思った。
それとなく聞いてみた。
「きみ、誰?」
「当ててごらんよ」と少年は笑いながら言った。
僕は頭に浮かんだことを口にした。
「もしかして、トム・ソーヤー?」
少年は、本を読みながら頭の中でイメージしていた
トム・ソーヤーそのものだった。
「やあ、よくわかったね。先週、僕のことを書いた本を読んでたものね。
あんなに興味をもってくれて嬉しいよ。
墓場でインディアン・ジョーが若いロビンソン医師を殺す場面で、
息を呑んで凍り付いてたよね。
ベッキーと洞窟に取り残され、迷子になったときには、
いっしょになって不安がっていたしね。
あんたも冒険が好きなんだ。」
そういうと少年は屈託なく笑った。
「呆気にとられる」という言葉があるけど、こういうことを言うんだ。
頭が真っ白になって、すぐには言葉が出てこなかった。
ようやく気を取り直して僕が言ったのは
「なんでアメリカ人が日本語を喋ってるんだい?」ってこと。
もっとほかに聞くことあるだろう。
「ほら、僕は意識の世界の人間だから、
あんたたちみたいに現実にとらわれないんだよ。
相手がしゃべる言葉で話すんだ。
ちゃんと声出してるけど、あんたの意識に直接話しかけてるんだよ。」
「ふうん。」
わかったような、わからないような…。
「で、えーと、なんでここにいるの?」と僕。
「あのねぇ、行ってこいといわれて」
「誰に?」
「レディバード」
何か言おうと思ったけど、言葉に詰まってしまった。
なんでまた。そりゃ、物語の主人公が目の前で話してくれたら、
こんな面白いことないけど、なにをいったい目論んでるんだろう。
「あのさ、レディバードは、こう言ってたよ。
『もっと自由になれ』って。
妄想っていうのは、そりゃよくないよ。現実をゆがめるからね。
でも、意識の世界は自由なんだから、現実にしばられすぎるなって。
とくにあんたは物語の案内人なんだから、もっと物語の中に入らなきゃって。
いや逆だな。
物語は現実じゃないなんて、区別するなだってさ。
僕がいまここにいるように、物語は読んだ人の意識の中に
現実としてあるんだよ。
ものに支配された現実と、ものに支配されない現実があるってわけさ。
たとえば知識は頭の中にあってものではないけど、現実でしょ?」
「ふうん。じゃあさ、そのポップコーンを僕にもくれる?」
「いいよ。どうぞ」
そういって、少年は包みを差し出した。
残り少ないポップコーンをつまんで口に入れると、
バター風味のポップコーンの味がした。
「ねえ、これって現実に僕が食べてるけど、きみは現実じゃない。
それ、どういうことだ?」
「だから、僕は現実なんだって。あんたにとって、まぎれもなくね」
そんなのありかよ…と思ってると、疲れているせいか、猛烈な眠気が襲い、
僕はいつのまにか、ソファーで眠りこけていたらしい。
気がついたら、電気をつけっぱなしの部屋で、僕はひとりだった。
トム・ソーヤーなんか、どこにもいない。
夢だったのかな。
ここでよくやる物語の手口は、トム・ソーヤーが口に入れ損ねた
ポップコーンが床に転がってるってやつだ。
見回してみたけど、そういうものはない。
夢だな…。
そう納得すると、さっさと歯を磨いてベッドに入って、眠りなおすことにした。
だってさ、くたくたに疲れてるんだから。
【見つけたこと】その物語が本物なら、物語のリアルは、自分次第。
─────────────────────────
レディバードが言ったこと
─────────────────────────
「あんたって、やっぱり残念よね」
「えっ?」
なんでまた、そんなことを言われないといけないんだ。
「だってさ、私がわざわざトム・ソーヤーに頼んで、
あんたのところに行ってもらったのに、夢だなんて。
あんた、夢だって言ったのよ。
ほんとに、いやになっちゃう」
「だって、寝てたし」
「眠りこけちゃっただけでしょ。
とっておきの冒険話を聞かせてくれるはずだったのに。
そのチャンスをふいにしたのよ」
「えっ、そうだったの?」
「そうよ。ハックルベリイ・フィンのこととか、
お金持ちになってどうしたのか、とか。
マーク・トゥエインの話だとか、山ほど聞けたのに、残念よね」
むむむ…。
なんと言っていいのか、僕はしょげてしまった。
それ……ものすごく残念じゃないか?
「もう1回きてもらえないかな」と、なだめすかすように言ってみる。
「キャラメル味のポップコーンを用意しとくから」
レディバードは口の端をきゅっとあげる独特の微笑み方でこう言った。
「む、り!」
それから、少し機嫌を直したらしく
「本当にそう思うのなら、聞いてみてあげてもいいわ」
ぼくは「お願い!」と両手を胸の前で合わせて平身低頭、懇願した。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
メルマガ配信しています。購読料は無料。
ご登録はこちらへ。

↑「『赤毛のアン』のキーワードBOOK」をご希望の方は
marupippo1222@gmail.com までお申し込みください。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆