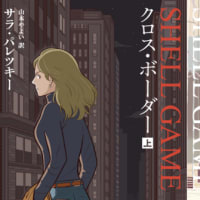@サラ☆
スウェーデンの作家、ヨハン・テオリンの『黄昏に眠る秋』、
2007年に発表されたデビュー作だ。
日本では2011年にハヤカワ・ミステリから刊行されている。
ひさしぶりに分厚くて、どっしりしたミステリを読んだ。
スウェーデンの南東にあるエーランド島が舞台。
(スウェーデンでは2番目に大きな島だそうだ。)
その島で1972年9月、家からそっと抜け出した5歳の少年が
忽然と姿を消した。
滅多にない濃霧に包まれて1メートル先も見えないような夕方のことだった。
そして、行方不明で生死もわからないまま、20数年が過ぎた秋のある日、
祖父の元に、その日に少年が履いていたサンダルの片方が送られてくる。
▶ここから物語は始まる。
祖父の元船長イェルロフとその娘で少年の母親、ユリアは、
再び少年の事件と向き合い、少年の行方を探し始める。
もう一つ、物語の構成として特徴的なのは、
もう一人の中心人物ニルス・カントの犯罪にまつわる歴史を、
別だての物語として展開していくこと。
19の項目が立てられているけれど、これは読者にだけ知らされる話。
さて、探偵役として活躍するのは、前にも言ったように
老人ホームに住まい、足腰が思うように動かせなくて
杖をついている老人のイェルロフ。ともに行動するのは同じく老人たち。
(息子を失ったことで、人生に行き詰まったままの娘のユリアをのぞけば、だけど)
スピード感の緩い会話を紡ぎながら、小さな物語の破片が語られていく。
あとから振り返ると、伏線だったとわかったり。
読者としては、
ドイツ兵を殺し、警官を射殺して島から逃げ出したニルス・カントの話の、
あの部分は、そういうことなのか。
えー、この人がこう絡んでいるのか。
と興味は尽きない。
雰囲気のある情景描写と文体は惹きつけられる。
イェルロフの別荘があるステンヴィーク村は、
夏には大勢の人たちがやってくる避暑地だけれど、
夏が終われば住む人も限られた閑散とした場所。
イェルロフとともに、少年の事件を追っていた老人が
事故とも殺人ともつかない形で殺されたり……。
いったい誰が、この事件が蒸し返されることをイヤがっているのか?
印象的だったのはランベルトのエピソード。
著者のヨハン・テオリンは元船長だった母方の祖父から
エーランド島の幽霊譚や民話を聞いて育ったそうだ。
だから、不思議なエピソードも違和感もなく語られる。
こんな話。
「あの子がいなくなって三日経っていたのに、どこにも手がかりがなくて。
そのとき、エラ(母親)がランベルトのことを思いついて、
ランベルトならばあれこれ見つけ出せるかもしれないと母は言ったんですよ。
それで有名な人なのだとエラは言ったんです」
ランベルトはユリアの家にやってきて、少年の部屋で寝た。
「ああ、それが兄のやったことでしたよ。
「あれこれ夢を見た。溺れた人間やなくしてしまった物。未来の出来事、
これから起ころうとしていること。
ランベルトは自分の死も数週間前に夢で見た。
自分の部屋のベッドの上で起こると予言した。
夜中の二時半で、心臓が止まるが救急車が間に合わないとね。
そして兄が言ったとおりの日に、そのままのことが起こったんですよ。
救急車は間に合わなかった」
ユリアはあの日、ランベルトが朝起きてきたとき
「イェンスの夢を見た」と言うのを聞いた。とても悲しそうな表情で。
「お兄さんはもっと話をするつもりだったはずなんですが、わたしはそれ以上
聞くことに耐えられなかった。
殴りかかって、出ていけと叫んだんです。……
わたしはキッチンに立ったまま泣きじゃくって、お兄さんが走り去る音を
聞いていたんですよ」
そのときにランベルトが言いかけたことを、いま聞きたいとユリアは言う。
「どうしても知りたい」と。
ランベルトの弟は、失踪から5年経ったころに出た新聞記事を読んだときに
兄が言ったことをユリアに告げる。
「わたしたちはキッチン・テーブルにむかって、まず、わたしが新聞記事を読んだ」
「次にランベルトが読んだ。兄があの少年の記事を読んでいるのを見て、
どう思うかと訊ねた。
そのときですよ、ランベルトは新聞を置いて、少年は死んでいるといったんです。」
「ランベルトは、それは石灰岩平原で起こったと言いましたよ。
石灰岩平原であの子は殺されたと」
「男がやったとランベルトは言いましたね。少年が消えたその日に。
憎しみに満ちた男が石灰岩平原で少年を殺したと。
それから石壁の隣の墓に少年を埋めたと」
それを聞いて、ユリアは本当だと信じる……。
とまあ、こんなエピソードだけれど、面白いなあと思う。
何にしても、長い年月の物語が、最後にはぐるっとまわって、
少年の身に起こったことにかえってくる。
大団円でイェルロフは殺されかけるけれど、なんとか助かり……。
(ヘリコプターは登場するは、車はぶつかるは、ドンパチはあるはで
ハラハラさせられる。)
分厚くても、興味は尽きない。
読み返しては「そうだったのか」と納得して、
何度も楽しめる上質のミステリーだった。